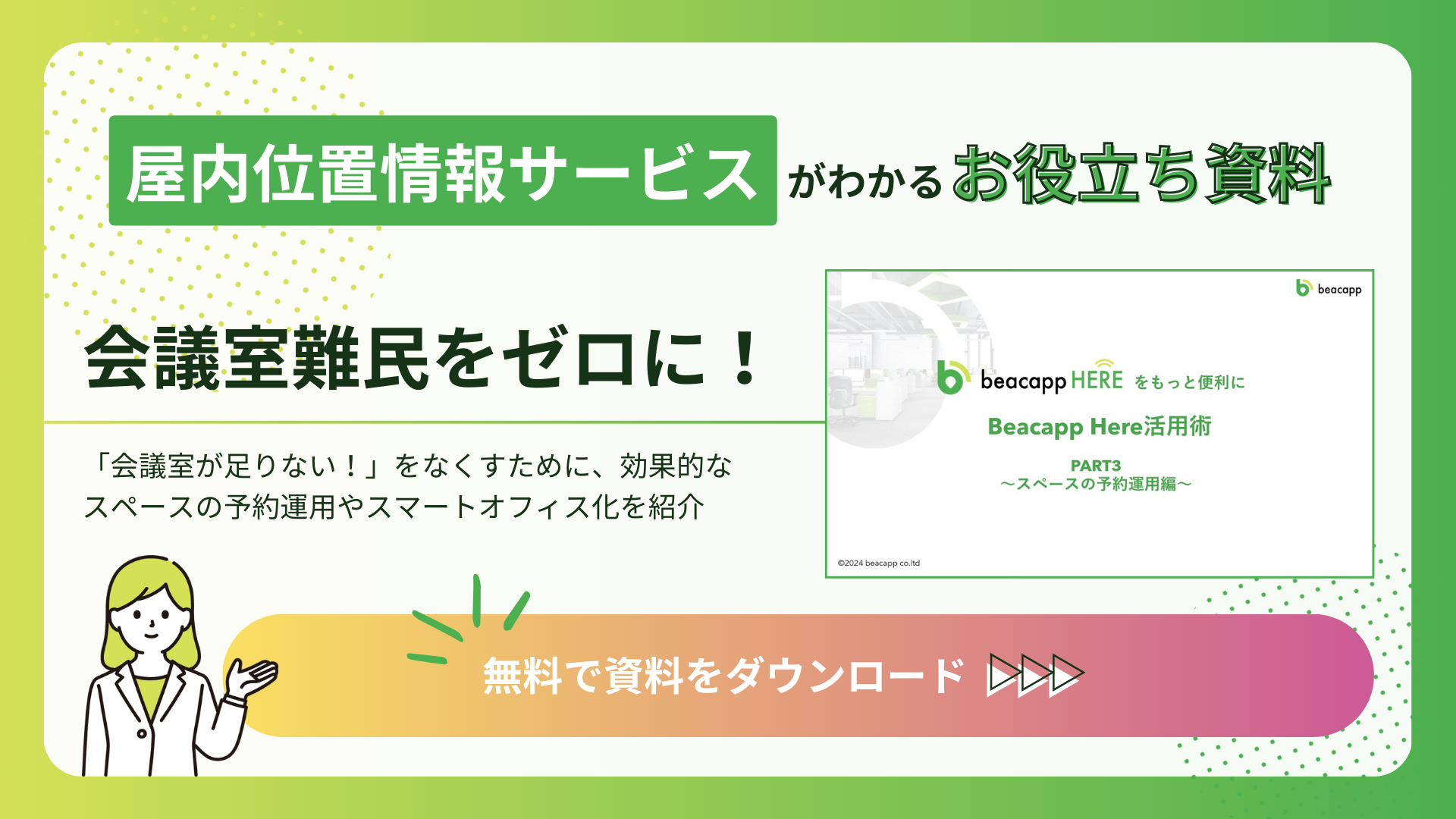健康経営とは、企業が従業員の健康を積極的に支援し、その維持・向上を企業活動の一環として取り組む経営戦略のことです。
従業員の健康が企業の生産性や働きやすさに直結するため、近年、多くの企業が注力しています。健康経営の推進により、企業全体の健全な成長を目指すとともに、社会的責任を果たす重要な取り組みとなっています。
そこで本記事では、健康経営の概念やメリット・デメリットについて詳しく解説します。本記事を最後までお読みいただくことで、健康経営の意味について理解し、自社の従業員満足度向上に役立てることが可能となりますので、是非とも最後までお読みください。
健康経営とは?
健康経営とは、企業が従業員の健康を重視し、その維持や向上を経営戦略の一環として取り組むことを指します。
具体的には、健康診断の実施やメンタルヘルス対策、運動促進プログラムの導入など、さまざまな施策を通じて従業員の健康を支援することが求められます。
このような取り組みは、従業員の健康状態が企業の生産性や業務効率に直結するため、企業にとっても重要な課題となっています。
健康経営が注目されている背景
近年、企業における健康経営が注目されるようになった背景には、さまざまな要因があります。
まず、労働環境の変化が挙げられます。テレワークやフレックスタイム制度の導入により、従業員の働き方が多様化し、健康管理の重要性が増しています。
特に、長時間労働やストレスの増加が問題視される中で、企業が従業員の健康を支援することが求められています。
また、少子高齢化が進む日本においては、労働力の確保が企業の大きな課題となっています。健康な従業員を維持することは、企業の生産性を高め、優秀な人材を引き留めるための重要な戦略となります。
さらに、健康経営は企業の社会的責任(CSR)とも密接に関連しており、企業が社会に対してどのように貢献するかが問われる時代に突入しています。
健康経営のメリット

健康経営を導入することで、企業にはさまざまなメリットがもたらされます。ここでは、各メリットについて解説します。
生産性の向上
健康経営を導入することで、企業の生産性向上につながります。
従業員の健康が改善されると、仕事に対する集中力やモチベーションが高まり、結果として業務効率が上がります。健康な従業員は、病気やストレスによる欠勤が少なく、安定した労働力を提供できます。
また、健康経営に取り組む企業は、従業員の健康を支援するためのプログラムや施策を導入することが一般的です。
例えば、定期的な健康診断やフィットネスプログラム、メンタルヘルスのサポートなどが挙げられます。これらの取り組みは、従業員が自分の健康に対して意識を高めるきっかけとなり、日常生活における健康的な選択を促進します。
社員の定着率が高くなる
健康経営を実施することで、企業は従業員の定着率を向上できます。
従業員が健康であることは、仕事のパフォーマンスやモチベーションに直結します。健康経営に取り組む企業は、従業員の健康を重視し、ストレスの軽減や健康的な職場環境の整備に努めるため、従業員は安心して働くことができます。
また、健康経営を通じて、企業が従業員の声に耳を傾け、健康に関するニーズや要望を反映させることで、従業員の満足度が向上します。
結果として、離職率が低下し、企業は優秀な人材を維持できるのです。
企業のブランディングになる
健康経営は、企業のブランディングにおいても重要な役割を果たします。
従業員の健康を重視する姿勢は、企業の社会的責任を果たすだけでなく、外部からの評価を高める要因となります。
特に、健康経営を実践している企業は、従業員の満足度が高く、職場環境が良好であることが多いため、求職者にとって魅力的な選択肢となります。
また、健康経営を推進することで、企業のイメージ向上にもつながります。健康的な職場環境を提供する企業は、顧客や取引先からの信頼を得やすく、ブランド価値を高めることができます。
健康経営のデメリット

健康経営は多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、各デメリットについて解説します。
健康状態の把握に時間がかかる
健康経営を推進する上で、従業員の健康状態を把握することは重要ですが、これには時間と労力がかかるというデメリットがあります。
まず、従業員一人ひとりの健康状態を把握するためには、定期的な健康診断やメンタルヘルスチェックを実施する必要があります。これらのデータを収集し、分析するプロセスは簡単ではなく、特に大規模な企業では膨大な情報を扱うことになります。
さらに、健康状態の把握には、従業員のプライバシーに配慮する必要もあります。健康情報は非常にセンシティブなデータであるため、適切な管理体制を整えなければなりません。
結果が出にくい
健康経営を導入する際のデメリットの一つとして、結果が出にくいという点が挙げられます。
企業が健康経営に取り組むことで、従業員の健康状態や職場環境の改善を目指しますが、その効果がすぐに現れるわけではありません。特に、健康施策の成果を測定するためには、長期的な視点が必要です。
例えば、健康診断の結果や従業員のストレスレベルの変化、さらには生産性の向上など、これらの指標は短期間での変化を捉えることが難しいため、施策の効果を実感するまでに時間がかかることが多いです。
また、健康経営の取り組みが従業員にどのように受け入れられるかも、結果に影響を与える要因となります。従業員が健康施策に対して積極的に参加しなければ、期待される効果は得られません。
従業員の不満が募る可能性がある
健康経営は多くのメリットをもたらす一方で、導入過程や施策の実施において従業員の不満が生じる可能性もあります。
特に、健康施策が従業員にとって強制的に感じられる場合や、個々のニーズに合わないプログラムが提供されると、逆にストレスを感じることがあります。
例えば、健康診断やフィットネスプログラムへの参加が義務化されると、参加を望まない従業員にとっては負担となり、職場環境に対する不満が高まることがあります。
また、健康経営の施策が十分に理解されていない場合、従業員はその意義を感じられず、取り組みへの参加意欲が低下することもあります。企業が健康経営を推進する際には、従業員とのコミュニケーションを密にし、彼らの意見や要望を反映させることが重要です。

健康経営を浸透させるための方法
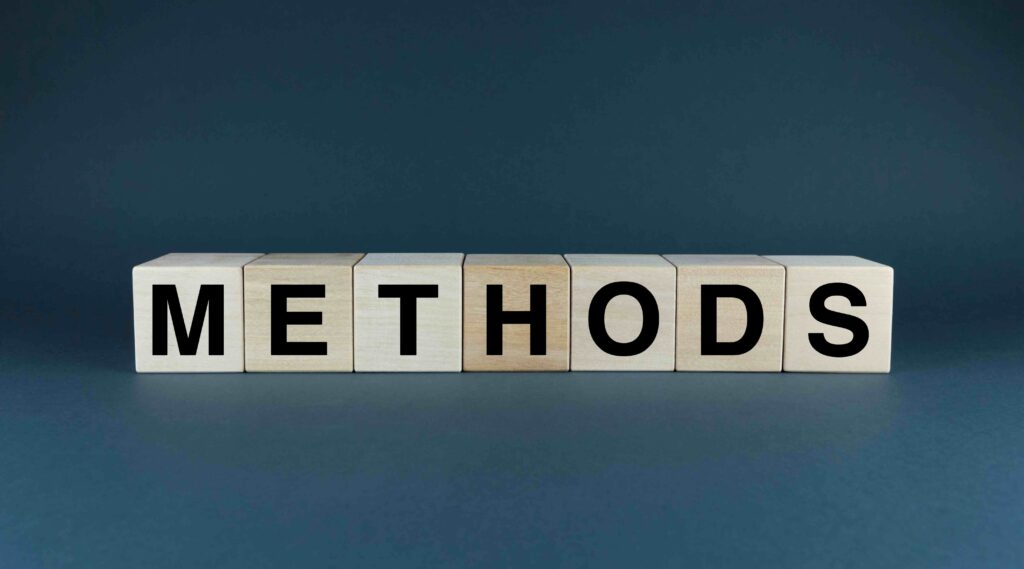
健康経営を企業内に浸透させるためには、いくつかの具体的な方法があります。ここでは、各方法について解説します。
「健康経営優良法人」の認定を取得する
健康経営を推進する企業にとって、「健康経営優良法人」の認定を取得することは大きなステップとなります。
健康経営有料法人の認定は、企業が従業員の健康管理に対して真剣に取り組んでいることを示すものであり、外部からの信頼を得るための重要な指標となります。
認定を受けることで、企業は健康経営に対する社会的な評価を高めることができ、優秀な人材の確保や顧客からの信頼を得ることにもつながります。認定を取得するためには、まず企業の経営理念や方針に健康経営を組み込むことが求められます。
具体的には、従業員の健康を重視した施策を計画し、実行するための組織体制を整える必要があります。
助成金を活用する
健康経営を推進するためには、さまざまな取り組みが必要ですが、その際に助成金を活用することが非常に効果的です。日本政府や地方自治体は、企業が従業員の健康を支援するための施策に対して助成金を提供しています。
助成金の種類は多岐にわたり、健康診断やメンタルヘルス対策、フィットネスプログラムの導入など、さまざまな健康施策に対して支援が行われています。
例えば、従業員の健康診断を実施する際の費用や、健康促進のためのセミナー開催にかかる費用が助成対象となることがあります。
また、助成金を活用することで、企業の健康経営に対する取り組みがより具体的かつ効果的になるだけでなく、従業員の健康意識を高めるきっかけにもなります。
助成金を受けるためには、申請手続きや条件を満たす必要がありますが、これを機に自社の健康経営の方針を見直し、より良い環境を整えることができるでしょう。
社員を教育する
健康経営を効果的に浸透させるためには、従業員への教育が不可欠です。健康に関する知識を深めることで、従業員自身が自らの健康管理に積極的に取り組むようになります。
具体的には、健康に関するセミナーやワークショップを定期的に開催し、栄養、運動、メンタルヘルスなど多岐にわたるテーマを取り上げることが重要です。
また、健康経営の理念や施策についての理解を深めるために、社内での情報共有も大切です。例えば、社内報やイントラネットを活用して、健康経営に関する最新情報や成功事例を発信することで、従業員の意識を高めることができます。
健康経営優良法人の認定要件
健康経営優良法人の認定を受けるためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。これらの要件は、企業が従業員の健康をどのように支援し、経営戦略に組み込んでいるかを評価する基準となります。
経営理念・方針
健康経営を実践するためには、まず企業の経営理念や方針に健康を重視する姿勢を明確に組み込むことが重要です。
経営理念は企業の根幹を成すものであり、従業員に対して企業がどのような価値観を持ち、どのような方向性を目指しているのかを示すものです。
この理念に健康経営を位置づけることで、従業員は自らの健康が企業の成長に寄与することを理解し、積極的に健康維持に努めるようになります。
具体的には、企業のビジョンやミッションに「従業員の健康を最優先に考える」というメッセージを盛り込むことが考えられます。
また、健康経営に関する方針を策定し、具体的な目標や施策を明示することで、従業員に対して健康経営の重要性を伝えることができます。
組織体制
健康経営を効果的に推進するためには、しっかりとした組織体制が不可欠です。
まず、経営層が健康経営の重要性を理解し、全社的な方針として位置づけることが求められます。経営者自身が健康経営の理念を体現し、従業員にその意義を伝えることで、組織全体が一丸となって取り組む土壌が整います。
次に、健康経営を専門に担当する部署やチームを設置することが重要です。このチームは、従業員の健康状態を把握し、必要な施策を立案・実行する役割を担います。
また、定期的に健康診断やストレスチェックを行い、データを収集・分析することで、従業員の健康ニーズを的確に把握することが可能になります。
制度・施策実行
健康経営を実現するためには、具体的な制度や施策を実行することが不可欠です。
まず、企業は従業員の健康を支援するためのプログラムを設計し、実施する必要があります。これには、定期的な健康診断やメンタルヘルスケアの導入、フィットネスプログラムの提供などが含まれます。
これらの施策は、従業員が自らの健康を意識し、積極的に改善に取り組むきっかけとなります。
さらに、健康経営を推進するためには、経営層からの強いコミットメントが重要です。経営者自身が健康経営の重要性を理解し、従業員に対してその意義を伝えることで、組織全体の意識が高まります。
また、健康経営に関する情報を社内で共有し、従業員が参加しやすい環境を整えることも大切です。
評価・改善
健康経営を効果的に推進するためには、定期的な評価と改善が不可欠です。企業は、導入した健康施策の効果を測定し、従業員の健康状態や満足度を把握する必要があります。
具体的には、健康診断の結果やアンケート調査を通じて、従業員の健康に関するデータを収集し、分析することが重要です。
評価の結果をもとに、施策の見直しや新たな取り組みを検討することで、より効果的な健康経営を実現できます。
法令遵守・リスクマネジメント
健康経営を推進する上で、法令遵守とリスクマネジメントは欠かせない要素です。
企業は従業員の健康を守るために、労働基準法や健康保険法などの関連法令を遵守する必要があります。これにより、従業員が安心して働ける環境を整えることができ、企業の信頼性を高めることにもつながります。
また、リスクマネジメントは、従業員の健康に影響を与える可能性のあるリスクを特定し、評価し、対策を講じるプロセスです。
例えば、職場のストレスや過重労働、感染症のリスクなどを把握し、適切な対策を講じることで、健康障害を未然に防ぐことができます。
健康経営優良法人の認定を受けた企業の事例3選
健康経営の重要性が高まる中、実際に「健康経営優良法人」の認定を受けた企業が増えています。ここでは、その中から特に注目すべき3社の事例を紹介します。
味の素株式会社
味の素株式会社は、健康経営の先駆者として知られています。同社は、従業員の健康を重視し、さまざまな施策を通じて健康経営を実践しています。
具体的には、健康診断の充実やメンタルヘルス対策、運動促進プログラムの導入など、多岐にわたる取り組みを行っています。
特に、味の素では「健康経営宣言」を行い、企業全体で健康を支援する文化を醸成しています。従業員が健康であることが、企業の生産性向上や業績向上に直結するという考え方のもと、健康に関する情報提供や啓発活動を積極的に行っています。
また、味の素は、健康経営優良法人の認定を受けており、その取り組みが外部からも評価されています。これにより、企業のブランディングにも寄与し、優秀な人材の確保や社員の定着率向上にもつながっています。
住友生命保険相互会社
住友生命保険相互会社は、健康経営の実践において先進的な取り組みを行っている企業の一つです。同社は、従業員の健康を重視し、さまざまな施策を通じて健康経営を推進しています。
特に注目すべきは、従業員の健康状態を定期的に把握し、そのデータを基にした個別の健康支援プログラムを実施している点です。これにより、従業員は自分の健康状態を理解し、必要な対策を講じることができるため、健康意識の向上にも寄与しています。
また、社内での健康イベントやセミナーを開催し、健康に関する知識を深める機会を提供することで、従業員同士のコミュニケーションも促進されています。
参考: 健康経営・働き方改革 | サステナビリティ | 住友生命
東京海上日動火災保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社は、健康経営の取り組みを積極的に進めている企業の一つです。同社は、従業員の健康を企業の重要な資産と捉え、健康経営を戦略的に推進しています。
特に注目すべきは、従業員の健康状態を定期的に把握し、個々のニーズに応じたサポートを行う体制です。これにより、早期の健康問題の発見や、適切な対策を講じることが可能となり、従業員の健康維持に寄与しています。
また、社内での健康促進イベントや、健康に関する情報提供を行うことで、従業員の健康意識を高める取り組みも行っています。

まとめ
健康経営は、企業が従業員の健康を重視し、その維持・向上を図ることで、企業全体の生産性や働きやすさを向上させる重要な経営戦略です。健康経営を実践することで、企業は従業員の定着率を高め、企業のブランディングにも寄与することが期待されます。
一方で、健康経営にはデメリットも存在します。健康状態の把握には時間がかかり、結果が出にくい場合もあります。
また、従業員の健康施策に対する不満が募る可能性もあるため、慎重な取り組みが求められます。これらのメリットとデメリットを理解し、自社に合った健康経営の方針を策定することが重要です。
————————————————————————————————————
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg