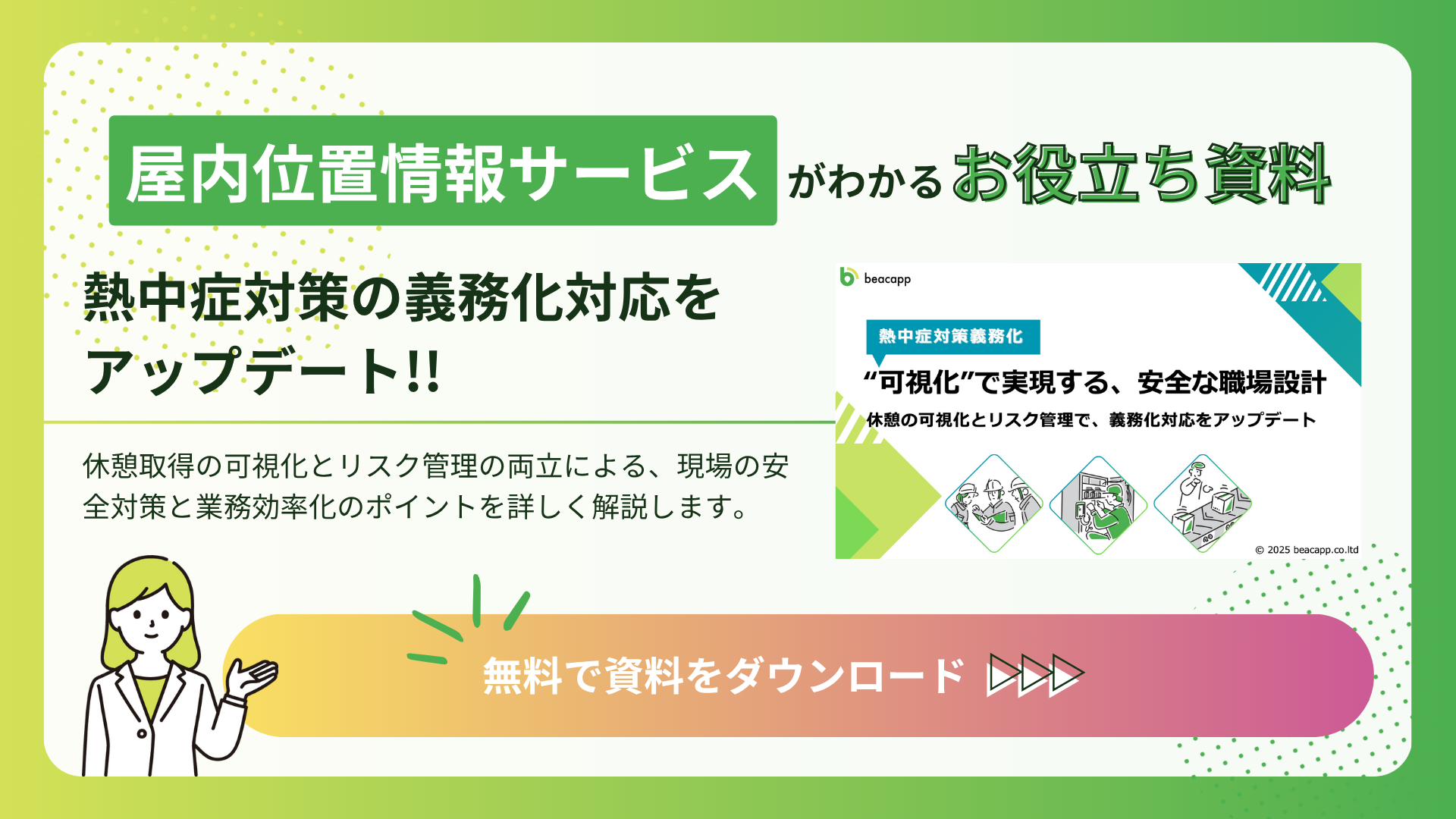製造業の現場では、作業の効率や納期を意識するあまり、安全が後回しになってしまうこともあります。そんな中で「安全宣言」は、企業として“安全を最優先にする”姿勢を明文化し、現場の意識を一つにするための大切な指針です。
この記事では、安全宣言の基本的な意味から、現場での活かし方、そして実践につなげる工夫までをわかりやすく紹介します。
「安全宣言」とは? 製造現場で求められる理由

製造業における安全宣言とは、事故や災害を未然に防ぎ、社員全員の安全意識を高めるための「行動の土台」となる言葉です。形式的に掲げるだけでなく、現場に根づく“実効性ある宣言”にすることが、真の安全文化の醸成につながります。
安全宣言は“経営と現場をつなぐ約束”
安全宣言の出発点は、経営層の「安全を最優先にする」という強い意思表示です。経営が本気で安全に向き合う姿勢を示すことで、現場の行動にも一貫性が生まれます。
また、現場からの声を取り入れたうえで策定することで、単なるトップダウンのメッセージではなく「全員で守る約束」として機能します。経営と現場が同じ方向を向くための“言葉の架け橋”こそ、安全宣言の本質といえます。
安全スローガンとの違いを理解する
安全スローガンは、「安全週間」など短期間の啓発活動で使われる合言葉のようなものです。一方、安全宣言は企業全体の方針や文化を表す“恒常的な指針”です。
たとえばスローガンが「今月の目標」だとすれば、安全宣言は「会社の理念」に近い存在といえます。短い言葉で意識を高めるスローガンと、全体の行動を方向づける安全宣言を併用することで、安全文化をより強く根づかせることができます。
製造業に特有のリスクと安全宣言の役割
製造現場では、機械の稼働・重量物の取り扱い・高温作業・薬品使用など、多様なリスクが日常的に存在します。一つのミスが重大な事故につながるからこそ、「安全意識の徹底」が求められます。
安全宣言には、こうしたリスクを明文化し、「どんな事故を防ぎたいのか」「どう行動すべきか」を具体的に示す役割があります。社員全員が同じ価値観で行動できるようにする、それが安全宣言の目的です。
安全宣言がもたらす効果
安全宣言を掲げることで、まず全社員の意識が一つにまとまります。また、経営層・管理職・現場が共通の価値観で行動するようになるため、判断や対応にも一貫性が生まれます。さらに、外部に対しても「安全を重視する企業」という信頼性を発信できる点も大きなメリットです。
安全宣言は“掲げて終わり”ではなく、現場で生きる言葉として活用することで、組織の文化を変える力を持っています。
伝わる安全宣言をつくる3つのステップ

どれだけ立派な安全宣言でも、「誰にも読まれない」「内容が伝わらない」ようでは意味がありません。伝わる安全宣言をつくるには、現場の声を反映し、具体性のある言葉で表現し、それを継続的に届ける工夫が必要です。
ここでは、実効性ある安全宣言を作成するための3つのステップを解説します。
① 現場の声を反映する
安全宣言は、現場の実態に即していることが何よりも重要です。
実際に作業を行う人たちが「共感できる内容」でなければ、どれほど正しいことが書かれていても形骸化してしまいます。そのためには、ヒヤリ・ハットの事例や、過去に起きたインシデント、日常の気づきなど、現場から寄せられた生の声を取り入れることが不可欠です。
現場との対話を通じて、「自分たちの声が反映されている」と感じられる宣言にすることで、当事者意識と実効性が高まります。
② シンプルで具体的な表現にする
宣言文が長すぎたり、抽象的だったりすると、内容が伝わらず心に残りません。伝わる安全宣言には「簡潔さ」と「具体性」が必要です。
例えば「安全第一」ではなく、「声かけ・確認・報告で事故ゼロを目指す」のように、具体的な行動を盛り込むと伝わりやすくなります。また、現場で日常的に使う言葉を選ぶことで、社員が自分の行動と結びつけやすくなり、自然と実践につながっていきます。
③ 発信方法を工夫する
せっかく良い安全宣言をつくっても、掲示板に貼っただけでは浸透しません。掲示物に加えて、朝礼での唱和、社内ポータルでの共有、安全大会での読み上げなど、定期的かつ多角的な発信が重要です。
とくに、管理職やリーダーが積極的に宣言に触れることで、「言葉に責任を持つ姿勢」が伝わり、現場にも広がっていきます。“目にする・耳にする・口にする”機会を増やすことで、宣言が日常の行動に自然と根づいていきます。
チームごとの小さな安全宣言も有効
会社全体の安全宣言に加えて、各チームや部署ごとに「ミニ安全宣言」を作成するのも効果的です。
たとえば「●●ラインでは、声かけと目視確認を徹底します」など、業務やリスクに応じた宣言を作ることで、具体的な行動に結びつきやすくなります。チーム単位で話し合って作成することで、現場メンバーの主体性も高まり、「自分たちで作ったから守ろう」という意識が育ちます。
小さな積み重ねが、全体の安全文化を支える土台になります。

製造業の安全宣言・スローガン例文集
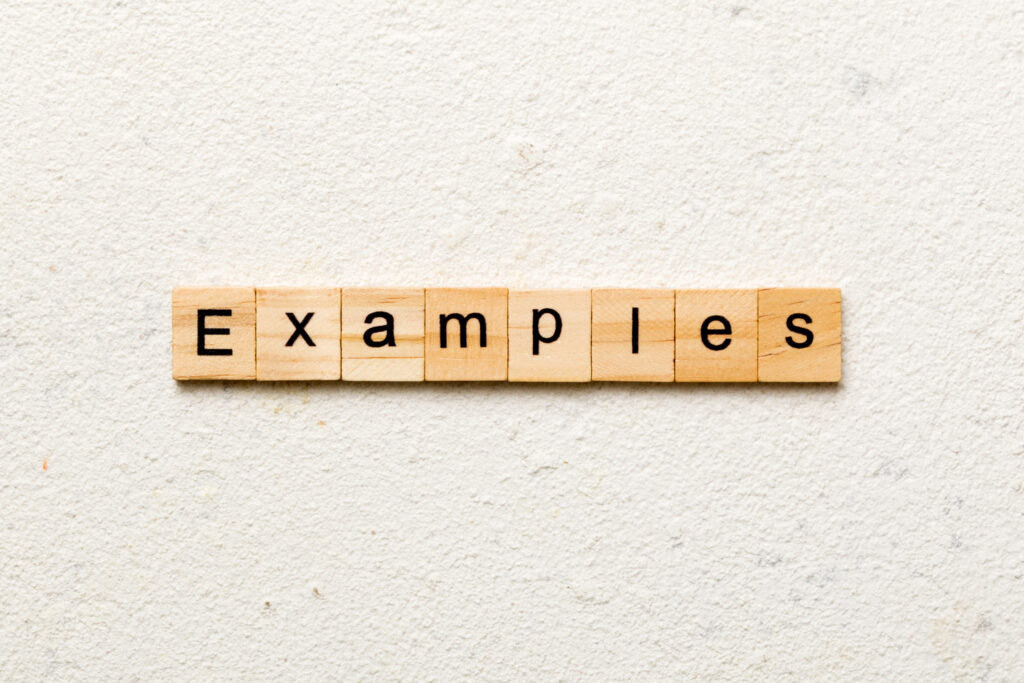
企業や現場の立場、目的に合わせて言葉を選ぶことで、社員にとって“自分ごと”として受け取ってもらえる「現場に響く安全宣言」を作ることができるようになります。
ここでは、経営層・現場リーダー・チームごとの視点で使える例文とともに、安全宣言を更新・見直すタイミングについても解説します。
経営層による安全宣言の例
経営層の安全宣言は、組織の方向性や価値観を示す「旗印」となります。形式的な言葉ではなく、「社員の命と健康を守る責任を負っている」というメッセージを明確に込めることが大切です。
例文①
「私たちは、すべての業務において“安全”を最優先とします。事故ゼロの職場を目指し、全社員が互いに支え合う風土をつくります。」
例文②
「安全なくして生産なし。全員参加の安全活動を推進し、“働く人を守る会社”であり続けます。」
例文③
「一人ひとりの安全行動が、会社の未来をつくる。私たちは“安全に妥協しない文化”を育てます。」
現場リーダーによる一言宣言の例
現場で日常的に使える「一言宣言」は、朝礼や点呼での唱和にも活用しやすく、継続的な安全意識の醸成に役立ちます。短くても、行動につながる“具体的なメッセージ”がポイントです。
例文①
「焦らず・慌てず・確認徹底。今日もゼロ災でいこう!」
例文②
「声かけひとつが、命を守る第一歩。」
例文③
「安全は誰かに任せない。自分の目と耳で確認する。」
チームや部署でのスローガン例
チームごとのスローガンは、作業内容やリスク特性に応じて作成することで、行動に直結する“合言葉”になります。全員で話し合って決めたスローガンであれば、より強い当事者意識も生まれます。
例文①
「止める勇気が未来を守る。異常を感じたらすぐ報告。」
例文②
「見て・指差して・声に出す。私たちの安全ルール。」
例文③
「ルールを守ってカッコいい!安全はプロの証し。」
見直しと更新のタイミング
安全宣言やスローガンは、掲げたら終わりではありません。現場の変化や事故の発生、設備の導入などをきっかけに、定期的に見直すことで“生きた言葉”として維持できます。
【更新のタイミング例】
- 毎年の安全週間・年度初めのキックオフ
- ヒヤリ・ハットや軽微な事故の発生時
- 新ライン・新設備の立ち上げ時
見直しの際には、アンケートやヒアリングを通じて、社員の声を取り入れると納得感のある内容になります。
“掲げるだけで終わらせない”ための実践法

安全宣言を掲げただけでは、現場の行動は変わりません。本当に大切なのは、その言葉が日々の業務や意思決定、現場の空気感にどう影響を与えているかということです。
ここでは、安全宣言を“形骸化させず、実行につなげる”ための実践的な工夫を4つご紹介します。
朝礼やミーティングで繰り返し確認する
安全宣言は、日々の業務の中で繰り返し触れることによって意識づけされていきます。毎朝の朝礼で読み上げたり、ミーティング冒頭で共有したりと、習慣化する工夫が重要です。特に「今日の安全目標」「昨日のヒヤリ事例」を絡めて話すと、現場との関連性が高まり、聞き流されにくくなります。
“毎日、声に出すこと”で、安全宣言はただの言葉から「行動のきっかけ」へと変わっていきます。
ヒヤリ・ハット事例と紐づける
「安全宣言で言っていることが、現場でどう活きるのか?」
その具体性を高めるには、ヒヤリ・ハットの事例と結びつけるのが効果的です。たとえば「報告・連絡・相談の徹底をうたう宣言」に対して、「報告が遅れてライン停止につながったケース」などを共有することで、実感を伴った学びになります。
安全宣言が“絵空事”にならないためには、現実と照らし合わせて、現場で語られる存在にすることが大切です。
行動の“見える化”で改善を継続する
安全は「意識」だけでは守れません。実際の行動をデータで把握し、改善につなげる仕組みが必要です。
近年では、IoTやビーコンなどを活用し、誰がどこにいたか、作業エリアでどんな動線があったかを可視化できるツールも増えています。たとえば Beacapp Here を導入すれば、滞在状況や接触傾向を分析し、「事故リスクが高まりやすい状況」を可視化することが可能です。
安全活動に“定量的な根拠”を持たせることで、より現実的な改善アクションを打てるようになります。
成果を共有し、称賛する文化を育てる
安全宣言の実践には、目に見える「成果」と、それを認め合う「文化」が欠かせません。
たとえば、「事故ゼロ◯日達成」を掲示したり、安全行動が優れたチームや個人を表彰するなど、ポジティブな見える化を行いましょう。称賛が増えることで、自発的な安全行動が促され、宣言が“形”ではなく“空気”として職場に根づいていきます。
数字だけでなく、努力や行動を評価する視点を取り入れることが、継続のカギとなります。

まとめ
安全宣言は、単なる掲示物や理念ではなく、現場で行動を生む「合言葉」です。経営と現場が一体となり、日々の業務の中で何度も触れ、考え、実践することで、その言葉は文化へと昇華していきます。
形だけで終わらない“生きた安全宣言”を育てていくためには、Beacapp Hereのようなツールを活用して行動を“見える化”することもおすすめです。社員一人ひとりの安全を守るために、今こそ安全宣言を“現場で機能する言葉”に変えていきましょう。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg