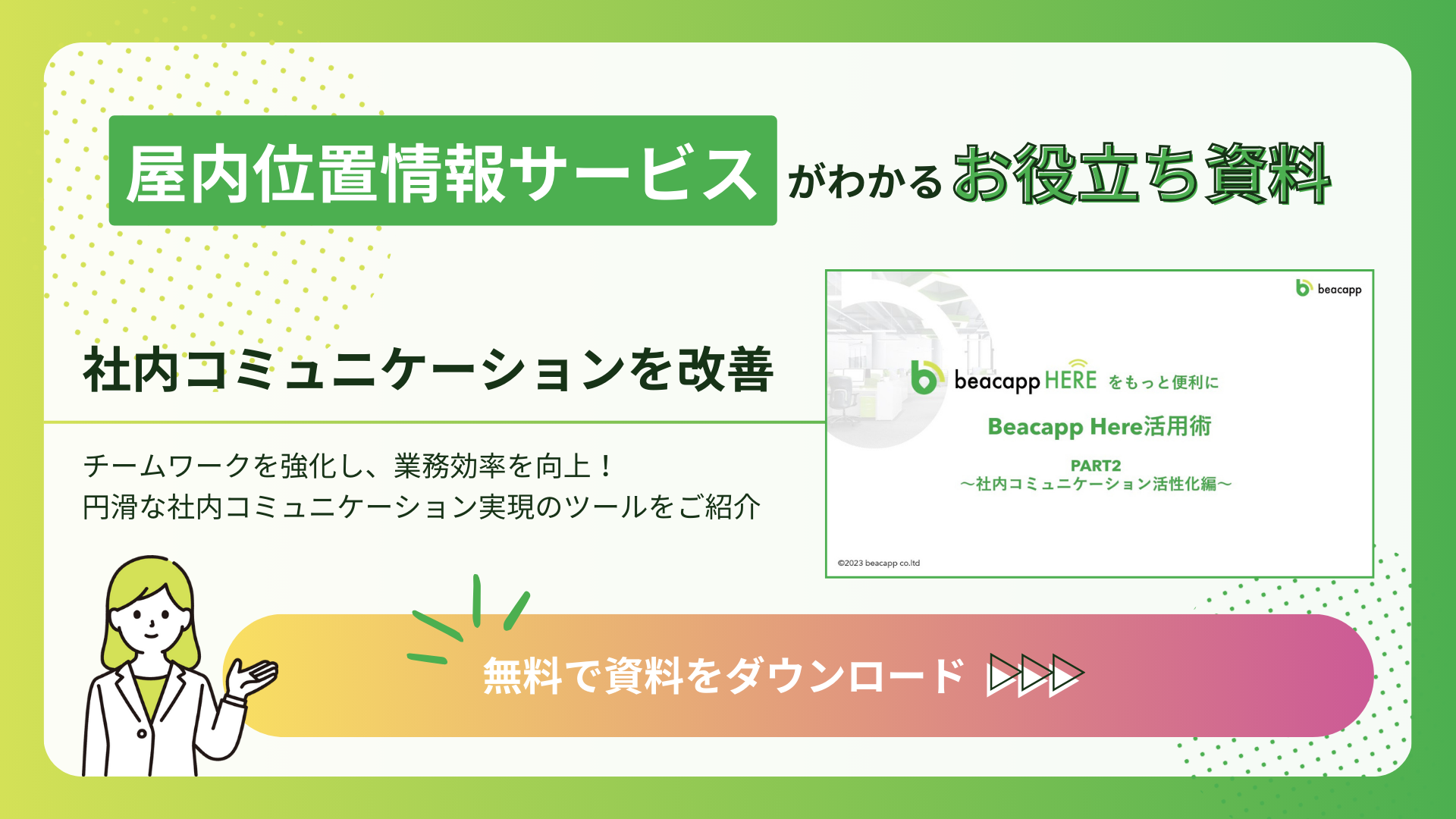近年、「従業員エンゲージメントの高さ」が企業の成長や離職率に大きく影響するという視点が注目を集めています。ただ給料や福利厚生が整っているだけでは、人は会社に定着しづらい時代。社員が「この職場で働き続けたい」と心から思える環境をどうつくるかが、経営の鍵となっています。
そして実は、エンゲージメントの高い企業の多くが共通して行っている取り組みがありました。それが、“職場の見える化”です。
従業員エンゲージメントが高い企業とは?
「従業員エンゲージメントが高い企業」とは、社員一人ひとりが会社の目標や価値観に共感し、自らの仕事に誇りを持って前向きに取り組んでいる状態の企業を指します。社員が“会社の一員としての責任”や“貢献したいという意志”を持っているため、生産性や創造性も自然と高まり、結果として顧客満足度や企業の競争力にも直結します。
「従業員エンゲージメントが高い企業トップ10」などのランキングが話題になる中、その違いを生む要素はどこにあるのでしょうか?
本記事では、“見える化”によってエンゲージメントを高めている企業の特徴と事例をもとに、実践的なヒントを探っていきます。
エンゲージメントとは?従業員満足度との違い

エンゲージメント(engagement)とは、社員が自社に対して持つ“愛着”や“貢献意欲”を意味します。よく似た言葉に「従業員満足度」がありますが、満足度は「会社から提供される待遇や制度への評価」であり、どちらかというと受け身の指標です。
一方エンゲージメントは、「自分の仕事に誇りを持っている」「会社にとって自分は重要だと感じている」といった、主体的な関与が評価軸になります。
企業にとっては、この“意欲的に働く社員”が多い状態をいかに実現するかが、組織活性化のカギになります。
なぜ今「働きがい」や「定着率」が重視されるのか
かつては給与や福利厚生といった“外的報酬”が企業選びの基準でした。しかし今は、「この仕事に意味があるか」「自分の成長につながるか」といった内的な充実感が、社員の定着に大きく影響しています。特にZ世代以降は「働く目的」や「社会的意義」に敏感で、たとえ待遇が良くても、やりがいや人間関係が乏しい職場からは離れてしまう傾向があります。
そのため企業側は、社員が「ここで働くことに納得している」と感じられる環境づくり、つまり**“働きがい”を見える形で支える仕組み**を求められているのです。
関連記事: 従業員エンゲージメントとは?高める方法や事例を紹介!
エンゲージメントが高い企業に共通する4つの視点
「従業員エンゲージメントが高い企業」に共通するのは、単なる制度整備ではなく、**職場のリアルな課題に向き合う“実行力”**です。以下の4つの視点から、エンゲージメント向上を実現している具体的な取り組みを見ていきましょう。
1. 働きやすい職場環境とフリーアドレスの最適化
フリーアドレスを導入したものの、「毎朝席を探すのがストレス」「どこに座れば仕事に集中できるか分からない」といった声は多く聞かれます。実は、**自由度の高い働き方ほど“管理されていないと逆に不便”**になることがあるのです。
エンゲージメントが高い企業では、こうした空間のストレスを放置せず、座席の利用状況や混雑度をリアルタイムに可視化。スマートフォンで座席予約ができたり、フロア全体の空き状況がひと目で分かるようにしたりと、「どこで働くかの選択」をサポートしています。
こうした取り組みによって、社員が自分らしく働ける環境を“日常的に”支える仕組みが実現されているのです。物理的な快適さの追求は、働く人の意欲を引き出す土台になります。
2. 社内コミュニケーションの活性化と見える化
テレワークやフリーアドレスにより、同じ会社にいながら「誰がどこにいるのか分からない」「偶然の会話が減った」といった“つながりの希薄化”が進んでいます。
エンゲージメントの高い企業では、この課題に対し「人の動きの可視化」や「在席状況の共有」を導入し、チーム連携や社内交流を自然に促進しています。
たとえば:
- 社員の現在地をスマホで確認し、声をかけやすくする
- 離れた場所で働く同僚とも、オンラインで「今いる場所」を共有
- チームごとの出社率や在席時間のデータを集計し、運用改善につなげる
こうした“見えるつながり”を生むことで、社員同士の信頼関係が育まれ、孤立感の解消や心理的安全性の向上につながります。
3. エンゲージメント施策の効果測定と改善
エンゲージメント向上を目的とした施策は、導入するだけで満足してしまいがちです。
しかし、実際にどれほど効果があったのか、継続的に測定・改善していく仕組みがなければ、形だけの取り組みに終わってしまいます。
成果を上げている企業では、行動データや稼働率、出社傾向などの可視化データをもとに、定量的にエンゲージメントの変化を追跡しています。さらにAIを活用して、データから課題を抽出し、改善案まで自動で提示できる仕組みを導入している事例もあります。大切なのは、現場の声や利用データに基づいた柔軟な改善を続けること。制度や施策は導入後が本番です。「施策をやりっぱなしにしない姿勢」が、社員からの信頼にもつながっています。
4. 経営と現場をつなぐ、リアルな“働き方改革
エンゲージメントが高い企業では、経営層が「社員の働きやすさ」や「職場環境の課題」を数字と実態の両面から把握し、具体的な施策につなげています。
特に注目されているのが、データを通じて現場のリアルな状況を“見える化”し、経営判断に活かすアプローチです。例えば、出社率や座席の稼働率、部門ごとの行動傾向を可視化することで、
- 「〇曜日に特定部署だけ極端に混雑している」
- 「会議室の稼働率が低い」
- 「あるフロアでの滞在時間が極端に短い」
といった“気づき”を得ることができます。このような情報をもとに、レイアウトの変更や人員配置の最適化、出社ルールの再設計を行うことで、「数字に基づく働き方改革」を現場レベルで進められるようになります。経営と現場が分断されない組織づくりこそが、エンゲージメントの根幹です。

従業員エンゲージメントの改善は「見える化」から始まる

職場の課題は、目に見えないからこそ放置されがちです。
エンゲージメントを高める第一歩は、「今どこに、どんなムダや不満があるのか?」を可視化すること。ここから本当の改善が始まります。
働き方の可視化”がもたらす組織の変化とは
従業員エンゲージメントの土台にあるのは、「社員一人ひとりが、安心して自分らしく働ける環境があるかどうか」です。しかしその実態は、目に見えづらく、感覚的な判断に頼られてきました。
そこで注目されているのが、「働き方の可視化」です。具体的には、以下のような情報をデータで“見える化”する仕組みです:
- 誰がどこで働いているか(出社・在席・稼働エリアの可視化)
- 各部署の混雑傾向や滞在時間
- 会議室や共有スペースの利用頻度
- フリーアドレス席の空き状況・予約状況
これらの情報を可視化することで、「混雑しているから集中できない」「あの部署と連携が取りにくい」などの現場の違和感をデータで把握できるようになります。
経営層は現場の“働きにくさ”に気づけるようになり、社員は「ちゃんと見てもらえている」という安心感を得られる。そんな双方向の理解と信頼が生まれるのです。
定着率や離職率の改善にもつながる
「なぜ人が辞めてしまうのか」を把握するのは難しいものです。退職理由は個人によりさまざまですが、実はその多くが“働きづらさ”や“評価されていない感覚”に起因しています。
たとえば、「上司が自分の働き方を理解していない」「どれだけ頑張っても誰にも気づかれない」「毎日、無駄な動きが多い」といった声は、表面化しにくいものの、エンゲージメントを大きく下げる要因です。
そこで、「見える化」が役立ちます。
日々の動線や滞在状況、フロアごとの稼働率などをもとに、社員がどのように職場を使っているか、どの場所で長時間過ごしているかなどを把握することで、業務のムダやストレス要因を“事実として”捉えられるようになるのです。
こうした客観的なデータに基づいた改善は、「ちゃんと自分たちの声が届いている」という信頼につながり、結果的に定着率の向上や離職率の低下を実現します。
エンゲージメントは、気持ちだけでなく“環境によって左右される”もの。だからこそ、見える化はその第一歩となるのです。
社員の「働きがい」と「つながり」を可視化しよう
「働きがい」や「人とのつながり」は、エンゲージメントの中核となる要素。
これらは感覚的なものと思われがちですが、データの力で“見える化”することで、具体的な改善アクションへとつなげることが可能です。
改善の第一歩は「気づく」ことから
「この職場、なんとなく働きづらい」――そんな声が現場から上がっていても、明確な原因や解決策が見えず、放置されてしまうケースは多いものです。
しかし、働きづらさの多くは“環境要因”によるもので、職場の状態を数値化・可視化することではじめて、改善の糸口が見えてきます。
たとえば「混雑が集中する時間帯」「空席が多いのに座りづらいレイアウト」「コミュニケーションが分断されやすいフロア構成」など、目に見えなかった課題がデータで明らかになれば、それは職場改善の強力な武器になります。
気づきから改善へ――その一歩を支えるのが、働き方の“見える化”なのです。
Beacapp Hereの活用事例

クラウド型の屋内位置情報サービス「Beacapp Here」は、従業員エンゲージメント向上の取り組みをサポートするツールとして、多くの企業で導入が進んでいます。ここでは、2社の導入事例をご紹介します。
事例1:日鉄テックスエンジ株式会社
大規模な技術系組織である日鉄テックスエンジでは、社員の業務効率とコミュニケーションの質を高める目的で「Beacapp Here」を導入。
社員の在席状況や部署間の人の流れを可視化し、「誰がどこで作業しているか」がひと目で分かる状態を実現しました。
これにより、プロジェクトチーム間の連携がスムーズになり、出社・在宅のハイブリッドワークにおいてもリアルタイムな連携が可能に。物理的な距離を越えて“つながれる”職場環境が、エンゲージメント向上に寄与しています。
参考:日鉄テックスエンジ株式会社| 導入事例 | Beacapp Here(屋内位置情報サービス) | 所在地見える化でオフィス内の在席管理 | オフィス DX
事例2:ダイビル株式会社
都市型オフィスビルを展開するダイビル株式会社では、オフィスの快適性と生産性の両立を目的に、Beacapp Hereを導入。
フリーアドレス運用下での座席予約やスペースの混雑状況の可視化を実現し、社員一人ひとりが自分に合った働き方を選択しやすい環境が整備されました。
導入後には「席探しのストレスが減った」「チームでの連携が取りやすくなった」といった声が多く聞かれ、職場全体の心理的安全性と働きやすさの向上につながっています。
参考:ダイビル株式会社| 導入事例 | Beacapp Here(屋内位置情報サービス) | 所在地見える化でオフィス内の在席管理 | オフィス DX

まとめ
従業員エンゲージメントを高めるためには、「働きがい」「つながり」「環境」のすべてをバランスよく整えることが求められます。
その第一歩として、職場を“見える化”し、現場で起きている課題にデータで気づくことが極めて重要です。Beacapp Hereは、そんな気づきと改善の橋渡しとなるツール。
“働きやすい職場”づくりを、今こそ次のステージへ進めてみませんか?
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg