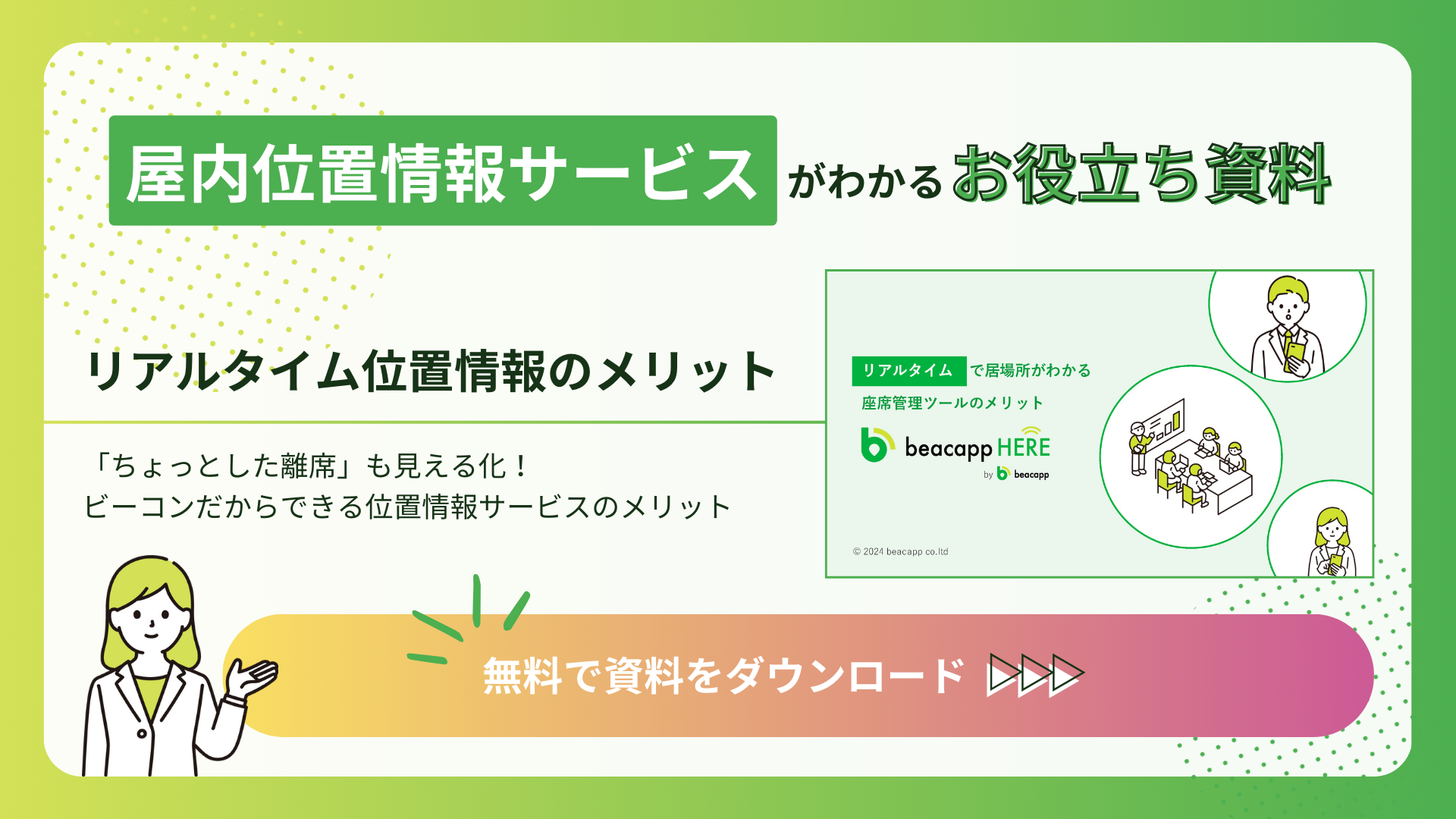働き方改革やDX推進、パンデミック後の新しいワークスタイルの定着により、多くの企業が「サテライトオフィス」や「フリーアドレス」を導入し始めています。これらはどちらも柔軟な働き方を可能にするための施策ですが、その目的や使われ方は異なります。
この記事では、サテライトオフィスとフリーアドレスのそれぞれの特徴を解説し、両者の違いを明確にしたうえで、導入の検討ポイントや現代のオフィス環境に適したソリューションをご紹介します。
サテライトオフィスとフリーアドレスの違い

サテライトオフィスとフリーアドレスは、どちらも働き方の柔軟性を高める施策ですが、その狙いや実現方法には違いがあります。本章では、両者の目的や空間設計の違いを整理し、それぞれの特徴を理解することで、自社に合った働き方の選択や併用の可能性を考えるヒントを提供します。
目的の違い
サテライトオフィスは「働く場所を分散する」ことが主な目的です。一方で、フリーアドレスは「働き方・スペースの柔軟化」を図る制度です。
つまり、サテライトオフィスは“どこで働くか”を分散する施策、フリーアドレスは“どう働くか”に焦点を当てた制度と言えるでしょう。
空間設計の違い
サテライトオフィスは、通常の執務エリアを小規模化・分散化したもので、独立した場所として設計されます。
フリーアドレスは、一つのオフィス内でのレイアウト変更により実現されるスタイルで、空間の“使い方”に変化を与えます。
このため、サテライトオフィスではアクセス性や設備共有が重要となり、フリーアドレスではゾーニングとユーザー動線の最適化が求められます。
併用・融合も可能
実は、両者は対立関係ではなく、併用活用も可能です。たとえば、「郊外のサテライトオフィスをフリーアドレスで運用する」といった使い方です。
このように組み合わせることで、「通勤の柔軟性」と「働き方の自由度」を同時に実現し、社員満足度と生産性の向上が期待できます。
サテライトオフィスとは?

テレワークの広がりとともに耳にする機会が増えた「サテライトオフィス」。
そもそもどのような場所なのかという基本的な意味や生まれた背景、都市型・郊外型・地方創生型などの種類と使われ方、そして導入によって得られる働きやすさや通勤負担の軽減といったメリットから、運営コストや管理の難しさといった課題まで、具体的に紹介します。
サテライトオフィスの定義と成り立ち
「サテライトオフィス」とは、本社とは別に設置された業務拠点のことを指します。その名の通り「衛星(satellite)」のように本拠地から離れた場所に存在しながら、組織の一部として機能することが特徴です。
この概念は、1980年代のアメリカで始まりました。当時は主に通勤時間の削減や、郊外居住者への対応を目的に整備されましたが、現在では多様な働き方やBCP(事業継続計画)対策としても注目を集めています。
種類と設置目的
サテライトオフィスには、主に以下の3つのタイプがあります。
- 都市型サテライトオフィス:
主に営業職や外回りの多い社員向けに、都心部の主要エリアに設置されます。
本社まで戻らずに業務が完結できるため、移動時間の短縮や業務効率の向上につながります。 - 郊外型サテライトオフィス:
社員の自宅近くに設けることで、通勤時間の短縮や満員電車のストレス軽減を図ります。
仕事と家庭のバランスが取りやすくなり、育児や介護との両立支援にもつながります。 - 地方創生型サテライトオフィス:
地方に拠点を構えることで、都心に集中しがちな働き手を分散させ、地域への人材流入を促します。
地元企業との連携や地域資源の活用によって、地域活性化にも貢献する取り組みです。
企業は、こうした目的や社員の働き方に応じて、自社専用のオフィスを構える場合もあれば、シェアオフィスやコワーキングスペースを活用して柔軟に運用することもあります。
導入によるメリットと課題
サテライトオフィスの導入は、通勤時間を削減し、働く場所の選択肢を広げることで社員の生産性やワークライフバランスを大きく改善します。さらに、災害時のリスク分散(BCP対策)や地方人材の採用促進といった効果も期待でき、多くの企業が注目しています。
しかし、その一方で、拠点ごとの管理負担や運営コストの増加、セキュリティ対策の難しさ、社員間のコミュニケーション不足による組織の分断など、見逃せない課題も浮かび上がります。
こうしたメリットと課題の両面を理解し、自社にとって最適な導入方法を見極めることが、サテライトオフィスを成功させる鍵となります。

フリーアドレスとは?

フリーアドレスとは、社員が固定の席を持たず、その日の業務や気分に合わせて自由に座席を選べる働き方です。近年、テレワークの普及や出社人数の変動に対応するための施策として注目を集めており、限られたオフィススペースの有効活用や社員同士の交流促進にもつながります。
一方で、座席が固定されないことで「居場所がない」と感じる社員が出たり、チーム連携が希薄になるといった課題もあります。これらを解決し、制度を定着させるには適切なフリーアドレスの仕組みや運用設計が欠かせません。
ここでは、フリーアドレスの成り立ちや背景を踏まえたうえで、成功に必要な具体的な仕組みについて解説します。
フリーアドレスの意味と背景
フリーアドレスは1990年代に日本の大手メーカーで試験導入が始まりました。当初はオフィスの効率化が主な目的でしたが、現在では柔軟な働き方を実現する手段として広く普及しています。
テレワークの浸透により出社人数が日ごとに変動するようになった今、オフィススペースの最適化や多様な働き方の推進という観点でも改めて注目されています。
実現に必要な仕組み
フリーアドレス制度を効果的に運用するためには、単に席を自由にするだけでは不十分です。まず、座席予約・管理システムを導入することで、社員がスムーズに空席を確保できる環境を整えることが重要です。
また、ロッカーや収納スペースを十分に確保することで、個人の荷物や資料の置き場所を明確にし、混乱を防ぎます。
さらに、ICT環境の整備も欠かせません。ノートPCや無線LAN、クラウドストレージの活用により、どの席でも業務が滞りなく行えるようにします。加えて、ペーパーレス文化の徹底も、フリーアドレスを円滑に運用するための鍵となります。
こうした物理的・技術的な整備とともに、社員のマインドセットや制度の浸透も重要です。フリーアドレスの理念を理解し、自律的に働く文化を育むことで、制度の定着と効果的な活用が可能になります。
期待される効果と注意点
フリーアドレスの導入には、オフィス運用や組織文化においてさまざまなメリットが期待できます。まず、社員が出社日や業務内容に応じて席を選べるため、オフィスの空席を減らすことができ、結果としてオフィスコストの削減につながります。
また、部署を超えた偶発的な交流が生まれやすくなり、社員同士のコミュニケーションの活性化や情報共有の促進も期待できます。さらに、多様な働き方への柔軟な対応が可能となり、組織全体の適応力や生産性向上にも寄与します。
一方で、席が固定されていないことによる「居場所のなさ」や「チーム連携の低下」が問題になることもあります。そのため、エリアゾーニングやABW(Activity Based Working)などの併用が重要です。
製品紹介

企業がフリーアドレスやサテライトオフィスを効果的に運用するには、単に制度を導入するだけでは不十分です。社員の働き方やオフィス利用状況を正確に把握し、最適な運用設計を行うためのツールが欠かせません。
ここでは、オフィス運用の効率化と社員の働きやすさを両立させるサービスをご紹介します。
Beacapp Hereによる座席管理と可視化
フリーアドレスをスムーズに運用するには、座席のリアルタイム管理が不可欠です。Beacapp Hereは、位置情報技術を活用して社員の在席状況やエリア利用率を可視化し、適切な席数管理をサポートします。
社員が「どこで・いつ・どのように」働いているかを可視化することで、無駄のないスペース活用が可能になります。
サテライトオフィス活用の最適化支援
Beacapp Hereは、複数拠点における出社率やエリア別の利用傾向も分析できるため、サテライトオフィスの配置や規模調整の判断材料としても有効です。
「本当にこの場所が必要か?」「稼働率の低い拠点は統合できないか?」といった問いに、データで明確な答えを導き出します。
AI WORK ENGINEとの連携による施策提案
さらに、AI WORK ENGINEと連携することで、利用データに基づいた働き方改善施策の自動提案も可能になります。AIが出社率やコミュニケーション量を解析し、必要に応じてレイアウト変更や増床提案を行ってくれます。
これにより、「分析」だけでなく「施策立案」まで一気通貫で対応可能になります。

まとめ
「サテライトオフィス」と「フリーアドレス」は、一見似ているようで、その役割や目的は異なります。前者は“働く場所”を拡張する施策であり、後者は“働き方・働く空間”の運用方法を変える制度です。
どちらか一方を導入すればよいというわけではなく、企業の働き方改革の方針や社員のニーズに応じて、併用も視野に入れるべきです。そして、その導入と運用を支えるのが、Beacapp Hereのような可視化ツールや、AI WORK ENGINEのような施策提案システムです。これらの仕組みを活用することで、持続可能で柔軟なオフィス運用を実現し、企業競争力を高めていくことができます。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg