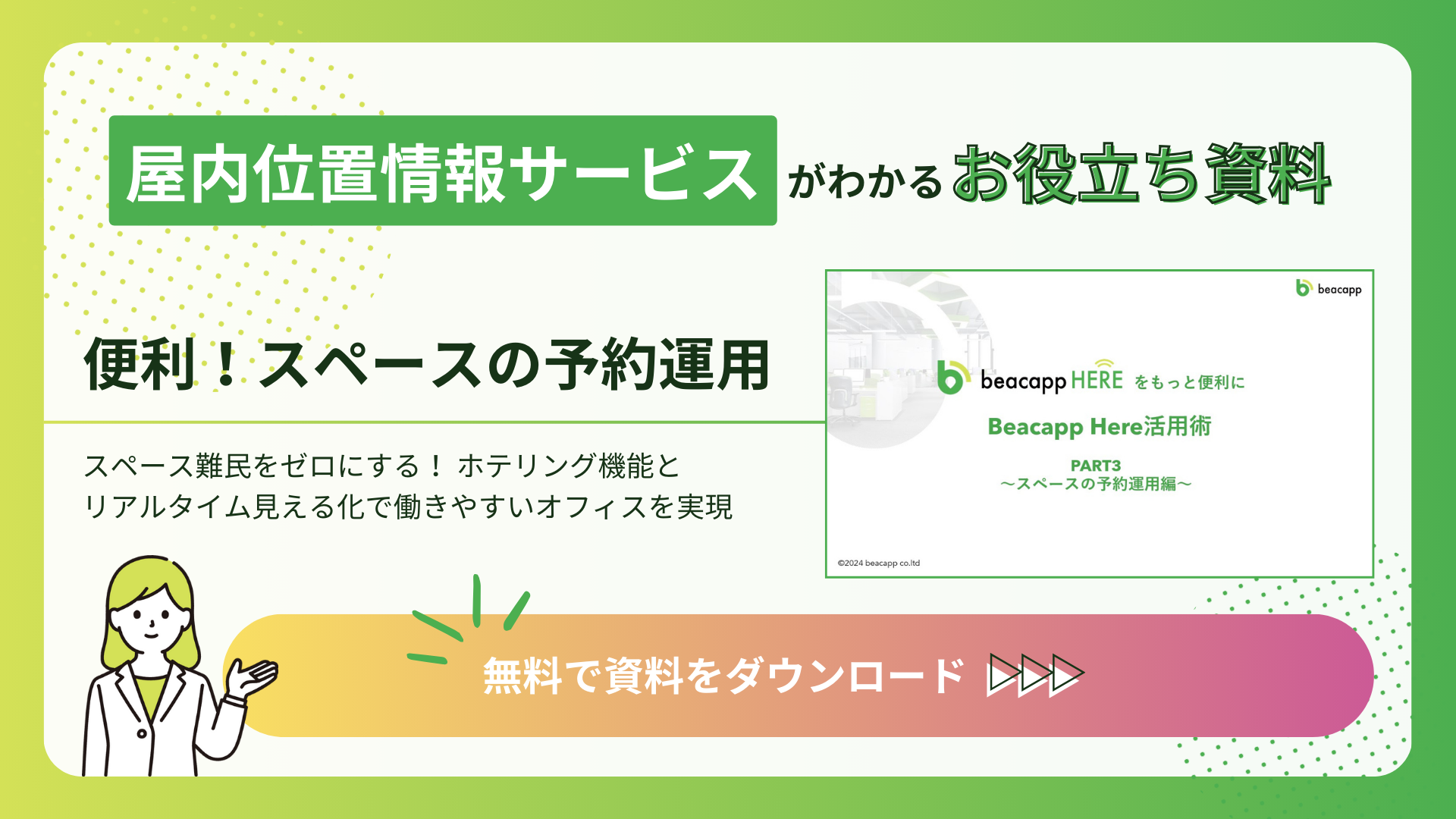フリーアドレスとは、オフィス内において個人に固定席を割り当てず、空いている席を自由に選んで働くスタイルです。働き方改革やスペースの有効活用を目的に導入する企業が増えていますが、出社回帰の流れが強まる中で「席が足りない」「空いている席が見つからない」といった新たな悩みが生まれています。
こうした状況はなぜ起きているのでしょうか?
本記事では、その背景を整理しながら、解決のヒントを探っていきます。
「フリーアドレスなのに席が足りない」背景とは?

フリーアドレスにおける座席確保の課題は、出社状況の変化や設計の見落とし、運用ルールの曖昧さなど、複数の要因が重なって起きています。
ここではまず、こうした「座席不足」の原因を4つに分けて整理してみます。
出社回帰で想定外の混雑が発生
コロナ禍を経てリモートワークが一気に浸透しましたが、近年では再び出社を推奨する企業が増えています。
その結果、「週に1~2回の出社」を前提に設計された座席数では対応しきれない事態が発生しました。特に火曜・水曜・木曜など、出社が集中しやすい曜日は、オフィスが想定以上に混雑し、座席の確保が困難になるケースも少なくありません。
稼働率と座席数のギャップ
フリーアドレスを導入する際、多くの企業が「稼働率〇%」という前提で座席数を決めています。
しかし、この想定稼働率が実態とズレていると、席が足りないという問題に直結します。部署や職種によって出社の傾向も異なるため、全体で見れば稼働率は低くても、特定エリアだけ混雑しているといった偏りも起こりがちです。
席の“占有”や“荷物置き”が席不足を引き起こす
「早く来た人が荷物を置いて仮押さえ」「一日中使うつもりで朝から確保」など、本来の“自由に選べる”という考え方が崩れているケースもあります。これにより、一部の席が事実上“固定席化”し、稼働していないにもかかわらず他の人が使えない状態となり、結果として「空いているはずなのに座れない」という矛盾が生まれてしまいます。
“誰がいつ来るか”が見えないことで運用が破綻する
フリーアドレスと同時に多くの企業で取り組まれているのが、ハイブリッドワークの導入です。ハイブリッドワークは、出社とリモートを組み合わせた働き方ですが、 この2つを同時に運用する中で「誰がいつ出社するかがわからない」という状況が問題となっています。
誰がいつ出社するかが見えない状態では、座席の事前調整や混雑の予測ができません。 計画性のない出社が積み重なることで、空間の有効活用が難しくなり、運用の形骸化を招いてしまうのです。
「席の取り合い」を避けるためにできること

ルールや仕組みを適切に整えることで、座席の混雑や取り合いを防ぐことは可能です。ここでは、実際の現場で取り組まれている対策や工夫を紹介します。
ホテリング(座席予約)で事前に使用を管理する
「座席予約システム(ホテリング)」を導入することで、座席不足を防ぐ動きが広がっています。
座席予約システムとは、その日に使いたい座席を出社前に予約することができるシステムです。 この仕組みによって、社員は出社時に座席を探すために時間を費やすことがなくなり、スムーズに業務につけるようになります。
また、利用状況のデータをもとに、空席の多いエリアや人気のある席を分析できるようになり、今後のレイアウト改善にもつなげやすくなります。
滞在状況や出社傾向の「見える化」で偏りを把握
どの曜日・時間帯に出社が集中しているのか、どの席が頻繁に利用されているのかといった傾向を「見える化」することで、混雑の偏りを把握しやすくなります。可視化の仕組みがあれば、無駄な席取りや早朝の席確保といった行動も抑制され、オフィス全体の運用がスムーズになります。
このようにリアルタイムの滞在状況を把握できるツールを活用することで、より快適で効率的な利用が実現しやすくなります。
出社ルールやガイドラインの明確化
フリーアドレスには、「いつ、どこに座ってもいい」という自由さがある一方で、最低限のルールがなければ混乱の原因になります。たとえば「予約席は15分以内に着席しないとキャンセル扱い」「荷物での席取りは禁止」など、ルールを明文化することでトラブルを未然に防ぐことができます。
先述した「ホテリング」ツールの中には、予約時間を一定時間過ぎても座席の利用が判定できない時には、自動で予約を解除できるツールもあります。空予約を防ぐことで、使いたい人に座席がきちんと届く環境を実現します。また、ガイドラインがあることで、社員同士の共通認識が生まれ、快適なオフィス運用が実現しやすくなります。
「居場所」ではなく「用途」で席を選ぶ意識づけ
「自分の居場所」としてではなく、「どんな作業をするか」に応じて席を選ぶという意識が根づくと、席の固定化や取り合いは起こりにくくなります。たとえば、集中したいときは静かなエリア、オンライン会議が多い日は遮音ブースなど、用途に合わせた選択を推奨することで、空間全体の使われ方も自然と分散されていきます。
混雑の防止には、ルールの整備とあわせて、こうした意識づけの浸透も欠かせません。

フリーアドレス運用でありがちな失敗と改善のヒント

フリーアドレスは柔軟な働き方を支える仕組みとして有効ですが、運用がうまくいかないことでかえって不満や混乱を招いてしまうケースもあります。
ここでは、現場でよく見られる失敗例と、それに対する改善のヒントを紹介します。
「いつもの席」が生まれる理由とABWによる意識改革
本来は自由に席を選べるはずのフリーアドレスでも、気づけば「なんとなくいつも同じ席に座る」という状況が起きがちです。これは、社員が安心して業務に集中できる場所を求める心理によるものですが、同時に座席の固定化につながりやすい側面もあります。
このような形骸化を防ぐためには、「どんな作業をするかによって場所を選ぶ」というABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)の考え方を取り入れることが効果的です。業務内容に応じて最適な席を選ぶという意識を社内に浸透させることで、席の使い方が自然と分散され、混雑の偏りも軽減されていきます。
座席数の見積もりミスを行動ログで見直す
フリーアドレスを導入する際、「出社率30%なら席数も30%でよい」といった単純な計算で座席数を見積もってしまうケースがあります。しかし、実際には出社日が特定の曜日に偏ったり、部署によって出社傾向が異なったりするため、机上の計算だけでは不十分です。
このようなギャップを解消するには、実際の出社・滞在データをもとにした行動ログの分析が欠かせません。実態に合ったデータを使ってレイアウトや席数を再設計することで、オフィスの使いやすさを大きく向上させることができます。
スペース不足はレイアウト変更でカバーできる
「席が足りない」と感じたとき、すぐに席数を増やそうと考えるのではなく、まずは現在のスペースの使われ方を見直してみることが大切です。たとえば、会議室がほとんど使われていない、通路が広すぎるといった無駄が見つかる場合もあります。
オープンスペースを可動式のパーテーションで区切って席を増やす、使われていないコーナーに集中席を設けるなど、レイアウトの工夫次第で空間の有効活用は可能です。このように限られた面積の中でも、柔軟な配置によって多様な働き方に対応できる環境をつくることはできるのです。
混雑緩和にはICTツールの併用が効果的
座席の予約状況や現在の混雑状況をリアルタイムで把握できるICTツールを導入することで、混雑の緩和や席不足の予防につなげることができます。特に、誰がどの席に座っているか、どの時間帯にどこが混雑するかといった情報が「見える化」されることで、社員の行動にも変化が生まれやすくなります。
混雑しているエリアを避けて別のエリアに移動する、自分の出社タイミングを調整するといった判断がしやすくなり、オフィス全体のバランスが整っていきます。このように、ルールや意識の改革とあわせてツールを活用することが、フリーアドレス運用の成功を支える大きな要素になります。
フリーアドレスを成功させる“設計”と“仕組み”

フリーアドレスは、働きやすさと効率を両立させる“仕組み”として設計することが重要です。
ここでは、実際の運用において成果を上げやすい設計視点と、仕組み化の工夫について整理していきます。
最適な座席数とは?「平均出社率」だけでは不十分
座席数を決める際に「社員の出社率が30%だから、席も30%でよい」と単純に計算してしまうと、運用に歪みが生まれることがあります。なぜなら、出社のタイミングは人によって偏りがあり、平均だけを見てもピーク時の混雑は読みきれないからです。
最適な座席数を算出するには、「最大混雑時の同時出社率」や「部署ごとの出社傾向」など、複数の視点を取り入れた判断が求められます。オフィス全体の利用状況を定期的に見直し、柔軟に調整できる設計こそが、ストレスの少ない運用につながります。
空間のゾーニングで多様な働き方に対応
社員が一人ひとり異なる業務をこなすなかで、すべての席を一律に扱うのではなく、「目的別」にエリアを分けることが効果的です。たとえば、「集中作業エリア」「打ち合わせスペース」「オンライン会議ブース」など用途に応じたゾーニングを行うことで、社員は目的に合った場所を選びやすくなります。
このような空間設計は、フリーアドレスを運用する上での混雑解消にもつながり、オフィスの快適性を高める要素になります。
使われ方を可視化するデータ収集と分析
席が“実際にどう使われているか”を把握するには、感覚だけでなくデータに基づいた分析が欠かせません。センサーやビーコン、出社ログなどを活用すれば、どの席がよく使われているか、逆に使われていない場所はどこか、といった傾向を可視化できます。
こうした定量的な情報があれば、レイアウトの改善や座席数の最適化に具体的な根拠を持たせることができます。設計や運用の見直しを継続的に行う上で、データに基づく判断は非常に有効です。
“使える席”を増やす工夫とは?
席数そのものを増やすのが難しい場合でも、「実質的に使える席」を増やす工夫は可能です。たとえば、長時間利用されにくい場所に短時間利用を促すサインを設置したり、荷物置きによる“仮押さえ”を防ぐための巡回ルールを設けたりといった、小さな仕組みが効果を発揮します。また、利用状況を社員が自分で確認できるようにすることで、「空いているのに誰も座らない席」の活用も促進できます。
スペースの制約があるからこそ、運用面での工夫がフリーアドレスの成否を分けるポイントとなります。

まとめ
フリーアドレスの本来の目的は、空間を有効に使いながら、社員の多様な働き方を支えることにあります。 だからこそ、誰もが安心して働ける座席環境をつくることが欠かせません。
「座れるか不安」という状況が続くと、制度そのものが形骸化してしまいます。 仕組みやルールを整備し、“席のある安心感”をつくることが、これからのオフィス運用の鍵となります。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg