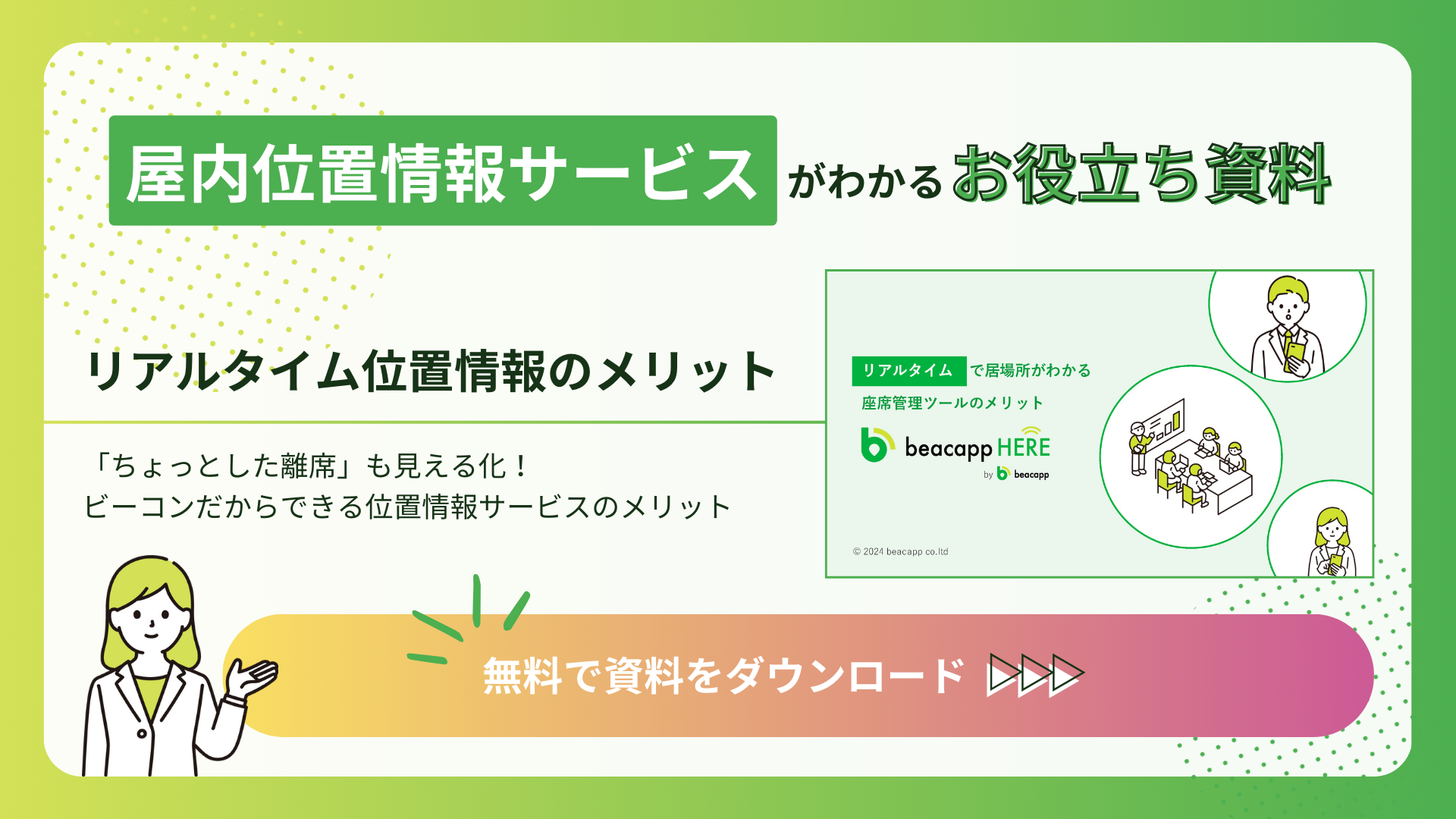働き方改革やリモートワークの普及により、フレックスタイム制を導入する企業が増加しています。その中でも「コアタイム」は、組織の連携や業務の効率化を保つために重要な役割を担っています。
本記事では、一般的なコアタイムの設定時間や実例、フレックスタイム制との違い、コアタイムを設定する際のポイントなどを詳しく解説します。
コアタイムの時間帯
コアタイムとは、フレックスタイム制度の中で「社員が必ず勤務していなければならない時間帯」のことです。出社や退社の自由度が高まる中でも、組織全体として共通の勤務時間を確保することが求められます。

コアタイムの目的とは?
コアタイムの主な目的は、社員全員が同じ時間帯に勤務することで、会議やチームミーティング、コミュニケーションをスムーズに行えるようにすることです。すべての時間がフレキシブルだと、誰がいつ働いているかがわからず、情報共有や意思決定に支障が出る恐れがあります。特にチームで連携して動く業務では、一定の重なり時間があることが重要です。
適切な時間帯の考え方
コアタイムを決める際には、社員の生活スタイルや通勤時間、業務内容に合わせて柔軟に設定する必要があります。例えば、都心部で通勤時間が長い社員が多い場合は、午前10時以降からのスタートが理想的です。逆に、早朝から業務を開始する文化がある職場では、午前9時から始まるコアタイムも効果的でしょう。
関連記事: コアタイムとは?意味や目的、フレックスタイムとの違いを解説!
コアタイムの時間帯例
実際に企業が導入しているコアタイムの時間帯は、業種や企業文化によって異なります。ここでは、よくある3つのパターンを紹介し、それぞれの特徴について解説します。
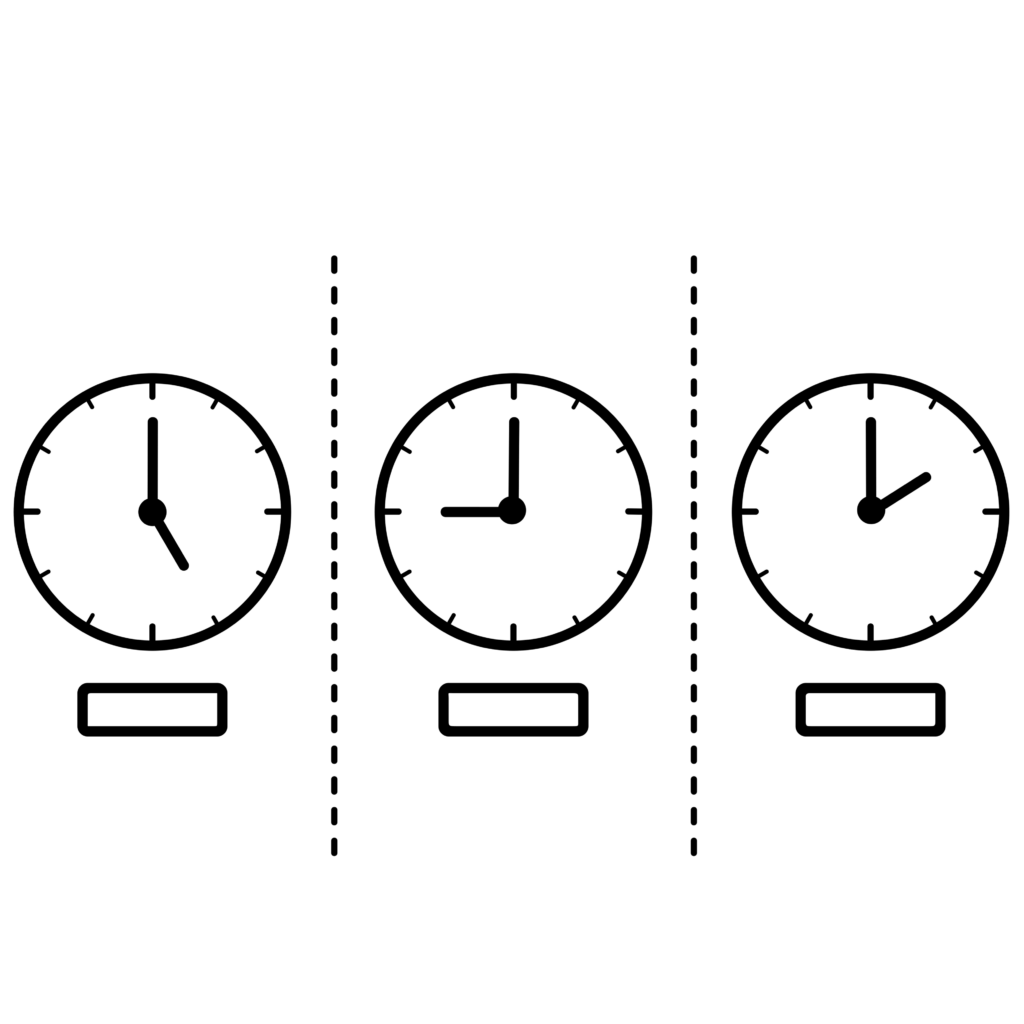
10:00〜15:00:最も一般的なパターン
多くの企業で採用されているのが「10:00〜15:00」のコアタイムです。この時間帯は、午前中と午後の両方に業務の山場を配置でき、かつ社員が余裕をもって出勤・退勤できる柔軟性があります。また、通勤ラッシュを避けることもできるため、社員のストレス軽減にもつながります。
このモデルは、オフィス勤務だけでなくリモートワークにも相性がよく、朝に集中作業、午後に会議という流れも組みやすいため、さまざまな業種で採用されています。
11:00〜16:00:朝の自由度を高めるパターン
「11:00〜16:00」という少し遅めのコアタイムを導入している企業もあります。朝に弱い社員や育児・介護中の社員への配慮として、始業時間を後ろ倒しにすることで、より多様なライフスタイルに対応できます。
このモデルは、チームのコミュニケーション時間を確保しながらも、午前中にプライベートの予定を入れたい社員にとって理想的です。朝の混雑を避けることができ、結果として遅刻の減少にもつながる可能性があります。
9:00〜14:00:午前中心型のパターン
「9:00〜14:00」のコアタイムは、早めの時間帯に集中して仕事を終わらせたい企業や社員に好まれるパターンです。特にエンジニアやクリエイティブ職のように、午前中に高い集中力を必要とする業務では効果的です。
午後の時間帯を自由に活用できるため、自己管理能力が高い社員にとっては非常に働きやすい環境となります。一方で、夕方に会議が発生しやすい職場とは相性が悪いこともあるため、業務特性に応じた運用が求められます。

フレックスタイムとコアタイムの違い
コアタイムとフレックスタイムの違いを理解することで、自社の労働時間制度をより効率的に設計できるようになります。

コアタイムとは?
コアタイムは、前述のとおり、フレックスタイム制の中でも「全員が共通して働く必要のある時間帯」です。この時間帯に会議や連絡業務を集中させることで、コミュニケーション不足や業務の遅延を防ぎます。
コアタイムを設けることで、フレックス制度の自由さと、一定の組織力を両立できるのが大きな利点です。
どちらが良い?導入目的で変わる
完全フレックスタイム制と、コアタイム付きフレックス制のどちらが良いかは、導入の目的によります。生産性向上や社員のワークライフバランス重視であれば、自由度の高い制度が向いています。一方、協調性や組織運営を重視する業務には、コアタイムを設けた制度のほうが効果的です。
コアタイムの時間帯の決め方
自社に最適なコアタイムを設定するには、業務の実態や社員のニーズを踏まえた柔軟な判断が必要です。

業務の特性を考慮する
まず最初に考慮すべきなのは、会社やチームの業務内容です。たとえば、クライアントとの連絡や取引が多い営業職であれば、取引先の営業時間に合わせたコアタイムが望ましいでしょう。逆に、成果物の納品が中心となるエンジニア職やデザイナー職は、集中できる時間帯を重視すべきです。
チームの働き方に合わせる
コアタイムを設定する際は、チーム全体の働き方にも目を向けましょう。部署ごとに必要な会議時間やコミュニケーションの頻度が異なるため、部署単位でのコアタイム調整も有効です。たとえば、開発チームは「午前中中心」、マーケティングチームは「午後中心」といった柔軟な設計が可能です。
社員の声を反映する
制度の押しつけにならないよう、社員へのアンケートやヒアリングを行うことも大切です。実際に働く人たちの意見を取り入れることで、納得感が生まれ、制度の定着にもつながります。また、制度導入後にも定期的にフィードバックを受け、必要に応じて時間帯の見直しを行う柔軟さが求められます。
コアタイムの時間帯を決める時の注意点
コアタイムを決める際には、いくつかの注意点があります。制度を有効に活用するために、以下のポイントを押さえましょう。

コアタイムの設定は自由に設定できる
コアタイムは法律で明確に時間帯が定められているわけではなく、企業の判断で柔軟に設定可能です。そのため、業務内容や社員の働き方に合わせて最適な時間帯を設計することができます。ただし、過度に自由度を高めすぎると組織としての一体感が薄れるリスクもあるため、バランスが重要です。
一般的にどのように設定されているのか
一般的には「10:00〜15:00」や「11:00〜16:00」など、5時間程度の時間帯がコアタイムとして採用されることが多いです。これにより、午前と午後にかけて効率よく業務を行える環境が整います。企業によっては、コアタイムを曜日単位や部署単位で分けているケースもあり、多様化が進んでいます。

まとめ
コアタイムは、フレックスタイム制度を円滑に運用するための重要な要素です。一般的には10:00〜15:00のような時間帯が多く採用されていますが、実際には業務の特性や社員のライフスタイルに合わせて柔軟に設定することが可能です。
制度を形骸化させないためにも、社員の声を取り入れながら、定期的な見直しと改善を行っていくことが理想です。自社に合ったコアタイムを導入し、生産性と働きやすさの両立を目指しましょう。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg