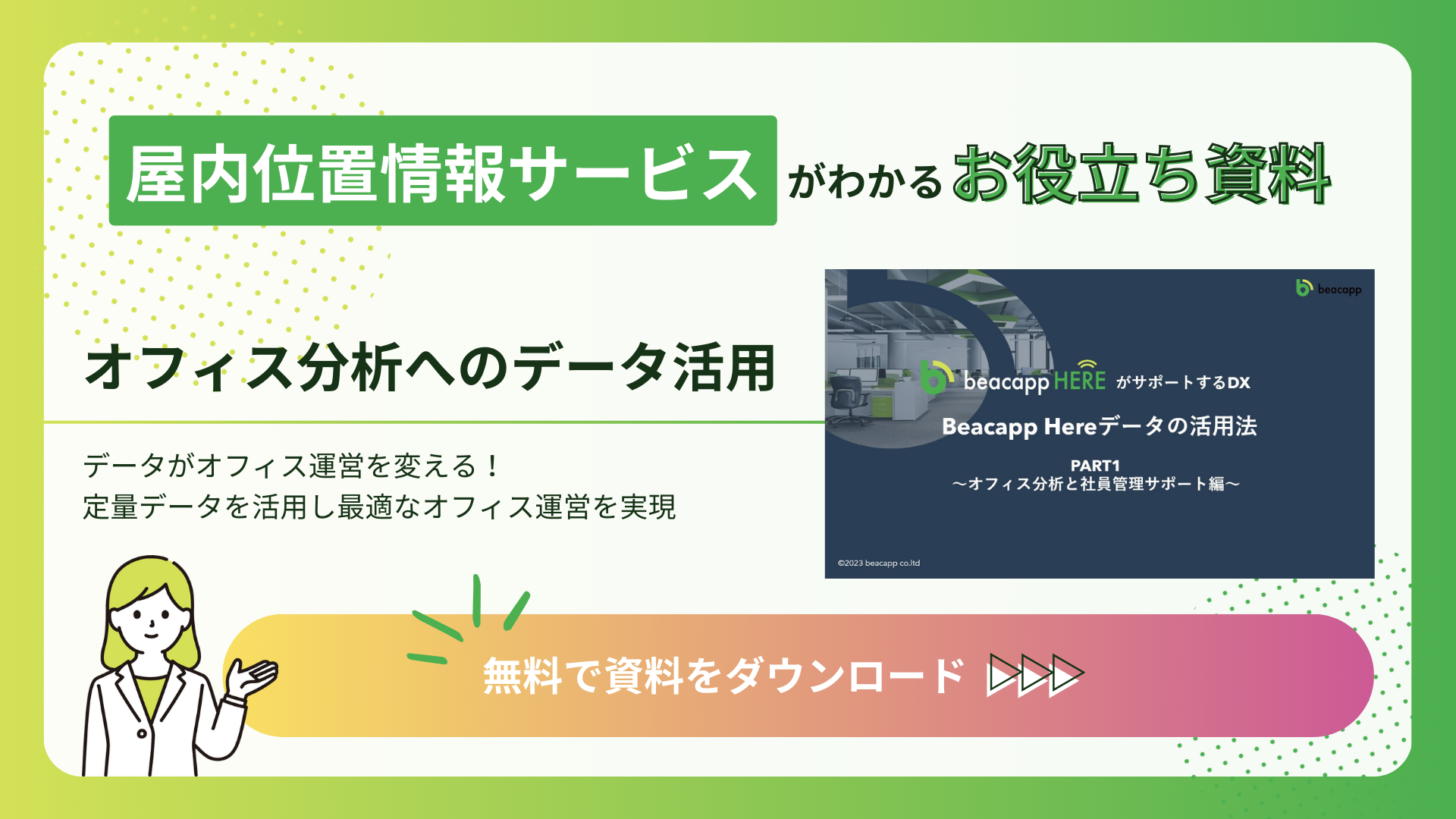「忙しすぎて休憩が取れない」「休憩室があっても落ち着かない」
医療の現場では、そんな声が珍しくありません。命を預かる責任の大きい仕事だからこそ、看護師や医師がしっかりとリフレッシュできる環境は必要不可欠です。
中でも休憩室は、職員の心身の回復を支える大切な空間です。今回は、病院における理想的な休憩室のあり方や、改善のポイントについて考えていきます。
病院の休憩室に求められる役割とは?

病院の休憩室は、単に「座って休む場所」ではなく、医療従事者が短時間でも心と体を切り替えるための貴重なスペースです。
現場の緊張感を一時的に手放せるような「安心して休める環境」こそが求められています。
患者と医療者の“空間の線引き”が心身の回復に
病院の中では、看護師や医師が常に患者やご家族と接する時間が続きます。その中で「自分だけの空間」「患者の目が届かない場所」があるかどうかは、心身の回復に大きく影響します。
休憩室が診療エリアの延長線上にあると、完全に気を抜くことができず、結果的に疲労が蓄積しやすくなります。たとえ短い時間でも、患者と接しない「オンとオフの境界」を明確に持てる空間があることで、リラックス度が変わります。
こうした空間の線引きは、働く側だけでなく、患者にとっても良い影響があります。医療者が適切に休憩を取り、笑顔でケアに戻ってくることで、現場全体の雰囲気が柔らかくなるからです。まさに、職員と患者の“間”をデザインすることが、休憩室の重要な役割といえるでしょう。
リフレッシュだけでなく「インシデントを防ぐ」意味も
病院におけるヒューマンエラーや医療事故の多くは、疲労やストレスによる判断力の低下が要因とされています。そのため、しっかりと休憩が取れているかどうかは、単なる労務管理の問題ではなく、安全性の担保にも関わってきます。
例えば、患者の薬剤を取り違える、転倒リスクを見落とすといった“インシデント”を防ぐには、高い集中力と冷静な思考が求められます。これを支えるのが、こまめな休憩と回復の時間です。
また、看護師や医師が「疲れすぎて判断できない」という状態を防ぐためにも、休憩室は重要な役割を果たします。つまり、休憩は自己管理の手段であると同時に、患者の命を守る一つの手段でもあるのです。
「仮眠できない」「物置化」…よくある休憩室の課題
休憩室が設けられていても、「物置のようになっていて落ち着かない」「仮眠用のスペースがない」「他人の出入りが多くて気が抜けない」など、実際には“休まらない場所”になってしまっているケースも少なくありません。
特に夜勤帯では、15分〜30分の仮眠がパフォーマンス維持に効果的とされていますが、横になれるスペースがなかったり、照明が明るすぎたりと、十分な休息を取れない環境が残っている病院もあります。
また、限られたスペースゆえにロッカーや備品置き場と兼用になっている休憩室も多く、雑多な雰囲気により逆に疲れてしまうといった声も聞かれます。
病院特有のストレス下でこそ“休める場所”が必要
医療現場では、命に関わるプレッシャーやシビアな判断が日常的に求められます。加えて、夜勤や急患対応などによる不規則な勤務、感情労働とも呼ばれる対人ケアの重圧など、他の業種にはないストレス要因が多く存在します。
こうした環境下で、きちんと“気持ちを落ち着ける場所”がないと、心身の疲弊が蓄積し、バーンアウト(燃え尽き症候群)やメンタル不調につながることもあります。
つまり、休憩室は「ただの設備」ではなく、ストレスマネジメントやメンタルヘルスケアの一環として考えるべき存在です。誰もが気兼ねなく、しっかりと休める空間の整備が、職員の健康と医療の質を守る鍵となります。
休憩室が職員に与える影響とは?

どれだけ医療スキルや経験があっても、疲労が蓄積した状態では本来のパフォーマンスを発揮できません。休憩室のあり方ひとつで、スタッフの集中力や満足度、さらには定着率にまで影響を与えることがあります。
休憩の質が、集中力や判断力に直結する
医療現場では、一つひとつの判断が患者の状態に大きく影響します。その判断力や注意力を支えるのが、日々のコンディションと、適切な休憩です。
休憩室が落ち着かない場所であったり、頻繁に人の出入りがある空間だったりすると、短時間の休憩では回復しきれず、慢性的な疲労感が残ります。逆に「静かで安心できる休憩室」があると、わずかな時間でも質の高い休息が取れ、仕事への集中力が格段に高まります。
医療事故の予防や、チーム内のスムーズな連携を保つうえでも、休憩室の環境は軽視できない要素です。
「ちゃんと休める職場」こそ離職防止につながる
多忙な業務に追われ、心身がすり減るような職場では、離職率が高くなりがちです。特に医療職のように人手不足が深刻化している業界では、定着率の向上が病院運営に直結します。「きちんと休める環境がある」「無理をしすぎない風土がある」という安心感は、職場への信頼感につながります。
これは単なる制度ではなく、実際の環境や設備がどうなっているか、現場での“休みやすさ”が重要です。実際、離職者の声として「休憩時間が確保されていなかった」「リフレッシュできる場所がなかった」といった理由が挙げられるケースもあります。休憩室は、働き続けたいと思える職場づくりに欠かせない存在なのです。
リラックスできる空間設計のポイント
「休憩」といっても、その時間の質は環境によって大きく左右されます。
たとえば、白色蛍光灯が眩しい空間では目が休まらず、座る場所が硬いと体に負担が残ってしまいます。落ち着いた間接照明やリクライニングチェア、静かなBGM、個別のスペースなど、ちょっとした工夫があるだけで、休憩の質は格段に向上します。
また、スタッフ同士が自然と会話できるようなソファ配置や、逆にひとりで静かに過ごせる“ひと区画”をつくることで、ニーズに応じた柔軟な使い方が可能になります。リラックスしやすい空間づくりは、結果的にストレス軽減とパフォーマンス向上を支える基盤になります。
設備・家具選びで差がつく休憩室の満足度
同じスペースでも、使っている設備や家具によって居心地は大きく変わります。硬いベンチしかない部屋と、リクライニング機能付きの椅子や簡易ベッドがある部屋では、休憩後の回復感がまったく違うはずです。
最近では、昼夜問わず活用される休憩室に合わせて、遮光カーテンや音漏れ防止の間仕切りなどを導入する病院も増えています。また、冷蔵庫や電子レンジ、給湯器といった家電の充実も、スタッフの満足度を高めるポイントになります。日々忙しく働くスタッフの声に耳を傾けながら、「ただ置く」だけでなく「快適に使える」設備を整えることが、現場の信頼と働きやすさにつながっていきます。
監視カメラは必要?病院休憩室のプライバシー問題

セキュリティやトラブル防止の観点から、休憩室への監視カメラの設置を検討する病院も増えています。しかし一方で、「見られている」という感覚が職員のストレスを高めるケースもあり、プライバシーとのバランスが課題となっています。
「見守り」と「監視」の境界線
監視カメラの設置は、不審者の侵入防止や備品の盗難防止といった目的で導入されることが多くあります。しかし休憩室という“私的な空間”においては、職員にとって「安心感」を与えるどころか、逆に緊張感を生む可能性もあります。
重要なのは、カメラの目的が“見守り”なのか“監視”なのかという明確な線引きです。管理者の意図が不透明なままだと、職員は「評価の材料に使われているのでは」と不信感を抱くこともあるでしょう。カメラを設置する場合は、その目的や使用範囲をきちんと周知し、必要最小限の範囲に限定することが求められます。
カメラがあることで休めなくなる人も
休憩室は、職員が業務から離れて心身をリセットするための空間です。しかし、天井や壁のカメラの存在に気づいた瞬間、「誰かに見られている」と感じて落ち着けなくなる人も少なくありません。特に仮眠をとる際や着替えの場面など、プライベート性の高い行動をともなう場合、監視カメラの存在は心理的な負担になります。
また、リラックスできない環境では、休憩の質が下がり、逆に疲労が蓄積してしまうことも。本来の休憩室の目的を考えれば、プライバシーを侵害しない空間設計は不可欠です。
不審者・患者の侵入対策としてのカメラ活用
一方で、休憩室がセキュリティ面で“無防備”になりやすいという課題もあります。近年では、患者やそのご家族が誤って休憩室に入り込んでしまったり、備品の持ち出しが発生したりするケースも報告されています。
そうした背景から、監視カメラを「入口付近」や「共有部分」のみ設置する病院も増えています。不審な人物の動きやトラブルの記録を目的とし、プライベート空間には極力干渉しない設計が理想的です。また、防犯対策としての意義を職員にも共有することで、カメラの存在に対する不信感を和らげる工夫も必要です。
プライバシー確保と安全性の両立をどう図る?
プライバシーと安全性、その両立は簡単ではありませんが、不可能ではありません。たとえば、カメラを「入口のみ」に設置し、室内は死角にする、映像は録画のみでリアルタイム監視しないといったルール設定が効果的です。
また、休憩室とは別に「スタッフ専用の更衣室や仮眠室」を用意し、そこには監視機器を設置しないことで、より安心して休める環境が整います。最近では、顔認証や入退室ログ管理など、カメラに頼らないセキュリティ手法も普及しています。技術や設計の工夫により、安心できる休憩空間をつくることは十分に可能なのです。
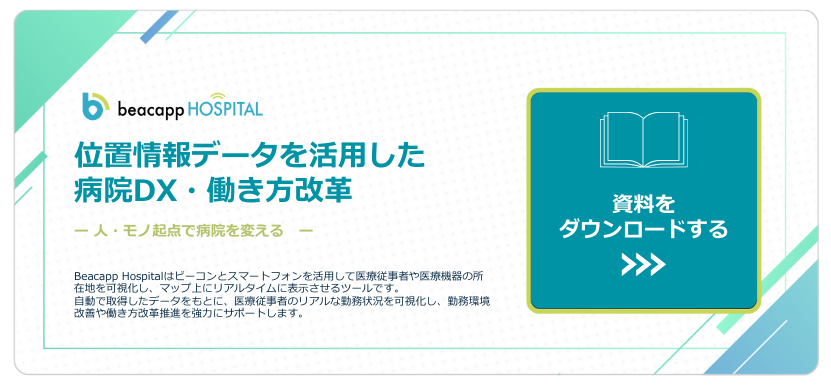
休憩室改善のポイントと取り組み事例
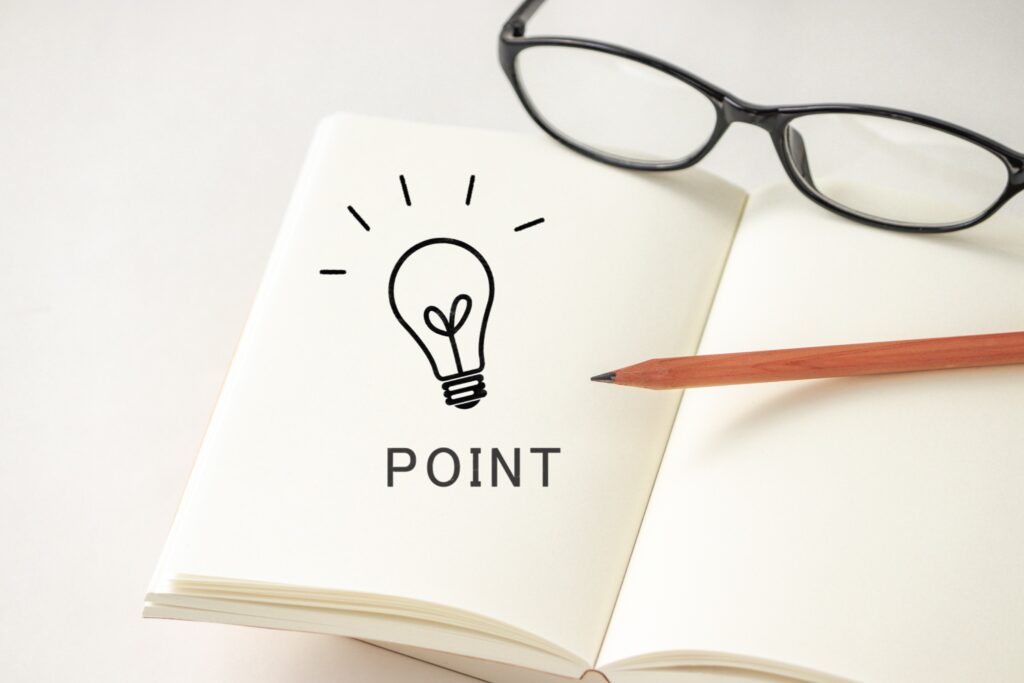
休憩室をより“休める”空間にするためには、設備の見直しや運用の工夫が欠かせません。限られたスペースや人員のなかでも実現可能な改善事例も多く、他院の取り組みがヒントになることもあります。
個室仮眠スペースや静音ゾーンの設置
仮眠を取ることで集中力や判断力が回復することは、複数の研究でも明らかになっています。しかし実際には「横になれる場所がない」「音や光が気になって眠れない」といった悩みを抱える医療者が多くいます。
こうした課題に対し、最近ではパーティションやカーテンで仕切られた個室仮眠スペースを設ける病院が増えています。さらに、照明を暖色に調整したり、防音マットを取り入れたりすることで、静かで落ち着ける“静音ゾーン”としての機能も高められています。
「ほんの15分でもしっかり休めた」という実感が、次の業務への活力につながります。
当直医・夜勤看護師のための設備強化
夜勤や当直業務は、心身への負担が大きく、疲労の蓄積も深刻です。そのため、特に深夜帯に働くスタッフ向けの休憩室は、一般のものより高いレベルの快適性が求められます。
たとえば、仮眠用ベッドの設置や、温かい飲み物が用意できるミニキッチン、照明の明暗調整などが挙げられます。他にも、電子レンジや給湯ポット、マッサージチェアなどを導入する事例もあります。
「夜勤明けでも回復しやすい」「しっかり身体を休められる」環境は、勤務の継続意欲や職員の満足度にも大きく寄与します。
利用状況の“見える化”で効率的な運用を
せっかく整備した休憩室も、「いつも混んでいて使えない」「空いている時間がわからない」といった理由で活用されないことがあります。そこで有効なのが、スペースの利用状況を“見える化”する仕組みです。
たとえば、混雑時間帯や空き状況をデジタルサイネージやスマホで確認できるようにすると、「今なら使える」という判断がしやすくなります。時間帯ごとの利用者数を記録することで、レイアウトの改善や導線見直しにも役立ちます。
限られた空間を効率よく、かつ公平に使うためにも、“見える化”は非常に有効なアプローチです。
ICTを活用した設備予約や混雑把握
近年では、ICT(情報通信技術)を活用して休憩室の管理や予約を行う事例も増えています。とくに有効なのが、スマートフォンやPCから休憩スペースの予約ができる「ホテリング」機能や、リアルタイムの空き情報を可視化する仕組みです。
たとえば、Beacapp Hereのようなソリューションを導入することで、「どのエリアが空いているか」「どの時間帯に混雑しやすいか」を誰でも把握でき、休憩室の利用効率を高めることができます。また、利用データを蓄積・分析すれば、設備の増設や改善の意思決定にもつなげやすくなります。
ICTを活用した仕組みは、今後の休憩環境づくりにおいて欠かせない要素となるでしょう。
安全で“休める”休憩室をつくるには

どれほど快適な休憩室を整備しても、安全性に不安があれば本当の意味で“休める空間”にはなりません。医療機関ならではのリスクや課題を踏まえたうえで、安心して利用できる環境づくりが求められています。
アクセス制限や入退室管理によるセキュリティ強化
病院内は多くの人が出入りする空間であり、患者や外部業者が誤って休憩室に侵入してしまうリスクもあります。そのため、休憩室には職員専用のアクセス制限を設けることが基本です。
たとえば、IDカードや顔認証、暗証番号による入退室管理を行うことで、不審者の侵入や備品の盗難リスクを大幅に減らすことができます。出入りの履歴を記録するシステムを導入すれば、万が一トラブルが発生した際にも対応しやすくなります。
「誰でも入れる場所」ではなく、「守られた職員専用の空間」であることが、心から休める環境につながります。
居場所管理とプライバシー確保の両立
セキュリティ向上の一環として「居場所管理」を取り入れる病院も増えていますが、職員のプライバシーとのバランスが重要です。たとえば、職員の位置情報を常に監視するのではなく、「誰がどこにいるか」を必要に応じて確認できる仕組みが理想的です。
Beacapp Hereのようなツールでは、個人のプライバシーを守りながらも、緊急時や業務連絡時に居場所が把握できる柔軟な管理が可能です。また、「今この人は休憩中」と可視化されることで、休憩を邪魔されにくくなるというメリットもあります。
セキュリティとプライバシーの両立が、信頼される運用の鍵となります。
設備投資だけでなく「使い方」の設計も重要
どれだけ良い設備を導入しても、それが有効に使われなければ意味がありません。「休憩中に電話対応を求められる」「使い方のルールが曖昧で遠慮してしまう」といったことがあると、本来の目的が果たせません。
そこで必要なのが、“使い方”まで設計された休憩室の運用ルールです。たとえば「仮眠中は声かけをしない」「1人1回30分まで」「予約制で静かに使う」といったガイドラインを明確にすることで、職員同士のトラブルも避けられます。
環境整備とあわせて、“気持ちよく使える仕組み”が整っていることが、継続的な活用に結びつきます。
データを活用した継続的な改善のススメ
休憩室づくりは「整えたら終わり」ではなく、継続的な改善が求められる取り組みです。そのためには、利用状況や満足度を可視化し、必要に応じて改善していくプロセスが大切です。
たとえば、Beacapp Hereなどを活用して休憩スペースの利用ログを蓄積すれば、「いつ混むのか」「どの設備が使われているのか」が明らかになります。また、アンケートや意見箱などを通じて、現場の声を取り入れることも重要です。
“現場のための空間”として、常に最適化される仕組みを持つことが、安心して働ける職場づくりに直結します。
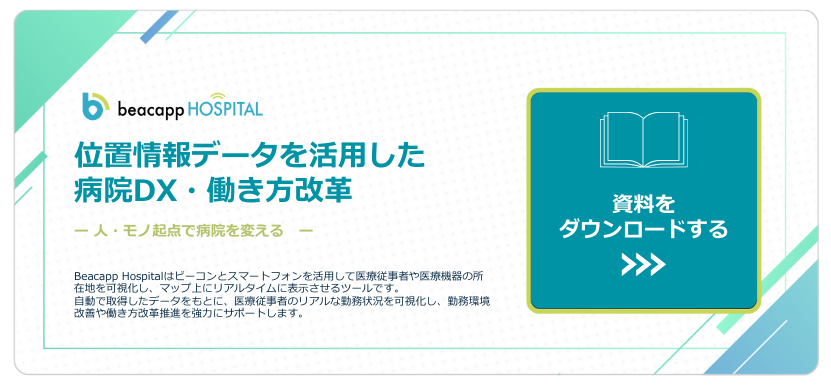
まとめ
病院の休憩室は、単なる“休む場所”ではなく、医療従事者の心身の健康を支え、ひいては患者への質の高いケアにつながる重要な空間です。快適性・安全性・プライバシーのバランスを取りながら、誰もが安心して使える環境を整えることが、離職防止やパフォーマンス向上にも貢献します。
技術やデータを活用しつつ、現場の声に寄り添った改善を重ねることが、これからの病院づくりに求められているのではないでしょうか。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg