オフィスや工場、医療現場など、働く場所が多様化・複雑化する中で注目されているのが「ゾーニング」という空間設計の考え方です。
ゾーニングは、目的に応じて空間を区分し、作業効率や安全性、快適性を向上させる手法として活用されています。
本記事では、ゾーニングの基本からオフィスでの応用、他業種での導入事例までを幅広く紹介します。
ゾーニングとは?

ゾーニングとは、空間を目的や機能ごとに明確に分けて設計する手法です。
もともとは都市計画に用いられてきた考え方ですが、近年ではオフィス、病院、工場、学校など、多様な現場での業務効率化や衛生管理、従業員満足度向上のために取り入れられています。
ゾーニングの目的とは?
ゾーニングの第一の目的は、業務内容や行動パターンに応じて空間を最適に使い分けることにあります。
例えばオフィスでは、集中作業が求められる人と会議や打ち合わせが多い人では、望ましい空間の条件が異なります。
ゾーニングにより、それぞれの業務に適した空間を割り当てることで、集中力の維持やコミュニケーションの活性化、ミスの削減など多くの効果が期待できます。
また、工場や食品業界では衛生区画の明確化が目的となるなど、目的は現場によって異なります。
ゾーニングの対象となる空間と分類
ゾーニングの対象となる空間は多岐にわたります。
オフィスにおいては「執務ゾーン」「集中ゾーン」「会議ゾーン」「リフレッシュゾーン」「来客ゾーン」などの分類が一般的です。
工場では「清潔ゾーン」「汚染ゾーン」「搬送ゾーン」など、衛生管理や安全性を重視した分け方が採用されます。
また、病院では「手術室」「待合室」「処置室」など、用途に応じた厳格なゾーニングがなされています。
空間を分類し、そのゾーンに適した設計やルールを導入することで、運用効率と安全性を両立するのがゾーニングの特徴です。
代表的なオフィスゾーンの種類

オフィス空間では、多様な働き方を支えるためのゾーンが求められます。
以下は代表的なオフィスゾーンの分類です。
集中ゾーンと執務ゾーンの違い
集中ゾーンとは、一人で作業に集中したい人のための静かな空間です。
パーティションや個室ブースなどが設けられており、会話や電話は禁止、視線を遮る設計なども施されています。
一方、執務ゾーンは通常の業務を行うためのスペースであり、フリーアドレス制や固定席制が導入されている場合があります。
ある程度の会話や電話も許容され、チーム単位の業務にも対応しています。
このように、集中ゾーンと執務ゾーンは役割が明確に異なるため、それぞれの業務目的に合わせた設計が重要です。
コミュニケーションゾーンとリフレッシュゾーン
コミュニケーションゾーンは、社員同士の交流や情報共有を促進する空間です。
オープンスペースの会議エリアやソファ席、カフェ風のラウンジなどが該当します。
チームをまたいだ雑談やアイデアのブレストが自然と生まれるような設計がポイントです。一方、リフレッシュゾーンは、社員が気分転換や休憩を取るためのエリアです。
リラックスチェア、マッサージ機、軽食スペースなどが配置され、心身のリフレッシュを支援します。
これらのゾーンが整備されることで、働きやすさとメリハリあるワークスタイルが実現します。
オフィスゾーニングのメリット

適切なゾーニングは、業務の効率化だけでなく、働きやすさや職場の魅力向上にもつながります。
業務の生産性向上
ゾーニングによって業務内容に最適な空間を使い分けることができれば、作業効率が向上します。
例えば、静かな集中ゾーンでは思考力が求められる業務に集中でき、電話や対話が必要な業務では専用のスペースが利用できます。
動線も整理されるため無駄な移動が減り、タスクの切り替えもスムーズになります。
ゾーン設計が「仕事のしやすさ」を高め、結果として生産性向上へとつながるのです。
従業員満足度とエンゲージメントの向上
多様なゾーンを設けることで、従業員が自分の働き方に合った場所を選べるようになります。
これは働きやすさや快適性に直結し、ストレスの軽減やワークライフバランスの実現にも貢献します。
また、コミュニケーションゾーンやリフレッシュゾーンがあることで、社員同士のつながりや帰属意識が生まれ、エンゲージメントの向上にもつながります。
物理的な空間設計が、組織文化やモチベーションに影響を与えることは見逃せません。

オフィスゾーニングの成功事例

実際にゾーニングを導入したことで大きな成果を上げた事例もあります。
フリーアドレスとゾーニングの融合成功例
あるIT企業では、フリーアドレス制を導入しながらも、集中・執務・会議・カフェ・来客応対といった明確なゾーニングを設けました。
社員はその日の業務に応じて最適なゾーンを選び、自由度を保ちつつも生産性の高い働き方を実現。結果として、部門間の連携も活発化し、離職率の低下にもつながりました。
コミュニケーション活性化に寄与した事例
製造業の本社では、部署間の壁を取り払い、中央にコミュニケーションゾーンを配置。
打ち合わせスペースや雑談ができるラウンジなどを設けたところ、部署を超えた交流が増加。
イノベーションの種となるアイデアや課題共有が活発になり、部門横断プロジェクトの成功事例も生まれました。
ゾーニング設計の進め方とポイント
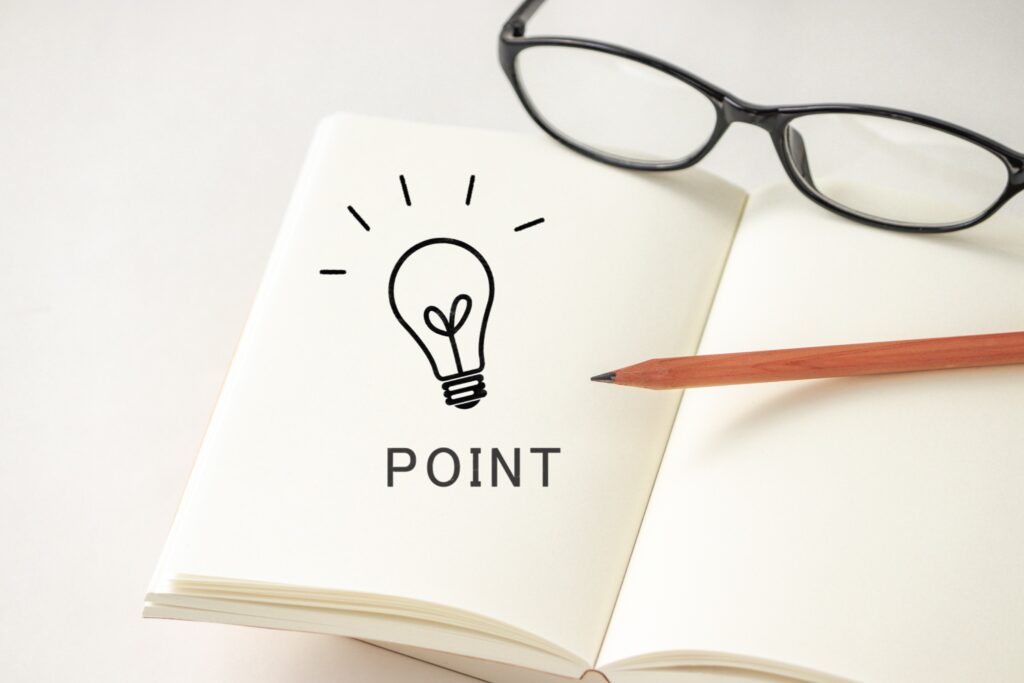
ゾーニングの導入は、戦略的なプロセス設計が求められます。
以下に代表的な進め方と注意点を解説します。
ゾーニング設計の基本ステップ
まずは、現状の業務内容や利用頻度、社員の行動パターンを可視化することが第一歩です。その上で、必要なゾーンを定義し、目的に応じたエリア設計を行います。
設計後には試験運用を経て、フィードバックをもとに調整・改善を重ねることが大切です。運用フェーズでは、利用ルールの明確化やサイン表示なども欠かせません。
ゾーニングでよくある失敗例と対策
よくある失敗としては、「誰も使わないスペースが生まれる」「動線が交差して混雑する」「目的とゾーンが一致していない」などが挙げられます。
これらは初期設計段階でのヒアリング不足や、実際の行動データに基づかない机上設計が原因です。対策として、定期的な利用状況のレビューや利用者アンケート、専門家のアドバイスなどを取り入れることが効果的です。
データ活用によるゾーニングの最適化
近年では、位置情報データや出社率・滞在時間などの実測データを活用したゾーニング改善が注目されています。
例えば、集中ブースの利用率が高ければ増設を検討し、逆に使われていないスペースは用途転換するなど、データに基づいた改善が可能です。
こうした手法により、より精緻で柔軟なゾーニングが実現できます。
工場や食品業界におけるゾーニングの重要性

ゾーニングはオフィスに限らず、工場や食品業界でも衛生・安全面から極めて重要です。
食品工場でのゾーニング事例と考え方
食品工場では、製造工程ごとに「クリーンゾーン」「準清潔ゾーン」「汚染ゾーン」などを設定し、交差汚染のリスクを防ぐゾーニングが行われます。
搬入・加工・包装・出荷といった工程が明確に分離され、一方通行の動線設計が基本です。また、ゾーンごとに異なる服装や衛生ルールが設定されることも一般的です。
ゾーニングによる衛生管理と作業効率の両立
衛生ゾーンを厳格に分けることにより、食品の安全性が確保されるだけでなく、作業ミスや事故の予防にもつながります。
さらに、作業ごとに適した設備・人員配置を行うことで、作業効率も自然と向上します。
衛生と効率という一見相反する要素を、ゾーニングによって両立させることが可能です。
現場でのゾーニング導入の注意点
ゾーニング導入時には、現場スタッフの理解と協力が欠かせません。
一方的にルールを押し付けるのではなく、現場の声を取り入れながら設計・運用していくことが重要です。
導入後も定期的な教育や見直しを行うことで、持続可能な衛生環境と効率的な現場運営が実現します。

まとめ
ゾーニングは、空間を戦略的に活用するための有効な設計手法です。
オフィスでは業務効率や従業員満足度の向上、工場では衛生管理と安全確保に直結する要素として機能します。
重要なのは、目的を明確にした上で、現場の声や実データを反映しながら柔軟に設計・改善していくこと。今後の働き方や生産現場を支えるうえで、ゾーニングの重要性はますます高まっていくでしょう。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg
