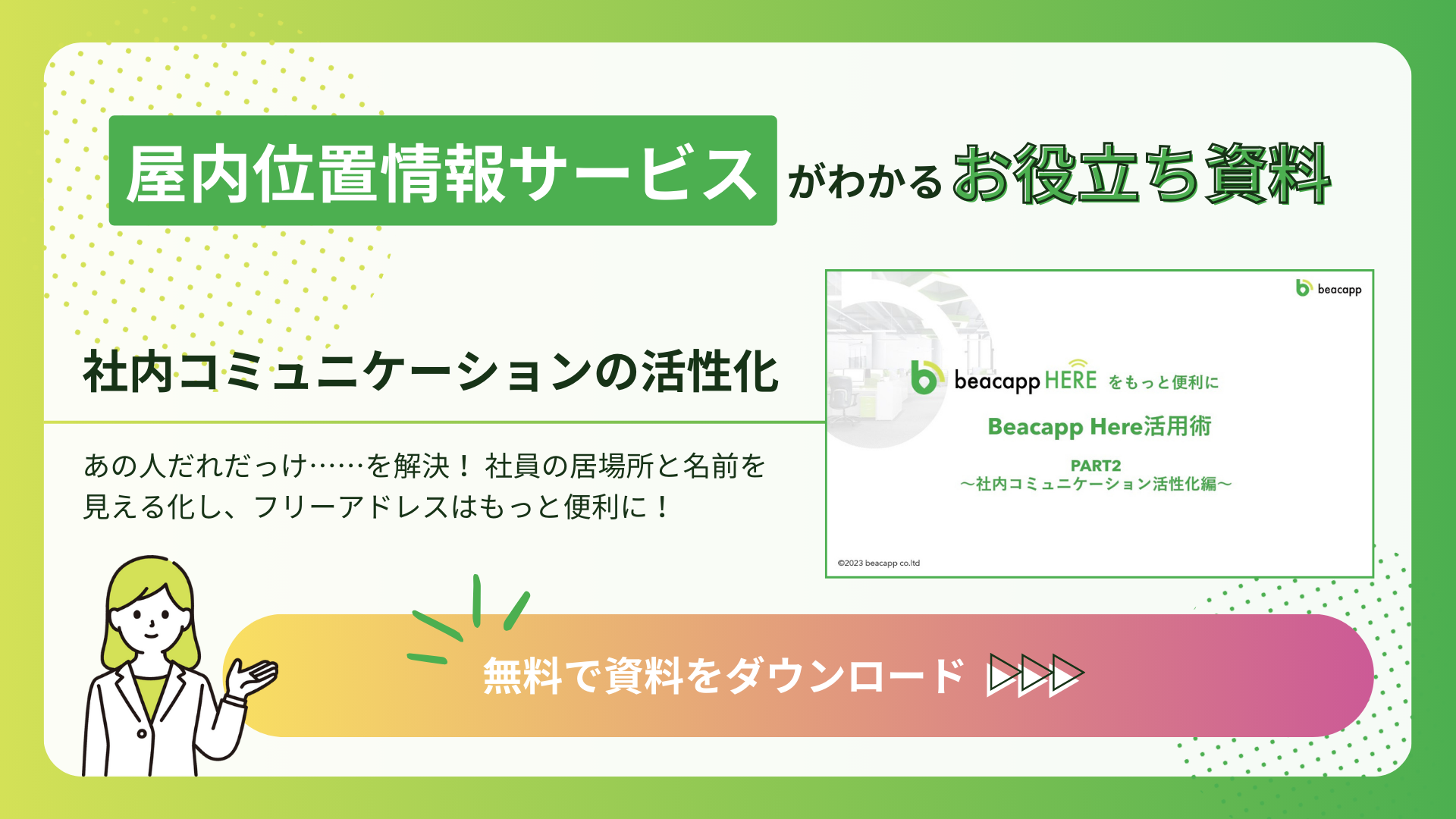コロナ禍を経て、リモートワークは日本社会に大きな変化をもたらしました。
感染拡大防止のための急速な導入は、多くの企業にとって働き方を見直す契機となり、従業員の働き方や企業文化に影響を与えました。
一方で、アフターコロナでは対面勤務への回帰やハイブリッド型の導入など、新たな段階へと移行しています。本稿では、その普及率の推移と背景を振り返り、今後の日本社会における位置づけを探ります。
リモートワーク普及率の推移

リモートワークはコロナ前は限定的でしたが、コロナ禍で急速に拡大し、現在は安定した普及率で推移しています。その変化の背景を時系列で整理します。
コロナ前の普及率と状況
コロナ前の日本では、リモートワークの普及率は非常に低い水準にありました。
総務省の調査によれば、2019年時点でのテレワーク実施率は20%ほどにとどまっており、多くの企業では制度自体が整っていない状況でした。
背景には、対面によるコミュニケーションを重視する企業文化や、紙ベースの業務、はんこ文化などが根強く存在していました。そのため、導入されていても一部の専門職や外回りの営業職に限られるなど、実質的に利用される機会は少なかったのです。
参考:総務省 令和2年版情報通信白書
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/pdf/n2300000.pdf
コロナ禍での急増
2020年の新型コロナウイルス感染拡大は、日本社会におけるリモートワーク普及を大きく後押ししました。緊急事態宣言の発出を受け、多くの企業が出勤抑制を実施し、在宅勤務を急速に導入しました。
その結果、2021年度の東京都内の従業員30人以上の企業におけるリモートワーク実施率は65.7%という調査結果が出されました。
特に都市部の大企業を中心にオンライン会議システムやクラウドサービスの導入が進み、従来の業務プロセスが急速にデジタル化しました。従業員の多くが初めて在宅勤務を経験し、働き方に対する価値観にも大きな変化が生まれました。
アフターコロナでの普及率推移
アフターコロナの現在、リモートワークはピーク時よりは減少したものの、コロナ前を大きく上回る普及率で定着しています。
出社を前提とした働き方に戻す企業もある一方で、ハイブリッド型勤務を採用する企業も増加しています。調査によると、週に数日リモート勤務を組み合わせるスタイルが一般的になりつつあり、従業員のワークライフバランス改善や人材確保の観点からも重視されています。
今後は、テクノロジー活用の進展と企業の柔軟な制度設計によって、リモートワークは持続的な働き方の一つとして根付いていくと考えられます。
日本におけるリモートワーク普及率の現状

現在の日本におけるリモートワークは、一部に定着しつつあるものの、業種や企業規模、地域によって普及度合いに差が見られます。ここでは、日本のリモートワークの普及率の現状についてご紹介します。
業種別にみた普及率
リモートワークの導入状況は業種によって大きく異なります。情報通信業や金融業、コンサルティング業などデジタル環境に適した業種では高い普及率を示し、多くの業務がオンラインで完結可能です。
一方、製造業や物流業、接客業など現場作業や対面対応が不可欠な業種では、リモートワークの導入が難しく、普及率は低水準にとどまっています。こうした業種間の差は、日本におけるリモートワークの定着を考える上で大きな課題といえるでしょう。
企業規模による違い
企業の規模によってもリモートワーク普及率には差があります。大企業ではテクノロジーへの投資余力があり、在宅勤務環境の整備が進んでいるため、比較的高い普及率を維持しています。特に従業員数の多い企業では、感染症対策や人材確保の観点からも積極的に制度を導入してきました。
一方で、中小企業ではコストやシステム導入のハードルが高く、制度設計や運用に課題を抱えるケースが多く見られます。そのため、大企業と中小企業の間で普及状況に格差が生じているのが現状です。
地域差と普及率
地域ごとの普及率にも顕著な差があります。東京や大阪など大都市圏では、業種構成や企業規模の特性からリモートワークが広く浸透しており、通勤抑制のニーズも高いことから高水準を維持しています。
これに対し、地方では製造業やサービス業の割合が高く、業務特性上リモート勤務の導入が進みにくい傾向があります。さらに、通信環境や人材確保の事情も影響しており、都市部と地方の間にはリモートワーク普及における格差が存在しています。こうした地域差を埋める取り組みが今後の課題といえます。
リモートワークのメリットと課題

リモートワークは働き方の幅を広げる一方で、働き手と企業の双方にとって新たな課題も浮き彫りになっています。ここでは、リモートワークにおけるメリットと課題についてご紹介します。
働き手にとってのメリット
リモートワークの大きな利点は、通勤時間の削減による時間的余裕の創出です。これにより、仕事と家庭生活の両立がしやすくなり、ワークライフバランスが改善されます。
また、自宅や好きな場所で働ける自由度は、精神的な負担の軽減や生産性の向上にもつながります。さらに、地理的な制約が少なくなるため、地方在住者や育児・介護を担う人にとっても働きやすい環境が整い、柔軟なキャリア形成が可能になる点もメリットといえるでしょう。
働き手が抱える課題
一方で、働き手にとっての課題も存在します。リモート勤務は孤独感を抱きやすく、チームとのコミュニケーション不足につながることがあります。
また、オンとオフの切り替えが難しいため、長時間労働や過労につながるケースも見受けられます。さらに、家庭環境や住居のスペースによっては、集中できる環境を整えにくい点も問題です。
成果が見えにくいため評価が不透明になる懸念もあり、モチベーションやキャリア形成に影響する可能性があります。
企業側のメリットと課題
企業にとってもリモートワークは、オフィスコストの削減や柔軟な働き方を提供することで人材確保に有利に働くという利点があります。
また、場所に縛られない働き方を認めることで優秀な人材を広く採用でき、従業員の満足度向上にもつながります。しかし一方で、従業員の労務管理やセキュリティ対策、コミュニケーション不足によるチーム力低下といった課題も顕在化しています。制度を単に導入するだけでは不十分で、働き手と企業双方の課題を解消する仕組みづくりが重要となっています。

今後のリモートワーク普及率の展望

リモートワークは一過性の働き方ではなく、社会の仕組みとして定着しつつあります。今後は多様な方向性で拡大していくことが期待されます。ここでは、今後のリモートワーク普及率の展望についてご紹介します。
ハイブリッドワークの定着
アフターコロナにおける働き方の主流は、オフィス勤務と在宅勤務を組み合わせたハイブリッド型へと移行しています。
週数日の出社を組み合わせることで、対面でのコミュニケーションとリモートによる柔軟性の両立が可能になります。企業にとっては生産性やチーム連携を確保しながら、従業員にとっては通勤負担の軽減や生活の自由度を高められるのが特徴です。
こうした働き方は、今後も多くの企業で制度として定着していくと考えられます。
地方創生との結びつき
リモートワークの普及は、地方創生との親和性が高いといえます。都市部に通勤する必要が減ることで、地方在住の人々も大都市圏の仕事に携わることができ、就業機会が広がります。
また、都市部から地方への移住を後押しし、地域経済の活性化にもつながります。企業にとっても、多様な地域から優秀な人材を確保できる点は大きなメリットです。
今後、リモートワークが持続的に拡大すれば、都市一極集中の是正や地域格差の縮小に寄与する可能性があります。
リモートワークを支えるツールの活用
リモートワークの定着には、デジタルツールの進化と活用が欠かせません。オンライン会議システムやチャットツール、クラウドサービスに加え、業務管理や人材育成をサポートする新しいプラットフォームも広がりを見せています。
AIやデータ分析を活用した効率的な業務支援も進み、リモート環境でも生産性を維持できる仕組みが整いつつあります。今後は、これらのツールを効果的に導入・活用する企業が競争力を高め、リモートワーク普及の担い手となるでしょう。
ハイブリッドワークを支援する「Beacapp Here」

ハイブリッドワークを実現するには、社員の出社状況や働く場所を可視化し、効率的に管理できる仕組みが欠かせません。その解決策として注目されているのが「Beacapp Here」です。
Beacapp Hereとは
「Beacapp Here」は、株式会社ビーキャップが提供する位置情報・出社管理サービスです。スマートフォンアプリを利用して、社員の所在や出社・在宅状況を簡単に把握できるのが特長です。
ビーコンとスマートフォンを活用することで、誰がどこで働いているのかをリアルタイムに可視化でき、管理者だけでなく従業員同士の確認にも役立ちます。これにより、リモートとオフィスを組み合わせたハイブリッドワークにおいても、スムーズなコミュニケーションやチーム連携が可能になります。
企業にとっての導入メリット
Beacapp Hereを導入することで、企業は出社率の把握や働き方の分析を容易に行うことができます。誰が出社しているかを瞬時に確認できるため、会議や打ち合わせの調整がスムーズになり、無駄な時間を削減できます。
また、BCP(事業継続計画)の観点からも有効で、災害や緊急時に社員の所在を迅速に把握できる点は安全確保に直結します。さらに、データを活用したオフィス利用状況の最適化にもつながり、スペースの有効活用やコスト削減を実現できます。ハイブリッドワークを円滑に進めるための実用的なツールとして、多くの企業から注目を集めています。

まとめ
リモートワークは新型コロナを契機に急速に普及し、現在は完全在宅から対面を組み合わせたハイブリッド型へと定着しつつあります。
業種・企業規模・地域による普及格差やコミュニケーション・評価の課題は残るものの、通勤時間削減や人材確保、BCP強化といったメリットが明確になりました。今後は、効果的な制度設計と評価基準の整備、通信環境やツールの充実、企業文化の変革が普及の鍵となります。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg