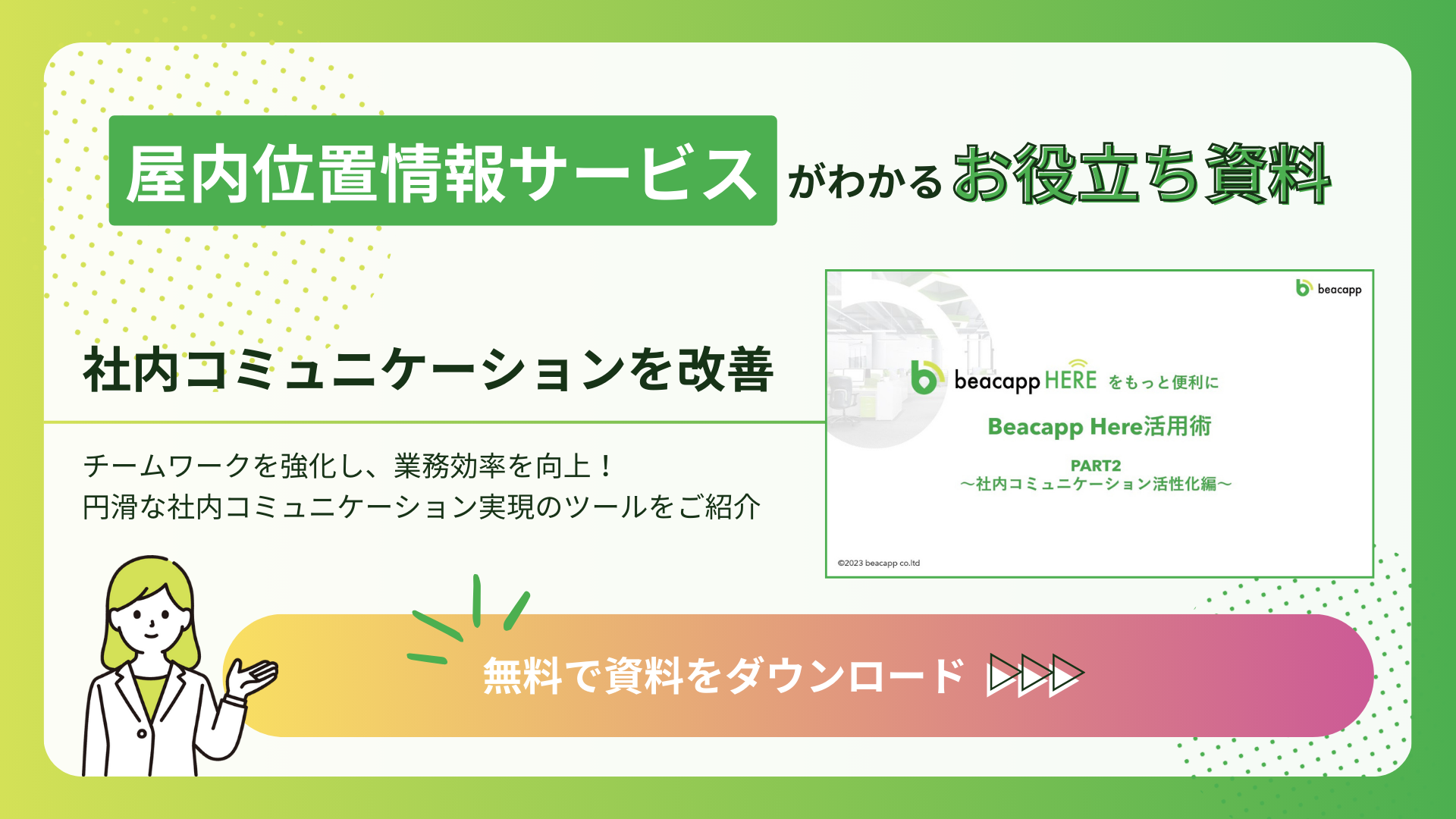インナーブランディングは、企業の理念を社内で理解させるブランディング手法であり、社員のエンゲージメントを高める上でよく利用されます。
そこで本記事では、インナーブランディングの意味や進め方について解説します。本記事をお読みいただくことで、インナーブランディングのポイントを理解し、従業員のエンゲージメント向上に役立ちます。
インナーブランディングとは

インナーブランディングとは、企業の理念や価値観を社内の従業員に浸透させるためのブランディング手法です。
この手法を通じて、企業のビジョンやミッションを従業員が理解し、共感することで、組織全体のエンゲージメントを高めることが目的です。
アウターブランディングとの違い
インナーブランディングとアウターブランディングは、企業のブランディング戦略において異なる役割を果たします。
インナーブランディングは主に社内に焦点を当て、企業の理念や価値観を従業員に浸透させることを目的としています。
一方、アウターブランディングは、顧客や外部のステークホルダーに向けたブランディング活動です。
企業の製品やサービス、ブランドイメージを外部に伝えることを重視し、マーケティング戦略や広告活動を通じて行われます。アウターブランディングは、顧客の認知度を高め、ブランドの信頼性を向上させることを目的としています。
インナーブランディングのメリット

インナーブランディングを推進することで得られるメリットについて説明します。
従業員の生産性が上がる
インナーブランディングを効果的に進めることで、従業員の生産性向上が期待されます。
これは、企業の理念やビジョンが社内でしっかりと浸透することによって、従業員が自らの役割を理解し、目標に向かって一丸となって取り組む姿勢が生まれるためです。
具体的には、企業の価値観や目指す方向性が明確になることで、従業員は自分の仕事がどのように企業全体に貢献しているのかを実感しやすくなります。
また、インナーブランディングによってコミュニケーションが活性化されることも、生産性向上の要因の一つです。従業員同士の情報共有や意見交換が促進されることで、チームワークが強化され、業務の効率化が図られます。
従業員の離職率が下がる
インナーブランディングを実施することで、従業員の離職率低下が期待できます。
企業理念や価値観が社内でしっかりと浸透することで、従業員は自分の仕事に対する意義を感じやすくなります。
また、インナーブランディングはコミュニケーションの活性化にも寄与します。従業員同士のつながりが強化されることで、職場環境がより良好になり、ストレスや不満が軽減されます。結果として、離職を考える従業員が減少し、企業全体の安定性が向上します。
コンプライアンス意識が向上する
インナーブランディングを進めることで、企業内のコンプライアンス意識向上が期待されます。
コンプライアンスとは、法令や規則を遵守することを指し、企業の信頼性や持続可能性に直結する重要な要素です。
インナーブランディングを通じて、企業理念や価値観を社員に浸透させることで、コンプライアンスの重要性を理解し、日常業務においてもその意識を持つようになります。
具体的には、企業の理念に基づいた行動規範や倫理規定を明確にし、それを社内で共有することが効果的です。定期的な研修やワークショップを通じて、社員がコンプライアンスについて考える機会を設けることで、より深い理解が得られます。
インナーブランディングのデメリット

インナーブランディングは、メリットだけでなく、デメリットも存在します。ここでは、各デメリットについて解説します。
運用コストがかかる
インナーブランディングを進める上で避けて通れないのが、その運用コストです。
企業がインナーブランディングを実施する際には、さまざまなリソースを投入する必要があります。
例えば、社内報やイベントの開催、ワークショップの実施など、これらはすべて人件費や物品費、さらには外部の専門家を招く場合にはその費用も考慮しなければなりません。
成果が短期的に出づらい
インナーブランディングは、その成果が短期的に現れにくいというデメリットも存在します。
特に、インナーブランディングの取り組みは、時間をかけて徐々に効果を発揮するものであり、即効性を求める経営者やマネージャーにとっては、忍耐が必要です。
例えば、社内のコミュニケーションや文化を変えるためには、継続的な努力と時間が必要です。社員が新しい価値観を受け入れ、実際の行動に移すまでには、数ヶ月から数年の時間がかかることもあります。
このような取り組みは、社員の意識や行動を変えることを目的としているため、短期間での結果を期待するのは難しいのです。
従業員からの反発が起きる可能性がある
インナーブランディングは、実施にあたっては従業員からの反発が起きる可能性も考慮しなければなりません。
特に、企業の方針や施策が一方的に押し付けられる形になると、従業員はその意図を理解できず、抵抗感を抱くことがあります。
反発の原因としては、従業員が自分の意見や感情が無視されていると感じることが挙げられます。
例えば、インナーブランディングの施策が従業員の実情やニーズに合わない場合、彼らはその取り組みを「形式的なもの」と捉え、参加意欲が低下することがあります。

インナーブランディングの手法/進め方

インナーブランディングを効果的に進めるためには、さまざまな手法を活用することが重要です。ここでは、具体的な手法をいくつか紹介します。
社内報
社内報は、インナーブランディングを進める上で効果的な手法の一つです。
企業の理念やビジョン、最新の業績情報、社員の活躍などを定期的に発信することで、従業員の意識を高め、企業文化を醸成する役割を果たします。
特に、社内報は情報の透明性を確保し、社員同士のコミュニケーションを促進するための重要な手段です。社内報を通じて、企業の方針や目標を明確に伝えることで、従業員は自分の役割や貢献がどのように企業全体に影響を与えるのかを理解しやすくなります。
社内イベント
インナーブランディングを効果的に進める手法の一つとして、社内イベントが挙げられます。
社内イベントは、社員同士のコミュニケーションを促進し、企業の理念や価値観を共有する絶好の機会となります。
例えば、定期的に開催される社員総会や懇親会、チームビルディング活動などがその代表例です。
これらのイベントでは、企業のビジョンやミッションを再確認するセッションを設けたり、成功事例を共有することで、社員が自らの役割を理解し、企業への帰属意識を高めることができます。
サンクスカード
サンクスカードは、インナーブランディングの手法の一つとして、社員同士の感謝の気持ちを伝えるためのツールです。
このカードを活用することで、日常的にお互いの努力や成果を認め合う文化を醸成し、職場の雰囲気をより良いものにすることができます。
具体的には、社員が同僚に対して感謝のメッセージを書いたカードを渡すことで、ポジティブなコミュニケーションを促進します。
サンクスカードは、特別なイベントやキャンペーンとして実施することもできますが、日常的に取り入れることで、より効果的なインナーブランディングの手法となります。
SNS
インナーブランディングにおいて、SNSも効果的な手法の一つです。
企業が公式アカウントを通じて、社内の情報や理念を発信することで、従業員同士のコミュニケーションを促進し、企業文化を浸透させることができます。
特に、SNSはリアルタイムで情報を共有できるため、従業員が参加しやすく、意見を交わす場としても機能します。
また、SNSを活用することで、従業員の声を直接反映させることができるため、エンゲージメントの向上にも寄与します。
例えば、社内イベントの様子や成功事例を投稿することで、他の従業員にもその活動の重要性を伝えることができます。
ワークショップ
ワークショップもインナーブランディングの手法としてよく利用される手法です。
ワークショップは、社員が企業の理念や価値観を深く理解し、実践するための場を提供します。ワークショップの利点は、参加者同士の意見交換やディスカッションを通じて、より具体的な理解を促進できる点です。
ワークショップでは、企業のビジョンやミッションをテーマにしたグループ活動を行い、社員が自らの意見やアイデアを出し合うことが重要です。
これにより、社員は自分の考えが企業の方向性にどのように寄与するのかを実感し、エンゲージメントが高まります。
インナーブランディングの成功事例3選
インナーブランディングは、企業の理念や価値観を社内に浸透させるための重要な手法です。ここでは、実際にインナーブランディングを成功させた企業の事例を3つ紹介します。
日本たばこ産業株式会社(JT)
日本たばこ産業株式会社(JT)は、インナーブランディングの成功事例として広く知られています。
JTは、企業理念やビジョンを社員に浸透させるために、さまざまな取り組みを行っています。特に、社員の意識を高めるためのコミュニケーション施策が効果を上げています。
その中でも特筆すべきが、社内SNSの活用です。JTでは、「E+Lab」というSNSを運用しており、新製品の社内向けプロモーションや、社内情報共有に利用されています。
日本航空株式会社(JAL)
日本航空株式会社(JAL)は、インナーブランディングの成功事例として広く知られています。
JALは、企業理念である「お客様第一」を社内に浸透させるために、さまざまな取り組みを行っています。
JALでは、自社のコーポレートメッセージの社内浸透が思うように進まず、動画コンテンツを制作し、オンデマンドで社員が閲覧できる環境構築を行っています。
社員は、PCやスマートフォンで閲覧できるようになっており、中期経営計画や社長メッセージ、各部署が制作したコンテンツなどが常時更新されています。
このような取り組みを通じて、JALは社員のエンゲージメントを高め、顧客満足度の向上にもつなげています。
参考: 日本航空株式会社 様(社内向け動画) | 株式会社ブイキューブ
スターバックスコーヒージャパン
スターバックスコーヒージャパンは、インナーブランディングの成功事例として広く知られています。
彼らは「人を大切にする」という企業理念を基に、従業員のエンゲージメントを高めるための多様な取り組みを行っています。
特に、スターバックスでは「パートナー」という言葉を用いて、従業員を単なるスタッフではなく、企業の重要な一員として位置づけています。このような言葉の選び方からも、インナーブランディングの重要性が伺えます。
具体的な施策としては、定期的な社内イベントやトレーニングプログラムが挙げられます。これにより、従業員同士のコミュニケーションが促進され、企業理念の理解が深まります。

まとめ
インナーブランディングを効果的に実施することで、従業員の生産性向上や離職率の低下、コンプライアンス意識の向上といった多くの利点が得られます。
しかし、運用コストや短期的な成果の難しさ、従業員からの反発といった課題も存在するため、慎重な計画と実行が求められます。
成功事例として挙げた企業の取り組みを参考にしながら、自社に合ったインナーブランディングの手法を見つけ、実践することが重要です。
最終的には、インナーブランディングを通じて企業全体の一体感を高め、より良い職場環境を築くことが目指されます。これからの企業活動において、インナーブランディングの重要性はますます高まることでしょう。
————————————————————————————————————
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg