チームで働いているのに、成果が出ない。メンバー間に溝がある——そんな悩みを抱えていませんか?
いま、多様な価値観や働き方が共存する職場では、意図的な「チームづくり=チームビルディング」が不可欠です。
本記事では、チームの定義から、ビルディングの意義・実践方法・得られるメリットまでを体系的に解説します。
チーム力を高めることで、組織全体の生産性・エンゲージメント・心理的安全性が向上します。
チームビルディングとは?
チームビルディングは、メンバー同士の信頼やコミュニケーションを深め、役割を明確にしながら、共通の目標に向けて効果的に協力し合うための継続的なプロセスです。
「チーム」とは

「チーム」とは、共通の目標に向かって協力し合う人々の集まりを指します。単に人数が集まっただけのグループとは異なり、チームはメンバー間の相互依存性が強く、各自の役割や責任が明確に定義されています。チームのメンバーは、互いのスキルや知識を活かしながら、協力して成果を上げることを目指します。
チームの特性として、コミュニケーションの重要性が挙げられます。メンバー同士が意見を交わし、情報を共有することで、より良い意思決定が可能になります。また、チーム内での信頼関係が築かれることで、メンバーは安心して自分の意見を表明できるようになります。
「チームワーク」との違い
チームビルディングとチームワークは、しばしば混同されがちですが、実際には異なる概念です。チームワークは、メンバーが協力して共通の目標を達成するためのプロセスや行動を指します。つまり、チームワークは「行動」に焦点を当てたものであり、メンバー間の協力やコミュニケーションの質が重要です。
一方で、チームビルディングは、チームの基盤を築くための意図的な活動やプロセスを指します。これは、メンバー同士の信頼関係を深めたり、役割を明確にしたりすることを目的としています。チームビルディングは、チームワークを促進するための土台を作るものであり、長期的な成果を生むための戦略的なアプローチと言えるでしょう。
「チームマネジメント」との違い
チームビルディングとチームマネジメントは、どちらもチームのパフォーマンス向上を目指す重要な概念ですが、そのアプローチや焦点には明確な違いがあります。
チームビルディングは、メンバー間の信頼関係やコミュニケーションを強化し、チームの結束を高めることに重点を置いています。具体的には、メンバー同士の相互理解を深めるための活動や、共通の目標に向かって協力するための環境づくりが含まれます。
一方、チームマネジメントは、チームの運営や管理に関する側面に焦点を当てています。リーダーシップや役割分担、業務の進捗管理など、チームが効率的に機能するための戦略や手法を指します。
つまり、チームマネジメントは、チームが目標を達成するための「仕組み」を整えることが主な目的であり、チームビルディングはその「仕組み」を支える「人間関係」を築くことに重きを置いているのです。
チームビルディングがなぜ求められるのか

多様な価値観や働き方が共存する中で、メンバー間の相互理解や円滑なコミュニケーションが求められています。これにより、チームのビジョンが浸透し、メンバーのマインドセットが形成されることで、役割分担や協働関係が促進されるのです。
チームビルディングの必要性
現代の職場環境は、急速に変化しており、さまざまな価値観や働き方が共存しています。
このような多様性の中で、チームが効果的に機能するためには、意図的なチームビルディングが不可欠です。チームビルディングは、メンバー間の信頼関係を築き、共通の目標に向かって協力するための基盤を提供します。
また、チームビルディングは、メンバー同士の相互理解を深め、円滑なコミュニケーションを促進する役割も果たします。これにより、誤解や対立を減少させ、チーム全体のパフォーマンスを向上させることが可能になります。
さらに、役割分担や協働関係の明確化を通じて、各メンバーが自分の強みを活かしながら貢献できる環境を整えることができます。
ビジョン浸透&マインドセット形成
組織のビジョンが明確であればあるほど、メンバーは共通の目標に向かって一丸となりやすくなります。ビジョンは、チームの方向性を示す羅針盤のような役割を果たし、メンバーが自らの役割を理解し、貢献する意義を見出す手助けをします。
また、マインドセットの形成は、チームの文化や価値観を共有することから始まります。ポジティブなマインドセットを持つことで、メンバーは困難な状況にも前向きに取り組むことができ、互いに支え合う関係を築くことができます。
メンバー同士の相互理解&円滑なコミュニケーションの促進
異なるバックグラウンドや価値観を持つメンバーが集まることで、意見の対立や誤解が生じることがあります。
これを解消するためには、まずお互いの強みや弱みを理解し合うことが必要です。
定期的なチームミーティングやワークショップを通じて、メンバーが自分の考えや感情を自由に表現できる環境を整えることが、相互理解を深める第一歩となります。
さらに、円滑なコミュニケーションを促進するためには、オープンな対話を奨励する文化を築くことが不可欠です。メンバーが意見を言いやすい雰囲気を作ることで、問題解決やアイデアの創出がスムーズに進みます。
役割分担&協働関係の促進
各メンバーが自分の役割を明確に理解し、それに基づいて行動することで、チーム全体の効率が向上します。役割が明確であれば、各自が自分の強みを活かし、責任を持って業務に取り組むことができるため、成果を上げやすくなります。
また、役割分担が適切に行われることで、メンバー同士の協働関係も強化されます。お互いの役割を理解し、補完し合うことで、チーム内の信頼関係が深まり、コミュニケーションが円滑になります。
役割分担を通じてメンバーの個性や専門性を尊重することが、チームの多様性を活かす鍵となります。多様な視点を持つメンバーが協力し合うことで、より創造的な解決策が生まれ、チームの成果を最大化することが可能になります。
チームビルディングによるメリット

チームビルディングによってメンバーのマインドセット形成、チームの心理的安全性の向上、さらにはメンバーのモチベーション向上や適切な人材配置によって、各メンバーの強みを最大限に活かすことが可能になります。
これらの要素が相まって、チーム全体のパフォーマンスが向上するのです。
マインドセットの形成
マインドセットを形成するためには、まずリーダーが模範を示すことが求められます。
リーダー自身が失敗を恐れず、学びの機会として捉える姿勢を見せることで、メンバーも同様の考え方を持つようになります。
また、定期的なフィードバックや振り返りの場を設けることで、メンバー同士が互いの成長を支援し合う環境を整えることができます。
さらに、チーム全体で共通のビジョンや目標を持つことも、マインドセットの形成に寄与します。共通の目的に向かって協力し合うことで、メンバーは一体感を感じ、ポジティブなマインドセットが育まれます。
チームの心理的安全性向上
心理的安全性とは、メンバーが自分の意見やアイデアを自由に表現できる環境を指します。
この安全な環境が整うことで、メンバーは失敗を恐れずに挑戦し、積極的にコミュニケーションを図ることができます。
心理的安全性が高まると、メンバー同士の信頼関係が深まり、意見の対立や異なる視点が生まれた際にも建設的な議論が行いやすくなります。
これにより、チーム全体の創造性や問題解決能力が向上し、結果として業務の効率化や成果の向上につながります。
メンバーのモチベーション向上
チーム内での信頼関係や相互理解が深まることで、メンバーは自分の役割に対する責任感を持ちやすくなります。
これにより、個々のメンバーが自発的に行動し、チーム全体の目標達成に向けて積極的に貢献するようになります。
またメンバー同士のコミュニケーションが活発化し、意見交換が行いやすくなることで、メンバーは自分の意見やアイデアが尊重されていると感じ、モチベーションが向上します。
適切な人材配置
各メンバーのスキルや特性を理解し、それに基づいて役割を割り当てることで、チーム全体のパフォーマンスを最大化することが可能です。
例えば、あるメンバーが優れたコミュニケーション能力を持っている場合、その人を顧客対応やチーム内の調整役に配置することで、円滑な情報共有が促進されます。
また、メンバーの興味やキャリア目標を考慮することも重要です。
自分の得意分野や興味に基づいた役割を与えられることで、メンバーはより高いモチベーションを持って業務に取り組むことができます。

チームビルディングを実施するプロセス/「タックマンモデル」

チームビルディングを効果的に進めるためには、タックマンモデルが有効です。このモデルは、チームが形成されてから機能するまでの5つの段階を示しています。このプロセスを理解することで、チームビルディングの実践がよりスムーズになります。
Step1:形成期
チームビルディングの最初のステップである「形成期」は、メンバーが集まり、互いに知り合う重要な時期です。この段階では、チームの目的や目標が明確にされ、メンバー間の信頼関係を築くための基盤が形成されます。
初対面のメンバー同士がコミュニケーションを取り、役割や期待を共有することで、チームの一体感が生まれます。
形成期では、リーダーが積極的に関与し、メンバーが安心して意見を述べられる環境を整えることが求められ、アイスブレイクやチームビルディングアクティビティを通じて、メンバー同士の距離を縮めることが効果的です。
この段階をしっかりと乗り越えることで、次の混乱期へとスムーズに進むことができ、チームの成長が促進されます。
Step2:混乱期
次のステップとしての「混乱期」は、メンバー間の意見の相違や役割の不明確さから、混乱や対立が生じることが一般的です。
メンバーはお互いの期待やコミュニケーションスタイルを理解しきれておらず、ストレスや不安を感じることもあります。
この混乱は、チームの結束を試す試練とも言えます。
この段階を乗り越えるためには、オープンなコミュニケーションが不可欠です。
メンバーが自由に意見を表明できる環境を整えることで、対立を建設的な議論に変えることが可能になり、リーダーはメンバーの意見を尊重し、適切なフィードバックを行うことで、混乱を解消し、チームの方向性を再確認する役割を果たすべきです。
Step3:統一期
3つ目のステップとしての「統一期」は、メンバー間の信頼関係が深まり、役割分担が明確になり、チーム全体が一つの目標に向かって協力し合う姿勢が強化されます。
メンバーはお互いの強みや弱みを理解し、補完し合うことで、より効果的な成果を上げることが可能になります。
この時期には、チームのビジョンや目標が共有され、メンバーがその達成に向けて主体的に行動するようになります。
コミュニケーションも円滑になり、意見交換やフィードバックが活発に行われることで、チームの結束力が高まります。
統一期を経て、チームはより成熟し、機能的な集団へと成長していくのです。
Step4:機能期
次のステップの「機能期」は、チームメンバーがそれぞれの役割を理解し、効果的に協力し合うことで、目標達成に向けた活動が本格化します。
メンバー間の信頼関係が深まり、コミュニケーションも円滑になり、意見交換が活発に行われるようになります。
この時期には、チームのパフォーマンスが向上し、各メンバーが自分の強みを活かしながら貢献できる環境が整います。
また、問題解決能力や創造性が高まり、チーム全体の生産性が向上することが期待されます。
Step5:散会期
最後のステップである「散会期」は、チームビルディングプロセスの最終段階であり、メンバーがそれぞれの役割を果たし、成果を上げた後に訪れます。
この段階では、チームの活動が終了し、メンバーが解散することになりますが、単なる終わりではなく、次のステップへの準備期間でもあります。
散会期では、チームの成果を振り返り、学びを共有することが重要です。
これにより、メンバーは自身の成長を実感し、次回のチーム活動に向けた意欲を高めることができます。
また、散会期においては、メンバー同士の関係性を再確認し、感謝の意を示すことも大切で、これによってチームの絆が強まり、将来的な協力関係の構築につながります。
チームビルディング実施のポイント
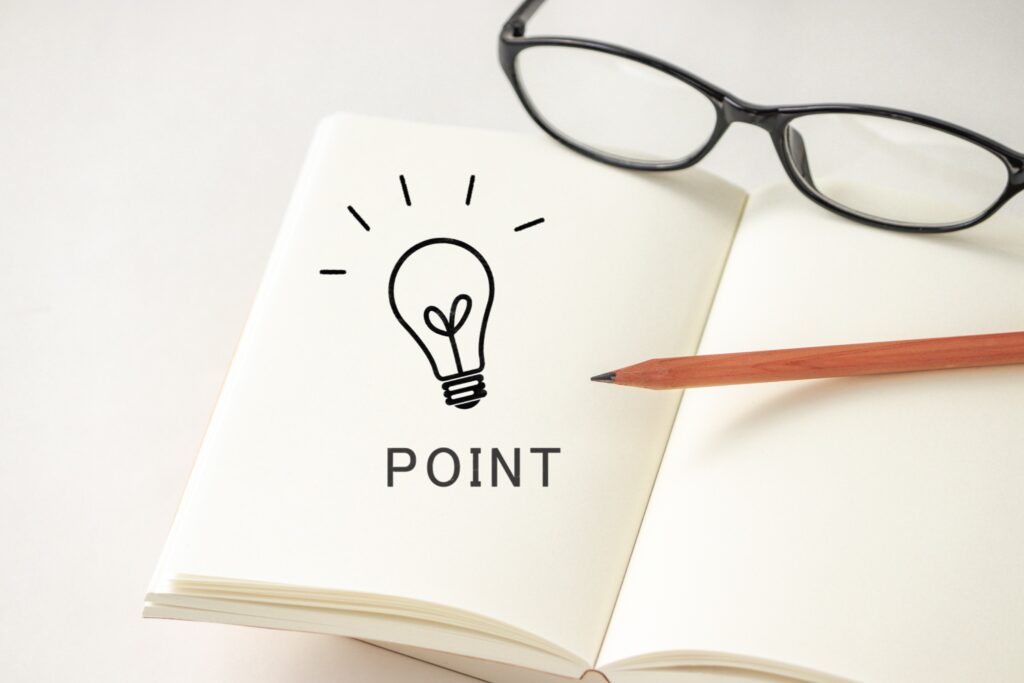
チームビルディングを成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
ポイントをおさえてチームビルディングを実施することで、より良いチームが形成されます。
さまざまな価値観を受け入れる
最初のポイントは、メンバーそれぞれの価値観を受け入れることです。
多様なバックグラウンドや経験を持つメンバーが集まることで、異なる視点やアイデアが生まれ、創造性が高まります。
しかし、価値観の違いは時に対立を生む要因ともなり得ます。
そのため、リーダーやメンバーは互いの意見を尊重し、オープンなコミュニケーションを心がける必要があります。
具体的には、定期的なチームミーティングやワークショップを通じて、メンバーが自分の考えや価値観を自由に表現できる場を設けることが効果的です。
こうした取り組みを通じて、チーム全体が一体感を持ち、共通の目標に向かって協力し合うことができるのです。
チームの具体的な目標を設定する
次のポイントは、具体的な目標を設定することです。
目標が明確であればあるほど、メンバーは自分たちの役割や貢献がどのようにチーム全体の成果に繋がるのかを理解しやすくなります。
これにより、各メンバーのモチベーションが向上し、チームとしての一体感も生まれます。
具体的な目標設定には、SMART原則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)を活用することが効果的です。
具体的で測定可能な目標を設定することで、進捗を確認しやすくなり、達成感を得ることができます。
メンバーの役割を明確にする
3つ目のポイントは、メンバーの役割を明確にすることです。
各メンバーが自分の役割を理解し、それに基づいて行動することで、チーム全体の効率が向上します。
役割が不明確な場合、メンバー同士の責任の所在が曖昧になり、タスクの重複や抜け漏れが発生しやすくなります。
役割を明確にするためには、まずチームの目標を共有し、それに基づいて各メンバーの強みやスキルを考慮した役割分担を行うことが必要です。
また、役割の明確化は定期的に見直すことも大切です。プロジェクトの進行状況やメンバーの成長に応じて、役割を柔軟に調整することで、チームのパフォーマンスを最大限に引き出すことができます。
メンバーの意見を尊重し、対立を恐れずに議論する
最後のポイントは、メンバーの意見を尊重することです。
多様なバックグラウンドや価値観を持つメンバーが集まるチームでは、意見の相違が生じることは避けられません。
しかし、これを恐れて議論を避けると、チームの成長や創造性が損なわれてしまいます。
対立を恐れず、オープンなコミュニケーションを促進することで、メンバーは自分の意見を自由に表現できる環境が整います。
議論を通じて、メンバーが互いに学び合い、成長する機会を提供することが、効果的なチームビルディングの鍵となるのです。
チームビルディング実践ができる具体例

チームビルディング実践に向けて、いくつかの具体例をもとに、実践することでチームの一体感を高めることができます。
心理的安全性を高める環境づくり
心理的安全性を高める環境づくりとしては、リーダーが率先してオープンなコミュニケーションを促進し、メンバーの意見を尊重する姿勢を示すことが求められます。
また、フィードバックを行う際には、建設的な意見を心がけ、批判ではなく改善のための提案を行うことが大切です。
さらに、定期的にチーム内での意見交換の場を設けることで、メンバー同士の信頼関係を深めることができます。
このような環境を整えることで、メンバーは安心して自分を表現できるようになり、結果としてチーム全体のパフォーマンス向上につながります。心理的安全性を高めることは、チームビルディングの基盤を築くための第一歩と言えるでしょう。
価値観の共有を図るイベント
価値観の共有を図るために、定期的に価値観を共有するイベントを開催することが推奨されます。
例えば、ワークショップやディスカッション形式のイベントを通じて、各メンバーが自分の価値観や信念を語る機会を設けることが効果的です。
これにより、メンバー同士が互いの考え方を理解し、共通の目標に向かって協力しやすくなります。また、価値観の共有は、チームの文化を形成する基盤ともなり、心理的安全性の向上にも寄与します。
このようなイベントは、単なる情報交換にとどまらず、メンバー同士の信頼関係を深める重要な機会となります。
団結力を高めるアクティビティ
団結力を高めるアクティビティは、メンバー同士の信頼関係を築き、協力する意識を育むための効果的な手段となります。
例えば、アウトドアでのチームチャレンジや、共同作業を通じて達成感を味わうワークショップなどが挙げられます。
これらのアクティビティは、単なる楽しみだけでなく、メンバー間のコミュニケーションを促進し、相互理解を深める機会を提供します。
特に、普段の業務では見えにくいメンバーの個性や強みを知ることで、チーム全体の結束力が強化され、成功体験を共有することで、チームの一体感が生まれ、今後の業務においても協力し合う基盤が築かれます。
リモートワーク下のコミュニケーション
リモートワークにおけるコミュニケーションの重要性はますます高まっています。
対面でのやり取りが減少することで、メンバー間の距離感が生まれやすく、誤解や情報の行き違いが発生するリスクも増加します。
そのため、意図的にコミュニケーションを促進する仕組みを整えることが求められます。
具体的には、定期的なオンラインミーティングや1対1のチェックインを設けることで、メンバー同士のつながりを強化することができます。
また、カジュアルな雑談の場を設けることで、業務以外の話題を共有し、信頼関係を築くことも効果的です。
さらに、プロジェクト管理ツールやチャットアプリを活用し、情報共有をスムーズに行うことも重要です。
チームビルディングに最適なオフィス

チームビルディングを効果的に実践するためには、オフィス環境が重要な役割を果たします。
メンバー同士のコミュニケーションが促進され、自然な交流が生まれる環境や
チームの絆を深める機会を提供できる環境など、こうしたオフィス環境が整うことで、チームの生産性やエンゲージメントが向上し、より良い成果を生む土壌が築かれます。
チームビルディング実践に繋がるオフィス環境
チームビルディング実践に繋がるオフィス環境とは、例えば、オープンなレイアウトやコラボレーションスペースを取り入れることで、メンバー同士のコミュニケーションが促進され、自然な対話が生まれやすくなります。
また、リラックスできる休憩スペースやカジュアルなミーティングエリアを設けることで、心理的安全性が高まり、意見を自由に交換できる雰囲気が醸成されます。
さらに、テクノロジーの活用も重要です。
リモートワークが普及する中で、オンラインツールを活用したコミュニケーションやプロジェクト管理が不可欠で、物理的な距離を超えてメンバー同士のつながりを強化し、チーム全体の一体感を高めることができます。
株式会社トランザクション
株式会社トランザクションは、オフィス環境内でのコミュニケーションを重要とされており、グループ会社も含めて複数のフロアにスタッフが分かれている状況があるため、相互にコミュニケーションが取りやすくなるような仕組みを導入しています。
まさにチームビルディングにおける価値観の共有や団結力の醸成、心理的安全性を産むためのコミュニケーションが活性化するような動きになるだろう。

まとめ
チームビルディングとは、共通の目標達成に向けて、メンバー同士の信頼関係やコミュニケーションを深め、役割を明確にしながら協働を促進するプロセスです。
心理的安全性や相互理解を土台に、個々の強みを活かす環境づくりやビジョンの共有を通じて、チーム全体のパフォーマンスやモチベーションを高めます。
タックマンモデルに基づく段階的な育成や、具体的な活動を通じた関係構築が成功の鍵となります。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg
