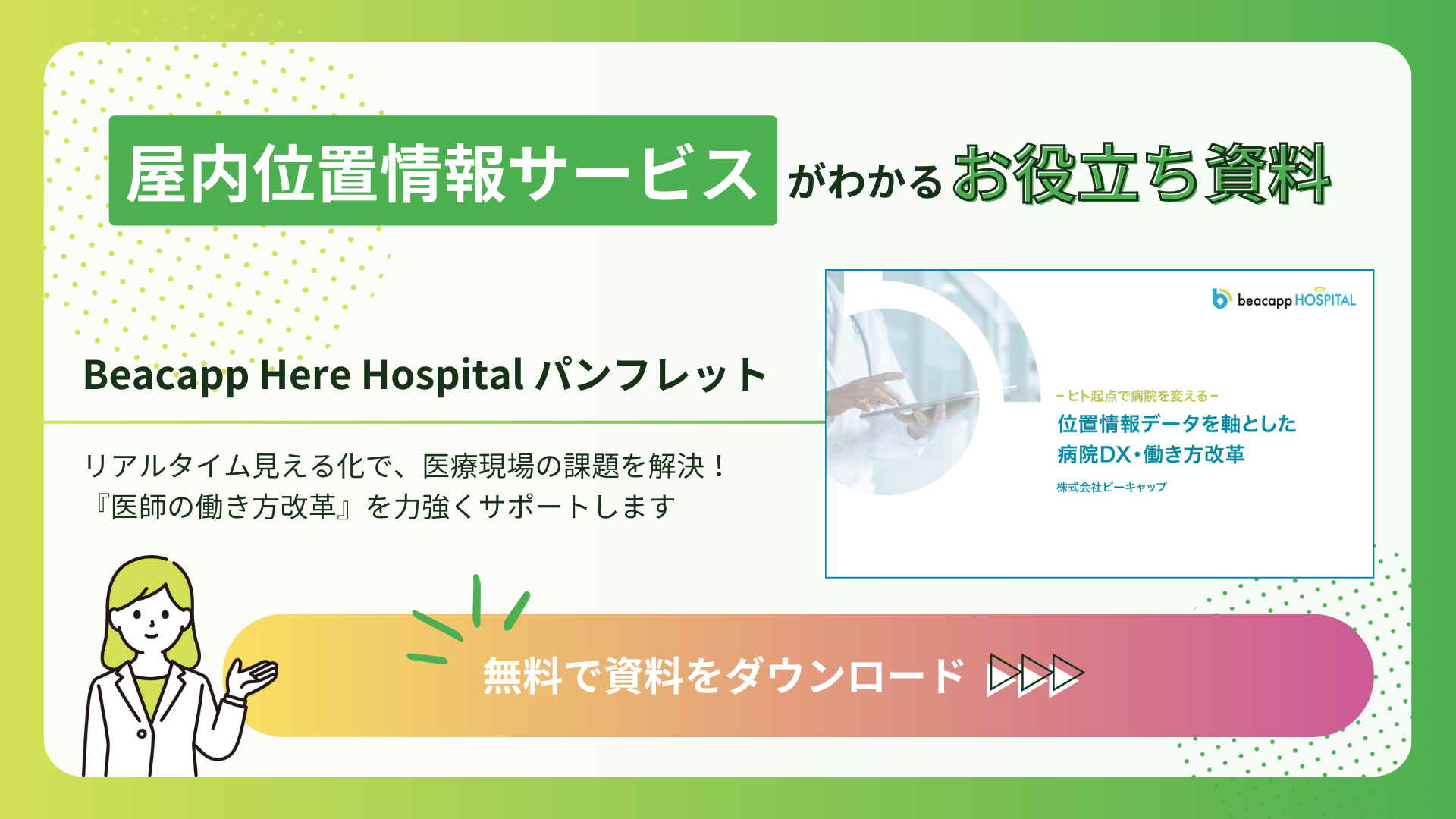病院の現場では、多様な業務が同時進行し、医療安全と効率の両立が常に求められています。しかし、人員不足や属人化、縦割りによる情報断絶が障害となり、改善の必要性は高まっています。
業務改善の第一歩は「現状の可視化」。
本記事では、その重要性と実践方法、委員会や補助金の活用、さらにはDXツールの事例を交えて解説します。
なぜ病院では業務改善が必要なのか?

手不足と業務の属人化が招くリスク
医療現場では慢性的な人手不足が続いており、限られた人員で膨大な業務をこなさなければなりません。その結果、特定の職員に業務が集中し、属人化が進行します。
属人化した業務は他のスタッフが把握しにくく、担当者が休職や退職した場合に業務が滞る危険性があります。業務の流れが担当者の経験や勘に依存するため、問題が見えにくく、非効率が放置されやすいのです。
人手不足と属人化は職員の疲弊を招くだけでなく、医療の質や安全を脅かすリスクを内包しています。
縦割り体制による情報断絶と業務効率の低下
病院は医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務職など、多様な専門職が協力して運営されています。しかし、部門ごとに独自の文化やルールが根付いており、情報が縦割りで閉ざされる傾向があります。その結果、必要な情報が共有されず、患者対応が遅れる、二重入力が発生するなどの非効率が生じます。
情報断絶は業務を煩雑にするだけでなく、患者体験にも悪影響を与えます。業務改善には、部門間の壁を取り払い、情報をスムーズに流通させる仕組みが欠かせません。
患者満足度と医療安全への影響
業務改善が不十分な環境では、患者への対応が後手に回り、待ち時間の増加や説明不足が起こりやすくなります。こうした体験は患者満足度を低下させるだけでなく、医療安全にも直結します。
例えば、情報共有が不十分なまま診療が進むと、誤診や投薬ミスのリスクが高まります。逆に、業務改善を徹底すれば、職員が余裕を持って業務に取り組め、医療サービスの質も向上します。つまり、病院業務改善は単なる効率化ではなく、患者と職員双方の安心を守る取り組みなのです。
病院業務改善の第一歩は「見える化」

職員の稼働ログから偏りやムダを発見
改善を進めるうえで欠かせないのが「見える化」です。どの業務に時間や人員が割かれているのかを把握しなければ、的確な施策は立てられません。職員の稼働ログを自動的に取得すれば、誰に業務が集中しているか、どの時間帯に負荷が高いかが一目でわかります。
例えば、特定の看護師が頻繁に長距離を移動している場合、動線や配置の改善が必要であることがわかります。データをもとに偏りやムダを把握することで、属人化を防ぎ、業務を公平かつ効率的に分担できるようになります。
定性的な声だけでは不十分、データ活用の重要性
現場の意見や感覚は改善の出発点として大切ですが、それだけでは課題を正確に把握できません。客観的なデータを併せて分析することで、業務の全体像が明らかになります。
例えば「忙しい」という声を裏付ける具体的な時間データがあれば、改善策を検討する説得力が増します。データ活用は改善活動の信頼性を高め、職員の納得感を得るうえでも不可欠です。
委員会による横断的なチェック
病院業務改善委員会のような横断組織が主体となり、各部門のデータを共有・分析する仕組みが必要です。委員会が改善活動をリードすることで、現場任せの属人的な取り組みから脱却できます。
さらに、委員会は外部の事例や制度を取り入れる窓口としても機能し、補助金申請やツール導入の調整役を担います。組織横断でのチェック体制こそが、改善を継続的に進める鍵となります。
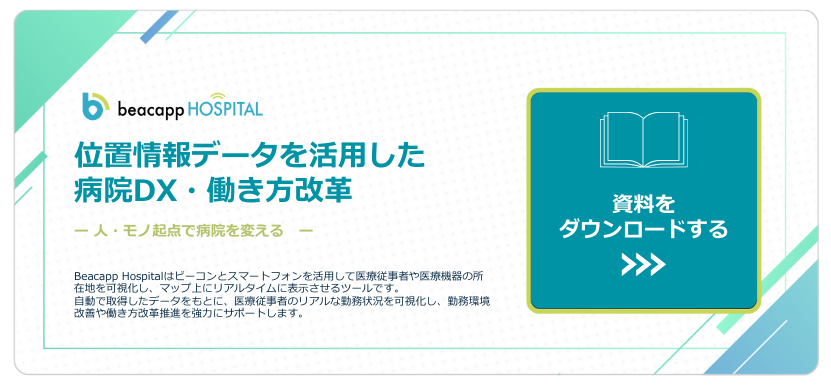
病院業務を改善するための実践施策

業務プロセスの棚卸と標準化
まず行うべきは、現場の業務を一つひとつ洗い出し、どのようなプロセスが存在するかを可視化することです。すると、二重入力や手順の重複など非効率な作業が明らかになります。そのうえで、標準化を行うことで業務の質を均一化し、属人化を防止できます。
標準マニュアルが整備されれば、新任職員でも早期に業務を習得でき、引き継ぎの負担も軽減されます。
ITツール導入とマニュアル整備の連動
電子カルテや勤怠管理システムなどのITツールは業務効率化の強力な手段ですが、導入だけでは成果が出にくいのが実情です。重要なのは、現場に即したマニュアルを整備し、職員が正しく運用できるよう支援することです。
例えば、操作方法やトラブル対応をわかりやすくまとめれば、導入初期の混乱を防げます。ツールとマニュアルをセットで整備することが、定着と効果を高めるポイントです。
多職種連携を促す「場」の設計
医師、看護師、薬剤師、検査技師など、多職種が協働する病院では、職種ごとの専門性が逆に壁となり、連携が滞ることがあります。その解消には「情報共有の場」を設けることが重要です。
定期的な合同ミーティングやチャットツールを活用した情報交換の仕組みを整えれば、リアルタイムでの意思疎通が可能になります。異なる職種の視点を活かし合うことで、改善活動の幅が広がります。
病院業務改善事例から学ぶ成功のポイント
実際の改善事例を参照することは大きなヒントになります。例えば、動線分析に基づいてナースステーションを再配置し、看護師の移動距離を削減した事例や、医療機器の所在管理システムを導入して探す時間を短縮した事例があります。
成功事例に共通するのは「小さな改善から始め、データで効果を検証する」ことです。スモールスタートを重ねて大きな成果へとつなげていく姿勢が、改善を定着させる鍵となります。
補助金・制度を活用した改善推進

病院業務改善に活用できる補助金制度
病院では、医療DX推進や業務効率化に関連する補助金が活用可能です。代表的なものに「医療機関向けDX推進補助」や「働き方改革関連助成金」などがあり、勤怠管理システム、医療機器のトレーサビリティシステム、テレワーク環境整備などが対象となります。
これらを活用することで、経営的な負担を抑えつつ業務改善の基盤を構築できます。
申請から導入までの流れと注意点
補助金申請には、事業計画書や見積書の提出が必要となり、申請から採択まで時間がかかるのが一般的です。また、導入後には実績報告も求められるため、計画的な準備が不可欠です。
注意すべきは「申請要件を満たしているか」を早期に確認することです。要件を誤解したまま進めると、せっかくの制度が利用できなくなるリスクがあります。専門家や委員会がサポートする仕組みを整えると安心です。
補助金活用事例と成果
ある病院では補助金を活用して電子カルテと勤怠システムを連動させ、残業削減に成功しました。また別の施設では、補助金で医療機器の管理システムを導入し、探す手間を削減したことで看護師の余剰時間が確保でき、患者対応に専念できるようになりました。こうした事例は「資金をきっかけに改善が進む」ことを示しています。補助金は単なる財政支援ではなく、組織変革を後押しする手段といえます。
「Beacapp Here Hospital」で実現する病院DXの第一歩
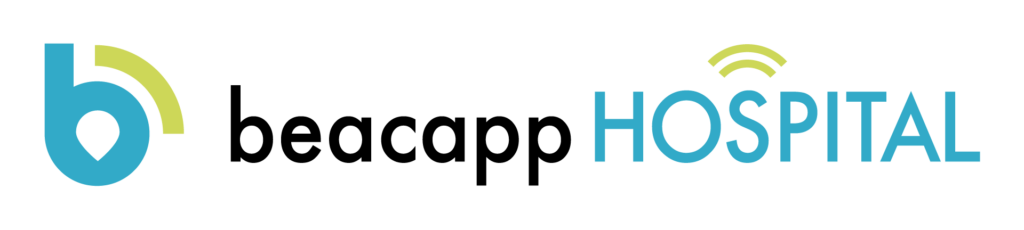
職員の位置情報で出退勤・所在を把握
従来のタイムカードや手入力による勤怠管理は、正確性や即時性に欠ける面がありました。「Beacapp Here Hospital」を導入すれば、入退館の動きをトリガーにして自動打刻が可能になり、出退勤状況をリアルタイムで記録できます。
加えて、院内での所在が把握できるため、「誰がどこにいるのか」を瞬時に確認でき、急な呼び出しや応援要請に対応しやすくなります。例えば緊急処置の場面で、最寄りの看護師や医師を即座に特定できることで、患者対応のスピードと安全性が高まります。災害時や非常時における安否確認にも有効で、危機管理の強化にもつながります。
現場負担をかけずに稼働状況を可視化
もう一つの強みは、稼働状況を「自動的に可視化」できる点です。職員が自ら記録を取る必要がないため、記録作業による負担やデータの抜け漏れが防げます。取得したログを分析することで、どの時間帯に業務が集中しているか、誰に負荷がかかっているかを把握でき、シフト調整や動線改善に役立ちます。例えば、看護師の移動距離が過度に長い場合、ナースステーションの配置や医療機器の位置を見直す根拠となります。現場の体感だけでは掴みきれない「偏りや無駄」をデータで明らかにし、改善策へつなげることができるのです。
▶︎ 導入事例はこちらをご参照ください。
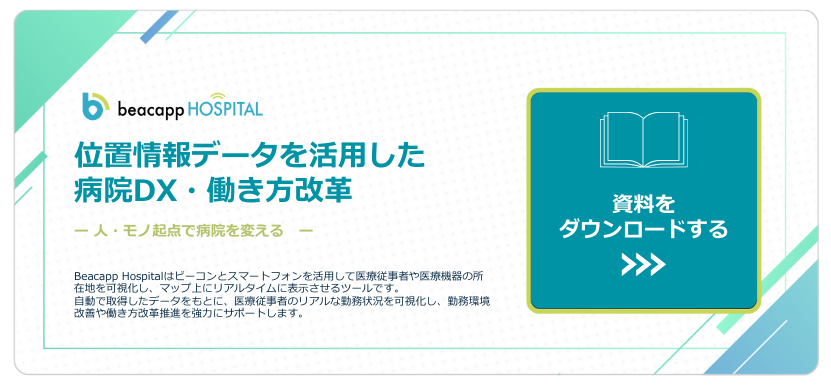
まとめ
病院業務改善は、属人化や情報断絶を解消し、データに基づいた仕組みを整えることから始まります。プロセス標準化やIT導入、補助金制度の活用に加え、DXツールによる稼働状況の可視化は大きな効果をもたらします。現場の負担を減らし、患者へのサービス向上につなげるために、組織的で持続的な改善活動が欠かせません。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg