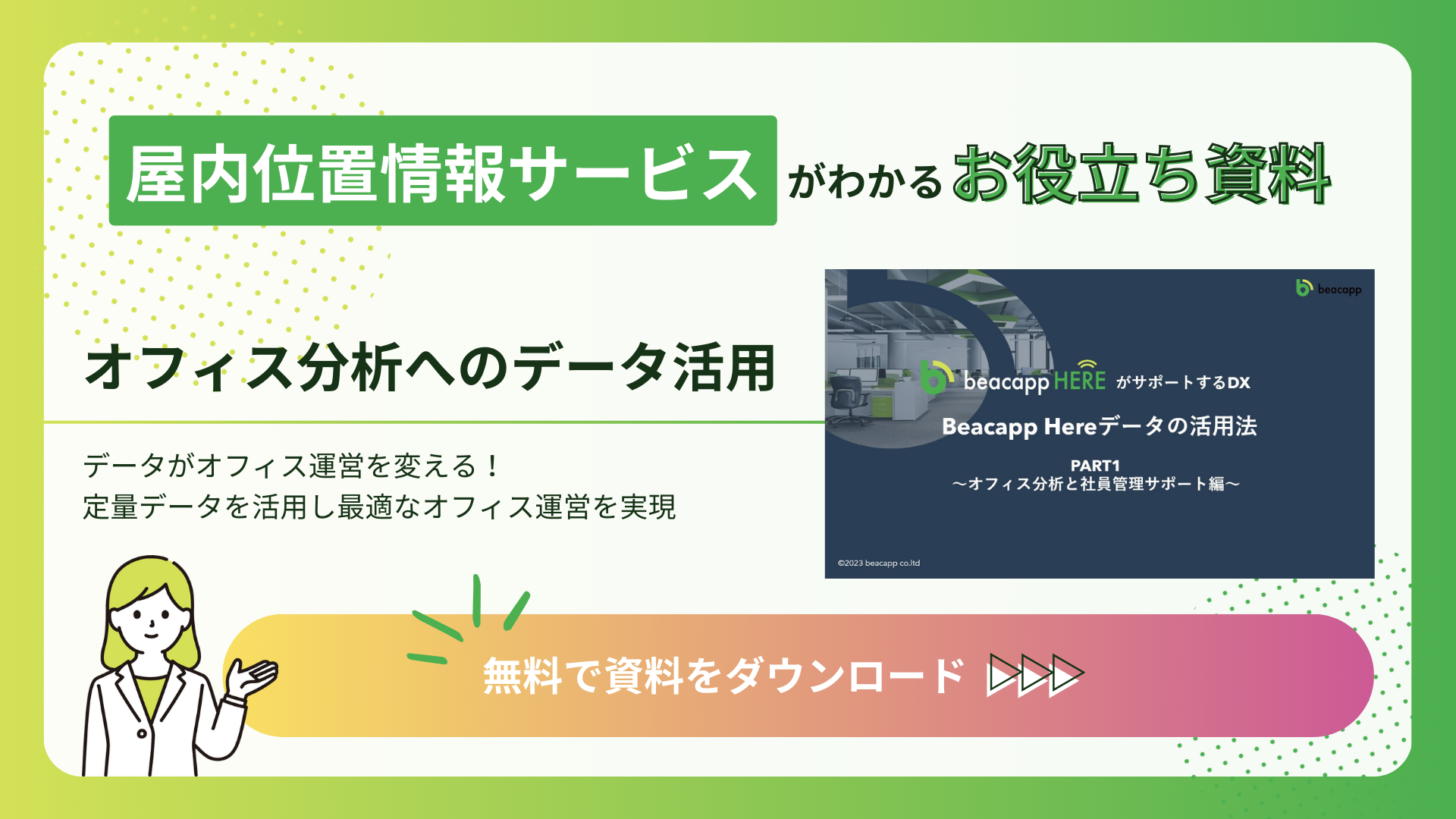リモートワークやハイブリッド勤務、さらにフリーアドレスやABWといった新しい概念の広まりによって、私たちの働き方は大きく変化しています。企業は生産性や効率だけでなく、社員の満足度や多様なライフスタイルに適応することが求められるようになりました。
本記事では「ワークスタイルとは何か」を整理しながら、具体的なワークスタイル例と導入のポイントをわかりやすく解説します。
ワークスタイルとは?基本の考え方と背景

ワークスタイル=働き方の設計思想
「ワークスタイル」とは、単に勤務形態の呼び名ではなく、企業や個人がどのように働き方をデザインするかを示す概念です。
時間や場所に制約されない柔軟な働き方を可能にする仕組み、オフィス環境のレイアウト、デジタルツールの活用などが組み合わさって初めて形になります。
従業員が力を発揮しやすい仕組みを整えることは、業績やブランド力にも直結します。そのため「ワークスタイル=働く環境を最適化する思想」と捉えるのが適切です。
多様化を促す社会的・経済的背景
ワークスタイルの多様化が注目される背景には、少子高齢化や人材不足といった社会課題、そしてデジタル技術の進展があります。
特に新型コロナウイルスの影響で、リモートワークが一気に普及し、従来の「出社が前提」という考え方が大きく揺らぎました。
さらにダイバーシティ推進や働き方改革法の施行も後押しとなり、柔軟な働き方は一時的な流行ではなく、持続可能な経営戦略の一部となっています。
ワークスタイル導入がもたらす効果
新しいワークスタイルを取り入れることで、企業は従業員の生産性向上だけでなく、採用力や定着率の強化も実現できます。また社員のワークライフバランスが改善されることで、健康面やモチベーションにも好影響を与えます。
単なる効率化ではなく、長期的に「人材が集まり成長できる環境づくり」に直結するのが大きなメリットです。
ワークスタイル例|代表的な働き方の種類

リモートワーク(在宅勤務)の特徴とメリット
リモートワークは、自宅やカフェなどオフィス以外の場所で業務を行う働き方です。通勤時間を削減できるため時間の有効活用が可能となり、育児や介護と両立する社員にとっても大きなメリットがあります。
一方で、孤立感や情報共有の難しさといった課題も存在します。そのため適切なコミュニケーション設計やITツールの導入が不可欠です。
ハイブリッド勤務で柔軟性を高める
リモートと出社を組み合わせた「ハイブリッド勤務」は、多くの企業で採用が進んでいます。オフィスでの対面交流の利点と、自宅で集中できる環境の利点を両立させることで、業務効率を高めながらも社員の自由度を確保できます。
勤務日や出社頻度を柔軟に設定する仕組みを整えることで、個々の働きやすさを尊重しつつ組織全体の一体感も維持できます。
フリーアドレス・ABWによるオフィス改革
固定席を設けないフリーアドレスや、業務内容に応じて働く場所を選ぶABWは、オフィス活用を最適化する代表例です。社員が自由に席を選べることで部署間の交流が増え、イノベーションが生まれやすい環境になります。
また、オフィス面積の削減や利用効率の向上にもつながるため、コスト削減と働きやすさの両立が可能です。
ワークスタイル導入のポイント

企業文化や事業特性に合わせた選択
ワークスタイルは「流行だから導入する」という発想ではうまくいきません。たとえば、製造業のように現場作業が必須の業態と、IT企業のようにオンラインで完結しやすい業態では最適解が異なります。
企業の歴史や風土、従業員の価値観に適合した形で導入することが重要です。形式だけを真似るのではなく「なぜこの働き方が自社に必要なのか」を明確にする必要があります。
コミュニケーション・ツール設計の工夫
リモートやハイブリッド勤務では、物理的な距離がある分、情報共有や雑談の機会が減少しやすくなります。そこでチャットツールやオンライン会議システムを効果的に組み合わせることが求められます。
また、業務報告や意思決定を見える化する仕組みをつくることで、距離を感じさせないチーム運営が可能になります。単なるIT導入ではなく「ツールをどう使いこなすか」が鍵です。
生産性と従業員満足度の両立を意識
効率性の向上だけを追い求めると、社員の疲弊やモチベーション低下を招く恐れがあります。逆に快適さだけを優先すると、組織全体の成果に悪影響を与える可能性もあります。
したがって「生産性と働きやすさのバランス」を常に意識し、定期的に見直すことが成功のポイントです。

ワークスタイルの課題と解決のヒント

孤立やチーム断絶を防ぐ取り組み
リモート勤務やフリーアドレスでは、顔を合わせる機会が減り「孤立」や「チームの分断」が生じやすくなります。これを防ぐには、雑談を含むカジュアルな交流の場を意識的に設けることが有効です。
オンラインランチや定期的なチーム振り返りの実施は、心理的なつながりを維持するうえで効果があります。
さらに、マネージャーが定期的に1on1面談を実施したり、匿名で意見を投稿できる仕組みを導入したりすることで、社員が安心して本音を共有できる環境を作ることが可能です。日常的な小さな接点の積み重ねが、信頼関係を育む基盤になります。
定性的サーベイと定量的ログの活用
従業員アンケートだけでは、働き方の実態を十分に把握することは難しい場合があります。近年は、入退室データやオンラインツールの利用状況など、定量的なログを併用する企業が増えています。
主観的な意見と客観的なデータを組み合わせることで、課題をより正確に捉え、改善につなげやすくなります。例えば「会議が多すぎる」という声が出た際に、実際の会議時間をログで確認することで、感覚と事実の差を可視化できます。
このように定性的調査と定量的データを補完的に活用することで、経営層も現場の状況を理解しやすくなり、的確な改善施策を打ち出すことが可能になります。
働く環境(物理的・心理的)の整備
快適なオフィス空間の整備や、相談しやすい心理的安全性の確保は、どのワークスタイルにおいても重要です。適切な照明や座席レイアウト、セキュリティ体制に加え、メンタルヘルスを支援する仕組みを整えることで、社員は安心して働くことができます。
また、ハイブリッド勤務の広がりに合わせて「在宅でも集中できる作業環境を整える支援」を提供する企業も増えています。たとえば在宅用の椅子やモニターを貸与する仕組み、オンライン相談窓口の常設などがその一例です。物理的な環境と心理的サポートの両面から整備することで、長期的なパフォーマンス維持につながります。
ツールを活用したワークスタイル改善例

Beacapp Hereでできること(出社状況・接触傾向・改善事例)
「Beacapp Here」は、ビーコン技術を用いて社員の出社状況や滞在場所を自動で把握できるツールです。誰がどこで働いているのかがリアルタイムに分かるため、オフィス利用率の最適化や、混雑回避に役立ちます。
また、部署を超えた接触傾向を分析することで、コミュニケーション不足や組織内の断絶を早期に察知できる点も強みです。導入企業の中には、データをもとにレイアウトを変更し、チーム間の交流を活性化させた事例もあります。
▶︎ 導入事例はこちらをご参照ください。
コラボレーションツールで強化するチーム連携
SlackやTeamsといったコラボレーションツールは、チャットやファイル共有だけでなく、プロジェクト進行の透明化に効果を発揮します。情報が散在しないよう、チャネルやタスク管理機能を使い分けることで、リモート環境下でもスムーズな意思疎通が可能になります。
特にグローバルチームや多拠点展開の企業では、言語やタイムゾーンを超えて協働するための基盤として欠かせない存在です。

まとめ
ワークスタイルは単なる勤務形態の違いではなく、企業の文化や戦略を体現する仕組みです。リモートやハイブリッド、ABWなどのワークスタイル例を理解することで、自社に合った導入のヒントが見えてきます。ツールを効果的に活用し、社員の働きやすさと組織成果を両立することが、これからの時代における鍵となるでしょう。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg