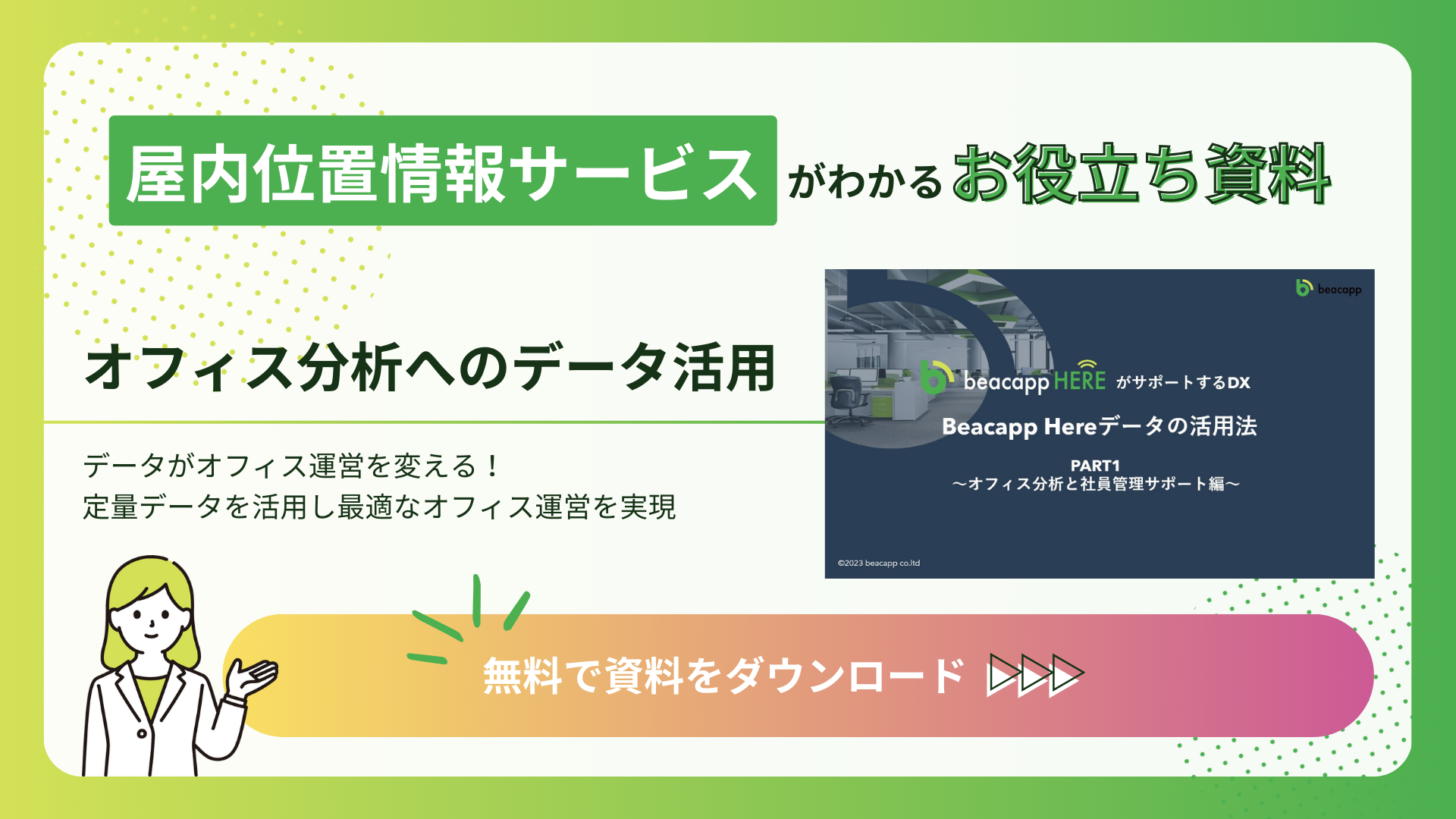多様な働き方が進む現代、企業には“働く環境”の質を向上させる取り組みが求められています。特に注目されているのが「ファシリティマネジメント」です。ファシリティマネジメントとは、単なる設備管理にとどまらず、従業員の生産性やエンゲージメントを支える重要な業務です。
本記事では、ファシリティマネジメントの仕事内容や必要なスキル、そして「Beacapp Here」による業務の“見える化”と効率化について詳しく解説します。
ファシリティマネジメントとは?

働き方やオフィスの在り方が変化する中で、施設や設備を「管理する」から「戦略的に活用する」へと、ファシリティマネジメントの役割が進化しています。本章では、その定義や業務範囲、企業における重要性を整理し、なぜ今注目されているのかを明らかにします。
ファシリティマネジメントの定義と背景
ファシリティマネジメント(Facility Management:FM)とは、企業の持つ「施設・設備・空間」といった経営資源を、戦略的に活用・管理する業務領域です。日本ファシリティマネジメント協会(JFMA)によれば、「経営および業務活動を支える施設・環境を、総合的に企画・管理・活用するマネジメント活動」とされています。
働き方の多様化や、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を背景に、オフィス環境の柔軟な運用が必要とされ、ファシリティマネジメントの役割は年々拡大しています。
業務範囲は施設管理から経営支援まで多岐にわたる
従来は建物や設備の「維持管理」が主な役割とされてきましたが、現代のファシリティマネジメントは、経営視点での戦略的な空間活用が重視されています。たとえば、フリーアドレスオフィスへの移行、リモートワーク導入後のスペース再設計、サステナビリティに配慮したエネルギー運用などが含まれます。
業務の幅広さから、施設管理だけでなく、経営、IT、総務、人事といった複数の部門と連携しながら推進されるのが特徴です。
企業のパフォーマンスに直結するファシリティ戦略
良質なファシリティマネジメントは、企業の生産性向上に直結します。たとえば、働きやすい職場環境を整えることで、従業員のパフォーマンスが向上し、離職率の低下にも寄与します。また、エネルギー管理やコスト削減を通じて、企業の利益にも貢献します。FMは「攻めの経営支援部門」として、経営層からも注目される存在となってきています。
DX・サステナビリティと連動する新しい役割
昨今では、ファシリティマネジメントにもDX(デジタルトランスフォーメーション)やサステナビリティの視点が求められています。IoTセンサーを使った出社状況の可視化や、環境負荷の少ない建物運用の実現など、FMの役割はますます高度化・多様化しています。脱炭素社会の実現に向けて、省エネ設備の導入やグリーンビルディングの推進なども、FMが担うべき重要なテーマとなっています。
ファシリティマネジメントの仕事内容とは?

ファシリティマネジメントの仕事は単なる施設の管理にとどまりません。組織の生産性を高め、安全・快適な環境を提供するために、運用・保守から空間設計、リスク管理、データ活用まで多岐にわたる業務を担っています。その具体的な仕事内容を紐解きます。
施設・設備の運用・保守・維持管理
FMの基本業務には、建物や設備の安全かつ快適な運用が含まれます。具体的には、空調・照明・給排水・エレベーターなどのインフラ管理、定期点検や法令遵守、緊急時のトラブル対応などが挙げられます。これらを適切に運用することで、建物の価値維持や利用者の安全を確保する役割を果たしています。
スペースプランニングとワークプレイス戦略
近年重視されているのが、働き方に合わせた空間設計=スペースプランニングです。オフィスのフリーアドレス化、ABW(Activity Based Working)の導入など、柔軟な働き方を実現する空間づくりが求められます。従業員の業務内容や働き方に応じて最適なレイアウトを設計し、生産性と快適性の両立を図ります。
リスク管理(BCP対策、災害対策、安全衛生)
自然災害や感染症リスクが高まる中、BCP対策はFMにとって重要な業務の一つです。災害時の避難経路や備蓄品の管理、感染対策としての換気管理や空間配置、安全衛生環境の整備など、リスクマネジメントの一翼を担います。従業員の安全と事業継続性を守る、企業の“縁の下の力持ち”といえます。
運用データの可視化と改善施策のPDCA
FMはデータドリブンな改善活動も行います。例えば、施設の使用状況やエネルギー消費データを収集・分析し、業務改善に活用します。これにより無駄なコストを削減し、より快適で効率的な職場環境づくりを推進できます。継続的なPDCAサイクルの実践が、FM業務の質を高める鍵となります。

ワークエンゲージメントとファシリティマネジメントの関係性

働く人々のモチベーションや満足度を高める「ワークエンゲージメント」は、現代の組織における重要な経営指標となっています。ここでは、その基本的な概念と、ファシリティマネジメントがどのようにエンゲージメント向上に貢献できるかを具体的に解説します。
ワークエンゲージメントとは?定義と基本概念
ワークエンゲージメントとは、仕事に対して前向きかつ没頭できる心理的な状態を指します。「活力」「熱意」「没頭」の3要素で構成され、従業員のパフォーマンスや企業全体の成果と密接に関わります。高いエンゲージメントは、離職率の低下や組織のイノベーション促進にもつながるとされています。
働く場の快適性が従業員の主体性と結びつく理由
オフィスの温度・照明・音環境、座席の配置や動線など、物理的な働く環境が心理面に与える影響は大きく、快適な環境は主体性や集中力を高める効果があります。FMはこの“働く場”の質を高める役割を担っており、従業員のモチベーションや満足度の向上に直接関与しています。
ファシリティマネジメントによるエンゲージメント向上施策
FMの視点からは、例えばフリーアドレス導入による自由度の高い働き方の実現、休憩スペースの充実、空気環境の改善などがワークエンゲージメント向上に寄与します。従業員が「働きたい」と思える職場づくりこそが、企業の持続的成長の基盤になります。
空間設計・行動導線・心理的安全性の影響
オフィス内の行動導線や動きやすさ、視界の抜け感、パーソナルスペースの確保といった空間設計も、心理的安全性に影響を与えます。誰でも気軽に意見が言える環境づくりには、物理的なレイアウトが大きく関わります。FMはこうした心理面への配慮も重要視し、設計段階から「人が安心して働ける空間とは何か?」という視点を取り入れます。
特にハイブリッドワークやチームごとの多様な働き方が一般化する中で、行動導線に無理がない配置や、偶発的なコミュニケーションを促すオープンスペースの設置などが、社員同士の連携強化にもつながります。ファシリティマネジメントは、物理的な“場”の最適化を通じて、心理的安全性や信頼関係の醸成を支援する役割を担っているのです。
ファシリティマネジメントに役立つ資格と必要なスキル

高度化・多様化するファシリティマネジメント業務を担うには、幅広い知識とスキルが求められます。本章では、役立つ資格や必要とされる能力、さらには資格取得がキャリアに与える影響について詳しく紹介します。
国内外の代表的な資格(CFMJ、ビル管理技術者など)
FM業務に必要な知識とスキルを証明する資格として、国内では「認定ファシリティマネジャー(CFMJ)」が代表的です。日本ファシリティマネジメント協会(JFMA)が認定し、総合的な知識・実務経験が求められます。
また、建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)は、法令に基づいた建物の維持管理に関わる国家資格で、ビル設備の保守業務に必須とされるケースも多いです。海外ではIFMA認定のCFM(Certified Facility Manager)が国際的に通用する資格とされています。
コミュニケーション力・論理的思考・マネジメント力
FM担当者には、多岐にわたる業務を円滑に進めるための“対人スキル”が求められます。建物利用者である社員から、設備業者、清掃・警備会社、さらには経営層まで、多くの関係者と調整する立場にあるためです。論理的思考をもって改善提案を行い、チームを動かすマネジメント力が、FMの仕事を成功に導く鍵となります。
業務改善に必要なデータ分析・ITスキル
近年では、IoTセンサーやBIツールなどを活用して、施設の使用状況を可視化することが一般的になりつつあります。
たとえば、空間の稼働率や出社傾向のデータを分析し、効率的なスペース運用やエネルギーコストの最適化を行う能力が求められます。エクセルやデータベース操作に加えて、Power BIやTableauなどのデータ可視化ツールの活用経験も大きな強みになります。
資格取得によるキャリアアップの可能性
資格を取得することで、FMに関する専門性を明確に証明でき、転職市場や社内での昇進にも有利に働きます。特に大企業や外資系企業では、CFMJやビル管理技術者を持つ人材が重宝され、プロジェクトリーダーやマネージャー職へのステップアップも可能です。
また、業務知識を体系化することで、より戦略的な提案や課題解決ができるようになり、経営層からの信頼も得やすくなります。
Beacapp Hereが実現 ファシリティマネジメントの見える化

DXの進展により、ファシリティマネジメントもデータドリブンな改善が可能になりました。「Beacapp Here」は、出社率や行動データの可視化を通じて、働き方の最適化と業務効率化を支援する革新的なツールです。その具体的な活用法と効果に迫ります。
出社率・滞在傾向・人の流れをリアルタイムで可視化
「Beacapp Here」は、スマートフォンやビーコンを用いてオフィス内の人の動きや滞在状況をリアルタイムで可視化するソリューションです。たとえば、どのフロアにどれだけの人がいるのか、誰がいつどこに出社していたかといった情報が即座に把握できます。これにより、FM担当者は混雑状況を見ながら空間配置を柔軟に変更することができ、快適なオフィス環境の実現に貢献します。
スペースの稼働率分析と空間最適化への応用
Beacapp Hereでは、会議室の稼働率やワークスペースの使用状況をデータとして収集・分析できます。使用頻度の低いスペースの見直しや、人気の高いスペースの拡充など、データに基づいた空間最適化が可能になります。これにより、スペースの有効活用が進み、不要な賃料や管理コストの削減にもつながります。
行動データに基づくワークプレイス改善とコスト削減
社員の行動パターンを可視化することで、「動線の無駄」や「使われていない設備」など、これまで見えなかった非効率を発見できます。こうした改善の積み重ねが、長期的なコスト削減とパフォーマンス向上を実現します。さらに、定量データに基づく改善提案は、経営層への説得力あるレポートにも活用可能です。
ワークエンゲージメントの向上を支援する機能とは
Beacapp Hereは、単なる施設の“見える化”だけでなく、「働きやすさ」や「心理的安全性」の向上にも寄与します。たとえば、アプリから「どの席が空いているか」をリアルタイムで確認できることで、出社前の不安を解消したり、ストレスなく最適な作業環境を確保できたりします。
また、滞在データとアンケート結果を組み合わせることで、「どの環境が最も満足度が高いか」「どの部署でエンゲージメントが低いか」といった、定性的・定量的な分析が可能になります。
このような機能は、ファシリティマネジメントが単なる設備管理ではなく、「人」に寄り添う戦略的な役割を担う存在であることを強く後押しします。結果として、エンゲージメントの可視化→改善→成果の測定というサイクルが可能になり、持続的な働き方改革へとつながっていきます。

まとめ
ファシリティマネジメントは、オフィス環境の最適化を通じて、従業員の生産性やエンゲージメントを高める戦略的な業務です。Beacapp Hereのようなツールを活用することで、出社状況や空間の利用状況をリアルタイムで把握し、感覚ではなくデータに基づいた判断と改善が可能になります。今後の働き方の進化に対応するためにも、ファシリティマネジメントの重要性はますます高まっていくでしょう。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg