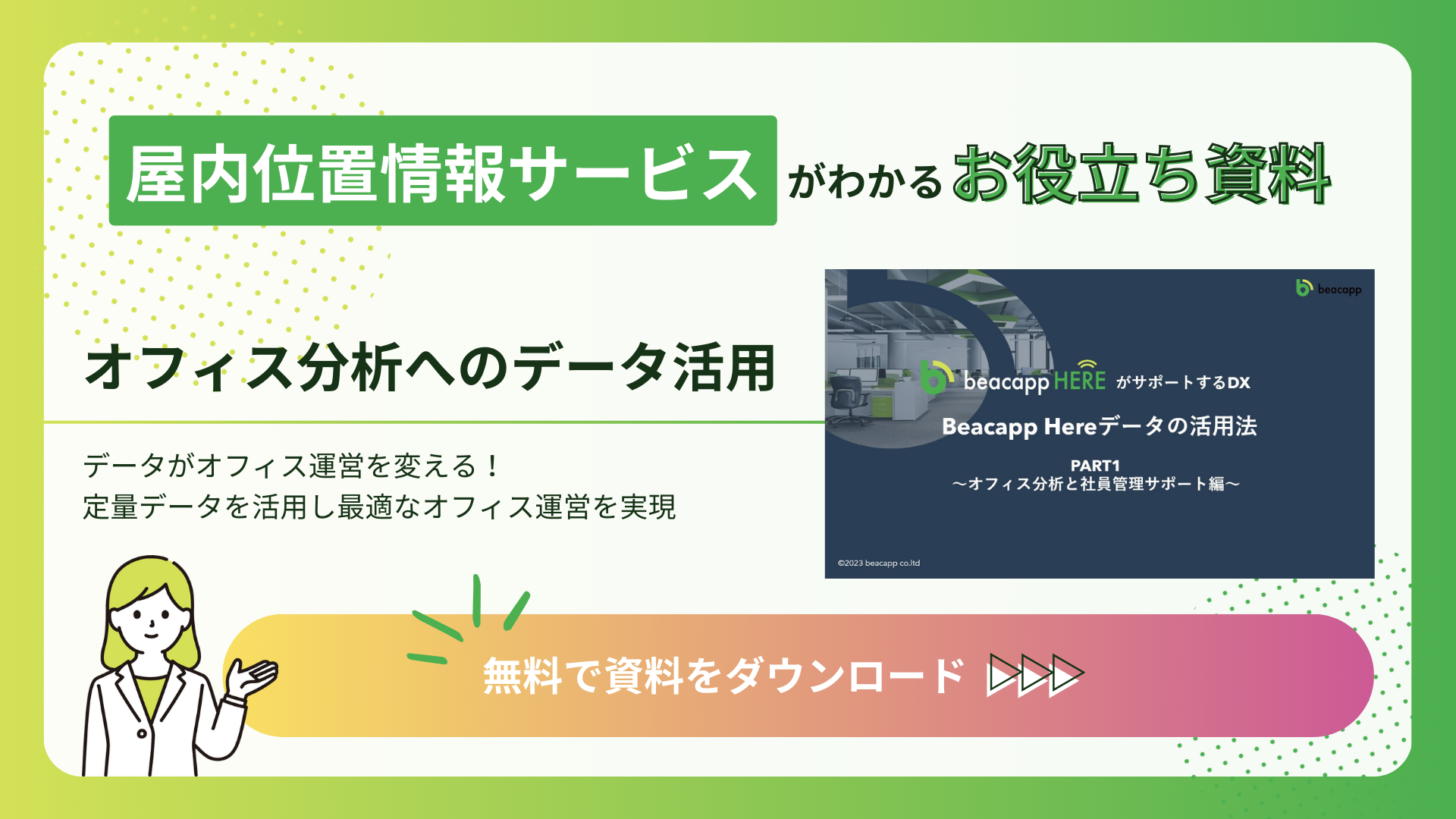近年、働き方の多様化やオフィスの在り方の見直しが進む中で、「ファシリティマネジメント(FM)」や「プロパティマネジメント(PM)」の重要性が高まっています。企業が保有・運用する施設や不動産を、いかに効率的かつ戦略的に活用できるかが、経営の成果にも直結する時代です。
本記事では、FMとPMの定義や役割の違い、現場で求められるスキル、そして共通する課題や最新のテクノロジーによる解決手段までを網羅的に解説します。施設管理に関わる方や、今後の業務改善を検討している方にとって、具体的なヒントとなる情報をお届けします。
ファシリティマネジメントとは?その目的と具体業務

ファシリティマネジメント(FM)とは、企業や組織が保有する施設や設備を効率的に管理・運用するための戦略的な手法です。その目的は、業務の生産性を向上させることや、コストの最適化、さらには従業員の快適な働き環境を提供することにあります。
働き方の多様化やテクノロジーの進化により、企業の施設管理にも柔軟かつ戦略的な対応が求められるようになっています。そこで注目されているのが、ファシリティマネジメント(FM)という考え方です。FMは、職場の生産性や快適性を高めるために、建物や設備、環境を包括的に管理・改善していく取り組みを指します。
ファシリティマネジメントの定義と目的
ファシリティマネジメント(FM)とは、企業や組織が保有する施設やインフラを効率的に運用・管理するための戦略的なアプローチを指します。その目的は、施設の機能性や快適性を向上させることで、従業員の生産性を高め、企業全体の業務効率を向上させることにあります。
FMは、単なる施設の維持管理にとどまらず、利用者のニーズを把握し、快適な作業環境を提供することが重要です。これにより、従業員のモチベーションや満足度を向上させ、企業の競争力を高めることが期待されます。
ファシリティマネジメントの主な業務
ファシリティマネジメント(FM)の主な業務は、企業や組織が保有する施設の効率的な運用と管理を行うことです。具体的には、施設の維持管理、設備の保守点検、空間の最適化、エネルギー管理、セキュリティ対策などが含まれます。
また、FMはコスト管理や予算策定にも関与し、施設の運用にかかる費用を最小限に抑えるための戦略を立てることも求められます。ファシリティマネジメントは、単なる施設管理にとどまらず、企業全体の戦略に寄与する重要な役割を担っています。
ファシリティマネージャーに求められる視点とスキル
ファシリティマネージャーは、企業の施設や設備を効率的に運用・管理するために、さまざまな視点とスキルを求められます。まず、戦略的思考が重要です。企業のビジョンや目標に沿った施設の運用計画を立てるためには、経営戦略を理解し、それに基づいた施設の最適化を図る必要があります。
次に、コミュニケーション能力も欠かせません。ファシリティマネージャーは、社内のさまざまな部門や外部の業者との連携が求められるため、円滑な情報共有や調整ができる能力が必要です。また、問題解決能力も重要で、突発的なトラブルや課題に対して迅速に対応し、適切な解決策を見出す力が求められます。
さらに、最新のテクノロジーに対する理解も不可欠です。IoTやビッグデータを活用した施設管理が進む中、これらの技術を駆使して効率的な運用を実現するための知識が必要です。
関連記事: ファシリティマネジメントとは?施設管理との違いや業務内容を解説!
プロパティマネジメントとは?その目的と具体業務

プロパティマネジメント(PM)とは、不動産の運営・管理を専門とする業務であり、主に賃貸物件の収益性を最大化することを目的としています。オーナーの利益を守りつつ、テナントにとっても快適な環境を提供することが重要な役割となります。
プロパティマネジメント(PM)は、不動産を単なる「所有物」としてではなく、「収益を生む資産」として戦略的に活用していくための管理手法です。物件の価値を保ちつつ、収益性を最大限に引き出すことが主な目的とされ、オーナーの利益とテナントの満足度の両立が求められます。
プロパティマネジメントの定義と目的
プロパティマネジメント(PM)とは、不動産の運営・管理を専門とする業務であり、主に賃貸物件や商業施設の価値を最大化することを目的としています。具体的には、物件の維持管理、テナントの募集・契約、賃料の設定や収集、さらには施設の運営に関する戦略的な計画を立てることが含まれます。
PMの目的は、単に物件を管理するだけでなく、投資家やオーナーに対して安定した収益を提供し、資産価値を向上させることです。これにより、テナントにとっても快適で魅力的な環境を提供し、長期的な関係を築くことが可能になります。プロパティマネジメントは、経済的な利益を追求するだけでなく、地域社会や環境への配慮も重要な要素となっています。
プロパティマネジメントの主な業務
プロパティマネジメント(PM)は、不動産の運営と管理を専門とする分野であり、その主な業務は多岐にわたります。まず、テナントの募集や契約管理が重要な業務の一つです。適切なテナントを選定し、契約条件を整えることで、物件の収益性を高めることが求められます。
次に、賃料の徴収や管理もPMの重要な役割です。定期的な賃料の請求や未払いのフォローアップを行い、収益の安定化を図ります。また、物件の維持管理も欠かせません。定期的な点検や修繕計画を立て、物件の価値を保つための適切なメンテナンスを実施します。
プロパティマネージャーに求められる視点とスキル
プロパティマネージャーは、不動産の運営や管理を担当する専門家であり、その役割を果たすためには多様な視点とスキルが求められます。まず、プロパティマネージャーは市場動向を把握し、競争力のある賃料設定やテナントの獲得戦略を立てるためのマーケティングスキルが必要です。
さらに、財務管理の知識も欠かせません。収支計画や予算管理を行い、物件の収益性を最大化するための分析力が求められます。加えて、法律や規制に関する理解も必要で、契約書の作成やトラブル対応において適切な判断を下すための法的知識が不可欠です。
最後に、プロパティマネージャーは、施設の維持管理や改善提案を行うための技術的な知識も必要です。

ファシリティマネジメントとプロパティマネジメントの違いとは?

ファシリティマネジメント(FM)とプロパティマネジメント(PM)は、どちらも不動産や施設の管理に関わる重要な役割ですが、その目的や業務内容には明確な違いがあります。
それぞれの役割を理解することが、効果的な運用につながります。
ファシリティマネジメントとプロパティマネジメントの違いを項目ごとに比較
FMは主に施設の運営効率や利用者の快適性を向上させることを目的とし、設備の保守管理や空間の最適化、環境の整備などを行います。一方、PMは不動産の価値を最大化することを重視し、賃貸契約の管理や収益の最大化、資産価値の維持・向上に焦点を当てています。
次に、業務内容においても違いが見られます。FMは、施設内の設備管理や安全対策、環境管理など、日常的な運営に関する業務が中心です。対して、PMは賃貸物件の管理やテナントとのコミュニケーション、収益分析など、より経済的な視点からの業務が求められます。このように、FMとPMはそれぞれ異なる視点と目的を持ちながら、施設や不動産の管理に貢献しています。
ファシリティマネジメントとプロパティマネジメントに共通する業務と、それぞれの専門領域
ファシリティマネジメント(FM)とプロパティマネジメント(PM)は、どちらも企業の不動産や施設の管理に関わる重要な役割を担っていますが、それぞれの専門領域には明確な違いがあります。共通する業務としては、施設の維持管理やコスト管理、テナントとのコミュニケーションが挙げられます。これらの業務は、効率的な運用を実現するために不可欠です。
一方で、FMは主に施設の機能性や快適性を向上させることに重点を置き、オフィス環境の改善や設備の最適化を図ります。これに対し、PMは不動産の価値を最大化することを目的とし、賃貸契約の管理や収益の最大化に注力します。
ファシリティマネジメントとプロパティマネジメントに共通する課題

ファシリティマネジメント(FM)とプロパティマネジメント(PM)は、それぞれ異なる役割を持ちながらも、共通の課題に直面しています。
施設の稼働状況や利用実態の把握が難しい
ファシリティマネジメント(FM)やプロパティマネジメント(PM)において、施設の稼働状況や利用実態を正確に把握することは非常に重要ですが、実際には多くの課題が存在します。例えば、オフィスの利用率や会議室の稼働状況をリアルタイムで把握することは、従来の手法では困難です。多くの企業では、利用状況を手動で集計したり、従業員からのフィードバックに依存しているため、データの正確性やタイムリーさに欠けることが多いのです。
また、施設の利用実態を把握するためには、さまざまなデータを収集し、分析する必要がありますが、これには時間とリソースがかかります。特に、複数の施設を管理している場合、各施設ごとのデータを統合することはさらに難易度が上がります。このような状況では、適切な意思決定ができず、業務改善の機会を逃してしまうことも少なくありません。
したがって、FMやPMの現場では、データ収集や分析の効率化が求められています。最新のテクノロジーを活用することで、施設の稼働状況を可視化し、より迅速かつ正確な判断ができる環境を整えることが、今後の課題となるでしょう。
データ不足による判断の属人化と改善の遅れ
ファシリティマネジメントやプロパティマネジメントにおいて、データの不足は大きな課題となります。特に、施設の稼働状況や利用実態に関する情報が不十分であると、意思決定が個々の経験や感覚に依存しがちです。このような判断の属人化は、業務の効率性を低下させ、改善策の実施が遅れる原因となります。
データの収集と分析を強化し、客観的な情報に基づいた意思決定を行うことが、ファシリティマネジメントやプロパティマネジメントの改善において不可欠です。最新のテクノロジーを活用することで、リアルタイムでのデータ収集が可能となり、より迅速かつ的確な判断ができるようになります。
屋内位置情報サービスで実現する施設管理・運用の可視化

近年、屋内位置情報サービスが注目を集めています。これにより、施設内の人やモノの位置情報をリアルタイムで把握することが可能となり、ファシリティマネジメントの効率化が図れます。
人やモノの位置情報を活用したファシリティ最適化の支援
近年、ファシリティマネジメントにおいては、位置情報サービスの活用が注目されています。特に、オフィス内での人やモノの動きをリアルタイムで把握することで、施設の効率的な運用が可能になります。例えば、従業員の出社状況や会議室の利用状況をデータとして収集し、分析することで、無駄なスペースを削減し、必要な場所にリソースを集中させることができます。
このような位置情報を活用することで、ファシリティマネージャーは、オフィスのレイアウトや設備の配置を最適化し、従業員の働きやすさを向上させることができます。また、データに基づいた意思決定が可能になるため、経営層にとっても戦略的な運用が実現しやすくなります。
会議室の稼働率や出社傾向を把握してレイアウトを改善
ファシリティマネジメントにおいて、会議室の稼働率や出社傾向を把握することは、効率的なスペースの利用に直結します。
例えば、特定の時間帯に会議室が頻繁に使用されている場合、その時間帯に合わせたレイアウトの見直しや、追加の会議室の設置を検討することが可能です。
また、出社傾向を分析することで、社員が集まりやすい環境を整えることができ、コミュニケーションの活性化にも寄与します。
さらに、データを基にしたレイアウト改善は、社員の満足度向上にもつながります。例えば、会議室の配置を見直すことで、移動時間を短縮し、業務の効率化を図ることができます。
接触傾向データによるコミュニケーション促進
接触傾向データは、施設内での人々の動きや接触のパターンを把握するための重要な情報源です。このデータを活用することで、企業は従業員同士のコミュニケーションを促進し、より良い職場環境を構築することが可能になります。
例えば、特定のエリアでの接触頻度が高い場合、その場所をオープンスペースとして活用することで、自然な会話やコラボレーションが生まれやすくなります。また、接触傾向データを分析することで、従業員が集まりやすい時間帯や場所を特定し、会議室の予約やレイアウトの最適化に役立てることもできます。
具体事例:三井不動産株式会社
三井不動産株式会社では、オフィスの利便性と生産性向上を目的に、位置情報サービス「Beacapp Here」を導入しました。社員の所在をリアルタイムに可視化することで、フリーアドレス環境でのコミュニケーションや会議調整がスムーズになり、業務効率やテナント満足度の向上に貢献しています。
さらに、蓄積されたデータを活用し、レイアウト変更や設備投資の判断にも役立てています。こうしたスマートな施設管理は、プロパティマネジメントの質を高める新しい手法として注目されています。
詳細な事例については、[こちらのリンク](三井不動産株式会社 | 導入事例 | Beacapp Here(屋内位置情報サービス) | 所在地見える化でオフィス内の在席管理 | オフィス DX)からご覧いただけます。

まとめ
ファシリティマネジメントとプロパティマネジメントは、目的や視点こそ異なりますが、いずれも企業や施設の価値を最大化するうえで欠かせない存在です。
FMは働く人の快適性や業務効率を、PMは不動産としての収益性と資産価値を重視します。両者を適切に機能させるためには、戦略的な視点に加え、データに基づく判断や最新技術の活用が不可欠です。今後のFM・PMは、テクノロジーとの融合によって、さらに進化していくことが期待されます。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg