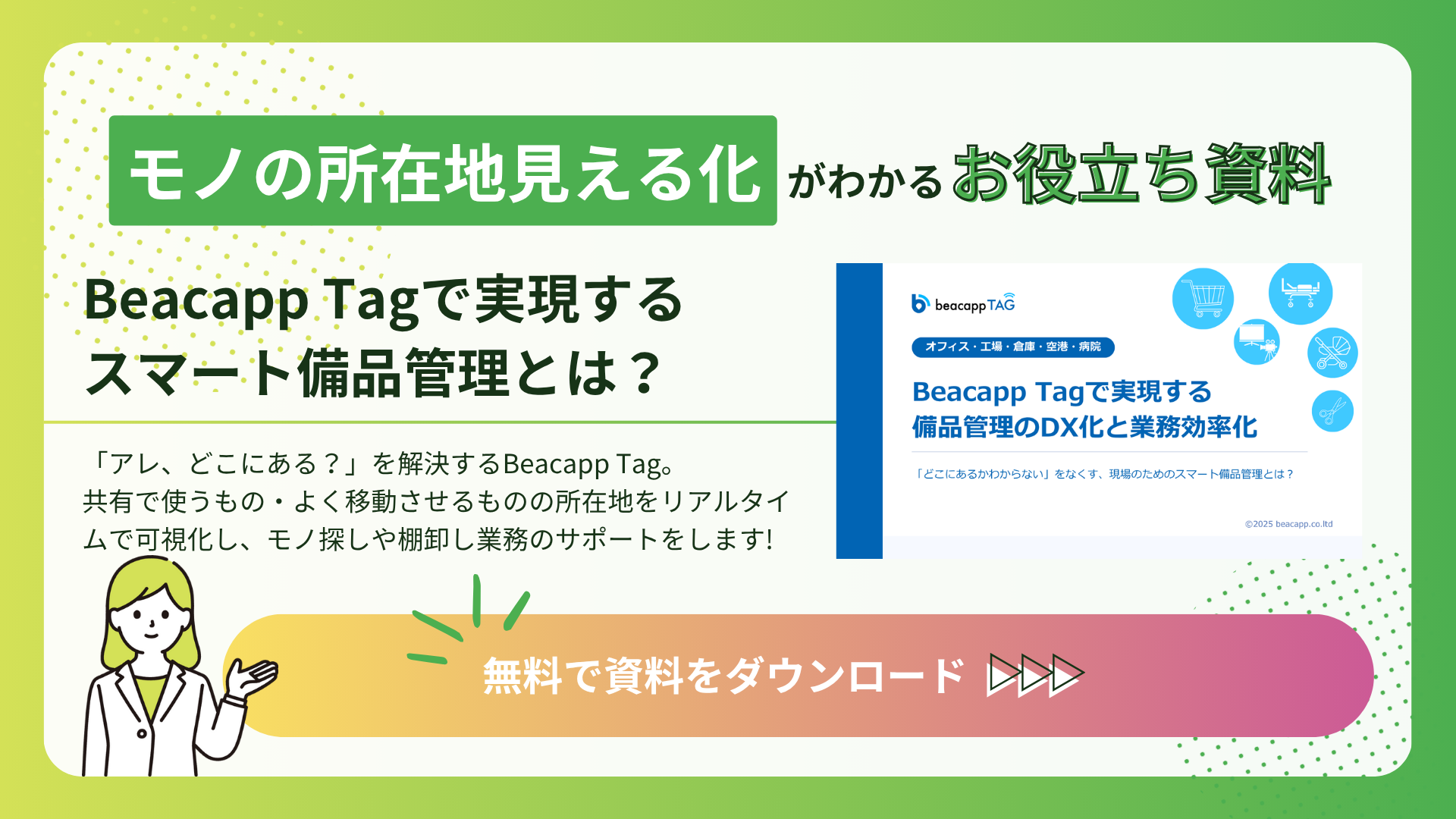工場現場における安全管理は、従業員の生命と企業の信頼性を守る上で極めて重要です。従来の手法に加え、近年ではデジタル技術が安全対策として広く導入されています。
本記事では、基本的な安全管理から、職場巡視、一人作業の可視化、BCP対策に至るまで、工場における安全確保のためのデジタル活用術を包括的にご紹介します。
工場の安全対策とは?知っておくべき基本ポイント

安全対策がなぜ重要か
工場内には、高温を発する機械設備、重量物を扱う重機、高圧電流が流れる電気設備など、様々な危険源が存在します。このような環境下で日々多岐にわたる作業が行われる中、事故を未然に防ぐための安全対策を徹底することは、従業員の生命と健康を守る上で極めて重要です。
万が一、工場で事故が発生した場合、負傷者は身体的・精神的な苦痛を強いられ、その後の生活にも多大な影響を及ぼす恐れがあります。また、事故により生産ラインの一時的または長期的な停止が発生し、製品の納品遅延や生産量の減少を招くことで、企業に多大な経済的損失を与えます。
これらのリスクを回避し、企業の持続的な発展を確実なものとするためには、安全対策の徹底が不可欠です。具体的には、危険源の特定とリスク評価、作業手順の明確化と遵守、安全装置の設置と定期的な点検、従業員への安全教育の実施と意識向上、そして緊急時の対応体制の確立などが挙げられます。
これらの対策を確実に実行することで、従業員が安心して業務に専念できる環境を整備し、企業の安定的な経営基盤を構築することが可能となります。
製造業における労働災害の発生状況や事故の種類
厚生労働省のデータ※によると、日本の製造業では毎年数万人規模の労働災害が発生しており、その多くは適切な対策によって予防可能です。これらの事故は、従業員の健康と安全を脅かすだけでなく、企業の生産性低下や経済的損失にもつながります。
主な事故類型としては、以下のようなものが挙げられます。
- 機械への巻き込まれ: 作業中に衣服や身体の一部が機械に巻き込まれる事故で、重傷を負うケースが多く見られます。機械の安全カバーの不備や、稼働中の機械への不適切な接近などが主な原因です。
- 墜落・転落: 高所作業や不安定な足場からの転落事故です。安全帯の不着用、手すりの未設置、作業場所の整理整頓不足などが背景にあります。
- 感電: 電気設備や配線の不適切な取り扱いにより、電流が人体を流れる事故です。電気工事の知識不足、絶縁保護具の不使用、老朽化した設備の放置などが原因となります。
- 化学薬品による火傷: 有害な化学物質の取り扱いミスにより、皮膚や目に火傷を負う事故です。保護具の不着用、換気不足、SDS(安全データシート)の確認不足などが挙げられます。
これらの労働災害の多くは、基本的な安全確認の怠りや不適切な作業手順に起因しています。具体的には、作業前のリスクアセスメントの不実施、安全衛生教育の不足、ヒューマンエラーを誘発しやすい作業環境などが挙げられます。
労働災害を減少させるためには、企業は以下の対策を講じる必要があります。
- リスクアセスメントの徹底: 作業工程における潜在的な危険源を特定し、そのリスクを評価するとともに、適切な防止策を講じる。
- 安全衛生教育の充実: 従業員に対し、作業内容に応じた安全知識や技能、緊急時の対応方法などについて定期的に教育を行う。
- 作業手順の明確化と遵守: 安全な作業手順を定め、それを周知徹底し、従業員が確実に遵守するよう指導・監督する。
- 安全設備の導入と維持管理: 機械の安全カバー、墜落防止設備、換気装置などの安全設備を適切に設置し、定期的に点検・保守を行う。
- 保護具の適切な使用: 作業内容に応じた保護具(ヘルメット、安全靴、保護メガネ、防護服など)を従業員に着用させ、その正しい使用方法を指導する。
- 作業環境の改善: 整理整頓の徹底、照明の確保、通路の確保など、安全で快適な作業環境を整備する。
労働災害の防止は、従業員の安全と健康を守るだけでなく、企業の社会的責任を果たす上でも極めて重要です。企業と従業員が一丸となって安全意識を高め、予防対策を徹底することで、より安全な職場環境を築き、持続可能な事業活動を実現することができます。
※厚生労働省 労働災害発生状況:
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei
工場が実施するべき安全対策とその種類
工場における安全対策は、大きく「ハード対策」と「ソフト対策」の二つの側面から総合的に実施され、それぞれが補完し合うことで、工場全体の安全性を高めます。
ハード対策:物理的な安全の確保
ハード対策とは、危険源そのものを排除または低減するために、物理的な設備や装置を導入する措置を指します。具体的には、以下のような対策が含まれます。
- 安全柵・カバーの設置: 可動部分や高温部分、高電圧部分など、直接触れることで危険が生じる箇所には、安全柵や保護カバーを設置し、作業員の誤接触を防ぎます。特に、ロボットや自動機械が稼働するエリアでは、作業員の侵入を制限する物理的なバリアが重要です。
- センサー・インターロックの導入: 機械の異常停止や扉の開閉を検知するセンサー、および特定の条件が満たされない限り機械が作動しないようにするインターロックシステムは、不測の事態による事故を未然に防ぎます。例えば、安全扉が開いている間は機械が稼働しない、といったシステムです。
- 換気装置・集塵機の設置: 有害物質や粉塵が発生する作業場では、適切な換気装置や集塵機を導入し、作業環境中の汚染物質濃度を許容範囲内に保ちます。これにより、呼吸器系の疾患やアレルギー反応のリスクを低減します。
- 緊急停止装置の設置: 予期せぬトラブルや緊急事態が発生した際に、瞬時に機械の運転を停止させるための緊急停止ボタンは、作業場内のアクセスしやすい場所に複数設置されるべきです。
- 耐震・防火設備の強化: 地震や火災といった災害に備え、建物の耐震補強、消火器・スプリンクラーの設置、避難経路の確保など、物理的な防災対策もハード対策の一部として重要です。
- 作業環境の整備: 照明の適切な照度確保、通路の明確化と障害物の排除、滑りにくい床材の採用など、物理的な作業環境の改善も事故防止に貢献します。
ソフト対策:人的要素による安全意識の向上
ソフト対策とは、従業員の安全意識を高め、危険を予知・回避する能力を向上させるための人的な取り組みを指します。ハード対策だけでは防ぎきれないヒューマンエラーによる事故を減らす上で極めて重要です。
- 安全教育・研修の実施: 新規入社時や配置転換時だけでなく、定期的に安全衛生に関する教育を実施することが不可欠です。これには、一般的な安全ルールの周知だけでなく、特定の作業手順や機械操作に関する危険性、緊急時の対応方法などが含まれます。
- 危険予知トレーニング(KYT): 作業開始前や作業中に潜在する危険を予測し、その危険を回避するための対策を話し合うトレーニングです。グループで行うことで、多角的な視点から危険源を特定し、安全意識を共有することができます。
- 職場巡視・安全パトロール: 管理者や安全担当者が定期的に職場を巡視し、危険な状況や不安全行動がないかを確認します。これにより、潜在的なリスクを発見し、改善を促すことができます。また、作業員とのコミュニケーションを通じて、現場の声を吸い上げる機会ともなります。
- ヒヤリハット活動: 実際に事故には至らなかったものの、一歩間違えば事故につながりかねなかった事例(ヒヤリハット)を積極的に報告・共有し、その原因と対策を検討する活動です。これにより、重大事故の予防につながります。
- リスクアセスメントの実施: 作業工程や使用する機械設備に潜む危険性や有害性を特定し、そのリスクの大きさを評価した上で、リスク低減措置を決定するプロセスです。法的な義務でもあり、具体的な安全対策を計画する上で基礎となります。
- 作業標準書の作成と遵守: 各作業の安全な手順を明確に定めた作業標準書を作成し、全ての作業員がこれを遵守するように徹底します。これにより、作業のバラつきをなくし、不安全な作業方法を排除します。
- 健康管理とメンタルヘルス対策: 従業員の健康状態は安全な作業遂行に直結するため、定期健康診断の実施、過重労働対策、ストレスチェック制度の導入など、心身の健康維持にも配慮します。
これらのハード対策とソフト対策を組み合わせ、PDCAサイクル(計画-実行-評価-改善)を回しながら継続的に安全活動を推進することで、工場全体の安全文化を醸成し、無事故・無災害の達成を目指すことが可能となります。
産業医・衛生管理者による職場巡視をデジタルで効率化する

作業環境
職場巡視における作業環境の確認は、安全衛生管理の基本です。単に目で見て確認するだけでなく、より詳細かつ継続的な監視が求められます。具体的には、以下の項目について定期的なチェックと改善策の検討が必要です。
- 換気状態: 粉塵、有害ガス、蒸気などが滞留していないか、換気扇やダクトが正常に機能しているかを確認します。CO2濃度計などのIoTセンサーを導入することで、換気状況をリアルタイムで数値で把握し、基準値を超えた場合に自動で警報を発したり、換気システムを稼働させたりすることが可能になります。
- 照度: 作業内容に適した十分な照度があるかを確認します。特に精密作業を行う場所では、適切な明るさの確保が目の疲労軽減やミスの防止に直結します。照度計を用いた定期的な測定に加え、時間帯や天候に合わせた自動調光システムの導入も有効です。
- 騒音: 製造ラインや機械設備から発生する騒音が許容範囲内であるかを確認します。騒音レベルが高すぎると、聴力障害のリスクだけでなく、集中力の低下やコミュニケーション阻害にもつながります。騒音計による測定に加え、防音対策や保護具の着用指導を徹底する必要があります。
- 温湿度: 作業者の健康と快適性に影響を与える温湿度を適切に管理します。特に夏場の熱中症対策や冬場の冷え込み対策は重要です。温湿度計のIoTセンサーを設置することで、季節や時間帯に応じた最適な空調管理を自動で行い、異常な温湿度を検知した際には速やかに対応できます。
- 危険物の取り扱い: 可燃物、毒物、劇物などの危険物が適切に保管され、安全な方法で取り扱われているかを確認します。保管場所の施錠、表示、緊急時の対応手順などを徹底し、定期的な教育訓練も不可欠です。危険物貯蔵庫の温度・湿度センサーやガス検知センサーを導入することで、漏洩や異常を早期に発見し、重大な事故を未然に防ぐことが可能になります。
これらの項目は、IoTセンサーを活用することでリアルタイムでのモニタリングが可能になり、異常検知時の即時対応を実現します。センサーが収集したデータはクラウド上で一元管理され、AIによる分析を通じて、潜在的なリスクの予測や改善点の特定に役立てることもできます。これにより、従来の定期巡視だけでは見落とされがちなリスクを早期に発見し、より積極的な安全管理体制を構築できます。
休息施設
従業員の健康と安全を確保するためには、作業環境だけでなく、休憩環境の整備も極めて重要です。適切な休憩環境は、従業員の心身のリフレッシュを促し、集中力の維持、疲労軽減、ストレス軽減に繋がり、結果として生産性の向上と労働災害の防止に貢献します。
巡視による休憩室の確認は、その第一歩です。清潔さはもちろんのこと、空調設備の適切な稼働による快適な室温の維持、十分な照度を確保した照明、そして分煙対策の徹底は必須要件です。これらの項目は、従業員が安心して休憩できる空間を提供するための基本となります。
さらに、近年ではスマートセンサーや環境計測機器の活用が注目されています。これらの機器を導入することで、休憩室内の温度、湿度、CO2濃度、照度、騒音レベルなどをリアルタイムで可視化できます。
例えば、CO2濃度が高すぎると眠気や集中力低下を引き起こすため、換気の目安として活用できます。温度や湿度は、季節や時間帯に応じて自動で調整するシステムと連携させることで、常に最適な環境を維持することが可能になります。これらのデータに基づいた客観的な改善策は、従業員にとってより快適で健康的な休憩環境の実現に繋がります。
また、従業員が休憩時間を効果的に活用できているかどうかのエビデンスとして、行動データを活用する企業も増加しています。例えば、入退室記録や休憩室の利用状況をデータで把握することで、休憩室の混雑状況や利用頻度を分析し、より多くの従業員が利用しやすいように休憩室の配置や数を最適化する検討が可能になります。また、従業員アンケートやヒアリングと組み合わせることで、休憩に対する満足度やニーズを把握し、よりきめ細やかな改善策を講じることができます。
これらの取り組みは、単に休憩環境を整備するだけでなく、従業員に対する企業の配慮を示すことにも繋がります。従業員が大切にされていると感じることで、エンゲージメントの向上、定着率の改善、ひいては企業全体の競争力強化にも貢献するでしょう。
5S
安全な職場環境の構築において、整理・整頓・清掃・清潔・しつけからなる「5S」は、その最も基本的な原則です。5Sが徹底された職場では、事故発生のリスクが大幅に低減され、作業効率の向上にも寄与します。
日常的な職場巡視は、5Sの維持・向上に不可欠な活動です。巡視の際には、以下の具体的な項目に焦点を当ててチェックを行うことが重要です。
- 工具の置き方: 工具が定められた場所に適切に整理され、使用後は元の場所に戻されているか。乱雑に放置されていないか。
- 導線の確保: 作業通路や避難経路に障害物がないか。人や物の移動がスムーズに行える十分なスペースが確保されているか。
- 不要物の有無: 作業に不要なものが置かれていないか。使用頻度の低いものは適切に保管されているか、あるいは処分されているか。
- 清掃状況: 床、設備、作業台などが清潔に保たれているか。油汚れや粉塵などが放置されていないか。
- 掲示物の整理: 安全に関する掲示物や注意喚起のポスターなどが、見やすく整理されて掲示されているか。
これらのチェック項目を定期的に確認し、問題点があれば速やかに改善していくことで、職場の安全レベルを向上させることができます。
また、従来の紙ベースでのチェックリストによる巡視では、記録の手間や情報の共有の遅れ、傾向分析の困難さといった課題がありました。しかし、デジタル技術を活用することで、これらの課題を克服し、より効率的かつ質の高い安全管理を実現することが可能です。
- デジタルチェックリストの導入: タブレットやスマートフォンで利用できるデジタルチェックリストを導入することで、巡視時の記録が容易になり、リアルタイムでの情報共有が可能になります。項目ごとに点数化したり、写真や動画を添付したりすることで、より詳細な記録を残すことができます。
- スマホアプリの活用: 専用のスマホアプリを使用することで、巡視ルートの最適化、チェック項目の自動表示、異常箇所の即時報告などが可能になります。また、GPS機能と連携させることで、巡視経路の履歴も残すことができます。
- 写真添付による状況把握: 巡視中に発見した問題点や改善前後の状況を写真で記録し、デジタルデータとして残すことで、視覚的な情報共有が容易になります。これにより、関係者間での認識のずれを防ぎ、迅速な対応を促すことができます。
- 傾向分析とPDCAサイクルの向上: デジタル化された記録データは、容易に集計・分析することが可能です。これにより、特定のエリアや工程における問題の傾向、ヒヤリハットの発生頻度などを把握し、効果的な対策を講じることができます。PDCA(計画-実行-評価-改善)サイクルを迅速かつ的確に回すことで、継続的な安全管理の質的向上に繋がります。
このように、5Sの徹底とデジタル技術の積極的な活用は、工場や職場における安全管理体制を強化し、より安全で快適な労働環境を築く上で不可欠な要素と言えるでしょう。
救急用具
緊急時の対応力を高めるためには、AED(自動体外式除細動器)や救急箱などの緊急時対応備品の設置状況と整備状態の確認が、職場巡視における極めて重要な確認項目となります。これらの備品が適切に配置され、いつでも使用できる状態に保たれているかを定期的にチェックすることが不可欠です。
さらに、これらの備品の管理をより効率的かつ確実に行うために、クラウド上で一元管理する仕組みの導入を推奨します。例えば、各備品にQRコードを付与し、スマートデバイスで読み取ることで、設置場所、最終点検日、使用期限、補充状況などの詳細情報を容易に記録・更新できるようにします。また、使用履歴をデジタルで記録化することで、どの備品がいつ、どこで、どのように使用されたかを追跡し、必要に応じた補充やメンテナンスを迅速に行うことが可能になります。
加えて、ビーコン技術を活用することで、各備品の正確な所在場所をリアルタイムで把握し、緊急時に迷うことなく辿り着ける体制を構築できます。これにより、広範囲にわたる工場やオフィスであっても、必要な備品をすぐに発見し、対応時間を大幅に短縮することが期待できます。
これらのデジタル管理システムを導入することで、備品の状態を常に最新の状態に保ち、老朽化や不足による緊急時の対応遅延リスクを最小限に抑えることができます。結果として、従業員の安全確保体制をより一層強化し、万が一の事態にも迅速かつ的確に対応できる職場環境を整備することに繋がります。
従業員の心身の健康管理
産業医や衛生管理者による健康管理は、従業員の健康状態を良好に保ち、生産性の向上に不可欠な要素です。これには、定期的な健康診断結果に基づく個別面談、メンタルヘルス不調の早期発見を目的としたヒアリング、ストレスチェックの実施とその後のフォローアップなどが含まれます。特に、ストレスチェックは労働安全衛生法により義務化されており、集団分析を通じて職場環境改善のきっかけとなる重要なツールです。
近年、これらの健康管理業務においてデジタル化が急速に進んでいます。従業員の健康状態に関するデータを匿名化した上で蓄積・分析することで、個々の従業員だけでなく、組織全体の健康リスクを早期に発見し、適切な対策を講じることが可能になりつつあります。例えば、匿名化された健康データを分析することで、特定の部署や業務においてメンタルヘルス不調のリスクが高い傾向にあることを特定し、その原因となっている職場環境の改善策を検討することができます。
さらに、ウェアラブルデバイスを活用し、心拍数、睡眠時間、活動量などのバイタル情報をリアルタイムで取得・分析することで、従業員の健康状態の変化をより詳細に把握し、疲労の蓄積やストレスレベルの上昇といった兆候を早期に検知することができます。これにより、産業医や衛生管理者は、より個別最適化された健康指導や介入を行うことが可能となり、従業員の健康維持・増進に貢献します。これらのデジタル技術の導入は、効率的かつ効果的な健康管理体制の構築を後押しし、より健康で安全な職場環境の実現に寄与すると期待されています。

工場での一人作業をデジタルで把握しリスクを回避する

工場での一人作業のリスク
一人作業中の事故は発見が遅れることで重大化しやすく、救命率の低下や事故後の対応遅延につながります。特に高所作業、薬品取扱い、高温・高圧機器使用時はリスクが高まります。こうした作業には、早期発見と迅速対応の体制構築が不可欠です。
一人作業の安全管理方法
従来は作業開始前後の電話報告や紙の記録が主流でしたが、デジタルツールにより安全管理が強化されています。例えば、ビーコンやスマートタグを用いて作業員の位置や行動履歴を記録することで、緊急時の発見時間を大幅に短縮可能です。
工場のデジタル化でリスク回避
ウェアラブルデバイスやIoTセンサーにより、作業員の転倒・倒れこみ・異常な心拍を検知し、リアルタイムでアラートを発信できます。また、状況に応じて自動通報や音声アシストを行う仕組みも導入されつつあり、工場全体の安全レベルが向上しています。
デジタルによる効率化事例
ある製造業では、作業員の動線をビーコンで可視化し、危険エリアへの侵入を防止するシステムを導入しました。これにより、安全教育の効果測定や、リスクエリアの再設計にも活用されています。デジタルによる記録はトレーサビリティ強化にも寄与しています。
災害に備えたBCP対策

工場のBCP対策とは
BCP(事業継続計画)は、企業が自然災害、パンデミック、サイバー攻撃、大規模なシステム障害といった予期せぬ突発的事象に直面した場合でも、事業活動を中断させずに継続し、または早期に復旧させるための包括的な計画です。この計画の目的は、顧客への供給責任を果たし、従業員の雇用を維持し、企業の存続を図ることにあります。特に工場においては、その特性上、BCP策定において考慮すべき主要な項目が多岐にわたります。具体的には、以下の点が挙げられます。
- 生産設備の被害想定と対策: 地震、火災、水害などによる生産設備の物理的損傷や機能停止を想定し、耐震補強、防火設備の強化、防水対策の実施、重要設備のバックアップ、代替生産ラインの確保などを検討します。
- 代替生産拠点の確保: 主要工場が被災した場合に備え、他の工場や協力会社への生産委託、あるいは代替拠点の早期立ち上げ計画を策定します。
- 部品供給網の多重化とリスク分散: 特定のサプライヤーや地域に依存することなく、複数の供給元を確保する、あるいは在庫を戦略的に配置することで、供給途絶のリスクを低減します。
- 従業員の安否確認体制と行動計画: 災害発生時における従業員の安全確保を最優先とし、迅速な安否確認システム、避難経路の確保、緊急連絡網の整備、災害時の出勤ルールなどを明確にします。また、精神的ケアの提供も重要です。
- デジタルツールを活用したBCP訓練: 形骸化を防ぐため、机上訓練だけでなく、デジタルツールを用いたシミュレーション訓練を定期的に実施します。これにより、計画の実効性を検証し、改善点を洗い出します。
- 逃げ遅れの把握と対策: 災害発生時に従業員が安全に避難できるよう、避難経路の確保、誘導員の配置、IoTセンサーなどを活用したリアルタイムでの避難状況把握、逃げ遅れが発生した場合の救助体制を構築します。
- クラウドでのマニュアル管理と情報共有: BCPマニュアルや緊急連絡先、設備情報などをクラウド上で一元管理することで、物理的な被災による情報喪失を防ぎ、いつでもどこからでもアクセス可能な状態を維持します。これにより、迅速な情報共有と意思決定を支援します。
- 電力・インフラの確保: 停電時や断水時に備え、自家発電装置の導入、水の備蓄、通信手段の確保など、インフラ途絶への対策を講じます。
- 情報システムのバックアップと復旧計画: 生産管理システムや基幹業務システムなどの情報システムのデータバックアップ、遠隔地でのデータ保管、システム障害時の早期復旧手順を明確にします。
これらの項目を詳細に計画し、定期的な見直しと訓練を行うことで、企業は予期せぬ事態発生時にも、その影響を最小限に抑え、事業の継続性を確保することができるのです。BCPは単なる危機管理計画ではなく、企業の持続的な成長を支えるための重要な経営戦略の一環と言えます。
工場の安全対策
災害時には、通常時とは異なる危険が発生します。例えば、停電による機器停止・倒壊、避難経路の混雑、避難指示の混乱などが考えられます。こうしたリスクを事前に想定し、マップ・マニュアル・避難訓練を通じて教育することが重要です。
デジタルによる効率化事例
ある化学工場では、災害発生時の行動シナリオをアプリに組み込み、現場ごとに最適な避難経路をガイドするシステムを導入しました。IoTセンサーが異常を検知すると自動で従業員へ通知され、避難の初動が迅速に行えるようになりました。定期訓練の履歴もクラウド上で一元管理されています。

まとめ
工場の安全対策は、従業員の命を守ると同時に、企業の持続的な成長を支える重要な要素です。デジタル技術の活用により、職場巡視の効率化や一人作業の安全性向上、BCP対策の高度化が進んでいます。本記事をきっかけに、皆様の工場でも新しい安全管理の形を検討してみてください。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg