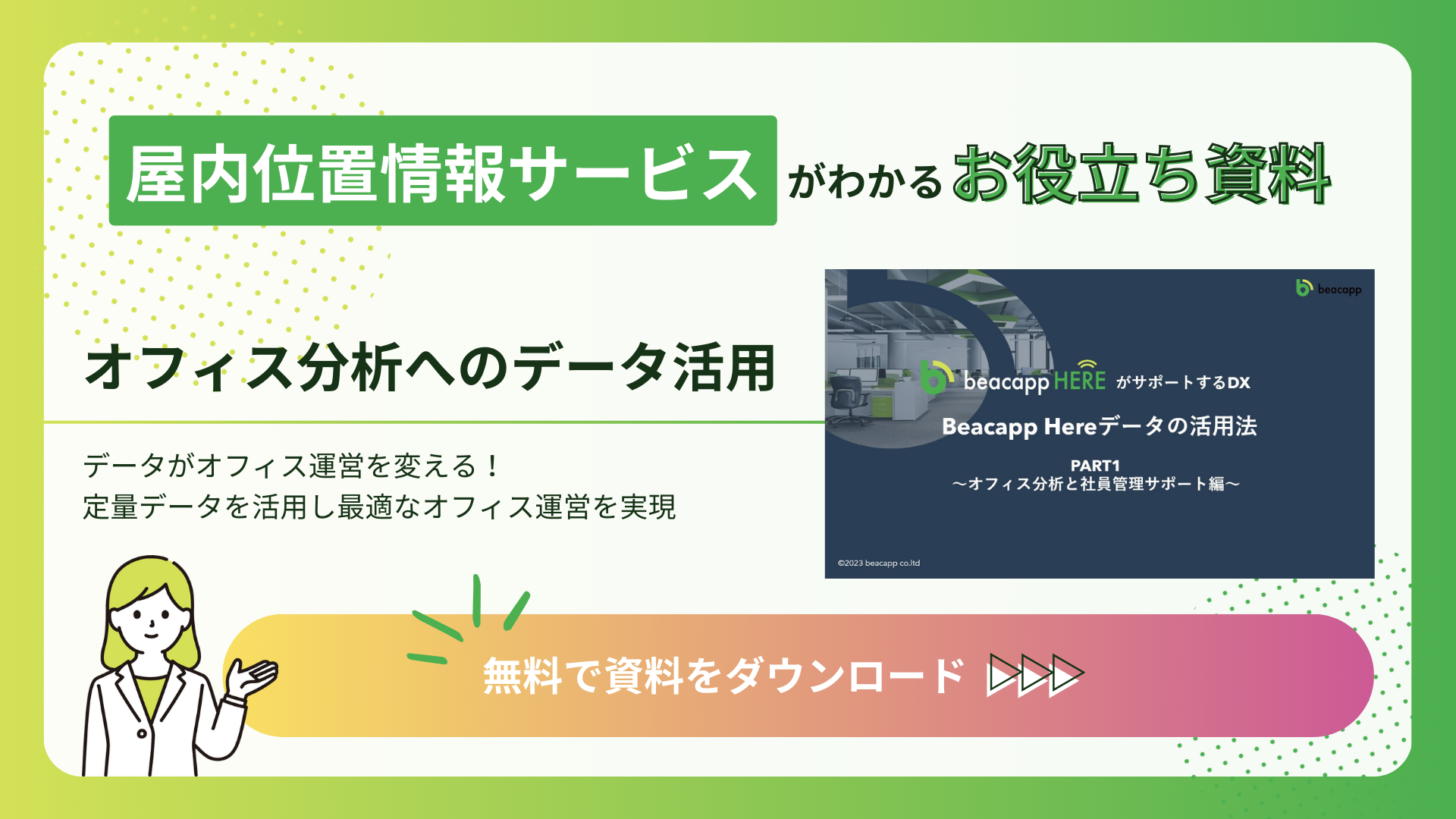働き方の多様化が進むなか、柔軟な勤務スタイルとして注目されているのが「コアタイムなしのフレックスタイム制」です。決まった時間に働く必要がないこの制度は、社員の自律性を促し、ワークライフバランスの向上にもつながる一方で、導入にはいくつかの注意点も存在します。
本記事では、制度の基本からメリット・デメリット、導入時のポイントまでをわかりやすく解説します。
コアタイムなしのフレックスタイム制とは?基本の仕組みを整理

フレックスタイム制には「コアタイムあり」と「コアタイムなし」の2種類があります。中でも「コアタイムなし」は、社員が働く時間を完全に自由に決められる仕組みとして注目されています。
ここでは、その基本的な仕組みや通常のフレックスタイム制との違い、導入のために必要な手続きについて整理します。
「コアタイムなし」とは?時間の拘束が一切ない働き方
「コアタイムなし」のフレックスタイム制とは、社員が働く時間帯を自分で自由に決められる制度です。一般的なフレックス勤務では、たとえば10時〜15時のような「必ず働く時間=コアタイム」が設定されますが、「なし」の場合はその拘束時間が存在しません。
始業・終業時間を社員自身が選べるため、早朝から働いて夕方には退勤したり、昼から夜にかけて勤務するなど、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。出勤時刻に縛られないため、満員電車の回避や個人の集中できる時間帯での勤務も実現しやすくなります。
通常のフレックスタイム制との違い
通常のフレックスタイム制と「コアタイムなし」の最大の違いは、勤務時間帯の自由度にあります。前者は「コアタイム」と「フレキシブルタイム(出退勤が選べる時間帯)」に分かれており、一定の時間はオフィスにいることが求められます。
一方で、コアタイムなしの場合は、1日のなかでいつ勤務を始めても、終えてもよく、極端にいえば“日によって出社時間がバラバラ”でも問題ありません。この違いが、より柔軟で自由な働き方を可能にしており、とくにリモートワークや裁量労働に近いスタイルを目指す企業に好まれています。
導入には「労使協定」の締結が必要
フレックスタイム制は、ただ制度を決めれば導入できるわけではありません。労働基準法の規定により、制度導入にあたっては、会社と労働者代表との間で「労使協定(労働時間に関する協定)」を締結し、その内容を書面で明確にする必要があります。
とくに「コアタイムなし」の場合は自由度が高いため、労働時間の総枠や清算期間の定め、休憩時間の扱いなどを詳細に記載しておくことが求められます。万が一この協定が不備だったり、周知が不十分だったりすると、制度そのものが無効とみなされるリスクもあるため、注意が必要です。
1日単位ではなく「清算期間」で労働時間を管理
コアタイムなしのフレックス制度では、毎日の労働時間ではなく「清算期間」というまとまった期間(例:1か月)単位で労働時間を管理します。これは「1日◯時間働く」といった決まりがなく、たとえばある日は3時間、別の日は10時間というように、日によって労働時間にバラつきが出る前提の運用です。
ただし、清算期間内に所定労働時間を満たす必要があるため、社員はある程度自律的にスケジュール管理をすることが求められます。企業側も、労働時間が過不足なく収まっているかを正確に把握するための仕組みやツールが必要となります。
自由度が魅力!コアタイムなしフレックスのメリット

コアタイムなしのフレックスタイム制は、自由度の高い働き方ができるという点で、多くの企業や求職者から注目を集めています。ここでは、制度を導入することで得られるメリットを、働き方の柔軟性やライフスタイルとの両立、そして採用面の効果まで、具体的にご紹介します。
業務に合わせて柔軟に働ける
社員が自分の業務や生活リズムに合わせて働けるのは、コアタイムなしの最大の魅力です。たとえば、集中力が高まる朝の時間に一気に仕事を進めたり、午後からの会議に合わせてゆっくり出勤したりと、業務内容に応じた時間の使い方が可能になります。
また、突発的な用事や家庭の事情により一時的に中抜けすることも認められやすく、社員の裁量を尊重した働き方が実現できます。こうした自由な勤務スタイルは、自発性を引き出しやすく、結果として業務の生産性向上にもつながります。
子育て・介護との両立がしやすくなる
コアタイムがないことで、育児や介護といったプライベートな事情を抱える社員にとっても、勤務の柔軟性が大きな支えになります。たとえば保育園の送迎や、親の通院付き添いといった予定を日中にこなした後に、落ち着いて業務に取り組むというスタイルが可能です。
「会社に合わせる」のではなく「生活に合わせて働ける」という環境は、従業員の安心感と定着率の向上に寄与します。家庭と仕事の両立を支援する制度として、コアタイムなしフレックスは非常に有効な手段といえるでしょう。
通勤ラッシュ回避などワークライフバランスが改善
出社時間の自由度が高いことで、通勤ラッシュを避けられるという利点もあります。満員電車によるストレスや疲労は、日々のパフォーマンスに大きく影響しますが、出勤時間をずらせるだけで体力的・精神的な余裕が生まれます。
また、就業時間を前倒しして夕方の時間をプライベートに使うといった調整もできるため、家事や趣味、家族との時間など、個々のライフスタイルに合わせた時間の使い方が可能です。コアタイムなしの制度は、単なる業務効率化だけでなく、社員の生活満足度の向上にも貢献します。
求人面でも“魅力的な制度”としてアピールに
働き方の柔軟性は、求職者が企業を選ぶ際の重要な判断材料になっています。コアタイムなしのフレックスタイム制は、「自律的に働ける環境が整っている企業」として好印象を与えることができ、求人媒体や採用ページでも強いアピールポイントになります。
とくに優秀な人材ほど、柔軟な勤務制度を重視する傾向があり、他社との差別化にもつながります。採用難が続く中、福利厚生の一環としてこうした制度を取り入れることは、企業の魅力を高める有効な手段といえるでしょう。

一方で注意点も。制度運用で気をつけたいポイント

柔軟で魅力的な制度である一方、コアタイムなしのフレックスには注意点も少なくありません。制度運用にあたっては、労働時間の把握や社員の自律性への依存、ルール整備の不備による混乱など、さまざまな課題が想定されます。
ここでは、導入企業が直面しやすいポイントを4つご紹介します。
労働時間の把握と勤怠管理の複雑さ
コアタイムが存在しないということは、企業側が社員の勤務実態を把握する難易度が高くなることを意味します。何時から何時まで働いたのか、どのくらいの時間働いたのかが日によって異なるため、打刻の管理やシステム上での記録が煩雑になりがちです。
また、労働基準法に基づく適正な労働時間の管理ができていない場合、企業側が法的リスクを負う可能性もあります。勤怠管理ツールの導入や、自動で記録される仕組みづくりなど、制度に合った運用設計が求められます。
欠勤・遅刻の判断が曖昧になりやすい
決まった始業時刻がないため、「何時に出社しなければならないか」という基準が曖昧になり、遅刻や欠勤の判断が難しくなることがあります。たとえば、まったく出社がなかった日でも「今日はたまたま働かなかっただけ」とされると、勤怠上の処理が不明確になります。
また、上司や人事担当者が社員の勤務実態を感覚的に把握することが難しくなるため、勤務状況の“見える化”が重要です。一定のルールを設けると同時に、出退勤の記録や行動ログなど、客観的なデータをもとに管理できる体制を整える必要があります。
休憩時間の確保が従業員任せになるリスク
1日のスケジュールを社員自身で決めることができる反面、適切なタイミングで休憩を取らないまま働き続けてしまうケースも想定されます。とくに忙しい日やリモートワークでは、「気づけば何時間も座りっぱなしだった」ということも少なくありません。
法律上、6時間以上の勤務で45分、8時間以上で1時間の休憩が必要ですが、自己管理に任せるだけでは不十分な場合もあります。休憩取得を促すアラート機能や、ログ上での休憩チェックなど、従業員の健康維持と法令遵守の両面を支える仕組みが求められます。
制度の形骸化を防ぐためのルール整備
制度だけを導入しても、社内で正しく機能しなければ意味がありません。社員によって制度の理解度に差がある、管理者ごとに判断が分かれる、といった状況は制度の形骸化につながります。
たとえば「自由に働いていい」と言われても、遠慮して従来通りの勤務時間に合わせてしまう社員が多い場合、本来の効果が発揮されません。制度をうまく機能させるには、明文化された社内ルールの整備と、対象社員への丁寧な周知・研修が重要です。定期的な制度の見直しも有効です。
実際に導入するには?必要なステップと制度設計のコツ
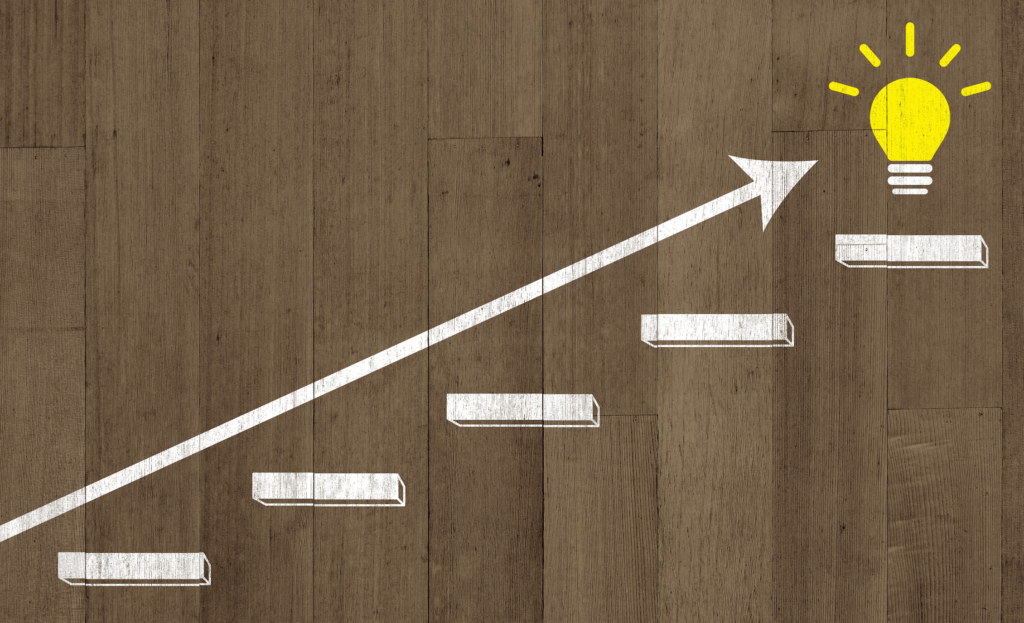
コアタイムなしのフレックス制度は、自由度が高い分、設計や運用には慎重さが求められます。労使協定の締結だけでなく、制度をうまく機能させるための社内体制やツールの整備が不可欠です。
ここでは、導入に必要なステップと運用を成功させるための工夫について解説します。
労使協定に明記すべき内容とは
まず制度を導入するうえで欠かせないのが、労働者代表と締結する「労使協定(36協定とは別)」です。この協定では、フレックスタイム制の適用対象者、清算期間の長さ、所定労働時間、休憩時間の取り扱いなどを明記する必要があります。
特にコアタイムなしの場合、労働時間の自由度が高いため、最低限の労働時間や休憩時間のルールをしっかり定めておかないと、長時間労働や休憩未取得といった問題を引き起こすおそれがあります。制度を法的にも実務的にも正しく運用するために、内容の精査と周知徹底が重要です。
清算期間・対象労働者の選定と周知
フレックスタイム制は、1日単位ではなく「清算期間」単位で労働時間を調整する制度です。多くの企業では1ヶ月単位で設定されますが、最大3ヶ月まで延長可能です。自社の業務サイクルに合った期間を見極めることが重要です。
また、全社員に一律で適用する必要はなく、部署や職種によって対象を分けることも可能です。対象者の選定にあたっては、公平性と業務上の実効性の両面から検討しましょう。制度導入時には社内向けの説明会やガイドライン作成を行い、社員の理解と納得を得ることが成功のカギとなります。
勤怠管理ツールの活用がスムーズな運用のカギ
制度を円滑に運用するためには、正確で効率的な勤怠管理が不可欠です。コアタイムなしでは、社員がそれぞれ異なる時間に勤務するため、手作業での管理には限界があります。
そこで、勤怠管理システムの導入が効果的です。打刻の自動記録、休憩時間の管理、清算期間内の労働時間集計など、ツールによって業務負担を大幅に軽減できます。また、異常値のアラート機能や労働時間の可視化により、労務リスクを未然に防ぐことにもつながります。制度とツールの整合性をとることが、運用成功のポイントです。
制度の「見える化」で従業員の理解と定着を促進
せっかく制度を導入しても、社内に十分浸透しなければ意味がありません。「自由に働ける制度」として魅力的に伝えるだけでなく、具体的な利用方法や注意点を“見える化”して共有することが重要です。
たとえば、「どの時間帯に働く人が多いのか」「休憩はきちんと取られているか」「働きすぎの傾向はないか」などをデータで示すことで、制度が形骸化するのを防ぎ、社員自身の意識づけにもつながります。制度の可視化によって、従業員も会社も安心して活用できる環境を整えましょう。
Beacapp Hereを活用した柔軟な働き方の実現

コアタイムなしのフレックス制度を円滑に運用するには、勤怠や行動を正しく「見える化」できる仕組みが欠かせません。Beacapp Hereは、社員の出社状況やオフィスへの滞在時間を自動で記録し、働き方の実態を可視化できるツールです。
ここでは、柔軟な働き方を支える具体的な活用方法をご紹介します。
(※Beacapp Hereでは、出社時の勤怠や行動のみ可視化することができます。)
出社・退社・滞在状況を自動で記録できる
Beacapp Hereは、ビーコンやスマートフォンの位置情報を活用し、社員の出社・退社・オフィスでの在席状況を自動で記録します。これにより、「いつ・どこで・どのくらい働いたか」といった情報を人手を介さず正確に記録でき、フレックス制特有のバラついた勤務時間もスムーズに把握可能です。
とくにコアタイムなしの場合は、出退勤のタイミングが社員ごとに異なるため、打刻忘れや記録ミスを減らす仕組みとして有効です。自動化により管理者の負担も軽減できます。
欠勤・遅刻判断もログベースで“曖昧さ”を防げる
自由な勤務時間が許される制度では、「遅刻なのか、単なる調整なのか」の判断が難しくなる場面もあります。Beacapp Hereでは、オフィスへの滞在時間や勤務傾向を把握できるため、感覚や推測ではなく、客観的なデータに基づいた勤怠管理が可能になります。
たとえば「連日15時以降にしか勤務していない」などのパターンも可視化されるため、適切な対応やフィードバックにつなげることができます。曖昧さを排除し、透明性のある制度運用を実現するうえで、行動ログの活用は非常に効果的です。
個人の勤務状況を可視化し、マネジメントを効率化
Beacapp Hereを導入することで、各社員の働き方の傾向や時間の使い方を可視化することが可能になります。たとえば、「長時間オフィスに滞在しているが離席が多い」「短時間勤務でも生産性が高い」など、単なる勤怠情報では見えないインサイトが得られます。
これにより、管理者は数字だけでなく行動に基づいたマネジメントができるようになり、評価の公平性や部下への声かけタイミングの精度も向上します。従業員の自律性を尊重しつつ、適切に支援・介入するスタイルを実現できます。
労働時間の傾向を分析し、働きすぎ・働かなさすぎを防ぐ
清算期間で労働時間を管理するフレックス制度では、極端な働き方が発生することもあります。出社状況を記録できるBeacapp Hereを活用すれば、「働きすぎていないか」「勤務実態にばらつきがないか」といった点を、ログデータから早期に把握可能です。
働きすぎている人には休息を、勤務時間が著しく少ない人にはフォローを、といったアクションを取りやすくなります。社員が健康的に、かつ企業としても持続可能な働き方を実現するための“安全網”として、行動データの分析は欠かせない要素です。

まとめ
コアタイムなしのフレックスタイム制は、社員の自律性や柔軟な働き方を促進する制度として注目されています。一方で、勤怠管理や制度の形骸化といった課題もあるため、適切なルール設計と運用体制が欠かせません。出社時の勤務実態を「見える化」できるBeacapp Hereを活用すれば、制度運用の透明性が高まり、働きすぎ・働かなさすぎの抑制にもつながります。
柔軟性と生産性の両立を目指す企業にとって、コアタイムなしのフレックスタイム制の導入を成功させるためには、制度とツールの両面からのアプローチが成功の鍵となります。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg