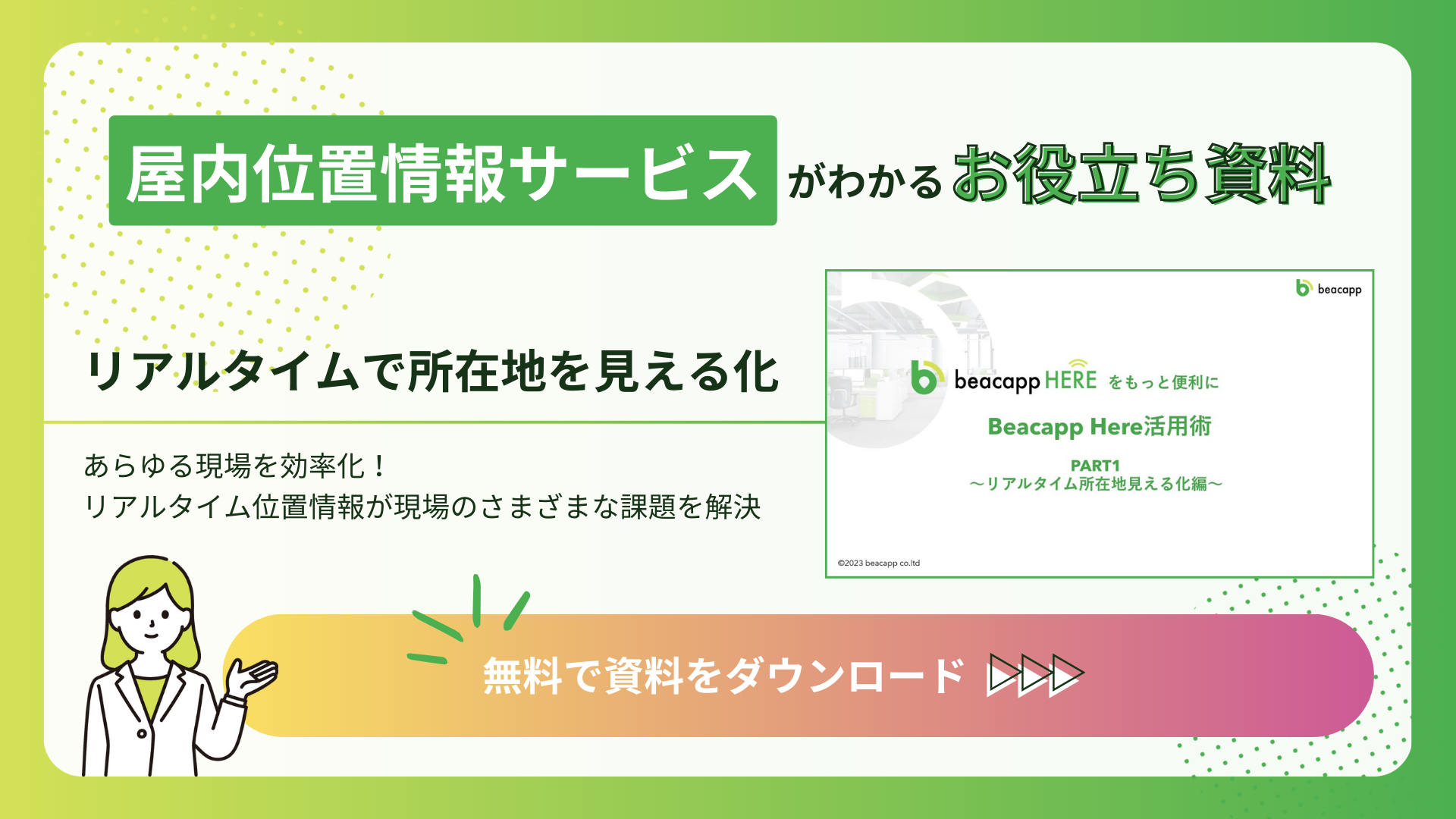企業が持続的に成長していくためには、顧客や市場への発信だけでなく、社員一人ひとりの心に理念やビジョンを浸透させることが欠かせません。その取り組みを指すのが「インナーブランディング」です。
本記事では、インナーブランディングの基本から背景、具体的な施策や成功のポイントまでを解説します。
インナーブランディングとは?

インナーブランディングとは、企業が掲げる理念やビジョン、価値観を社員に浸透させ、行動や判断に一貫性を持たせる取り組みを指します。単に社内広報やスローガンの共有にとどまらず、社員一人ひとりが自分の役割を理解し、組織の目指す方向と重ね合わせて働ける状態をつくることが目的です。
外向けのブランド発信を支える基盤であり、社員の意識と行動を整えることで、企業全体の一体感や競争力の向上につながります。
インナーブランディングが求められる背景

近年、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。働き方改革やリモートワークの普及、人材の流動化、さらに価値観の多様化によって、社員が企業と関わるスタンスは従来とは異なるものになっています。
こうした変化の中で、企業が成長を続けるためには、社員一人ひとりが理念やビジョンを理解し、共感しながら主体的に働く状態をつくることが重要になってきました。インナーブランディングが求められる背景には、社員が「何のために働くのか」を見失いやすい現代の働き方や環境があります。
社員のエンゲージメントやモチベーションを高めることは、単に職場の雰囲気を良くすることにとどまりません。自社の理念を土台にした働き方を共有できれば、組織全体が同じ方向を目指しやすくなり、変化の大きい社会環境の中でも柔軟に対応できる強い組織づくりにつながります。
ここでは、インナーブランディングによって特に期待される効果を整理します。
企業理念の浸透が期待できる
企業理念やビジョンは、社員の行動や判断の基準となる重要なものです。しかし、理念が単なる「掲げられた言葉」にとどまってしまうと、現場の業務と結びつかず、活用されないまま形骸化してしまうリスクがあります。
インナーブランディングは、理念を日々の仕事に落とし込み、社員が「自分の業務が会社の理念とどう関わるのか」を理解できるようにする取り組みです。これにより、全社的に一貫した価値観が形成され、企業文化として根付いていくことが期待されます。
社員のエンゲージメント向上につながる
社員が理念やビジョンに共感し、自らの役割を意識して働くようになると、組織への帰属意識やエンゲージメントが高まります。
エンゲージメントの高い社員は、自発的に業務改善に取り組んだり、仲間をサポートしたりと、前向きな行動を起こす傾向があります。結果として、業務効率の向上、離職率の低下、顧客満足度の向上など、企業全体にプラスの効果をもたらします。
インナーブランディングは、社員の働きがいを生み出し、組織の成長を支える基盤となるのです。
インナーブランディングの測定方法

インナーブランディングは目に見えにくい取り組みであるため、感覚的な評価だけでは効果を判断しづらいという課題があります。そのため、定期的に社員の意識や行動の変化を測定し、定量的に把握することが重要です。測定を通じて現状の強みや課題を明らかにすることで、次の施策の改善や方向性の修正につなげることができます。
測定方法として多くの企業で取り入れられているのが、従業員意識調査やエンゲージメントサーベイです。社員の声を数値化することで、理念の浸透度やエンゲージメントの高さを客観的に把握できるだけでなく、部署ごとの傾向を分析することで改善すべき領域を特定できます。
測定方法
代表的な方法は、年に1回または半期ごとに実施される従業員意識調査です。設問の一例として、次のような内容が挙げられます。
- 「この会社で働き続けたいと思うか」:社員の定着意欲や会社への愛着を測る指標です。
- 「上司との信頼関係はあるか」:マネジメントの質や現場での関係性を確認します。
- 「組織のビジョンに共感できるか」:理念や方向性が浸透しているかを把握します。
- 「自分の成長を感じているか」:業務を通じたスキルや経験の向上を測定します。
これらの結果を数値化・分析することで、部署や職階ごとの傾向が浮き彫りになり、具体的な改善の手がかりを得ることができます。加えて、定点的に実施することで時間の経過に伴う変化を追跡でき、施策の有効性を検証することが可能になります。
アンケート調査に加えて、日常的なコミュニケーションや社内SNS上での発信内容などを補助的に分析する企業も増えており、定量・定性の両面から測定を行うことが効果的です。

Beacapp Hereを活用したインナーブランディング施策

インナーブランディングを定着させるには、社員同士のつながりを生み出し、理念やビジョンを日々の業務やコミュニケーションの中で体感できる仕組みが必要です。
そこで有効なのが、リアルタイム位置情報を可視化できる「Beacapp Here」です。社員がどこで働いているかを直感的に把握できるこのサービスは、部署間の連携やイベントでの交流、日常的な信頼関係づくりに役立ちます。
以下では、インナーブランディングにおける具体的な活用シーンをご紹介します。
リアルタイムな「誰がどこにいるか」可視化による部署連携強化
テレワークやフリーアドレスの普及により、社員の所在がわかりにくくなり、部署間の連携に課題を抱える企業は少なくありません。
Beacapp Hereを活用すれば、誰がどこで働いているのかをリアルタイムに把握できます。たとえば、プロジェクトメンバーの在席状況を確認したうえで声をかけたり、急ぎの打ち合わせをスムーズに設定したりすることが可能になります。
これにより、部門を超えた連携が取りやすくなり、組織全体の一体感やスピード感の向上につながります。
社内イベントにおける交流促進・一体感づくり
インナーブランディングの定着には、理念を共有するだけでなく、社員同士の交流を通じて「組織の一員であること」を体感できる場が重要です。
Beacapp Hereは、イベント時の社員の動きを可視化し、誰がどこに集まっているのかを把握できるため、コミュニケーションのきっかけを生み出します。たとえば懇親会や社内フェスでの利用により、普段関わりの少ない部署同士の交流を自然に促すことが可能です。
リアルタイムに参加状況が共有されることで、一体感が醸成され、組織全体の結束力を高める効果が期待できます。
働き方の見える化による信頼醸成・心理的安全性の向上
リモートワークの広がりにより、「誰がどのように働いているのか」が見えにくいことで不安や不信感が生じるケースもあります。
Beacapp Hereは、勤務場所や在席状況を共有することで、働き方の透明性を高めることができます。これにより、上司や同僚が互いの働き方を理解しやすくなり、余計な誤解やストレスを防ぐことができます。また、社員自身も「自分の働きがきちんと見えている」という安心感を得られるため、心理的安全性の向上につながります。
結果として、オープンな社風の醸成や主体的な行動の促進が期待できます。
Beacapp Hereを活用したインナーブランディング成功のポイント

Beacapp Hereを活用してインナーブランディングを成功させるには、社員が自然に・日常的に利用できる仕組みづくりが重要です。アイコンの登録を促進したり、プロフィール欄に業務内容や経験を共有することで、お互いのスキルやプロジェクト参加履歴を把握でき、社内のナレッジ共有や協力体制の強化につながります。
社員の経験や成功事例を見える化して共有
社員が参画したプロジェクトや、そこでの課題・成果をプロフィール欄に入力することで、個々の経験が社内で共有されます。これにより、新しいメンバーも過去の取り組みや成功事例を学びやすくなり、会社全体の成長ストーリーを理解できます。また、成功体験や工夫の共有は、他部署とのコラボレーションや新たなアイデア創出のきっかけにもなります。
社員同士の理解が深まることで、エンゲージメントの向上や組織全体の一体感を高めることが可能です。

まとめ
インナーブランディングは、企業理念やビジョンを社員に浸透させ、組織全体の一体感やエンゲージメントを高めるための重要な取り組みです。Beacapp Hereの活用により、社員の位置情報や経験を可視化することで、部署間の連携強化や交流促進、信頼醸成が可能になります
日常の業務に自然に組み込みながら活用することで、組織の成長と社員の満足度向上の両立が期待できます。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg