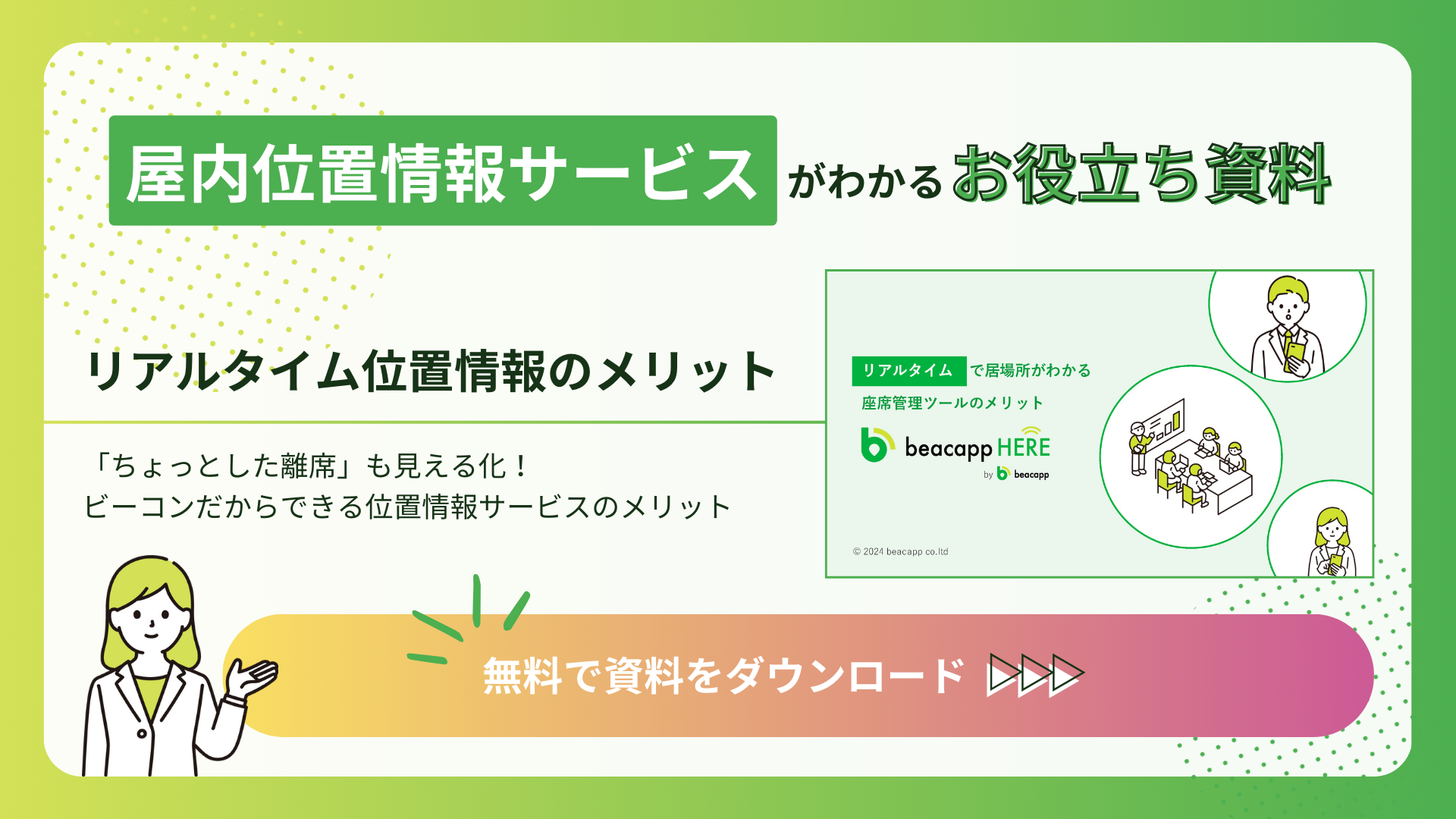テレワークやフレックスタイムの普及により、社内での何気ない会話や情報共有の機会が減ったと感じている企業も多いのではないでしょうか。社員同士のコミュニケーションが不足すると、業務の連携ミスやモチベーションの低下など、さまざまな課題を引き起こす可能性があります。
本記事では、社内コミュニケーション不足の主な原因や、それによって起こりうる影響、さらにコミュニケーションを活性化させるための具体的な施策についてご紹介します。組織力を高めるためのヒントを得るためにも、ぜひ最後までご覧ください。
社内コミュニケーションが不足している主な3つの要因とは?
本項では社内コミュニケーションが不足する主な要因を三つご紹介いたします。本項に当てはまる要因があれば、あなたの企業でもコミュニケーションが不足しているかもしれません。
テレワークやフレックスタイムなどで他の人と会う機会が減る
テレワークやフレックスタイムは、柔軟な働き方を実現する一方で、社内コミュニケーションの機会を減少させる要因ともなっています。従来のオフィス環境では、同僚との何気ない会話や情報交換が日常的に行われていましたが、リモートワークが普及することで、カジュアルなコミュニケーションが失われつつあります。特に、顔を合わせる機会が減ることで、社員同士の信頼関係やチームワークが希薄になり、業務の連携が難しくなります。
また、フレックスタイム制度により、各社員が異なる時間帯に働くことが一般的になった結果、同じ時間にオフィスにいる社員が少なくなり、コミュニケーションの機会がさらに制限されることもあります。
社員の心理的な障壁がある
社内コミュニケーションが不足する要因の一つに、社員の心理的な障壁が挙げられます。特に、テレワークやフレックスタイム制度の導入により、対面でのコミュニケーションが減少すると、社員同士の距離感が生まれやすくなります。
また、社員が自分の意見や感情を表現することに対して不安を感じる場合もあります。特に、新入社員や若手社員は、先輩や上司に対して遠慮や緊張感を抱きやすく、意見を言い出せないことが多いです。このような心理的な障壁は、チーム内の信頼関係を築く妨げとなり、業務の円滑な進行を阻害する要因となります。
社員の業務が多忙である
現代のビジネス環境では、社員一人ひとりが多くの業務を抱え、常に忙しい状態に置かれています。このような状況では、業務に追われるあまり、他の社員とのコミュニケーションが後回しになりがちです。
また、業務が多忙であることは、社員のストレスや疲労感を増加させ、心理的な余裕を失わせる要因にもなります。結果として、社員同士のコミュニケーションが減少し、誤解やすれ違いが生じやすくなります。このようなコミュニケーション不足は、業務の効率を低下させるだけでなく、チーム全体の士気にも悪影響を及ぼすことがあります。
社内コミュニケーションが不足することで起こること

社内コミュニケーションが不足すると、さまざまな問題が発生し、組織全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。本項では、社内コミュニケーションが不足することで起こる主な4つを紹介いたします。
社員同士での誤解やすれ違いが発生する
特に、テレワークやフレックスタイムの導入により、対面でのコミュニケーションが減少すると、情報の伝達が不十分になりがちです。例えば、メールやチャットでのやり取りでは、相手の表情や声のトーンが伝わらないため、意図が正しく理解されないことが多くなります。
また、業務の進捗状況や重要な情報が共有されないまま進むことで、誤解が生じることもあります。これにより、プロジェクトの方向性がずれたり、業務の連携がうまくいかなくなったりすることが懸念されます。結果として、社員同士の信頼関係が損なわれ、チーム全体の士気にも悪影響を及ぼすことになります。
社内での情報共有が遅れる、行き届かない
テレワークやフレックスタイムの導入により、対面でのやり取りが減少すると、重要な情報が適切なタイミングで伝わらないことが増えます。これにより、プロジェクトの進行が遅れたり、業務の優先順位が誤って認識されたりすることが起こり得ます。
また、情報が行き届かないことで、社員が必要なデータや知識を持たずに業務を進めることになり、結果として業務の質が低下する恐れもあります。特に新入社員や異動したばかりの社員にとっては、必要な情報を得る手段が限られてしまうため、孤立感を感じることも少なくありません。
他の社員に相談しづらくなる
テレワークやフレックスタイム制度の導入により、顔を合わせる機会が減少すると、気軽に質問や相談をすることが難しくなります。これにより、社員は自分の問題を一人で抱え込むことが増え、結果として業務の効率が低下する恐れがあります。
また、相談しづらい環境は、社員の心理的な負担を増加させ、ストレスを引き起こす要因にもなります。特に新入社員や異動したばかりの社員は、周囲との関係構築が不十分なため、助けを求めることに対してためらいを感じることが多いです。このような状況が続くと、チーム全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼすことになります。
ミスが多発する要因になる
コミュニケーションが不足すると、業務の連携が不十分になり、結果としてミスが多発する要因となります。例えば、情報が正確に伝わらなかったり、誤解が生じたりすることで、業務の進行に支障をきたすことがあります。特に、テレワークやフレックスタイムの導入により、対面でのコミュニケーションが減少すると、社員同士の意思疎通が難しくなり、重要な情報が共有されないまま進行してしまうことも少なくありません。
また、業務が多忙な中で、社員が他のメンバーに確認や相談をすることをためらう場合もあります。このような状況では、問題が早期に発見されず、結果として大きなミスにつながることがあります。

社内でのコミュケーション活性化によるメリット

社内コミュニケーションを活性化させることで前項あげた4つを解決する他、多くのメリットがあります。本項では社内コミュニケーション活性化によるメリットを4つご紹介いたします。
社員のモチベーション向上
コミュニケーションが円滑になると、社員同士の信頼関係が深まり、チームワークが強化されます。これにより、社員は自分の意見やアイデアを自由に発信しやすくなり、職場における自己表現の場が増えるのです。
また、コミュニケーションが活発になることで、業務に対する理解が深まり、各自の役割や目標が明確になります。これにより、社員は自分の仕事に対する意義を感じやすくなり、結果としてモチベーションが高まります。さらに、定期的なフィードバックや感謝の言葉が交わされることで、社員は自分の努力が認められていると実感し、より一層のやる気を引き出すことができます。
社員の離職防止
コミュニケーションが不足している環境では、社員は孤独感を抱きやすく、仕事に対するモチベーションが低下することに対して、オープンなコミュニケーションが促進されることで、社員同士の信頼関係が築かれ、職場への帰属意識が高まります。
また、定期的なコミュニケーションを通じて、社員の意見や悩みを把握することができるため、早期に問題を解決することが可能です。これにより、社員は自分の声が尊重されていると感じ、離職を考えることが少なくなります。さらに、コミュニケーションが活発な職場では、チームワークが向上し、業務の効率も上がるため働きやすい環境が整います。
アイディアや問題解決に対しての能力が高まる
コミュニケーションが活性化されることで、社員は自由に意見を交換しやすくなり、問題解決に向けた多角的なアプローチを促進します。例えば、異なる部署の社員同士が意見を交わすことで、普段は気づかない視点や解決策が見つかることがあります。また、オープンな対話は、社員が自信を持って発信できるようになり、結果として組織全体の知識やスキルが向上します。
さらに、コミュニケーションが活発になることで、社員は互いにサポートし合う文化が醸成され、問題解決に対する意識が高まります。これにより、業務上の課題に対して迅速かつ効果的に対応できるようになり、組織の生産性向上にも寄与します。
主体的に行動する社員が増える
コミュニケーションが円滑になると、社員同士の信頼関係が深まり、意見を自由に交換できる環境が整います。このような環境では、社員は自分の考えやアイディアを積極的に発信しやすくなり、業務に対する責任感も高まります。
また、コミュニケーションが活発になることで、チーム全体の目標に対する理解が深まり、各自が自分の役割を意識するようになり、結果として組織全体のパフォーマンスが向上することが期待されます。主体的に行動する社員が増えることで、組織はより柔軟で創造的な対応が可能となり、変化の激しいビジネス環境においても競争力を維持することができるのです。
コミュニケーションを活性化させるには?
本項では、社内コミュニケーションを活性化させるために3つの具体的な施策をご紹介いたします。本項をご覧いただくことでコミュニケーションの機会を増やし、社員同士の距離を縮めることができるでしょう。
1on1の面談を実施
1on1の面談は、業務の進捗状況や課題、さらには個々のキャリアに関する相談など、幅広いテーマについて話し合うことができます。特に、テレワークやフレックスタイムが普及する中で、対面でのコミュニケーションが減少しているため、1on1の面談は重要性を増しています。
1on1の面談は、上司と部下の関係をより密接にし、信頼関係を築く機会にもなります。社員は意見や悩みを話せる環境が整うことで、コミュニケーションが円滑になります。また、上司側も部下の状況を把握しやすくなり、適切なサポートを提供できるようになります。
定期的に社内のイベントや懇親会を開催する
定期的な社内イベントや懇親会の開催することで、社員同士がリラックスした環境で交流できる機会を提供し、普段の業務では得られない人間関係の構築を促進します。特に、テレワークやフレックスタイム制度が普及する中で、顔を合わせる機会が減少しているため、意識的にこうした場を設けることが重要です。
懇親会やイベントでは、業務に関する話題だけでなく、趣味やプライベートな話題についても自由に話すことができ、社員同士の距離感を縮める効果があります。また、チームビルディングの一環として、ゲームやワークショップを取り入れることで、協力し合う姿勢を育むことも可能です。
社内SNSやツールの普及
社内SNSやコミュニケーションツールの導入が非常に効果的です。特に、テレワークやフレックスタイムが普及する中で、対面でのコミュニケーションが減少しているため、オンラインでのつながりを強化することが求められています。
社内SNSを活用することで、業務に関する情報や進捗状況をリアルタイムで共有できるため、情報の透明性が向上します。また、社員が自分の意見やアイデアを気軽に発信できる環境が整うことで、創造的な発想が生まれやすくなります。さらに、社内ツールを通じて、業務に関する質問や相談がしやすくなるため、社員同士の連携も強化されます。
BeacappHere
Beacapp Hereは、社員が快適に働ける環境を実現するための、フリーアドレス運用に最適なアプリです。座席の予約機能や、チームメンバーの現在地をリアルタイムで確認できる機能を備えており、社員同士のスムーズな連携や声かけを促進します。テレワークやフリーアドレスの浸透によって、社内コミュニケーションの不足が課題となる中、Beacapp Hereはその解決をサポートします。さらに、オフィス内の混雑状況を可視化することで、社員がその日の業務内容や気分に合わせた最適な作業場所を選びやすくなり、座席探しのストレスを軽減。業務効率の向上にも貢献します。
BeacappHere導入企業の事例

本項では「BeacappHere」を導入した企業の事例をいくつかご紹介します。これから紹介する事例をご覧いただくことで「BeacappHere」がもたらす効果を実感することができます。
事例1 株式会社隈研吾建築都市設計事務所
複数オフィスを展開しつつリモート併用の設計事務所では、「誰がどこにいるか」を自然な形で把握できず、コミュニケーションに課題がありました。PC操作不要で位置を自動検知する「Beacapp Here」は、既存スマホとビーコンで即導入が可能。Microsoft Teamsとの連携により、誰がどのフロアにいるかが一目で分かるようになり、顔と名前が一致しづらい外国人スタッフへの配慮も改善。さらに、防災備品の設置場所などをマップ上で共有することで、社内情報を空間に“重ねて”表示する新たな活用スタイルが生まれました。
参考:導入企業インタビュー 株式会社隈研吾建築都市設計事務所
事例2 ダイビル株式会社
大阪オフィスのフルリニューアルを契機に「Beacapp Here」を導入しました。コロナ禍以降、従来の島型・固定席のオフィススタイルに疑問を抱き、部署間連携や働き方の柔軟性を高めるためグループアドレス制を採用。その上で「Beacapp Here」を活用し、部署ごとにエリアをグルーピング。誰がどこにいるか、リアルタイムで可視化することで、対面での声掛けやコミュニケーションが活性化しました。特に、他拠点から大阪オフィスの在席状況を確認してから連絡・訪問する運用が定着し、オフィス間の連携もスムーズに。また、オフィス分析ダッシュボードにより継続的な環境改善にも取り組み、「明日もっと行きたくなるオフィス」を目指す取り組みが評価されています。
参考:導入企業インタビュー ダイビル株式会社
事例3 三井不動産株式会社
オフィス移転を機に、「Beacapp Here」を導入。ビーコンとスマホによる屋内位置情報で、社員がオフィス内どこにいるかをリアルタイムに可視化し、「誰がどこで働いているか分からない」課題を解消しました。さらに分析オプションの「Beacapp Here Pro」を活用し、社員同士の遭遇頻度や動線データを定量的に収集。三井デザインテックとの協業を通じ、得られた分析結果と社内アンケートを組み合わせ、偶発的コミュニケーションが生まれやすいレイアウトへと設計を改善。導入後には「コミュニケーションが増えた」との実感がアンケートで上がり、データ上でも遭遇量の増加が確認されました。
参考:導入企業インタビュー 三井不動産株式会社

まとめ
社内コミュニケーションの不足は、業務効率の低下や社員のモチベーション低下につながる重要な課題です。社員同士の会話や情報共有の機会が減少することで、誤解やすれ違いが生じやすくなり、心理的な障壁や多忙な業務もコミュニケーションを妨げる要因となっています。これらの問題を解決するためには、本記事で挙げた具体的な施策を講じることが重要です。
組織力を高めるために、今一度社内コミュニケーションの重要性を見直し、積極的に取り組んでいきましょう。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg