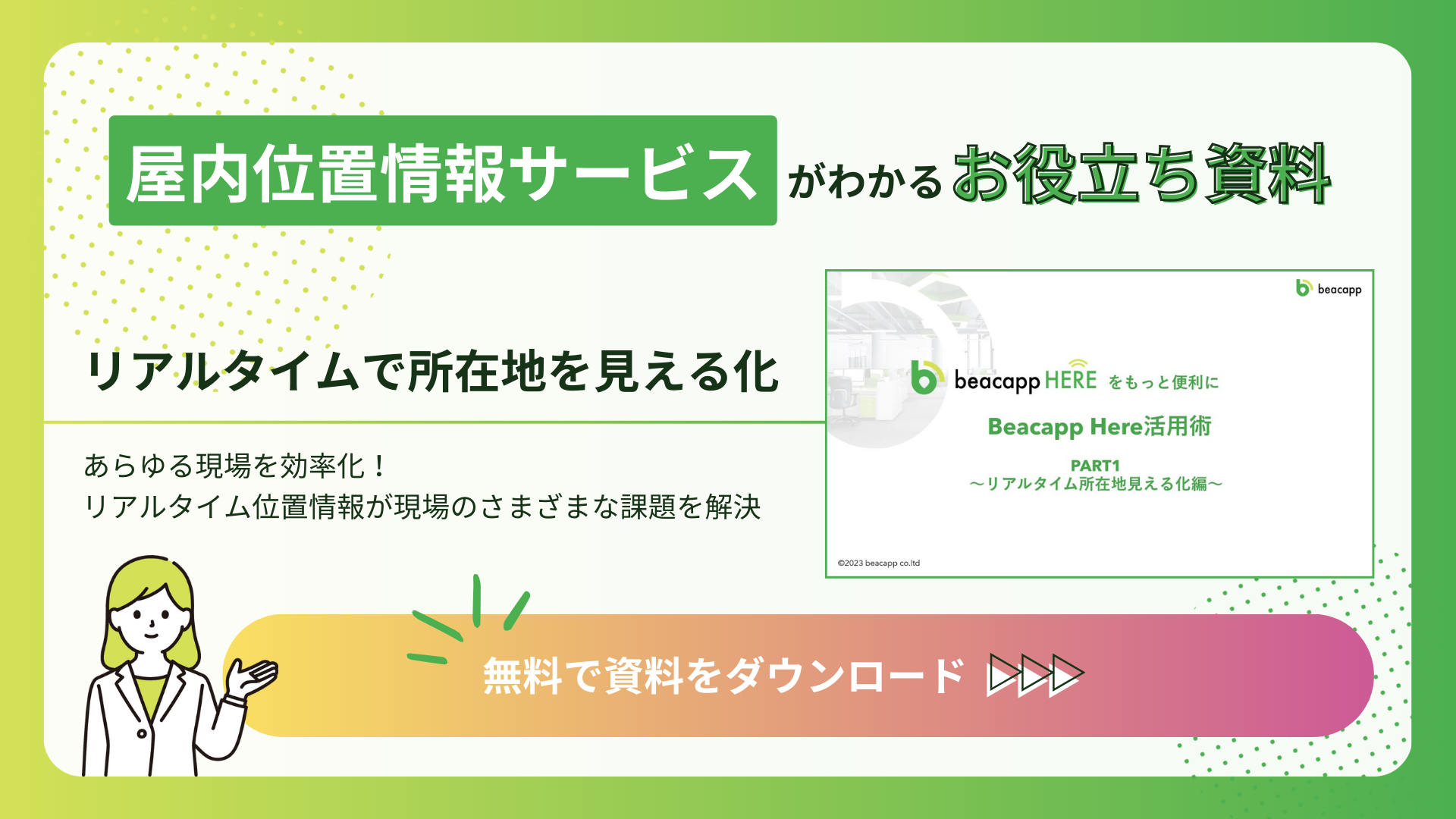オフィスでの働きやすさを考えるうえで、休憩場の存在は欠かせません。仕事の合間にリフレッシュできる環境は、社員の集中力や生産性を高めるだけでなく、コミュニケーションや心理的安全性にも大きく影響します。
本記事では、休憩場の必要性や設計ポイント、活用事例まで幅広く解説します。
オフィスにおける休憩場とは?

休憩場とは、社員が業務の合間にリラックスしたり、軽い雑談や情報交換を行ったりできるスペースを指します。
オフィスの一角に設置されることが多く、椅子やソファ、テーブルなどを配置した単純なスペースから、カフェ風・ラウンジ風にデザインされたおしゃれな空間まで様々です。適切に設計された休憩場は、集中力の回復だけでなく、社員同士の交流や組織の一体感向上にもつながります。
オフィスに休憩場が必要とされる背景

現代のオフィスでは、単にデスクで仕事をこなすだけではなく、社員が快適に働ける環境づくりが重要視されています。休憩場はその一環として、業務効率や社員満足に直接的な影響を与える場です。
ここでは、休憩場の設置が求められる理由を4つの観点から解説します。
休憩スペースが生産性に与える効果
集中して働き続けることは体力・精神面ともに負荷が大きく、長時間の業務は効率低下を招きます。休憩場は短時間のリフレッシュを可能にし、集中力や判断力の回復に役立ちます。実際、適度な休憩を取る社員は作業効率が向上する傾向にあり、結果的に業務の生産性を高める効果が期待できます。
ストレス軽減とメンタルヘルスの観点
休憩場は単なる休息の場ではなく、心理的な安全性を確保する場としても機能します。業務の合間に一息つける環境があることで、過度なストレスの蓄積を防ぎ、メンタルヘルスの維持に役立ちます。リラックスできる空間は、社員の心身の健康を支えるだけでなく、離職率の低下や長期的な組織の安定にもつながります。
コミュニケーション活性化のきっかけとなる場
休憩場は社員同士の偶発的な出会いや会話を生み出す場でもあります。普段は部署が異なり接点の少ない社員同士も、休憩場で気軽に話すことで情報交換やアイデア共有が進みます。このような交流はチームワークの向上や新たな発想の創出につながり、職場全体の活性化にも寄与します。
企業ブランディングや採用力への影響
快適な休憩場は社員の働きやすさに直結するだけでなく、企業イメージや採用力にも影響します。オフィス見学や面接の際、休憩場が整備されていることで「社員を大切にする企業」という印象を与えやすく、優秀な人材の獲得や定着にもつながります。また、社内文化や価値観を体感できる場として、ブランディングの役割も果たします。
休憩場の種類と特徴

オフィスにおける休憩場には、目的や利用シーンに応じてさまざまなタイプがあります。単に座って休むだけでなく、集中やコミュニケーション、アイデア創出など多様な機能を持たせることができます。
ここでは代表的な休憩場の種類と、それぞれの特徴を紹介します。
オープン型の休憩スペース
オープン型休憩スペースは、オフィスの一角に開放的な空間を設け、複数の社員が自由に利用できるスタイルです。フリーアドレスやソファ、テーブルを配置することで、偶発的な会話や情報交換が生まれやすくなります。部署を越えた交流を促進し、チームワークや組織全体の一体感向上に寄与します。
個室型・半個室型のリフレッシュスペース
個室型や半個室型のスペースは、集中したいときや静かに休みたいときに最適です。周囲の視線や音を遮ることで、短時間のリフレッシュや業務準備に集中できる環境を提供します。オープンスペースと併用することで、社員が状況に応じて使い分けられる柔軟な休憩環境を整えられます。
カフェ風・ラウンジ風のデザイン事例
近年は、カフェやラウンジのようなデザインを取り入れた休憩場が増えています。木材や緑を多用した空間、照明や音響の工夫により、リラックスしながらも交流が生まれやすい環境が実現可能です。社員が自然と集まり、コミュニケーションやブレインストーミングのきっかけをつくる役割も果たします。
ワークスペースとのバランスを考えた設計
休憩場を設置する際は、ワークスペースとの距離や動線も重要です。近すぎると雑音や視線が気になり、遠すぎると利用率が下がります。また、オフィス全体のレイアウトに合わせて、集中エリアと交流エリアを分けることで、メリハリのある働き方を支援できます。環境と利用目的のバランスが、快適な休憩場づくりの鍵となります。

成功しているオフィス休憩場の事例

休憩場は設置するだけでは十分に活用されません。成功しているオフィスでは、社員の利用意欲を高める工夫や、目的に応じた設計がなされています。
ここでは、実際の取り組みをもとに4つの事例を紹介します。
事例① オープンスペースで偶発的な交流を生む
ある企業では、オープンスペース型の休憩場を設け、ソファやテーブルを自由に使える環境を整えました。部署を越えた社員同士が自然に顔を合わせることで、雑談や情報交換が活発化。偶発的な会話から新しいアイデアが生まれるなど、チームワークの向上にもつながっています。
事例② 個室休憩スペースで集中とリラックスを両立
個室型休憩室を導入した企業では、短時間で集中したい社員や静かに休みたい社員が快適に利用できるようになりました。防音や間仕切りを工夫することで、業務への切り替えもスムーズに。オープンスペースと併用することで、社員のニーズに合わせた柔軟な休憩環境を提供することが可能です。
事例③ リフレッシュスペースを福利厚生の一部に組み込む
リフレッシュスペースを福利厚生制度の一環として位置付けた事例もあります。
例えば、コーヒーや軽食を用意したカフェ風休憩場を設置し、自由に利用できる仕組みに。社員は昼休みや仕事の合間に気軽に立ち寄れるため、リラックスしつつ社員同士の交流も促進され、組織全体の雰囲気が向上する効果も期待できます。
事例④ デザイン性を取り入れたブランド強化の工夫
企業のブランドイメージを意識して休憩場をデザインする企業も増えてきています。内装や家具、色彩に工夫を凝らすことで、オフィス全体の印象向上や社員の満足度向上につながります。また、訪問者や採用候補者に対しても「働きやすいオフィス」という印象を与えることができ、採用活動や企業ブランディングにも効果を発揮します。
休憩場を効果的に活用するポイント

休憩場は設置するだけでは最大の効果を発揮しません。社員が積極的に利用できる環境づくりや運用ルールを整えることが重要です。
ここでは、休憩場を効果的に活用するための4つのポイントを紹介します。
社員のニーズを反映したスペース設計
休憩場を設計する際は、社員の利用目的やライフスタイルを考慮することが重要です。短時間のリフレッシュ向け、雑談や打ち合わせ向け、集中作業向けなど、用途に応じたゾーニングを行うことで、社員が自然に利用しやすい空間が生まれます。アンケートや意見交換を通じてニーズを反映させることも有効です。
ルールやマナーを整備して使いやすさを維持
休憩場の利用ルールを明確にすることで、誰もが快適に使える環境を維持できます。たとえば、飲食可能エリアの指定、騒音の管理、清掃や片付けのルールなどを整備することが大切です。社員同士が互いに配慮しながら利用できる環境は、心理的安全性の向上や交流の促進にもつながります。
オフィス全体の動線や環境との調和
休憩場は単独で設置するだけでなく、オフィス全体の動線や働く環境とのバランスを意識することが大切です。デスクや会議室からアクセスしやすく、かつ仕事の妨げにならない位置に配置することで、社員が自然に立ち寄れるようになります。
環境と休憩場の調和は、利用頻度や満足度に直結します。
定期的な利用状況の把握と改善サイクル
休憩場の効果を最大化するには、定期的な利用状況の把握と改善が欠かせません。アンケートや観察、ツールによるデータ収集を行い、利用者の声や傾向を分析することで、椅子やテーブルの配置変更、利用ルールの見直しなど、改善策を継続的に検討できます。こうしたPDCAサイクルが、快適な休憩環境の維持につながります。
ツールを活用した休憩場の利用促進と効果測定

休憩場の活用状況を把握し、効果的な改善を行うにはデータの活用が有効です。従来のアンケートだけでなく、ツールを使った見える化によって、利用率や混雑状況、社員の交流傾向などを正確に把握できます。
ここでは、ツール活用による休憩場運用のポイントを紹介します。
利用率を把握するデータ活用の意義
社員がどの程度休憩場を利用しているかを把握することは、改善策の検討に欠かせません。利用頻度や滞在時間をデータ化することで、「あまり使われていない」「特定の時間帯に集中している」などの課題を明確化できます。データに基づく判断は、感覚だけでは分かりにくい実態を可視化する手段として有効です。
混雑状況や利用傾向の可視化
休憩場の混雑状況や利用傾向を可視化することで、社員が快適に利用できる環境づくりが可能になります。たとえば、ピークタイムの混雑緩和策や、配置変更による動線改善を行うことができます。こうしたデータは、オフィス全体のレイアウト最適化や利用促進施策の計画に活かすことができます。
コミュニケーション促進とリフレッシュ効果の検証
ツールを活用することで、社員同士の交流やリフレッシュの効果も確認できます。どの社員がどのくらい交流しているか、滞在時間や場所の偏りなどを分析することで、交流の促進策やリフレッシュ環境の改善点が見えてきます。データを基に施策を改善することで、休憩場の効果を最大化できます。
事例紹介:Beacapp Hereによる利用傾向の把握
Beacapp Hereを導入することで、社員の出社状況や滞在場所をリアルタイムに把握できます。休憩場の利用状況もデータ化でき、ピークタイムや混雑状況、部署ごとの活用傾向を分析可能です。この情報をもとにレイアウト調整や利用ルールの改善を行うことで、快適な休憩環境を維持しつつ、コミュニケーションの活性化にもつなげられます。

まとめ
オフィスにおける休憩場は、単なる休息の場ではなく、社員の生産性向上やメンタルヘルス維持、コミュニケーション活性化に大きく寄与します。設置するだけでなく、社員のニーズに合わせた設計やルール整備、利用状況の定期的な見える化が重要です。ツールを活用することで、データに基づいた改善サイクルを回し、快適で働きやすい職場づくりを実現できます。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg