「今日は出社?それとも在宅?」
働き方の選択肢が増えた今、そんな会話が日常になりました。一方で、似たように使われる「出社」と「出勤」という言葉の違いを、正確に説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか。本記事では、これらの言葉の意味を整理しながら、現代の働き方やオフィスのあり方についても掘り下げていきます。
「出社」と「出勤」はどう違う?働き方の視点から考える
かつては同じように使われていた「出社」と「出勤」ですが、働く場所が多様化した現代では、その違いが意識されるようになってきました。意味の違いを知ることで、チーム内でのすれ違いや誤解を防ぐヒントにもつながります。
まずは、それぞれの言葉がどのように使われているのかを見ていきましょう。

「出社」=会社という場所に身を置くこと
「出社」とは、文字通り“会社に出る”ことを指します。オフィスに足を運び、自席につくことや、対面での業務に参加する行為が含まれます。かつては働く=出社することが当たり前でしたが、現在は「物理的に会社に行くこと」が選択肢のひとつとなっています。
ビジネスシーンでは、「明日は出社します」「今日は出社していません」といった使い方をされ、場所に焦点があるのが特徴です。つまり“どこで働くか”を明示する言葉として、「出社」は今でも使われ続けています。
「出勤」=業務を開始すること(場所に縛られない)
「出勤」は、「勤務を開始すること」そのものを指します。働く場所に関係なく、業務に従事している状態が「出勤」なのです。そのため、オフィスにいようと自宅にいようと、勤務時間に仕事をしていれば「出勤している」と言えます。
たとえば「出社せずに出勤する」「在宅勤務だけど出勤している」といった表現が成り立つのも、出勤が“行動”ではなく“状態”に近い概念だからです。つまり、出勤は「どこで」よりも「何をしているか」に重きを置いた言葉と言えるでしょう。
在宅・リモートが普及して“出社しない働き方”が当たり前に
コロナ禍以降、リモートワークや在宅勤務が急速に普及し、多くの企業が柔軟な働き方を取り入れるようになりました。その中で、「出社せずに出勤する」ケースが一般的になっています。たとえば、朝自宅でパソコンを開いてログインすることで“出勤”となる一方、会社には一度も足を運ばない=“出社していない”という状態が生まれました。
このように、働く=会社に行くという前提が崩れたことで、「出社」と「出勤」の違いがより明確になってきたのです。
言葉のズレが生むコミュニケーションの誤解
「出勤してますか?」と聞かれて「はい」と答えたところ、相手は「オフィスにいる」と勘違いしていた―そんなすれ違いが起きるのも、言葉の認識の違いが原因です。
とくにリモートワークやフリーアドレスが広がる中では、「出社=オフィスにいる」「出勤=働いている状態」といった使い分けが、社内でも浸透しきっていないことがあります。
こうした小さな誤解が、連携ミスや確認漏れの原因になることも。あらためて言葉の意味をすり合わせることが、ハイブリッド時代のスムーズなコミュニケーションに欠かせません。
関連記事: リモートワークの廃止・減少の背景とは?在宅勤務の未来を考える
出社率・出勤率から見る「働き方のリアル」
出社率・出勤率という言葉をニュースや社内資料で目にする機会が増えました。数値で働き方を可視化しようとする流れは強まっていますが、これらの指標だけでは“働き方の実態”までは見えてこないこともあります。ここでは、出社率・出勤率の違いと、オフィス回帰の流れの中で見落とされがちな課題について考えてみましょう。

出社率は“物理的な接点”、出勤率は“実働の状態”
出社率と出勤率は似たように使われることがありますが、意味は異なります。出社率とは「従業員のうち、実際にオフィスへ足を運んだ人の割合」、つまり物理的な接点を示す数値です。一方、出勤率は「勤務していた人の割合」であり、在宅勤務も含めた稼働状態全体を表しています。
たとえば、社員の多くが在宅勤務で業務に取り組んでいる場合、出勤率は高くても出社率は低いというケースもあります。数値を正しく読み解くには、その裏側にある働き方を想像することが大切です。
数字が上がっても、働き方の質は別問題
出社率や出勤率が高ければ、「働いている人が多い」「順調に業務が回っている」と思いがちですが、実際はそれだけでは判断できません。たとえば、出社率が高くても、オフィスでのコミュニケーションが少なかったり、部門間の連携が希薄だったりすれば、組織としての一体感は損なわれがちです。
また、出勤率が高い状態でも、長時間労働や過重な業務が隠れている可能性もあります。指標としての「数字」を過信せず、実際に人がどう働いているのかという中身に目を向けることが求められます。
オフィス回帰が進む中で浮かぶ“形だけの出社”問題
コロナ禍を経て、最近では“出社推奨”の動きが再び強まっています。特にチームビルディングや雑談の重要性が見直され、オフィスへの回帰が進む企業も増えています。しかしその一方で、「ただ出社しているだけ」「オンライン会議をオフィスでこなしているだけ」といった“形だけの出社”が課題になることも。
出社率が上がっても、コミュニケーションや協働の質が伴っていなければ、本来の目的は果たせません。出社が“目的化”してしまうと、働き方の柔軟性を損ねる恐れもあるのです。
実態を捉えるには「行動の見える化」が必要
数値で管理される出社率・出勤率だけでは、働き方の質や社員の状態を深く知ることはできません。重要なのは、その場に「誰がいて」「何が起きているか」を行動レベルで把握することです。
たとえば、どの部署の誰が、どの場所で、どれくらいの頻度で他者と接点を持っているか。オフィス内での滞在傾向やフロア間の移動、チーム間の物理的距離などを把握すれば、形だけの出社から“意味のある出社”への転換も可能になります。そのためには、リアルな行動データの活用が鍵となります。

変わる働き方の中で「見えなくなったもの」
リモートワークやフリーアドレスなど、働き方が柔軟になる一方で、「見えなくなったもの」も増えてきました。どこで・誰と・どのように働いているのかが把握しづらくなった今、チームの関係性や社員のコンディションをどう読み取るかが問われています。
この章では、現代の働き方に潜む“見えづらさ”について掘り下げていきます。

場所に縛られない働き方が生んだ“分断”
テレワークや在宅勤務の普及は、ワークライフバランスの向上や通勤負担の軽減といった多くのメリットをもたらしました。一方で、働く場所の分散は「同じ空間を共有しないことによる孤立感」や「偶発的なコミュニケーションの減少」といった課題も生んでいます。
日常のちょっとした雑談や、顔を合わせて気づく体調の変化など、“オフィスにいれば自然に共有できていたこと”が分断されることで、チーム内のつながりが希薄になることも。場所の自由度が増した今こそ、意識的な関係構築が重要です。
管理職もチームの状態を把握しにくくなっている
メンバーの働き方が多様化する中で、マネジメントの難易度も上がっています。とくにハイブリッドワークでは、「今日は誰が出社しているのか」「最近あの人と顔を合わせていないな」といった感覚的な把握が難しくなりがちです。
業務の進捗は確認できても、メンバーの心理的な変化やチームの関係性といった“見えない部分”はなおさら捉えづらいのが実情です。管理職にとって、従来の「目の届く範囲でのマネジメント」から、「データや仕組みで支えるマネジメント」への転換が求められています。
サーベイだけでは分からない“行動の変化”
定期的なエンゲージメントサーベイやアンケートは、組織の声を集める有効な手段ですが、それだけでは“変化の兆し”を見逃してしまうこともあります。
たとえば、回答内容はポジティブでも、実際には出社頻度が急に下がっていたり、昼休みの時間帯に一人で過ごす傾向が強まっていたりといった“行動の変化”が見えていない場合、対処が後手になる可能性があります。表面的な数値だけでなく、実際の行動パターンに目を向けることが、働き方の本質を捉えるヒントになります。
リアルタイムな状況把握がチーム力を支える
「どこで」「誰と」「どのように働いているか」をリアルタイムで把握できれば、チームの関係性や働き方の変化にもいち早く対応できます。とくにハイブリッドワーク環境では、“気づいたときには遅い”というケースも少なくありません。
メンバーの行動や接点のデータを活用し、変化に敏感なマネジメントを実現することが、チーム力の維持・向上につながります。感覚や経験則に頼るのではなく、客観的な情報をもとにした“支える姿勢”が、これからの時代の管理職には求められています。
出社と出勤をつなぐ「データ活用」とその可能性
「出社」と「出勤」の違いが注目される今、その“ギャップ”を埋める手段として、行動データの活用が注目されています。感覚や記憶に頼らず、誰が・どこで・どのように働いているのかを可視化することは、職場の改善やチームづくりにもつながります。この章では、実際に役立つ可視化の手法とツールの可能性を紹介します。

見えなかった“働く実態”を可視化する方法
出社しているのに孤立している人がいたり、在宅でも積極的にチームと連携している人がいたり。現代の働き方では、見た目や出社状況だけでは本当の働き方は読み取れません。
そこで注目されているのが、行動データの可視化です。オフィスへの出入り情報、在席時間、会議参加傾向などの情報をもとに、個人やチームの状態をリアルに把握することで、働き方の“質”を見える形で捉えられるようになります。数字だけでは掴めない、リアルな実態把握が可能になるのです。
人の流れ・接触傾向のデータが活きるシーン
たとえば「誰がどこにいるか」「どの部署とどれくらい接点があるか」といったデータは、オフィスレイアウトの改善や部署間の連携強化に役立ちます。人の流れや滞在傾向を把握することで、無駄な動線のカットや偶発的な交流の促進といった施策も打ちやすくなります。
また、新入社員や中途社員がどの程度既存メンバーと接点を持てているかを把握するのにも有効です。可視化によって“なんとなくの不安”が数値として捉えられるため、具体的な改善アクションにつなげやすくなります。
Beacapp Hereで実現するオフィス改善のヒント
位置情報を活用して人の動きをリアルタイムで可視化できるツール「Beacapp Here」では、出社状況やフロアの混雑度、接触傾向などを定量的に把握することができます。
三井不動産では、Beacapp Hereのデータとアンケート結果を組み合わせることで、社員の動きに合ったオフィスレイアウトの最適化に成功しました。単なる出社率ではなく、どこに誰が集まり、どんな接点が生まれているのかという“人の動き”を分析することで、より快適で効果的な働き方を支援しています。
▶︎ 社員の動きに合ったオフィスレイアウトの最適化に成功した三井不動産の活用事例を見る
出社と出勤の「ギャップ」を埋めるテクノロジー
出社しているだけでは見えない、出勤しているだけでも伝わらない―そんな“ギャップ”を埋めるのが、テクノロジーの力です。働く場所がバラバラでも、リアルタイムに行動を把握できる仕組みがあれば、曖昧だった働き方の実態が明確になります。
とくにハイブリッドワークが定着しつつある今、「見えない」ことが組織の弱点になりかねません。Beacapp Hereのようなツールを活用することで、出社と出勤の両方を正しく捉え、“個と組織”の健全な関係を築くためのベースが整います。
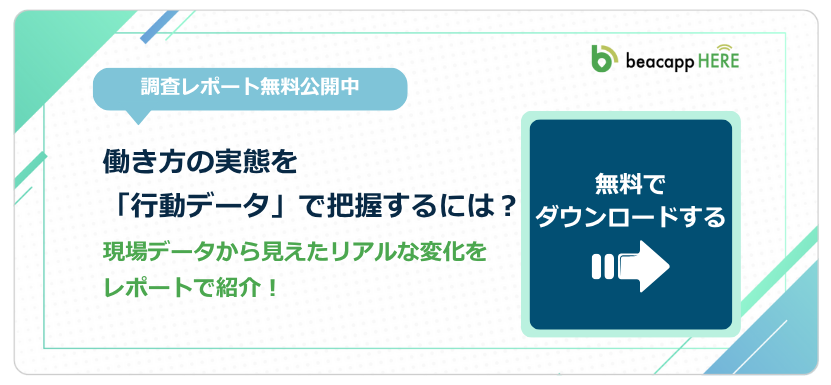
まとめ
「出社」と「出勤」は、働く場所やスタイルが多様化した今だからこそ、改めて違いを意識したい言葉です。ただ出社率や出勤率を追うだけでは、本当の働き方や組織の状態は見えてきません。
大切なのは、“誰が・どこで・どのように働いているか”を正しく把握し、チームがよりよく機能するよう支えること。行動の見える化やデータ活用を通じて、意味のある働き方へとつなげていきましょう。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg
