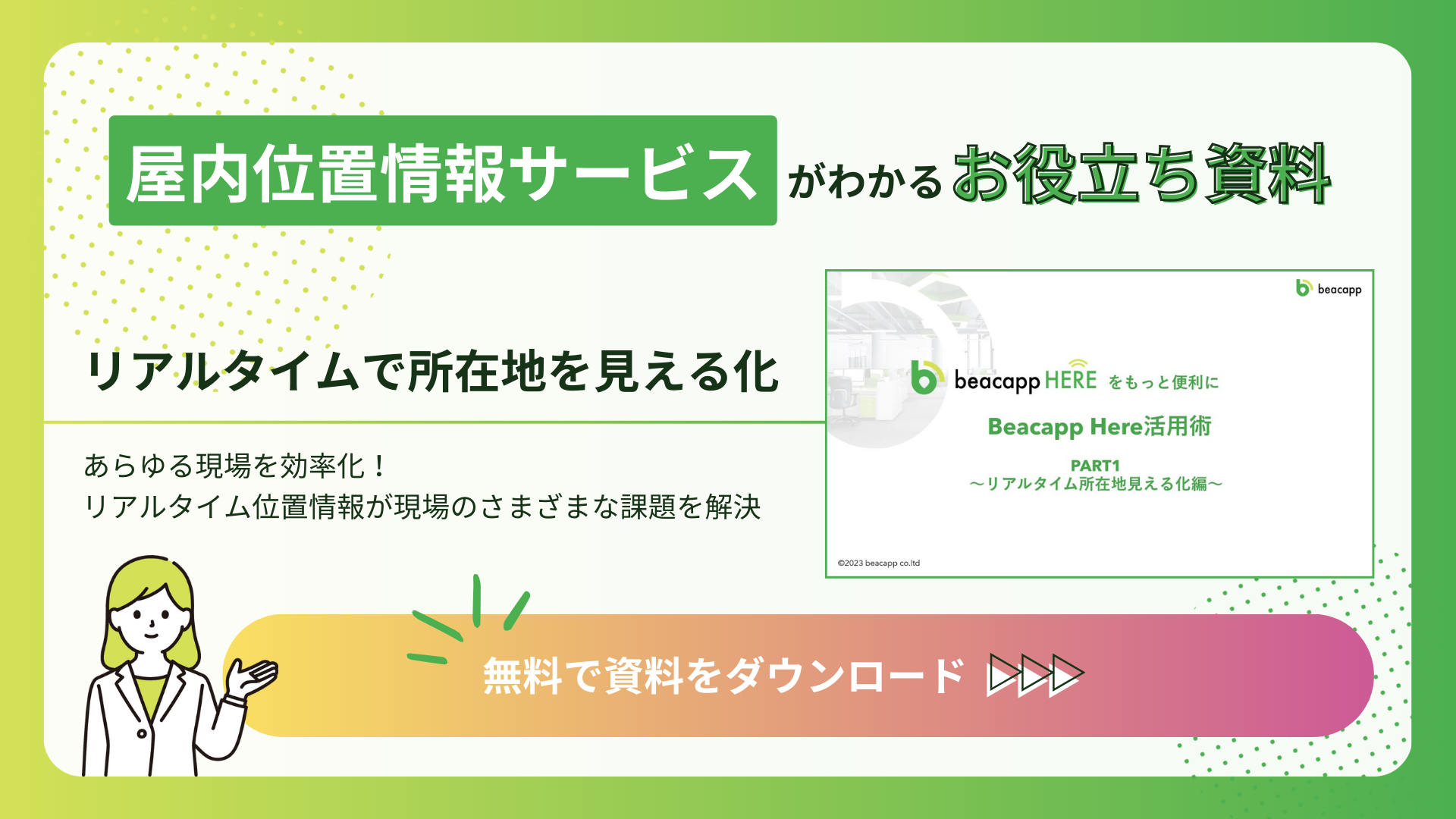営業車・社用車の運用における管理の煩雑さや、出退勤の記録漏れによる勤怠リスクは、多くの企業が直面している課題です。
従業員が車で出社し、社内に立ち寄らずに退勤するなど、実際の行動が勤怠記録と一致しないケースも散見されます。
こうした背景のなか、GPSやビーコンを活用した車両管理と勤怠補助のソリューションが注目されています。
この記事では、社用車の可視化によって得られるメリットや、具体的な導入方法、運用の注意点まで詳しく解説します。
なぜ営業車・社用車の「可視化」が今求められるのか

車両の可視化は、単なる運行管理にとどまらず、勤怠精度の向上や人材リソースの最適化にも直結する重要な経営テーマとなっています。
勤怠漏れや労務トラブルのリスク
従業員が営業車や社用車を使って出社・退社する場合、物理的にオフィスに立ち寄らず直行直帰するパターンや、駐車場に車を止めたままそのまま帰宅するパターンも少なくありません。
こうした行動が記録に残らず、「勤務していたはずなのに打刻がない」「実態と合わない勤怠記録」といった労務トラブルの原因となることがあります。
近年では労働時間管理が厳格化され、勤怠記録の正確性が企業のリスクマネジメントに直結するようになりました。
GPSやビーコンを活用して、車両の動きをもとに出退勤時刻を推定・補完することは、こうした問題を未然に防ぐ有効な手段です。
社用車の利用実態が不透明になりやすい
複数人が同じ営業車を使い回すケースでは、誰が・いつ・どこへ・どれくらいの時間車を使ったのかが不明瞭になりがちです。
また、車両がどこにあるのかが把握できないため、予約や共有がスムーズに進まず、非効率な運用になっている企業も少なくありません。
こうした不透明さは、利用者間のトラブルや車両管理の属人化にもつながります。
可視化によって利用履歴が残るようになれば、責任の所在も明確になり、透明性のある運用が可能になります。
運用効率・コスト最適化への要求の高まり
車両管理の見える化は、運用効率化やコスト削減にも直結します。
例えば、あまり使われていない車両や、アイドリング時間が長いケースを把握できれば、リース車両の台数見直しや燃費改善にもつながります。
また、営業活動の稼働率が高いエリアに車両を重点配置するなど、データに基づいた合理的な判断ができるようになります。
単なる「管理」ではなく「戦略的運用」のためにも、位置情報による可視化は大きな武器となるのです。
GPSやビーコンを活用した社用車管理の仕組み

社用車の管理においては、GPSやBluetoothビーコンを活用した低コスト・高精度のソリューションが登場し、手軽に可視化を実現できるようになっています。
GPSとビーコンの違いと併用のメリット
GPSは広域での位置測位に優れた技術であり、屋外や走行中の追跡には最適です。
しかし、地下駐車場やビルの谷間などでは位置精度が落ちる場合があり、細かな行動検知には不向きな側面もあります。
一方、Bluetoothビーコンは屋内や特定エリアでの検知に優れ、建物内の動きをリアルタイムで把握するのに適しています。特に駐車場や社屋内にビーコンを設置し、スマートフォンアプリと連携させることで、「誰が・どこに・どれだけいたか」を高精度に可視化できます。
GPSとビーコンを併用することで、社外での動き(GPS)と社内や駐車場での動き(ビーコン)の両方をカバーし、実態に即した運用記録が残せます。
スマートフォン連携による運転者特定の仕組み
Beacapp Here のようなシステムでは、車両側に小型のビーコンを設置し、社員がスマートフォンを携帯していれば、自動的に「誰がその車に乗っているか」を検知できます。
例えば、ある営業車に搭載されたビーコンが特定のスマホ(社員A)と一定時間以上検知された場合、その時間帯は社員Aがその車を使用していたというログが残ります。これにより、利用者の手動入力を必要とせず、運転者の自動識別が可能となります。
共用車両でもトラブルなく運用できる点は、多くの企業にとって大きな魅力です。
Beacapp Hereによる勤怠補助と稼働分析
Beacapp Here は、もともとオフィス内の人の動きを可視化することに強みを持つソリューションですが、その技術を応用すれば、車両の位置情報と組み合わせた勤怠補助が可能になります。
例えば、以下のようなログが自動で取得されます:
・駐車場に到着した時間
・誰がどの車に乗っていたか
・滞在時間(=勤務時間の補足材料)
この情報を勤怠システムと連携させることで、記録漏れの検知や勤務実態の補完が可能となります。
また、ダッシュボード上で稼働率を可視化すれば、車両の稼働偏差や余剰の把握にもつながります。

実際に期待できる導入効果とメリット

GPSやビーコンを活用することで、社用車管理と勤怠管理が連動し、管理コストの削減や労務リスクの低減など、多くの効果が期待できます。
勤怠精度の向上と記録漏れの防止
最大のメリットは、勤怠精度の向上です。
従業員がオフィスに立ち寄らず退勤してしまう場合でも、駐車場の滞在ログや運転履歴が記録されていれば、出退勤の記録漏れを自動で検知します。
これにより、労働時間の透明性を保ち、労基署への対応もスムーズになります。
記録を補完することで、本人の証明負担も減り、社員・管理側の双方にメリットがあります。
運用効率化と車両の最適配置
利用履歴データを分析すれば、「稼働していない車」「特定の社員しか使っていない車」「偏った利用傾向」などが明らかになります。
これをもとに配置や車両台数を見直せば、リース費・保険料などの固定費も圧縮可能です。
また、稼働が集中している車については、走行距離や点検履歴と連携し、メンテナンスの最適なタイミングを見計らうこともできます。
安全運転や業務DXへの貢献
運転時間や経路、停車時間などを記録することで、「長時間運転の抑止」「適切な休憩の促進」「過密スケジュールの是正」など、安全面でも大きな効果が期待できます。
さらに、こうしたデータをもとに運用フローを見直すことは、社用車管理のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進にもつながり、業務効率や生産性の向上にも貢献します。
導入の流れと運用の注意点

導入時は、技術面だけでなく、制度や社内の理解も大切です。スムーズな展開のためのポイントを押さえておきましょう。
導入ステップ:計画〜運用開始まで
1.課題整理と目的設定
→ 勤怠補助が主目的か、車両稼働率分析か、明確に。
2.デモ・トライアル
→ Beacapp Here では最大2ヶ月の無料トライアルが可能。
3.ビーコン設置/スマホ設定
→ 車両へのビーコン設置、スマホアプリのインストール。
4.管理画面設定と運用テスト
→ 利用者・管理者の操作性を確認。
5.本導入・定着支援
→ 利用マニュアルや社内説明会などを実施。
利用者への周知とルール整備
位置情報を扱うため、社員側の心理的な抵抗をなくすための配慮が重要です。たとえば:
・取得範囲は「勤務時間中のみ」
・プライバシーは侵害しない
・勤怠や業務記録の補助が目的
こうしたルールを明文化し、就業規則・労使協定への反映を検討することで、導入後のトラブルも防止できます。
データ活用と他システム連携
Beacapp Hereでは、API連携を活用することで、既存の勤怠管理システムや業務報告システムとデータ統合が可能です。
たとえば以下のような連携が実現できます:
・勤怠システムと連携して出退勤補完
・BIツールで車両利用の可視化
・日報ツールと統合して行動記録を自動作成
これにより、データの価値を最大限に引き出し、業務全体のデジタル化を一歩進めることができます。

まとめ
営業車・社用車の可視化と勤怠補助は、企業にとって今後ますます重要なテーマです。
GPSとビーコンというシンプルかつ強力な技術を活用することで、「誰が・どこで・いつ・何をしていたか」という行動を正確に記録し、透明性の高い働き方を支える仕組みを構築できます。
Beacapp Hereのようなツールを導入することで、管理の負担軽減だけでなく、リスクマネジメント、運用効率化、社員の安心感向上にもつながる点が魅力です。
社用車管理に課題を感じている企業こそ、今こそ「見える化」の一歩を踏み出す絶好のタイミングといえるでしょう。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg