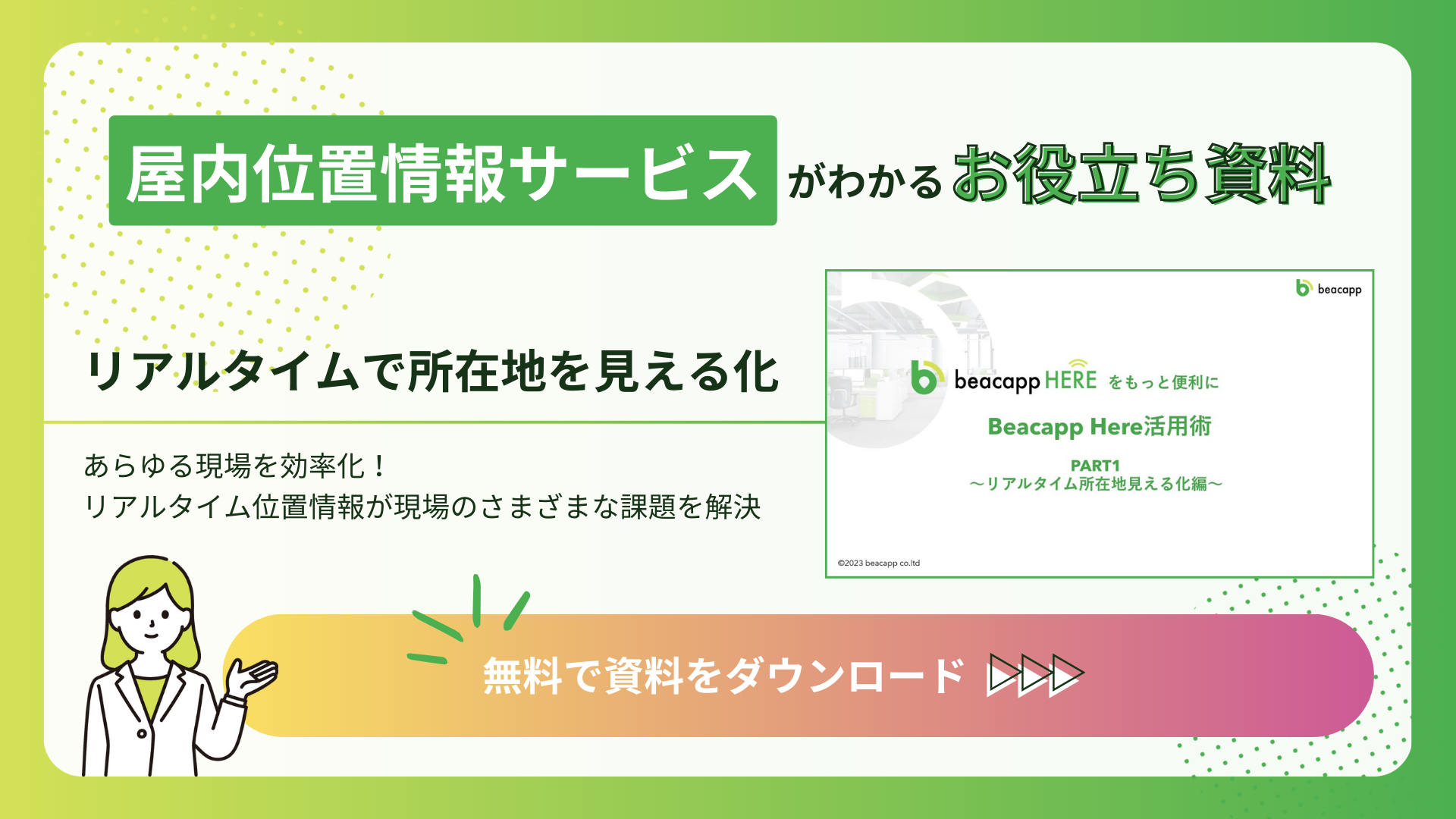「在宅勤務って、そもそもどういう働き方?」と疑問に思ったことはありませんか?
コロナ禍をきっかけに急速に広がった在宅勤務は、今や多くの企業にとって当たり前の選択肢になりつつあります。しかし、制度の仕組みや対象者、他の働き方との違いなど、意外と知られていないことも多いのが現実です。
本記事では、在宅勤務の基本からその実態まで、わかりやすく丁寧に解説します。
在宅勤務とは?制度と働き方の基本をわかりやすく解説
「在宅勤務」と聞いても、制度としての定義やリモートワークとの違いがよくわからない…という方も多いのではないでしょうか。在宅勤務は今や多くの企業に取り入れられている働き方ですが、その内容や対象者、国の定義は意外と複雑です。
ここでは、在宅勤務の基本をわかりやすく整理していきます。

在宅勤務とは?簡単に説明するとこういうこと
在宅勤務とは、会社に出勤せずに「自宅で仕事をする働き方」のことです。パソコンやスマートフォン、インターネットなどの通信機器を使って、業務を自宅で完結させるのが基本となります。働く場所は変わりますが、勤務時間や仕事内容は通常の出社勤務と変わらないケースがほとんどです。
また、在宅勤務は「好きな時間に好きなだけ働ける」わけではなく、企業が定めた就業ルールに則って働く必要があります。業務報告や勤怠管理も求められるため、「自宅での勤務環境を整えること」も重要なポイントです。
厚生労働省の定義から読み解く在宅勤務
厚生労働省では「テレワーク」を「情報通信技術(ICT)を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方」と定義し、その中に「在宅勤務」を位置づけています。在宅勤務は、テレワークの中でも「自宅に拠点を置く勤務形態」であり、企業と雇用契約を結んだ労働者が対象となります。
つまり、在宅勤務は一時的な措置ではなく、制度として整備されるべき働き方です。厚労省も導入ガイドラインを提示し、労働時間管理・評価制度・情報セキュリティ対策などの整備を企業に促しています。制度の理解を深めることで、より安心して働ける環境が整います。
在宅勤務の対象者・職種はどう決まる?
在宅勤務が可能かどうかは、業務内容や職種によって大きく異なります。例えば、企画・営業・事務・ITエンジニアなど、主にパソコンを使って完結できる仕事は在宅勤務に向いているとされています。
一方、製造業や医療・介護・接客業など、現場での対応が求められる職種は、在宅勤務の導入が難しい傾向にあります。また、企業側がセキュリティや生産性の観点から対象者を限定するケースもあるため、全社員が等しく適用されるとは限りません。
ただし、技術の進化や業務設計の見直しによって、対象範囲は今後さらに広がる可能性があります。
在宅勤務とリモートワーク・テレワークの違いとは
「在宅勤務」「リモートワーク」「テレワーク」は似たような意味で使われることが多いですが、実はニュアンスに違いがあります。
「テレワーク」は最も広い概念で、通信技術を活用して「自宅・サテライトオフィス・カフェなど、会社以外の場所で働くすべてのスタイル」を含みます。「リモートワーク」は英語由来で、主にIT業界を中心に使われることが多い言葉です。
「在宅勤務」はその中でも「自宅」に限定された働き方を指します。つまり、在宅勤務はテレワークの一種であり、もっとも具体的な言い方ともいえるのです。用語の使い分けを知ることで、より制度理解が深まります。
在宅勤務のメリット・デメリット
在宅勤務には通勤のストレスがなくなったり、集中できる環境を作れたりと、さまざまなメリットがあります。一方で、コミュニケーション不足や仕事とプライベートの線引きが難しいといった課題も存在します。この章では、働く側・企業側双方の視点から、在宅勤務の長所と短所を整理してみましょう。
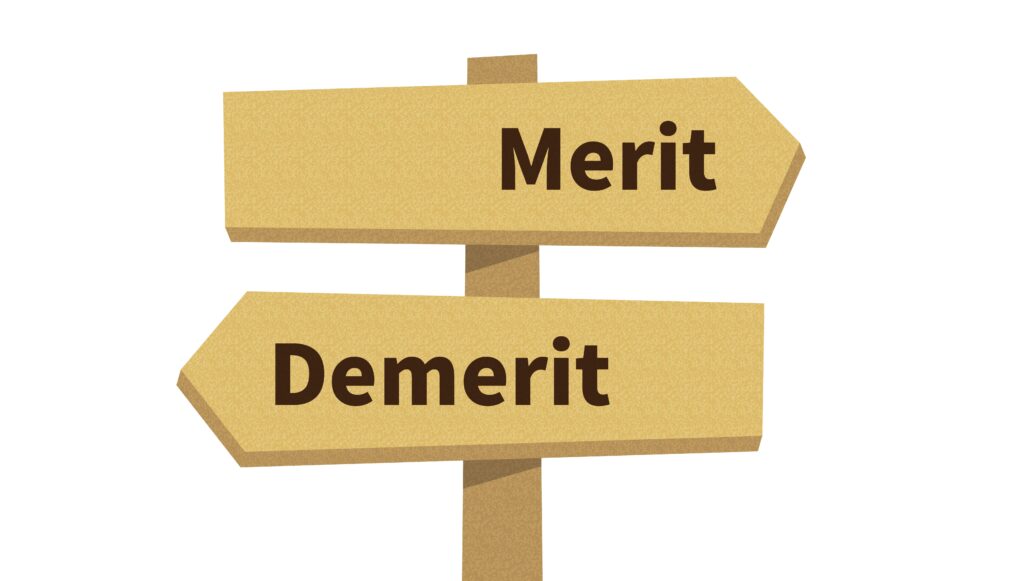
在宅勤務のメリット:柔軟な働き方でストレス軽減
在宅勤務の大きなメリットは、通勤時間がなくなることで心身の負担が減る点です。毎朝満員電車に揺られる必要がなくなり、余った時間を家事や育児、自己学習などに充てることができます。自分のペースで始業準備ができることで、心理的な余裕も生まれやすくなります。
また、オフィスでは話しかけられて集中できないという人にとっては、自宅の静かな環境で仕事に没頭できる点も魅力です。場所にとらわれない働き方が可能になることで、地方在住者や育児中の方でも仕事を継続しやすくなるという社会的メリットもあります。
在宅勤務のデメリット:孤独感や情報格差のリスクも
一方で、在宅勤務には「孤独感」を感じやすくなるというデメリットもあります。人とのふれあいが減ることで、相談や雑談がしづらくなり、精神的な不安や孤立感につながるケースもあります。特に入社間もない社員や、チームとの関係が浅い人は要注意です。
また、オフィスでの何気ない情報共有ができないことで、認識のズレや情報格差が生まれやすくなります。対面のような自然なコミュニケーションが減ることで、業務に必要な情報が伝わりにくくなるリスクもあるのです。
企業側の視点:在宅勤務の運用で直面する課題
企業側にとっての在宅勤務の悩みは、主に「業務の進捗把握」と「労務管理の難しさ」です。オフィスであれば一目で把握できる出退勤状況や稼働状況が、在宅では見えづらくなります。また、長時間労働やサボりといった不安もぬぐえません。
さらに、セキュリティの問題も重要です。自宅のネットワーク環境やパソコンの管理が不十分な場合、情報漏洩のリスクが高まります。こうした課題に対応するためには、ツールの導入やルール整備など、制度設計とマネジメント手法の見直しが求められています。
従業員満足度を左右する要素とは?
在宅勤務の成否を左右するのは、単に制度の有無ではなく「どれだけ快適に、安心して働けるか」です。例えば、自宅でも仕事がしやすいようにパソコンや椅子を支給する、チャットツールで雑談しやすい雰囲気をつくる、といった小さな工夫が大きな満足度につながります。
また、「評価制度が不透明で不安」と感じる社員も少なくありません。在宅でも正当に評価されているという実感が得られるような制度設計が、エンゲージメント向上に欠かせないのです。社員の声に耳を傾けながら、継続的に働き方を改善していく姿勢が問われています。

在宅勤務と給料の関係
在宅勤務が普及する中で、「在宅になると給料はどうなるの?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。給与体系や評価制度、通勤手当の扱いなど、在宅勤務には働き方の変化に応じた新たな仕組みが必要になります。この章では、給料との関係性や制度の変化をわかりやすく整理していきます。

「在宅勤務だと給料が下がる?」の誤解
在宅勤務になると「働いている姿が見えない」「サボっていると思われそう」といった不安から、「給料が下がるのでは?」と心配する人もいます。しかし実際には、在宅勤務を理由に基本給を減額することは労働契約上認められていません。
給料が変わる場合は、在宅勤務に伴う「評価制度の見直し」や「職務内容の変更」など、他の要因が関係していることが多いのが実情です。つまり、在宅勤務そのものが給料に直結しているわけではなく、「どのように評価されるか」が重要なポイントとなります。
成果主義・時間管理型…在宅勤務で進む評価制度の変化
在宅勤務では「オフィスにいない=働いていない」という誤解が生まれやすいため、評価制度の見直しが求められています。そこで注目されているのが、「成果主義」や「プロセス重視型」の評価手法です。
例えば、タスクの達成度やプロジェクトの進捗状況を可視化し、結果をもとに評価するスタイルが増えています。また、時間ベースでの管理も根強く、勤務時間の自己申告や勤怠ログの記録が重要な指標になります。どちらにせよ、納得感のある評価制度を整備することが、モチベーション維持につながるといえるでしょう。
在宅勤務手当や福利厚生の見直し
在宅勤務に移行すると、通勤交通費の支給がなくなる一方で、自宅の光熱費や通信費が増えるという声もあります。そこで多くの企業が導入しているのが「在宅勤務手当」や「在宅用備品支給」といった新しい福利厚生です。
たとえば、月額で定額の在宅勤務手当を支給したり、Wi-Fiやモニター、椅子などの環境整備をサポートする仕組みが代表的です。こうした支援があることで、在宅でも快適に仕事ができる環境が整い、社員の生産性向上にもつながります。
不公平感をなくす制度設計のポイント
在宅勤務者と出社勤務者の間で「働きやすさ」や「評価」に差があると、不公平感が生まれ、チーム全体の士気に影響を与える可能性があります。たとえば、出社することで上司に顔を覚えられる一方で、在宅では存在感を示しにくいといった声もあります。
このようなギャップを防ぐには、評価基準やコミュニケーションの機会を平等に設計することが重要です。出社・在宅を問わず、成果や貢献が公平に認識されるよう、制度やツールを見直していく必要があります。
在宅勤務の今後の展望と課題
コロナ禍をきっかけに急速に広がった在宅勤務は、アフターコロナ時代に入った今もなお、多くの企業で活用されています。しかし、出社とのバランスをどうとるか、制度をどう持続可能なものにするかなど、課題も残されています。今後、在宅勤務はどのような形で定着していくのかを考えてみましょう。

コロナ禍で普及、今は「選択制」が主流に
2020年の新型コロナウイルス流行をきっかけに、多くの企業が急遽導入した在宅勤務。当初は「感染症対策」という非常時の対応でしたが、働く場所や時間に柔軟性が持てることから、恒久的な制度として定着する企業も増えました。
現在では、「完全在宅」「週数回の出社」「自由選択制」など、企業によって運用方法はさまざまです。重要なのは、一律の方針ではなく、業務やチームに合った選択肢を提供することです。社員が自分に合った働き方を選べる環境が、今後のスタンダードとなっていきそうです。
ハイブリッドワークの中での役割とは?
「完全リモート」か「フル出社」か、という二択ではなく、両方の良さを取り入れた「ハイブリッドワーク」が注目されています。たとえば、集中したい業務は自宅で行い、チームでの意思疎通やブレストはオフィスで行うといった使い分けが進んでいます。
このように在宅勤務は、オフィスと役割を分担しながら補完し合う存在へと進化しています。出社と在宅、それぞれのメリットを活かすことで、生産性と満足度の両立が可能になります。そのためには、出社・在宅のバランスや頻度を戦略的に設計することが求められます。
在宅勤務とメンタルヘルス対策の重要性
在宅勤務の継続で見過ごせないのが、メンタルヘルスへの影響です。人との接触が減ることで孤独感が増し、ちょっとした不安や疲れが蓄積されやすくなります。特に若手社員や中途入社者など、組織との関係構築が不十分な人ほどリスクが高まります。
そのため、企業はオンライン面談や1on1、バーチャル雑談会などを通じて、定期的なコミュニケーションの機会を設けることが求められています。心理的安全性を保ちながら働ける環境こそが、長期的な制度運用の鍵となるのです。
制度とテクノロジーの両輪で支える時代へ
在宅勤務を持続可能なものにするには、「制度」と「テクノロジー」の両面からの支援が不可欠です。勤怠管理・労務管理・コミュニケーションといった各領域で、ツールの活用が急速に進んでいます。
たとえば、出社・在宅の状況を可視化したり、行動データをもとにチームの接触傾向や稼働バランスを分析したりといった仕組みが注目されています。Beacapp Hereのようなツールを活用すれば、働き方の見直しや業務改善にもつながります。データと仕組みの力で、より柔軟で快適な働き方が実現できる時代へと進んでいるのです。
在宅勤務を支えるツールと仕組み
在宅勤務が当たり前になった今、業務を円滑に進めるには「ツールの活用」が欠かせません。特に、Web会議やチャット、勤怠管理や出社状況の把握などは、在宅でも働きやすい環境づくりに直結します。ここでは、代表的なツールや、働き方の“見える化”を支える仕組みについて紹介します。
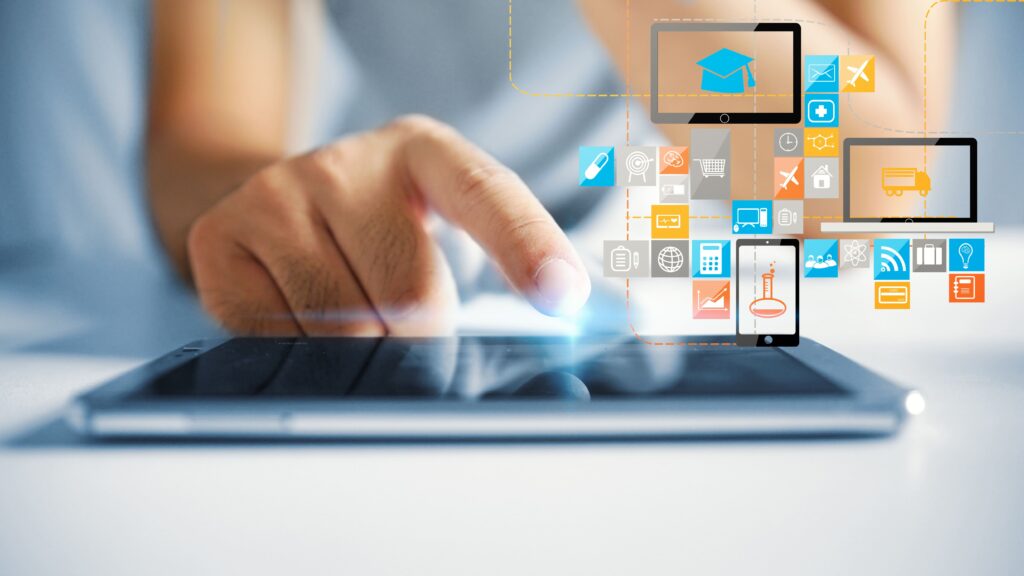
Web会議・チャット・業務ツールの定番を紹介
在宅勤務を支える基本ツールといえば、Web会議システム(Zoom、Microsoft Teamsなど)とチャットツール(Slack、Chatworkなど)です。これらのツールを活用することで、場所にとらわれない円滑なやり取りが可能になります。
加えて、業務の進捗を可視化するプロジェクト管理ツール(Notion、Backlog、Asanaなど)も有効です。タスクの見える化によって、チーム全体の認識を揃えやすくなり、リモートでも成果を出しやすい仕組みが整います。**「どこにいても一緒に働ける環境づくり」**が、これからの業務効率化の鍵です。
在宅・出社の状況把握ができる可視化ツール
在宅勤務が定着した一方で、「誰がどこで働いているのか分からない」という悩みを抱える企業は少なくありません。特にハイブリッドワーク環境では、日によって出社・在宅が入り混じるため、全体像の把握が難しくなりがちです。
そこで注目されているのが、「出社状況をリアルタイムで見える化するツール」です。部署別・日別に出社人数を把握したり、混雑を避けて働く時間を調整できたりする仕組みが、働きやすさと業務効率の向上につながります。こうした環境整備は、単なる便利機能ではなく、チームの健全な運営にも直結します。
チームマネジメントのための行動ログ活用
リモート環境では、単に出社・在宅の有無だけでなく、「誰が・いつ・どこで・誰と関わっていたか」といった行動パターンの把握も重要になります。これにより、チーム内の連携状況や孤立リスク、接触の傾向などを定量的に分析できるようになります。
たとえば、特定メンバーが他部署とまったく接点を持っていない、あるいは上司との接触が極端に少ないといった状況もログから見えてきます。感覚だけに頼らず、事実に基づいてマネジメントを改善していく視点が、これからのチーム運営には求められています。
Beacapp Hereで実現するハイブリッドワークの最適化
こうした「働き方の見える化」を実現するツールのひとつが、Beacapp Hereです。社員の出社・在宅状況や行動傾向を自動で記録し、組織の働き方をリアルタイムで把握できます。たとえば、部署ごとの出社率や、オフィス内での接触傾向を可視化することで、コミュニケーションの断絶や属人化リスクを未然に防ぐことが可能です。
また、オフィスの空き状況を確認したり、出社傾向をもとにレイアウトを見直したりといった活用も広がっています。無理に管理するのではなく、働き方を自然にサポートする仕組みとして導入されているのが特長です。在宅勤務と出社勤務を組み合わせた、ハイブリッドワークの理想形に近づくための手段として、今後さらに注目されていくでしょう。
▶【無料DL】社員の出社・在宅状況をリアルタイムに見える化する方法とは?

まとめ
在宅勤務は、働く人にとっても企業にとっても大きな変化をもたらす働き方です。柔軟性や効率性といったメリットがある一方で、孤立感やマネジメントの難しさといった課題も存在します。こうした変化に対応するには、制度づくりだけでなく、働き方を“見える化”する仕組みが重要です。
Beacapp Hereのようなツールを活用すれば、出社・在宅の状況や社員同士の関係性をデータで把握し、より快適で健全なハイブリッドワークを実現できます。これからの働き方を支えるヒントとして、ぜひ一度チェックしてみてください。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg