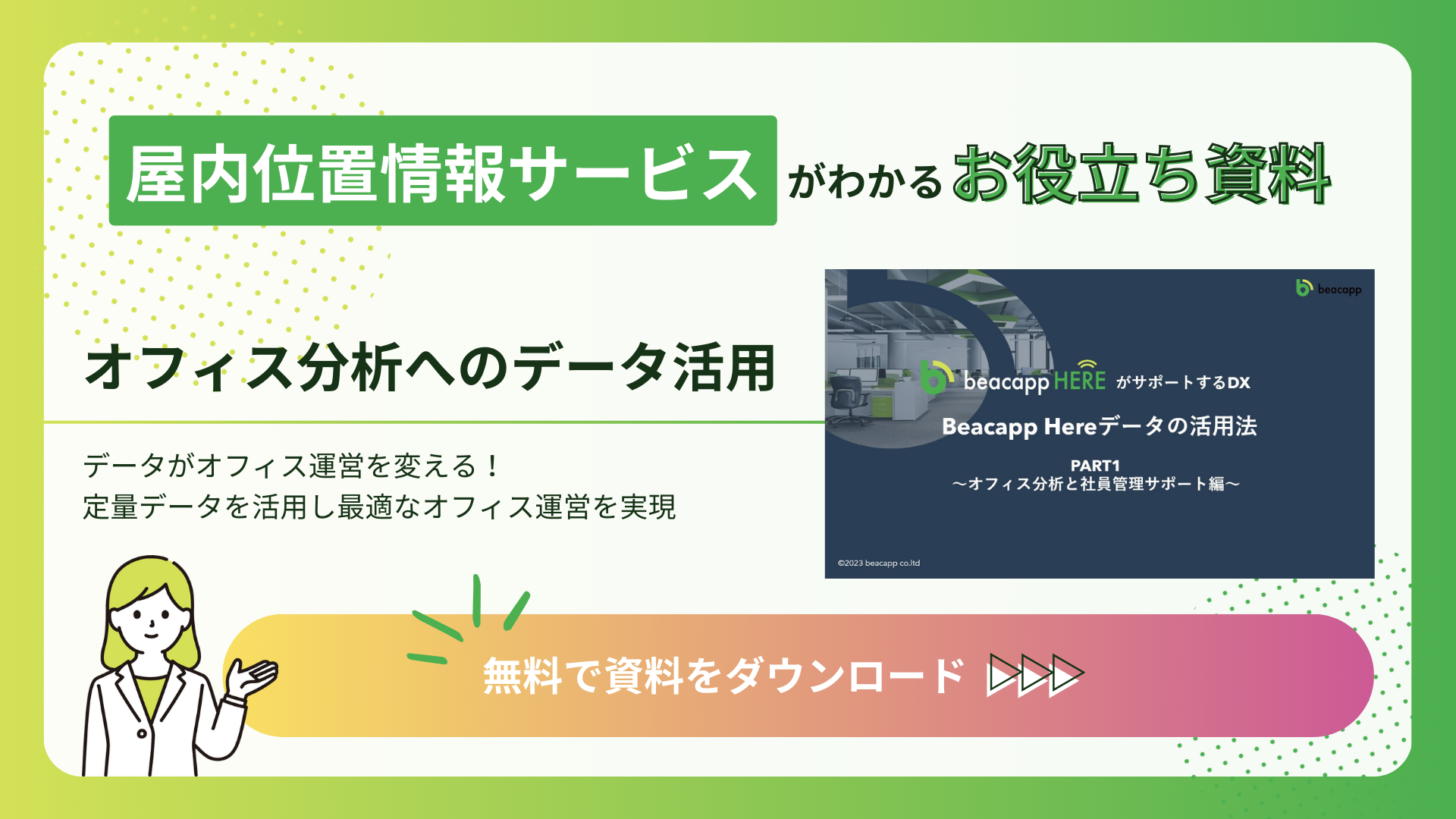コロナ禍を経て、企業の働き方やオフィスの在り方は大きく変化しました。その中でかつて「柔軟な働き方の象徴」とされたフリーアドレス制度が、今、廃止の動きに直面しています。なぜ制度の見直しが進むのか?
本記事ではフリーアドレスの課題と企業事例を整理し、ポストコロナ時代の理想的なオフィス像を探ります。さらに、スマートオフィスを実現する最新ツールについてもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
フリーアドレスが抱える課題と廃止の理由

フリーアドレスとは、社員に固定席を設けず、出社のたびに空いている席を選んで働くスタイルです。働き方改革やICTの進展により導入が加速しましたが、制度の運用上の問題やコロナ禍を機に多くの課題が浮き彫りとなり、廃止や再設計を進める企業が増えています。
フリーアドレス制度の基本とは
フリーアドレス制度とは、オフィス内に固定席を設けず、出社時に好きな場所で業務を行うスタイルを指します。社員はその日の気分や業務内容に応じて座席を選び、日替わりで異なる環境で仕事を進められるという柔軟性が特徴です。
ここで、混同されがちなABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)との違いも整理しておきましょう。ABWは「業務の種類や目的に応じて働く場所を自ら選ぶ」考え方で、フリーアドレスはその手法のひとつにすぎません。つまり、ABWは概念であり、フリーアドレスはその実践的な仕組みの一形態なのです。
制度が拡大した背景
フリーアドレス制度が広がった背景には、いくつかの要因があります。
第一に、「働き方改革」の一環として、社員の自律性や多様な勤務スタイルを尊重する動きが強まったことです。第二に、女性活躍推進や外国籍社員の増加といったダイバーシティの拡大によって、固定席に依存しない柔軟な働き方が求められたことです。
また、IT技術の進化によってノートパソコンやクラウドの普及が進み、どこでも仕事ができる環境が整ったことも、制度導入を後押ししました。さらに、企業にとってはオフィススペースの有効活用や賃料削減といった経済的なメリットもあり、多くの企業が積極的に導入を進めていったのです。
コロナ禍での利用変化
新型コロナウイルスの拡大は、フリーアドレスの運用に大きな影響を及ぼしました。感染防止の観点から、共用スペースの使用やデスクの共有を避ける動きが強まり、フリーアドレスの運用にブレーキがかかりました。
また、在宅勤務の一般化により社員の出社率が低下し、そもそも「誰が来るか分からない」「空間の最適な割り当てが困難」といった問題が浮上しました。
結果として、従来のフリーアドレス運用は実質的に形骸化しました。制度の意義や価値が薄れていき、多くの企業が廃止や見直しを余儀なくされたのです。
ABWとフリーアドレスの違い
先にも述べたように、ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)は、業務の目的や内容に応じて最適な作業場所を選ぶという概念です。フリーアドレスはその具体的な実践方法の一つにすぎません。両者は同義ではなく、混同しない運用が重要です。
関連記事: フリーアドレスとは?オフィス導入に向けた取り組みと成功事例
実際にフリーアドレスを廃止した企業事例

多くの企業が導入したフリーアドレスですが、その一方で制度の廃止や見直しを決断する企業も増えてきました。廃止の背景には、制度の理想と現実のギャップや、業務の性質に合わない点が顕在化したことが挙げられます。
たとえば、IT関連企業A社では、部署間の偶発的な交流を目的に全社的なフリーアドレスを導入しましたが、結果として「誰がどこにいるか分からない」「新人への声掛けが減る」といった問題が表面化しました。特に若手社員の孤立感や、対面による教育・報連相の機会損失が大きく、業務効率にも影響を及ぼしていました。
ここではフリーアドレスの制度を廃止や見直しをした背景を、事例をもとに解説します。
フリーアドレスを見直した背景
制度を見直した最大の理由として、「コミュニケーションの断絶」が挙げられる企業がありました。社員が日替わりで異なる席に座ることで、チーム内の一体感や迅速なやり取りが損なわれ、プロジェクトの進行に支障をきたしたケースもあります。また、紙資料や個人のツールを置けないことから、「働きにくさ」を訴える声も多くなりました。
さらに、管理職層からは「部下の様子を見守りにくい」「相談や雑談の機会が減った」という声も挙がり、組織的なパフォーマンス低下の要因として指摘されるようになりました。
再設計後のオフィスの工夫
制度を廃止した企業では、完全な固定席への回帰ではなく、フレキシブルな設計に再構築する傾向があります。具体的には、チームごとに「エリア制」を導入し、プロジェクト単位や部署単位で一定のスペースを確保することで、自由度と組織的連携を両立させています。
さらに、一部企業では「集中ブース」や「雑談エリア」など用途に応じたスペースを設け、ABW的な要素を柔軟に取り入れるハイブリッド型のオフィスを構築。これにより、社員の心理的安全性や生産性を向上させる空間設計が実現されています。
廃止による成果と反応
制度廃止後の効果としては、「チームの一体感が戻った」「情報共有が円滑になった」「新人の教育がしやすくなった」などの声が多く聞かれます。コミュニケーションの密度が上がることで、業務のスピードや品質も改善され、従業員満足度の向上にもつながっています。
加えて、社員が自身の居場所に安心感を持てるようになったことで、集中力が高まり、エンゲージメントが向上したという報告もあり、制度見直しが組織全体の活性化に寄与しています。
参考:導入・廃止を柔軟に見直す企業文化
一部の企業では、フリーアドレスや固定席を「状況に応じて使い分ける」柔軟な制度運用を実践しています。導入・廃止を前提にせず、PDCAサイクルで環境改善を継続する企業文化が、社員の満足度を支えています。

これからのオフィスに求められるもの

フリーアドレスの成否に関わらず、これからのオフィスに必要なのは「選べる働き方」と「エンゲージメントの最大化」です。出社・在宅・サテライトなど働く場所が多様化する中で、どこでも快適に働ける空間設計と、社員のつながりを強める施策が求められています。
また、オフィスを単なる作業場所としてではなく、社員同士の信頼関係や創造性を育む「エンゲージメント拠点」と捉える考え方も浸透しつつあります。その実現のためには、物理的な空間設計だけでなく、デジタルツールやデータ活用による環境整備が不可欠です。
こうした流れの中では、働き方の自由度に加え、それを支える制度設計や空間づくり、人と人とのつながりを強める工夫が不可欠です。
「選べる働き方」がキーワード
ポストコロナの時代には、「いつ・どこで・どのように働くか」を社員自身が選べる環境が求められています。これにより、ワークライフバランスが整い、主体性を持った働き方が促進されます。
企業側も一律の制度運用ではなく、職種や業務内容に応じた柔軟なルール設計が重要です。その中で、必要に応じて出社し、対面での連携やコミュニケーションができるオフィスの存在意義は、むしろ以前より高まっているとも言えるでしょう。
エンゲージメントを高める空間設計
エンゲージメントを高めるためのオフィス空間には、心理的安全性を確保し、社員が「自分らしくいられる」環境が必要です。たとえば、集中できる静音エリア、雑談を促すカフェ風スペース、アイデアを視覚化できる共有ホワイトボードの設置など、用途ごとに最適化されたレイアウトが有効です。
こうした空間設計は、コミュニケーションの活性化だけでなく、部署を越えた協業や偶発的な交流を促す仕掛けとしても機能します。
DXを活用した最適化
空間設計や働き方の最適化には、デジタルツールの導入が不可欠です。たとえば、座席予約アプリや出社率の分析ツールを導入すれば、無駄なスペースやエネルギーを削減しながら、最適なレイアウトを維持できます。
また、リアルタイムで社員の在席状況や会議室の利用率を可視化することで、管理部門の負担も軽減できます。これらのDXは、組織全体の運営効率と従業員満足度の向上という二重の成果をもたらします。
Beacapp Hereで実現するスマートオフィス

これからのオフィスには、「効率」と「つながり」の両立が求められます。その課題を解決するツールとして注目されているのが、「Beacapp Here」です。これは、社員の居場所の可視化やオフィスの利用状況のデータ取得、座席の予約運用などを可能にするスマートオフィス支援ツールです。
フリーアドレスやABWの運用においては、「どこに誰がいるか分からない」という不安がつきものですが、Beacapp Hereを使えば、リアルタイムで位置情報を確認できるため、業務の効率が大幅に向上します。
座席と居場所の「見える化」
Beacapp Hereでは、社員がBluetoothセンサーやスマートフォンアプリを通じて、どの席に誰がいるのかをオフィス内で即座に把握できます。これにより、席探しの時間を削減し、特定のメンバーを探す手間も大きく省けます。
また、在席状況が可視化されることで、リアルなコミュニケーションの機会が増え、偶発的な出会いや雑談によるアイデア創出も期待できます。ABW運用における「自由」と「不安定さ」のバランスをうまくとることができるのです。
オフィス利用のデータ活用
さらに、このツールの大きな強みは「データの活用」です。社員の出社頻度、滞在時間、利用エリアの傾向などを自動で記録し、分析することで、実際の働き方に即したオフィスレイアウトや人員配置の見直しが可能になります。
例えば、あるエリアの利用率が著しく低い場合には、用途変更や縮小を検討することで、無駄なスペースの削減が可能となります。一方、人気の高い場所を拡張したり、用途を特化することで、より快適な職場環境の実現にもつながります。
エンゲージメントの可視化支援
Beacapp Hereは、社員の行動データから「働き方の傾向」や「他者との接触頻度」などを可視化できるため、組織のエンゲージメント向上にも貢献します。どの社員が孤立しているか、あるいはチーム内でどれほどの交流があるかといったデータは、人的資本経営にとって重要な指標です。
これにより、上司や人事部門が社員の状況を早期に把握し、必要な支援や配置転換を検討する材料として活用できます。単なるオフィス管理ツールを超えて、人的課題にアプローチするソリューションとしても注目されています。
導入実績や活用事例も交えて紹介
Beacapp Hereは、大手企業を中心に導入が進んでおり、IT・製造・金融・コンサルティング業界など幅広い分野で実績があります。多拠点での活用やABW型オフィスとの併用事例も多数あり、業種や企業規模に応じた柔軟なカスタマイズが可能です。
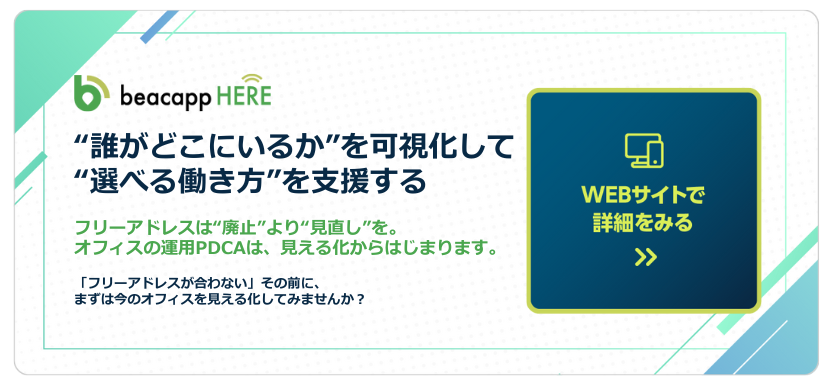
まとめ
かつて「働き方改革の象徴」とされたフリーアドレスは、コロナ禍や制度の形骸化を背景に見直しが進んでいます。しかし、制度の廃止は終わりではなく、新たなオフィス像を模索する転換点でもあります。これからの時代に求められるのは、「柔軟性」と「つながり」を両立したオフィス環境です。
デジタルツールや空間設計の工夫を通じて、社員が安心して働ける場をどう構築するかが、企業の競争力を左右する鍵となるでしょう。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg