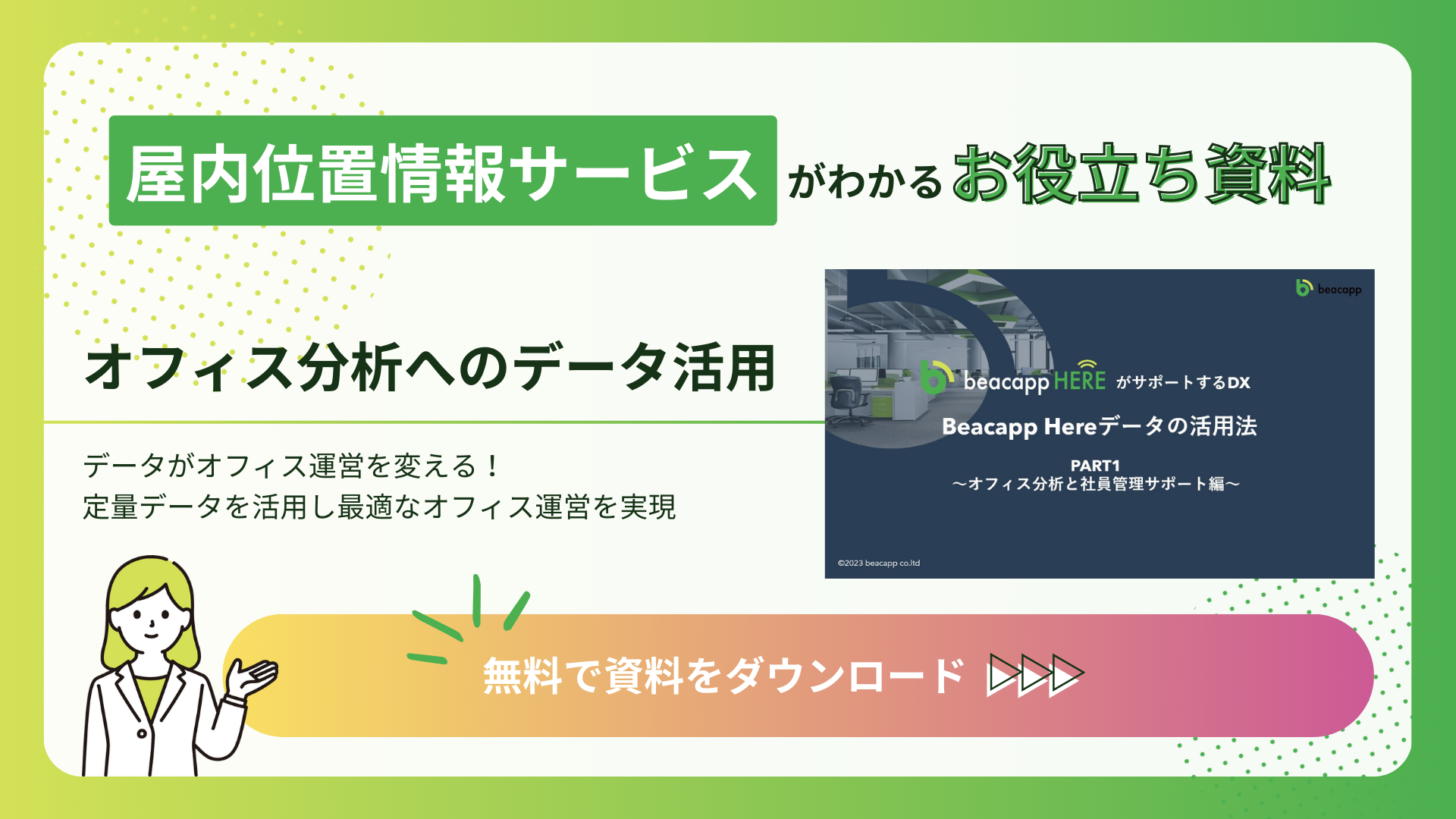近年、働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、企業は従業員の働き方の多様化を求められています。中でも在宅勤務やモバイルワークは、オフィス以外の場所で効率的に業務を行う手段として注目されています。
本記事では、在宅勤務の基本やモバイルワークとの違い、導入のメリット・課題、成功のポイントまでをわかりやすく解説します。
ワークスタイルの多様化と「在宅勤務」の基本

「在宅勤務」とは? 定義と広がり
在宅勤務とは、従業員がオフィスに出社せず、自宅を拠点として業務を行う働き方です。
パソコンやクラウドサービス、オンライン会議ツールなどのICT環境を活用することで、オフィスにいるのと同等の業務遂行が可能となります。もともとは育児や介護と仕事を両立するための制度として注目されましたが、近年は働き方改革やパンデミックの影響を背景に多くの企業で導入が進みました。
在宅勤務を整備することで、通勤時間を削減し、従業員は集中できる時間を確保できます。また企業側にとっても、オフィススペースや光熱費の削減などコスト面のメリットが期待できます。
モバイルワークとは? テレワークとの違い
モバイルワークは、オフィスや自宅に限定されず、移動中や外出先、カフェや出張先など、場所を問わずに業務を遂行できる柔軟な働き方を指します。テレワークの一種ですが、自宅を中心とする在宅勤務とは異なり、働く場所が固定されない点が大きな特徴です。
モバイル端末やクラウドサービスを活用すれば、社外からでもリアルタイムで情報共有や意思決定が可能となります。特に営業職や出張の多い職種では有効で、顧客対応のスピードを高める効果も期待できます。テレワーク全体の中でモバイルワークは「機動性」を重視する働き方として位置づけられています。
在宅勤務が注目される背景(働き方改革・DX・パンデミック)
在宅勤務が注目される背景には、働き方改革、DX(デジタルトランスフォーメーション)、そしてパンデミックの影響があります。
働き方改革では、長時間労働の是正や多様なライフスタイルに合わせた働き方が求められ、在宅勤務は有効な選択肢となりました。DXの進展によりオンライン会議やクラウドサービスが普及し、従来は難しかったリモート業務が現実的になりました。さらにパンデミックをきっかけに、感染リスクを回避しつつ事業を継続する施策として急速に普及しました。
こうした社会的・技術的要因が重なり、在宅勤務は持続可能な働き方として認知されています。
在宅勤務・モバイルワークの共通点と相違点の整理
在宅勤務とモバイルワークはいずれもオフィス以外で業務を遂行できる柔軟な働き方であり、ICTツールの活用が前提という点で共通しています。ただし、両者には明確な違いがあります。在宅勤務は自宅を拠点とするため、比較的落ち着いた環境で集中作業が可能であり、育児や介護との両立に適しています。
一方、モバイルワークは移動中や外出先でも働ける自由度の高さが特徴で、営業活動や出張業務との相性が良い働き方です。企業がどちらを導入するかは、業務内容や従業員の特性、求められる即時性や柔軟性の度合いによって判断されます。
在宅勤務のメリットと課題
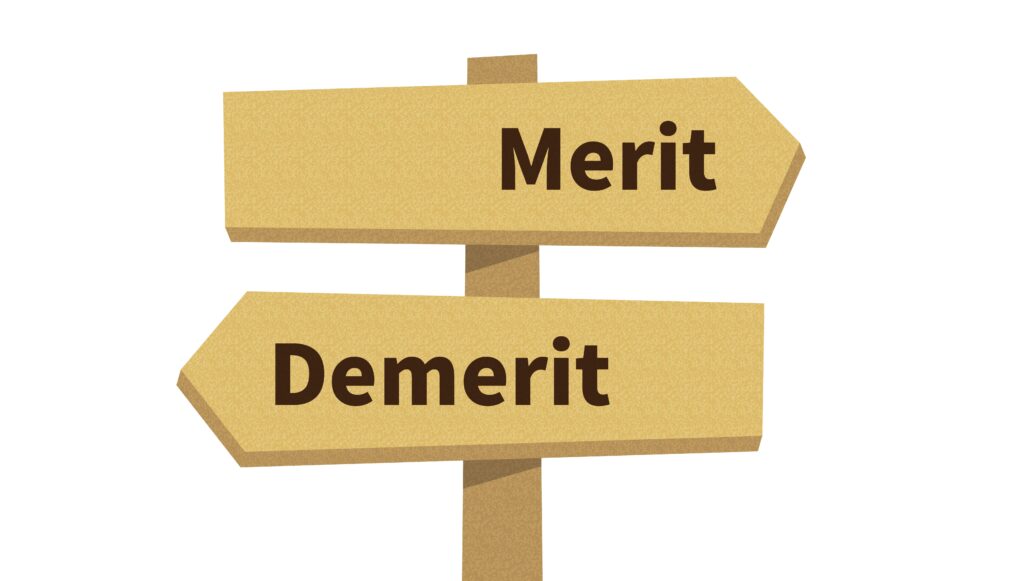
柔軟な働き方で生産性が向上する
在宅勤務の大きなメリットは、時間や環境を柔軟に調整できる点にあります。通勤時間を削減できることで、その分の時間を業務や自己学習に充てることができ、生産性向上につながります。
また、自宅という落ち着いた環境では、集中力を高めやすく、資料作成や企画立案などの思考型業務に適しています。加えて、従業員自身が生活リズムに合わせて効率的に働けるため、体調や家庭の事情に応じた柔軟な働き方が可能になります。企業にとっても、効率的な人材活用やオフィス維持コスト削減といったメリットが期待でき、組織全体の競争力向上に直結します。
ワークライフバランスと従業員満足度の向上
在宅勤務は、従業員のワークライフバランス改善に大きく寄与します。通勤による負担が軽減されることで心身の疲労が減り、業務後のプライベートな時間を有効に活用できるようになります。育児や介護を担う従業員にとっては、家庭との両立が容易になり、離職防止やキャリア継続にもつながります。
また、自分の生活スタイルに合わせて業務を進められる柔軟性が、従業員の満足度やエンゲージメントを高め、企業へのロイヤルティを強化します。働きやすい環境は優秀な人材の定着や採用にも効果的であり、結果として企業全体のパフォーマンスや競争力向上を後押しします。
課題① コミュニケーション不足と孤立感
在宅勤務の課題として最も指摘されるのが、コミュニケーション不足による孤立感です。オフィスでの対面交流が減ることで、雑談やちょっとした相談の機会が失われ、チームの一体感や信頼関係が希薄になりがちです。その結果、情報共有の遅れや誤解が生じやすくなり、業務効率に影響を与える場合があります。
また、従業員が孤立感を抱え続けると、モチベーションの低下や精神的ストレスの増大につながる可能性もあります。こうした課題を解決するためには、定期的なオンライン会議やチャットツールの活用、非公式な交流の場を設けるなど、意識的にコミュニケーションを補う取り組みが求められます。
課題② セキュリティリスクと労務管理
在宅勤務では、社外ネットワークや個人端末を利用する機会が増えるため、情報漏えいや不正アクセスのリスクが高まります。公共Wi-Fiの使用もセキュリティ上の脆弱性を生む要因です。
さらに、労務管理の面では勤務時間や休憩状況の把握が難しく、長時間労働や健康被害を招く恐れがあります。こうしたリスクは、在宅勤務を長期的に続けるうえで見過ごせない課題であり、企業と従業員双方の信頼を揺るがす要因となり得ます。

モバイルワークとテレワークの違いを整理する

テレワークの包括的な概念としての位置づけ
テレワークとは「情報通信技術を活用し、場所や時間にとらわれずに働く勤務形態」の総称です。
自宅で働く在宅勤務や、外出先で働くモバイルワーク、サテライトオフィス勤務などをすべて含む包括的な概念です。つまり、テレワークは働く「方法論」を示す言葉であり、個々の勤務形態を包括する上位の枠組みといえます。国や自治体の施策でもテレワークという用語が広く使われており、柔軟な働き方を推進するための政策的キーワードになっています。
企業が導入を検討する際には、テレワークの中から自社の業務や従業員に最適な形態を選び、制度設計することが求められます。
モバイルワーク=場所を選ばない柔軟な働き方
モバイルワークは、オフィスや自宅に限らず、カフェ、移動中、顧客先など、どこでも仕事ができる働き方です。ノートPCやスマートフォン、クラウド型業務システムを利用し、インターネット環境があれば業務が進められるのが特長です。営業やフィールドワークを伴う職種では特に有効で、移動時間を活用した業務効率化や、顧客対応の迅速化に寄与します。
また、災害や緊急時にも拠点を問わず働けるため、事業継続性の観点からも注目されています。ただし、場所を選ばない自由度の一方で、セキュリティや労務管理が複雑になりやすいため、企業側の仕組みづくりと従業員のリテラシー向上が重要となります。
在宅勤務は「テレワークの一形態」である
在宅勤務は、テレワークに含まれる一つの働き方であり、自宅を拠点として業務を行う点に特徴があります。通勤時間をなくし、自宅環境で集中して働けることから、生産性向上やワークライフバランス改善の効果が期待されます。
一方で、家庭環境によっては業務に集中しにくい場合や、孤立感を抱きやすいといった課題もあります。したがって、在宅勤務は万能ではなく、他のテレワーク形態と併用しながら最適化することが望ましいでしょう。
テレワークの中で「最も導入しやすい形態」として広がってきた背景を理解し、自社の制度にどのように組み込むかが重要です。
導入目的や対象従業員によって最適解が異なる
テレワーク導入の最適解は、企業の目的や対象従業員によって異なります。
例えば、集中業務が多いスタッフには在宅勤務が適し、営業や顧客対応が中心の職種にはモバイルワークが有効です。また、地方拠点や出張の多い従業員にはサテライトオフィス勤務が利便性を高めます。導入目的が「生産性向上」なのか「人材定着」なのかによっても選択肢は変わります。重要なのは、テレワークを単なる制度として導入するのではなく、自社の経営戦略や人材戦略と結びつけて設計することです。
従業員の特性や業務内容を踏まえ、柔軟に組み合わせることで、テレワークは真に効果を発揮します。
在宅勤務を成功させるためのポイント

コミュニケーション手段の整備(チャット・会議ツール)
在宅勤務を円滑に進めるには、適切なコミュニケーション基盤の整備が不可欠です。オフィスのように気軽な会話ができないため、チャットツールやビデオ会議を活用し、情報共有を効率的に行う仕組みを構築する必要があります。チャットは日常的なやり取りや迅速な確認に、会議は定期報告や意思決定に活用するなど、目的に応じて使い分けることが効果的です。
また、非公式な雑談の場を設けることで孤立感を防ぎ、チームの一体感を維持できます。形式だけの導入にとどまらず、利用ルールや活用方法を明確にし、誰もが使いやすい環境を整えることが、在宅勤務の成功を支える重要な要素です。
業務可視化と進捗管理の仕組みづくり
在宅勤務では、従業員がどのように業務を進めているかを上司や同僚が直接把握することが難しくなります。そのため、タスク管理ツールやプロジェクト管理システムを導入し、業務の進捗を「見える化」することが重要です。可視化によって、進行状況の遅延や課題を早期に発見でき、チーム全体で適切にフォローし合う体制を築けます。
また、透明性の高い管理は従業員の責任感や主体性を高め、業務効率化にもつながります。ただし、過度な監視にならないよう配慮し、信頼をベースにしたマネジメントを心がけることが肝心です。バランスの取れた仕組みづくりが、在宅勤務の成果を最大化させます。
セキュリティ・労務管理体制の強化
これらの課題を克服するには、具体的な仕組みづくりが不可欠です。セキュリティ面ではVPNや二段階認証、端末の一元管理や遠隔操作によるデータ削除などを導入し、情報漏えいを防止します。
労務管理では勤怠管理システムや業務ログを活用し、勤務時間や休憩状況を正確に記録することが重要です。明確なルールとツールを組み合わせることで、従業員は安心して働け、企業もリスクを最小限に抑えることができます。
従業員の自律性を支えるマネジメント手法
在宅勤務では、従業員が自律的に業務を進められるよう支援するマネジメントが不可欠です。従来のような「目に見える管理」ではなく、目標設定や成果に基づいた評価が重要になります。上司はタスクの進め方を細かく指示するのではなく、達成すべきゴールを明確に伝え、進捗に応じたサポートを行う姿勢が求められます。
また、信頼関係を前提とした柔軟なマネジメントは、従業員のモチベーションを高め、自律性を引き出します。さらに、キャリア形成やスキルアップの支援を組み合わせることで、従業員は安心して成長を目指せます。自律と信頼を軸にしたマネジメントが、在宅勤務の質を大きく左右します。
ツールを活用した在宅勤務・モバイルワークの推進
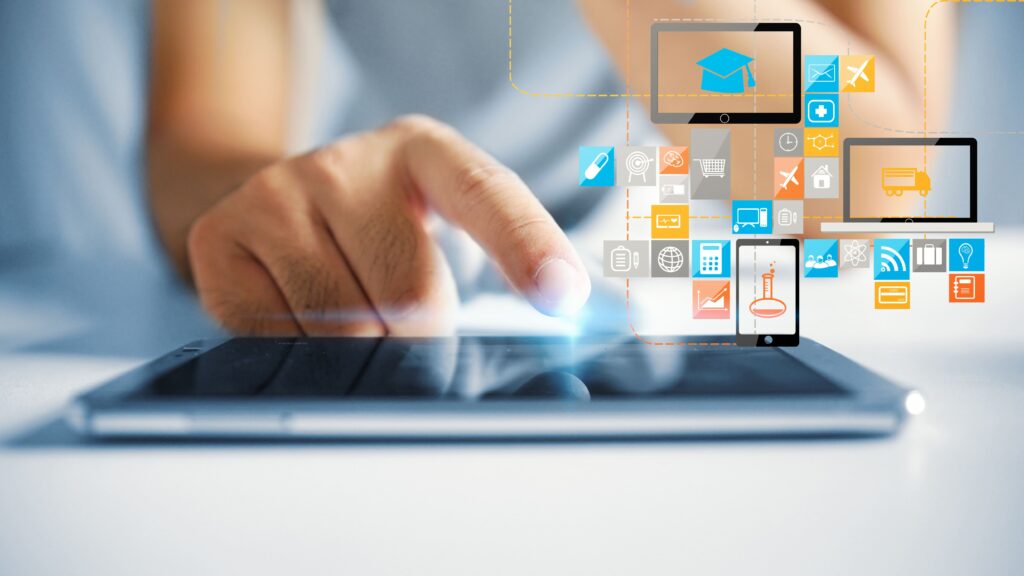
業務ログ・勤務状況の「見える化」の重要性
在宅勤務やモバイルワークでは、従業員の勤務実態が見えにくくなることが大きな課題です。そのため、業務ログや勤務状況を「見える化」する仕組みが重要です。
ツールで業務の開始・終了時刻、作業内容、成果物を記録することで、上司や同僚が状況を把握しやすくなり、適切な業務分担やサポートが可能になります。また、労務管理の観点でも勤務状況の透明化は不可欠で、過重労働防止や休暇取得の適正化につながります。
単なる監視ではなく、従業員の働きやすさを守る仕組みとして「見える化」を位置づけることが、信頼関係維持にも重要です。
従業員の接触傾向や出社状況を把握するメリット
在宅勤務と出社勤務を併用するハイブリッドワークが広がる中で、従業員の接触傾向や出社状況を把握することは大きなメリットをもたらします。
例えば、オフィス出社の頻度や誰と接触したかを把握することで、感染症対策や健康管理に活用できます。また、チームごとの出社状況を可視化することで、出社日の調整やオフィス利用の最適化も実現可能です。
さらに、従業員の行動傾向を分析することで、コミュニケーションの偏りや孤立のリスクを早期に察知でき、適切なサポートにつなげられます。接触状況の把握は、単に管理のためではなく、従業員の健康・安心を守り、効率的な組織運営を実現する基盤となるのです。
社員の満足度向上とエンゲージメント管理にも貢献
在宅勤務やモバイルワークの効果を正しく評価するには、定量データと定性データを組み合わせた働き方分析が有効です。定量データとして勤務時間、業務量、生産性指標などがありますが、これだけでは従業員の満足度やモチベーションは把握できません。そこで、アンケートや1on1面談などの定性データを組み合わせることで、働き方の全体像を立体的に理解できます。
この分析は、制度改善や新施策の検討に役立つだけでなく、従業員の声を反映した柔軟な働き方の実現にもつながります。データと声の両面から分析する姿勢が、持続的な在宅勤務・モバイルワークの鍵となります。
Beacapp Hereでできること(勤務状況可視化・改善事例)
「Beacapp Here」は、従業員の勤務状況や行動を可視化し、在宅勤務やモバイルワークの課題解決を支援するツールです。出社・退社や在席状況を自動で記録できるため、勤怠管理の精度が向上し、労務リスクを軽減します。
また、オフィスでの接触状況を把握できる機能は、感染症対策やハイブリッドワークにおけるチーム調整に有効です。さらに、蓄積されたデータを分析することで、業務効率の改善やオフィススペースの最適化にも役立ちます。
実際の導入事例では、勤怠把握の自動化によって管理部門の負担軽減や、従業員の安心感向上が報告されています。Beacapp Hereは、働き方改革を支える実践的なソリューションといえるでしょう。

まとめ
在宅勤務やモバイルワークは、柔軟な働き方の実現や生産性向上、従業員満足度向上に大きく貢献します。一方、コミュニケーション不足やセキュリティリスクなどの課題も存在します。適切なツールの活用や管理体制の整備、マネジメント手法の工夫により、企業は課題を克服し、最適な勤務形態を構築できます。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg