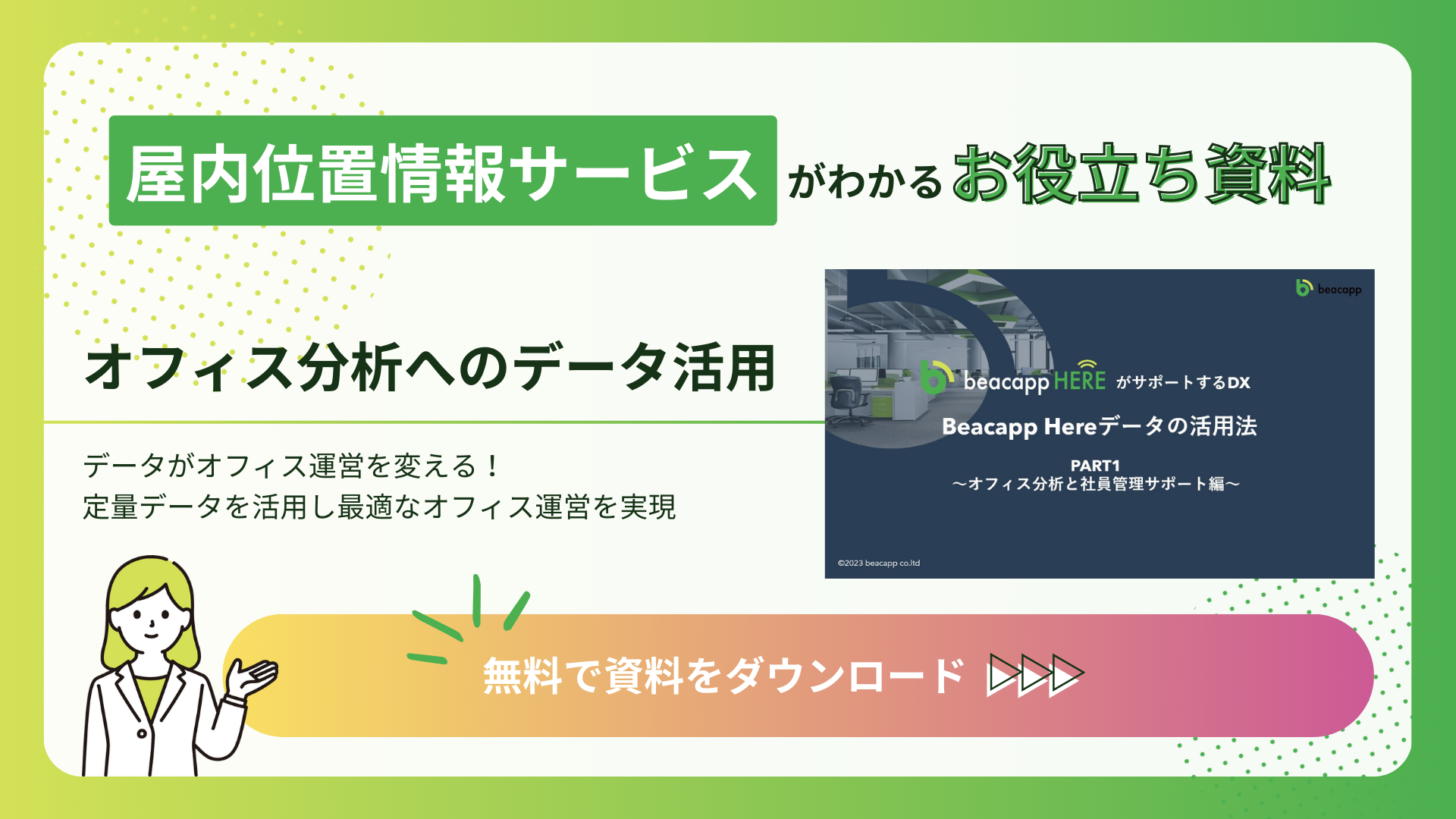多様な働き方が求められる今、フレックスタイム制を導入する企業は増えていますが、「コアタイム制度」の設計や運用に悩む声も少なくありません。
「自由」と「統一感」のバランスをいかに取るかが、制度の成功を左右します。
適切に運用すれば、チーム連携の強化や業務効率の向上にもつながる重要な制度です。
本記事では、コアタイム制度の定義から、設定時の注意点、業種別の傾向、制度のメリット・課題、そして運用の工夫までを解説。
働き方改革を一歩進めたい方に役立つ情報をお届けします。
コアタイム制度とは?基本を理解

コアタイム制度は、フレックスタイム制の一環として導入される働き方の一つです。
コアタイム制度は、柔軟性と統一感を両立させるための重要な仕組みとして、多くの企業で注目されています。
コアタイム制度の定義と仕組み
コアタイム制度とは、フレックスタイム制の一部として導入される制度で、従業員が勤務時間を柔軟に設定できる一方で、特定の時間帯に出勤することが求められる仕組みです。
この制度では、コアタイムと呼ばれる時間帯が設定され、その時間内は全員が勤務していることが求められます。
これにより、チーム内でのコミュニケーションや連携が円滑に行えるようになります。
コアタイム導入の背景と目的
コアタイム制度の導入背景には、「働き方改革」や「柔軟な働き方」のニーズの高まりが関係しています。
テレワークやフレックスタイム制の普及により、従業員は自律的に働けるようになった一方で、チーム間のコミュニケーションや業務の連携に課題が生じるケースも増えました。
こうした中で注目されているのが、特定の時間に全員が勤務する「コアタイム制度」です。
この制度を導入することで、会議や情報共有が効率化され、組織全体の一体感が生まれます。
コアタイムとフレックスタイムの関係
「コアタイム制度」とは、フレックスタイム制の一部で、全従業員が共通して勤務する時間帯を設ける仕組みです。
フレックスタイム制では、始業・終業時間を自由に設定できるのが特徴ですが、コアタイムを設けることで、チーム内の連携やコミュニケーションの確保が可能になります。
特に、会議や共同作業が発生しやすい職場では、全員が同じ時間に働く時間帯があることで、業務効率が向上します。
柔軟な働き方を推進しながら、最低限の統一性を保つ「ハイブリッド型」の勤務制度として、コアタイム制度はフレックスタイム導入企業で広く採用されています。
コアタイムの制度設計でよくある誤解
コアタイム制度の設計には誤解がいくつかあります。まず、「コアタイムを設定すればすべての業務がスムーズに進む」と考えられがちですが、実際はコアタイムだけで業務効率化が進むわけではありません。
業務内容やチームの特性に応じて柔軟に運用することが重要です。
また、「コアタイムは全社員に同じ時間を適用すべき」という誤解もありますが、業種や職務によって働き方は異なります。
一律のコアタイム設定が必ずしも効果的とは限らず、各チームや個人のニーズに合わせた柔軟な制度設計が必要です。
関連記事: コアタイムとは?意味や目的、フレックスタイムとの違いを解説!
コアタイムの時間帯・平均
コアタイム制度において、設定されるコアタイムの時間帯は企業によって異なりますが、一般的には午前10時から午後3時の間に設定されることが多いです。
また、コアタイムの平均時間は通常、3〜5時間程度であり、業種や企業文化によっても異なる傾向があります。
よく設定されるコアタイムの例
コアタイムの設定は企業によって異なりますが、一般的に多くの企業で採用されている時間帯があります。
例えば、午前10時から午後3時までの5時間をコアタイムとするケースが多く見られます。
この時間帯は、社員が出社し、業務を行う上での基本的な時間として設定されており、チーム内のコミュニケーションや会議を行うための共通の時間として機能します。
また、コアタイムを短縮し、午前10時から午後2時までの4時間に設定する企業も増えており、特に育児や介護を行う社員に配慮した制度設計が進んでいます。
コアタイムの平均時間・開始時間の傾向
最近の調査によると、コアタイムの平均時間は約4時間程度であり、特に午前中の時間帯に多くの企業が集中しています。
また、コアタイムの開始時間については、企業の業種や文化によっても異なりますが、午前9時や10時に設定されることが一般的です。
これにより、フレックスタイム制度を利用する社員は、柔軟に出社時間を調整しつつ、コアタイムには必ず業務開始していることが求められます。
業種別にみるコアタイムの違い
コアタイムの設定は、業種によって大きく異なることがあります。
例えば、IT業界ではフレックスタイム制度が一般的で、コアタイムも比較的柔軟に設定されることが多いです。
開発チームは集中力を要する作業が多いため、午後に設定することもあります。
一方、サービス業や営業職では顧客対応が多いため、午前中に設定することが一般的です。
これにより、顧客対応やチームミーティングが円滑に行えるようになります。
また、製造業では、工場の稼働時間に合わせたコアタイムが設定されることが多く、業務の特性に応じた時間帯が選ばれます。
時間設定を行う際の注意点
コアタイムの時間設定は、制度の成功に直結する重要な要素です。
まず、社員のライフスタイルや業務内容を考慮することが不可欠です。また、業務の特性によっても適切なコアタイムは異なります。
顧客対応が多い業種では、顧客のニーズに合わせた時間帯を設定することが重要です。
したがって、社員からのフィードバックを取り入れながら、試行錯誤を重ねることが大切です。
最終的には、全社員が納得できる時間設定を目指すことが、制度の定着と効果的な運用につながります。

コアタイム制度のメリットとは?

コアタイム制度は、柔軟な働き方を実現しつつ、業務の効率化を図るための重要な手段です。
従業員は自分のライフスタイルに合わせた勤務時間を選択できるため、仕事とプライベートの両立がしやすくなります。
柔軟な働き方と業務の効率化
コアタイム制度は、従業員に柔軟な働き方を提供する一方で、業務の効率化にも寄与します。
具体的には、従業員が自分のライフスタイルや業務の特性に応じて勤務時間を調整できるため、仕事の生産性が向上します。
また、コアタイムに全員が出社することで、チーム内のコミュニケーションが活発になり、情報共有がスムーズに行われます。結果として、従業員の満足度が向上し、企業全体のパフォーマンスも向上することが期待されます。
チーム内の連携・コミュニケーション維持
コアタイム制度は、柔軟な働き方を実現する一方で、チーム内の連携やコミュニケーションを維持するための重要な要素でもあります。
コアタイムが設定されることで、全員が同じ時間帯に勤務するため、顔を合わせる機会が増え、自然なコミュニケーションが促進されます。この時間帯にチームメンバーが集まることで、情報共有や意見交換が活発になり、業務の進捗状況を把握しやすくなります。
労働時間の可視化による自己管理意識の向上
コアタイム制度を導入することで、労働時間の可視化が進み、従業員の自己管理意識が向上することが期待されます。具体的には、各自が自分の働き方を見える化することで、時間の使い方や業務の進捗を把握しやすくなります。
また、可視化されたデータは、個々の業務パフォーマンスを振り返る材料にもなります。さらに、チーム全体での労働時間の共有が進むことで、メンバー間の協力やサポートも強化され、より良い業務環境が生まれることが期待されます。
採用活動におけるアピールポイントになる
コアタイム制度は、企業の採用活動においても大きなアピールポイントとなります。
特に、働き方の多様性を重視する求職者にとって、フレックスタイム制の導入は魅力的な要素です。
コアタイムを設定することで、一定の時間帯にチームメンバーが集まりやすくなり、コミュニケーションや協力が促進されるため、職場の雰囲気やチームワークの良さをアピールできます。
コアタイム制度の課題
コアタイム制度は一定のメリットがある一方で、導入・運用にあたってはいくつかの注意点があります。
業務の特性やチーム構成によっては、制度が形骸化したり、生産性に悪影響を及ぼす可能性もあります。本章では、代表的な3つの課題について解説します。
コアタイムが業務効率を下げるケース
一斉に同じ時間帯に出社を求めることで、業務の流れが分断され、生産性が低下することがあります。
特に、個々の集中作業が求められる業務では、不要な会話や会議が増え、業務が停滞する要因になりがちです。
また、自分にとって最も効率の良い時間帯で働けないことで、成果の質が下がるケースも見受けられます。
実質的な「固定時間勤務」化のリスク
フレックス制度の一環であるコアタイムが、厳格に運用されることで実質的な「固定時間勤務」へと変質してしまうケースがあります。
本来の目的である柔軟な働き方が失われ、社員は定時出社と変わらぬプレッシャーを感じることになります。これにより、働き方の自由度やモチベーションの低下を引き起こす可能性があります。
誤った制度運用による不公平感
制度が適切に運用されていない場合、社員の間で不公平感が生じやすくなります。たとえば、一部の社員だけがコアタイムを厳しく求められる状況では、不満や不信感が広がる恐れがあります。
また、ルールが不明確なまま運用されると、制度そのものへの信頼も損なわれます。公平性を確保するためには、明確なルールと社内共有が欠かせません。
コアタイムなしのフレックス制度とは
コアタイムなしのフレックス制度は、従業員が自分のライフスタイルや業務に合わせて自由に勤務時間を設定できる制度です。
コアタイムがないことで、従業員は自分の最も生産的な時間帯に働くことができ、仕事とプライベートの両立がしやすくなります。
コアタイムなし制度の特徴と導入背景
この制度の大きな特徴は、特定時間に出社する義務がないことです。
業務の成果を重視し、自律的な時間管理を促す仕組みで、育児・介護との両立や副業との調整も可能になります。背景には、働き方改革の推進や、多様な価値観・ライフスタイルに対応する必要性があります。
企業側にとっても、優秀な人材確保や定着率の向上という観点から導入するメリットがあります。
完全フレックス制における運用のポイント

完全フレックス制を導入する際には、運用のポイントを押さえることが重要です。まず、社員が自由に働く時間を選べる一方で、業務の進捗やチームの連携を維持するための仕組みを整える必要があります。
さらに、社員が自分の働き方を選ぶ自由を尊重しつつ、業務の成果に対する評価基準を明確にすることが求められます。これにより、個々の働き方がチーム全体の目標達成にどのように寄与しているかを理解しやすくなります。
成果主義の相性と課題
成果主義とフレックス制度は相性が良い反面、運用には注意が必要です。
時間ではなく成果を評価するという考え方は、柔軟な働き方と一致しますが、コアタイムを設けることで自由度が制限されると、成果主義の本質を損なう恐れもあります。社員が成果を出しやすい環境を維持しつつ、チームの連携も保てるよう、制度設計にバランス感覚が求められます。
コアタイム制度を効果的に活かす運用とマネジメントの工夫
コアタイム制度を成功させるためには、運用を形骸化させないための制度設計と周知が不可欠です。
明確なルールを設定し、全社員に理解してもらうことで、制度の意義を浸透させることが重要です。
運用を形骸化させないための制度設計と周知
コアタイム制度を効果的に運用するためには、まず制度設計が重要です。
具体的には、制度の目的や期待される効果を明確にし、社員に理解してもらうことが不可欠です。制度の導入時には、全社員に対して説明会を実施し、疑問点や不安を解消する場を設けることが推奨されます。
また、定期的に制度の見直しを行い、社員からのフィードバックを反映させることで、運用が形骸化するのを防ぐことができます。
業務時間・勤務状況の可視化で得られるインサイト
コアタイム制度を導入する際は、業務時間や勤務状況の可視化が欠かせません。社員一人ひとりの働き方や業務の進捗を正確に把握することで、特定時間帯の業務集中を見極め、効果的なリソース配分や業務改善が可能になります。
これにより、過重労働のリスクを軽減し、健康的で効率的な働き方を促進します。また、可視化された情報はマネージャーや経営層の戦略的な意思決定を支え、生産性向上や組織全体のパフォーマンスアップにつながります。
チーム全体の働き方を把握・最適化するための仕組みとは
チーム全体の動きを把握するには、個人ごとの勤務時間や業務の進捗を可視化する仕組みが必要です。業務の重なりや無駄を防ぎ、コミュニケーションを円滑にするためには、共通のツールで情報を共有し、定期的にレビューを行うことが有効です。
現場の声を反映させた柔軟な見直しも制度の質を高める鍵となります。
データを活用した柔軟な制度改善の重要性
データを活用することで、制度の効果測定や改善点の抽出が可能になります。
例えば、業務の生産性や出社傾向を分析することで、より合理的なコアタイムの設定や勤務スタイルの見直しが行えます。
さらに、社員からのフィードバックも定量的に把握すれば、働きやすい制度運用につながり、企業全体の成長を支える基盤となります。

まとめ
コアタイム制度は、自由な働き方とチーム連携を両立させる重要な仕組みです。
業務内容や社員の生活に合わせた柔軟で公平な時間設定により、効率的な業務運営が期待できます。勤務状況の可視化は過重労働の防止や経営判断にも役立ちます。
組織の実態に合わせて制度設計を進め、コアタイムを活かして働き方改革を前進させましょう。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg