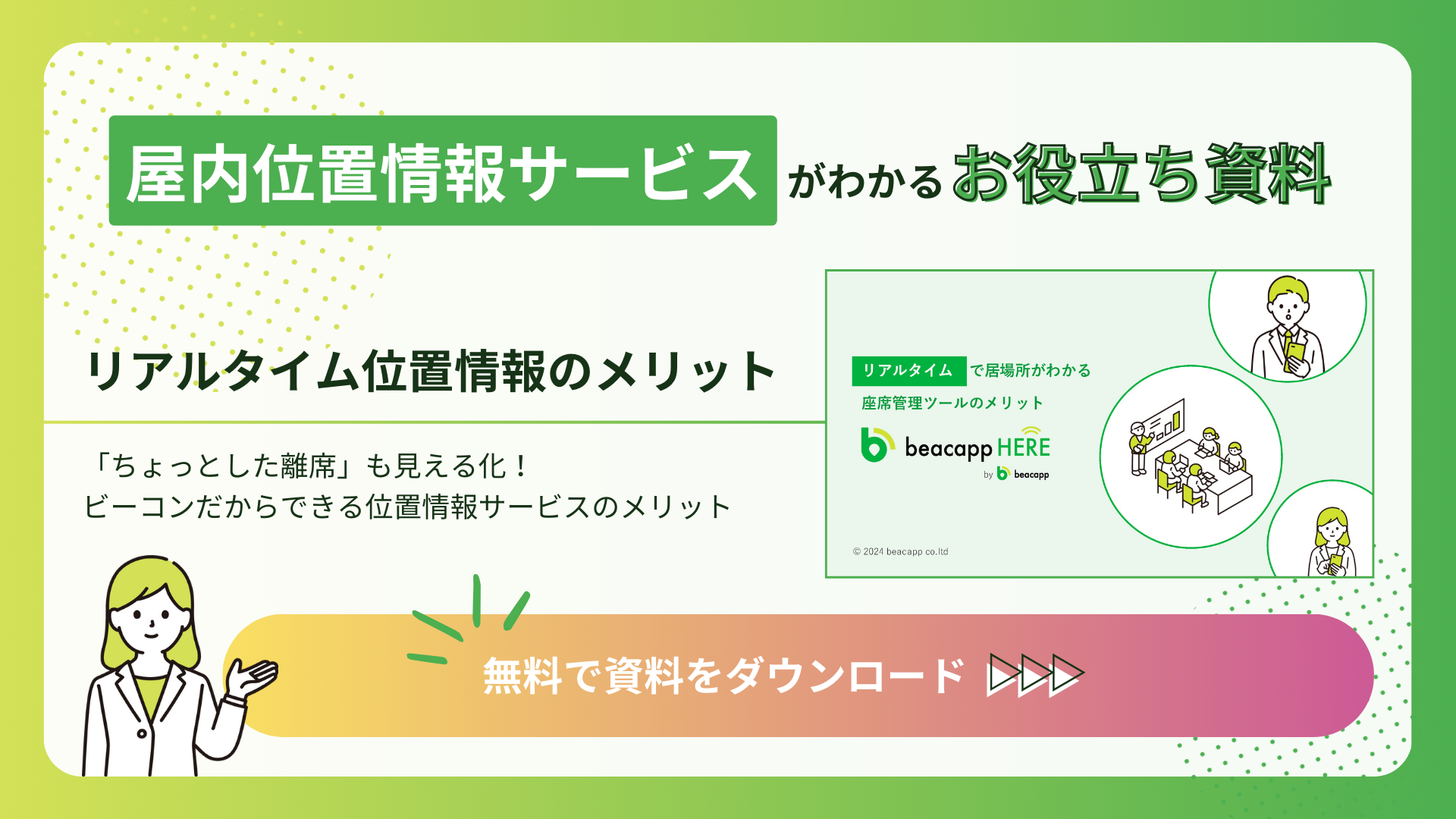コロナ禍以降、働き方の多様化が進み、オフィスの在り方も大きく変化しています。
その中で、一時代を築いた「フリーアドレス」という働き方が、近年では「時代遅れではないか」と囁かれるようにもなっています。
しかし、果たして本当にそうなのでしょうか?本記事では、フリーアドレスの本質と現在の課題、さらに進化した形での活用法について多角的に解説します。
フリーアドレスは時代遅れなのか?
「自由な席選び」という一見柔軟な制度が、なぜ「時代遅れ」と見られるようになったのか。その背景と誤解について整理します。
批判される理由とは
フリーアドレスに対する批判の多くは、実際の運用面における問題に起因しています。
たとえば「毎朝座席を探すのが面倒」「荷物の置き場所がなくストレスを感じる」「チームでの連携が取りづらくなった」など、利便性よりも不便さを感じている社員が少なくありません。
これらの問題は、「フリーアドレス」という制度そのものではなく、制度の導入と運用設計のミスマッチによるものであるケースが大半です。
時代遅れに見える本当の理由
多くの企業がフリーアドレス導入を目的化してしまい、「なぜ導入するのか」というビジョンが曖昧なまま進められたことで、形骸化してしまった例が見られます。
また、感染症対策の観点で“固定席化”が再評価された時期もあり、それが「フリーアドレス=古い」という印象につながった可能性も否めません。
本質を見直すことが重要
フリーアドレスの本質は「柔軟な働き方を可能にする環境整備」にあります。
単に席を自由にすることではなく、業務内容や気分、必要なコミュニケーションに応じて働く場所を選べるという自由度が本来の価値です。
この本質を理解した上で再構築すれば、決して時代遅れではなく、むしろ今こそ求められる働き方の一つとなります。
関連記事: フリーアドレスとは?オフィス導入に向けた取り組みと成功事例
現代の働き方にマッチするフリーアドレスの役割

リモートワーク、ハイブリッドワーク、副業など多様な働き方が広がる中、フリーアドレスはその柔軟性で再評価されています。
出社率低下に対応する合理的手段
毎日全社員が出社する時代は終わり、オフィスの利用頻度もまちまちです。
出社率が50%未満の企業では、従来の「全社員分の固定席」を用意することが非効率になります。
フリーアドレスはこうした状況下で、無駄な席数を削減し、限られたスペースを有効活用する合理的な選択肢となります。
偶発的なコミュニケーションを生む
異なる部署やチームの人間が日替わりで隣同士になれば、思わぬ情報交換や協働が生まれる可能性も高まります。
フリーアドレスの最大の強みの一つは、部門を超えた「セレンディピティ=偶然の出会い」を促す点にあります。
これはリモートワークでは得にくい価値の一つです。
オフィスの新しい価値創出につながる
もはやオフィスは「仕事をする場所」から「人とつながる場所」「文化を醸成する場所」へと役割をシフトしています。
フリーアドレスを中心に据えた空間設計は、ワーカーの創造性を刺激し、組織文化の形成にも貢献します。

導入がうまくいかない企業の共通点

フリーアドレスがうまく機能しない企業には、いくつかの共通した落とし穴があります。
ゾーニング設計の不備
単に固定席をなくしただけでは、社員は働きづらさを感じてしまいます。
業務内容に応じて「集中ブース」「チームワークエリア」「電話・Web会議可能エリア」「リフレッシュスペース」などのゾーン分けがなされていなければ、居心地の悪いオフィスになってしまいます。
ITツール・ルールの未整備
フリーアドレスを機能させるには、座席予約システムや空席情報の可視化、ロッカーの整備、ルールブックの周知などが不可欠です。
これらが整備されていないと、座席探しや荷物の管理に時間を取られ、生産性が低下してしまいます。
業務内容とのミスマッチ
紙資料や複数モニター、大量の書類を扱う業務にとって、日替わりのデスクでは業務効率が下がることもあります。全社的に一律で導入するのではなく、部門ごとのニーズや特性に応じた設計が求められます。
進化するフリーアドレスの今
フリーアドレスは「席が自由」という古い概念を超え、テクノロジーと融合しながら、より高度なワークプレイス戦略へと進化しています。
アクティビティ・ベースド・ワーキング(ABW)との融合
ABWとは、業務内容に合わせて最適な場所を選ぶ働き方です。
たとえば集中作業は静かなブースで、チームミーティングはオープンスペースで、といったように「活動」に基づいたスペース利用が可能になります。
フリーアドレスはそのベースとなる柔軟性を提供します。
デジタルツールによる運用の高度化
「Beacapp Here」などの位置情報可視化サービスを導入すれば、誰がどの席を使っているか、どこが混雑しているかをリアルタイムで把握できます。
これにより、空席の見える化、密集回避、コミュニケーションの活性化がデータドリブンに実現できます。
従業員エンゲージメントとの連動

フリーアドレスの設計・運用を社員の声や満足度調査と連動させることで、よりパーソナライズされた職場づくりが可能になります。
「働きやすさ」を起点にしたフリーアドレスの運用は、離職防止やモチベーション向上にもつながります。

まとめ
フリーアドレスは、決して「時代遅れ」な制度ではありません。
むしろ、現代の多様化した働き方、テクノロジーの進化、組織の目的に即したオフィス運用において、柔軟かつ戦略的に活用できる優れた手段です。
重要なのは、「形だけの導入」に留まらず、その本質と目的を見極めたうえで設計・運用を行うことです。ゾーニング設計やデジタルツールの活用、そして従業員のニーズとの適合。
この3つを柱に、フリーアドレスを進化させることで、企業はより豊かなワークプレイス体験と生産性向上を同時に実現できます。
フリーアドレスを“終わった制度”と捉えるのではなく、“未来へつながるオフィス戦略”として再定義してみてはいかがでしょうか。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg