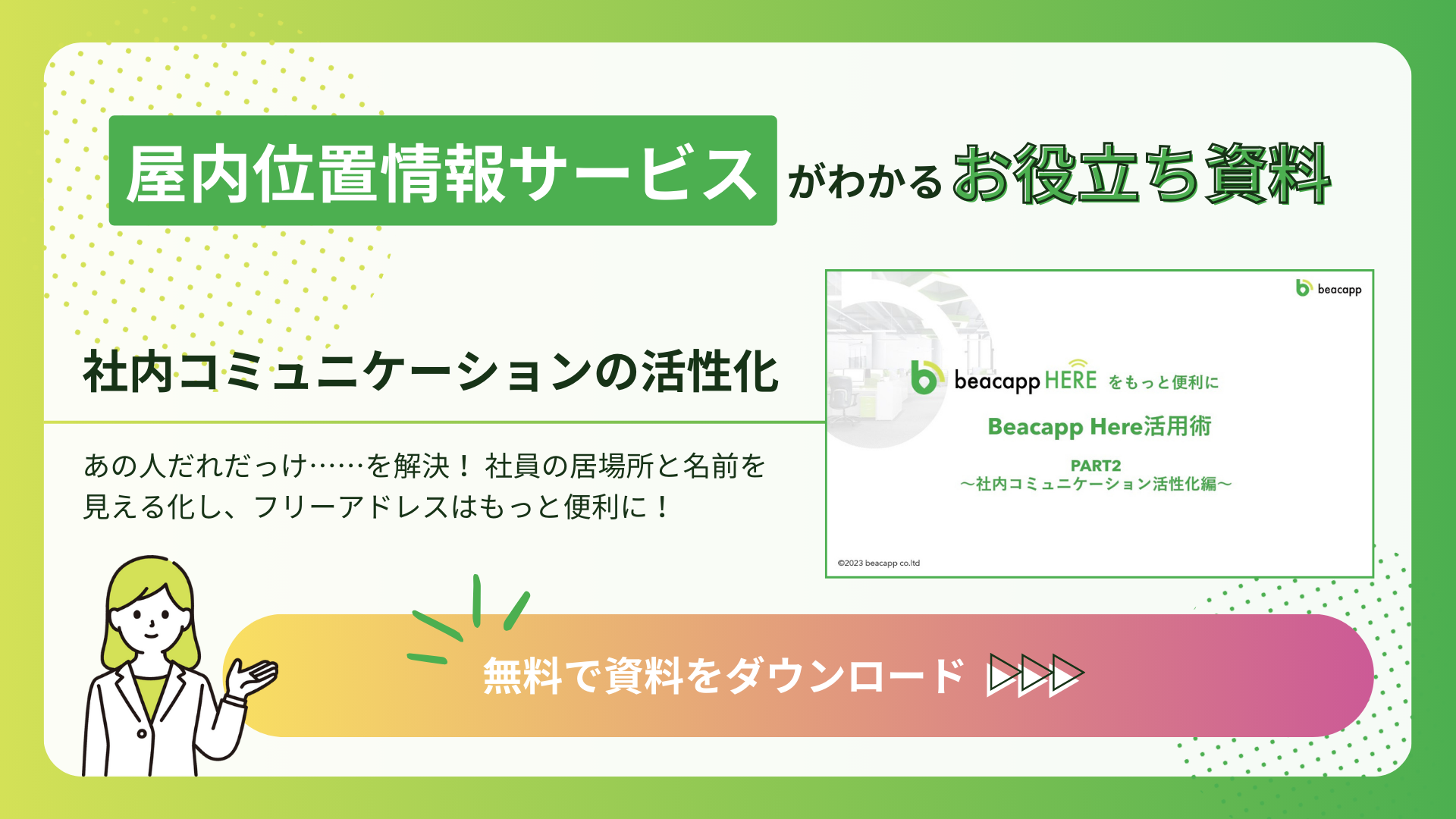「最近、仕事に集中できない」「情熱が湧いてこない」と感じることはありませんか?
こうした悩みの背景には、”ワークエンゲージメント”という重要な概念が関係しています。仕事に積極的に関わる心理状態をいかに維持・向上させるかが、個人と組織の未来を大きく左右する時代が来ています。
ワークエンゲージメントとは何か?
ワークエンゲージメントは、仕事に対する前向きで能動的な心理的状態を表します。単なる「やる気」や「満足度」とは異なる、持続的で深い関与の姿を示す概念です。
ユトレヒト・モデルによる定義
ワークエンゲージメントは、オランダの心理学者ウィルマー・シャウフェリ(W. Schaufeli)らによって提唱され、3つの要素で定義されます。
- 活力(Vigor):仕事にエネルギッシュに取り組み、疲れにくい状態。
- 熱意(Dedication):仕事に意味や価値を感じ、強く没頭できる姿勢。
- 没頭(Absorption):仕事中に時間を忘れ、集中状態に入る没入感。
この3要素がそろって初めて、真のエンゲージメントが実現しているとされます。
従業員満足度やモチベーションとの違い
多くの企業が「従業員満足度」や「モチベーション」の向上に取り組んでいますが、ワークエンゲージメントはそれらと一線を画します。
- 従業員満足度:主に待遇や職場環境への満足。受動的。
- モチベーション:個人の動機づけ。内発的・外発的に左右される。
- ワークエンゲージメント:仕事との深い関係性。自律的・持続的。
つまり、エンゲージメントは「働く人が自発的に組織に貢献しようとする状態」を生み出す、次のステージの指標です。
エンゲージメントが重視される社会的背景
現代の働き方は、変化と多様性に満ちています。リモートワーク、ジョブ型雇用、副業容認など、従来の枠組みが崩れる中、社員一人ひとりの「仕事への主体的な関与」が企業の成果に直結するようになりました。
その中でワークエンゲージメントは、個人と組織の間にある“信頼と貢献”の橋渡し役を担っているのです。
ワークエンゲージメントの測定と可視化

目に見えにくい「心理的関与度」をどのように測定し、マネジメントに活かせばよいのでしょうか。
代表的な測定指標:UWESとは?
世界的に広く用いられているのが「ユトレヒト・ワークエンゲージメント尺度(UWES)」です。上述の3要素(活力・熱意・没頭)について、それぞれ複数の設問があり、5〜7段階評価で自己回答してもらう形式です。
例:「私は仕事にとても活力を感じる」「私は仕事に深くのめり込むことがある」
数値化することで、個人ごとの推移や部署間の比較が可能になります。
サーベイツールとエンゲージメントの可視化
最近では、クラウド型のパルスサーベイを活用して、毎週・毎月など高頻度で社員の心理状態を測る企業も増えています。
短時間・少設問でのフィードバックを積み重ねることで、リアルタイムの状況把握が可能です。
加えて、従業員の行動ログ(出社頻度・会議参加状況・チャット分析など)と組み合わせることで、数値だけでは見えない「実態」に近づく試みも進んでいます。
測定結果の使い方と注意点
重要なのは、「測ること」ではなく「活かすこと」です。エンゲージメントスコアが低いチームを見つけたら、ヒアリングやワークショップを通じて背景を探り、実態に即した改善施策を打つことが求められます。
また、スコアが悪いことを責めたり、評価の材料にしてしまうと、逆効果になるリスクも。対話のきっかけとしての活用が鍵です。

ワークエンゲージメント向上のためのアプローチ
エンゲージメントを高めるには、組織全体の視点と個人の働き方、双方へのアプローチが必要です。
心理的安全性の確保
エンゲージメントの前提として不可欠なのが「心理的安全性」です。
Googleのプロジェクト「Aristotle」によれば、高パフォーマンスなチームには「気兼ねなく意見を言える空気」があることが判明しました。叱責されず、失敗が許容される環境でこそ、人は自分らしく、積極的に仕事に関わることができます。
キャリア自律支援とパーパスの共有
社員が「自分の成長実感」や「会社とのつながり」を持てるかが、エンゲージメントの源泉です。
- キャリアパスの明示
- スキルアップの機会提供
- 組織のミッションと個人の価値観の接続
こうした要素が整えば、社員は自ら能動的に学び、仕事に打ち込むようになります。
職場環境と制度の最適化
ハード面の整備も大切です。快適な椅子や集中できる空間、休憩のしやすさなど、「働きやすさ」は意欲に直結します。
また、評価制度やインセンティブの透明性、公正さも心理的な納得感に関わります。小さな成功体験を積み重ねられる仕組みが、エンゲージメントを育みます。
ワークエンゲージメントのメリットと企業への影響

エンゲージメントの高い組織には、様々な良いサイクルが生まれます。
生産性と創造性の向上
ワークエンゲージメントが高い社員は、創造性や問題解決能力にも優れ、自己裁量で仕事を進めやすくなります。チーム全体としてのスピード感やパフォーマンスも自然と上がっていきます。Gallup社の調査でも、エンゲージメントの高い企業は利益率・生産性・品質のすべてで優れているという結果が出ています。
離職率・欠勤率の低下
仕事に意義を感じ、周囲とのつながりが深い状態にあると、離職や欠勤のリスクは大きく減少します。とくに若手世代にとっては「キャリアの意味づけ」が職場選びの重要指標になっています。企業にとっては、人材確保・採用コスト削減の面でも大きな恩恵があります。
エンゲージメントの高い組織文化の波及効果
エンゲージメントは連鎖します。前向きな姿勢や協力的な行動がチームに浸透することで、組織全体の文化が活性化されます。単なる福利厚生では得られない「組織的な幸福感」が醸成されるのです。
Beacapp Hereによるワークエンゲージメント支援

最後に、ワークエンゲージメント支援の実務において注目されている「Beacapp Here」の役割を簡単にご紹介します。
行動データの可視化による課題の抽出
Beacapp Hereは、位置情報を活用して出社率・エリア利用率・会議室稼働率などをリアルタイムで把握できるサービスです。
従業員の行動傾向をデータで可視化することで、エンゲージメントの阻害要因を客観的に捉えることができます。
オフィス環境改善やハイブリッドワーク支援
「どのエリアに人が集まっているか」「どのスペースが使われていないか」といった情報を活用し、集中ブースの設置やレイアウト改善といった施策に結び付けることが可能です。
働きやすい職場づくりは、エンゲージメント向上の基盤です。
施策のPDCAを高速で実現
Beacapp Hereでは、AI WORK ENGINEと連携しながら、データ収集→課題分析→施策提案→効果検証を一貫して行う仕組みが整っています。
定性的なサーベイだけでなく、定量的な行動データと併用することで、組織改善を科学的に進めることができます。

まとめ
ワークエンゲージメントは、これからの時代における働き方・組織の在り方を根本から変えるキーワードです。
単に満足度を上げるのではなく、「仕事に意義と情熱を持ち続けられる状態」をいかに実現するかが問われています。
そのためには、制度や環境の整備、データに基づくマネジメント、そして何より「人に関心を持つ組織文化」が不可欠です。
Beacapp Hereのようなツールを活用しながら、エンゲージメント経営の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
▶︎株式会社ビーキャップ
https://jp.beacapp-here.com/corporate/
▶︎Beacapp Here|ホームページ
https://jp.beacapp-here.com/
▶︎Beacapp Here|Facebook
https://www.facebook.com/BeacappHERE/
▶︎Beacapp Here|Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCSJTdr2PlEQ_L9VLshmx2gg